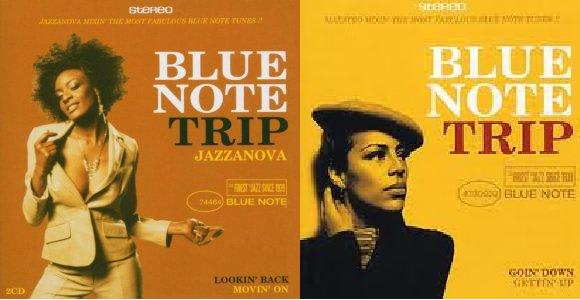前作『Modern Day Jazz Stories』からの、コンセプトまんまの続編。
ターンテーブルやサウンドエフェクトなど、「今風な」装飾を施しながらも、
やっていることは古典的なジャズ、という感じ。
日本のビデオゲーム『SFⅡ』のボイスをサンプリングしているのも、前作同様w
前作よりもヴォーカル曲を増やしているせいか、そこまで「ジャズ色」は強くなく
そっちを期待した側には、もの足りない印象が拭えない。
前作とメンバーは入れ替わり、
ヴォーカルは Cassandra Wilson → Jhelisa
ベースは Charnett Moffet → Reginalt Viel
となっている。
端正な出来だが、#3 Tryin' Time 以外は印象に残りづらいアルバム。