
「アシッドジャズ」と言えば彼ら、TBNH こと The Brand New Heavies が代表格だ。
やはり、彼らもいわゆる「今の音」ではないとは思うが、
このアルバムは、今でも聴くたびに「やっぱりいいなぁ」と思わせる何かがある。
まず、ヴォーカル N'dea Davenport の声のよさ!
のびやかで透明感にあふれ、なおかつ力強さに満ちている。
「生きる歓び」みたいなものを感じずにはいられない。
ドラムの Jan Kincaid はキーボードの他ヴォーカルもとり、# back to love や # keep together などでデュエットしている。
こちらもなかなかのものだ。
そして“バンド”としての音作りにも注目したい。
ギター、ベース、ドラム、キーボードがつくる音の土台に、トランペット、サックス、トロンボーンという3管が
埋もれず目立ちすぎず、良い力加減で乗っかってバンドサウンドを構成している。
ホーン隊はそれぞれ曲中でソロもとっており、単なる音の装飾係ではない。
Simon Bartholomew のギターカッティングはエッジが利いていて、Andrew Levy のベースはシンプルながらもタメが絶妙。
なんというか、それぞれのパートが生々しく、いかにも生演奏しているぞ、というような“楽器が鳴っている”感じがする。
インストゥルメンタル曲(#6 ten ton take、#10 snake hips)を聴くと、それがより実感できる。
このアルバムには別バージョン(↓)があり、

見ての通りジャケットが異なっていて、収録曲も若干違っている。
具体的に言うと、こちらには
# Midnight at the oasis
# World keep spinning
の2曲が収録されていない。
# Midnight at the oasis (「真夜中のオアシス」)は、Maria Muldaur のカバー。
ここではオリジナルに近いアレンジのものが収録されているが、
のちに曲の冒頭でシャウトするアレンジのものがリリースされた(後述)。
今では、そちらのほうがよく知られている印象だ。
その2曲の代わりに
# los burritos
というインストゥルメンタルが入っているのだが、これは曲というよりもインタールードのようなもの。
スタジオでメンバーたちがジャムっている様子を録ったような曲だ。
どちらを買ったらよいか、と尋ねられたら、迷わず冒頭の写真のほうをおすすめする。
【関連シングル】
具体的に言うと、こちらには
# Midnight at the oasis
# World keep spinning
の2曲が収録されていない。
# Midnight at the oasis (「真夜中のオアシス」)は、Maria Muldaur のカバー。
ここではオリジナルに近いアレンジのものが収録されているが、
のちに曲の冒頭でシャウトするアレンジのものがリリースされた(後述)。
今では、そちらのほうがよく知られている印象だ。
その2曲の代わりに
# los burritos
というインストゥルメンタルが入っているのだが、これは曲というよりもインタールードのようなもの。
スタジオでメンバーたちがジャムっている様子を録ったような曲だ。
どちらを買ったらよいか、と尋ねられたら、迷わず冒頭の写真のほうをおすすめする。
【関連シングル】
Back To Love

特筆すべきは、Ray Hayden(ここでは Opaz 名義でクレジットされている)の手によるリミックスが収録されていることだ。
クラブで映えるメロウな味付けは、さすが Ray Hayden! と嬉しくなってしまう。
そして、シングルでしか聴けない佳曲 # Baby don't use me 。
なぜアルバムに収録されなかったのか分からないくらい、ファンキーでカッコいい。
フリーキーに吹きまくるサックスがまた、素晴らしい。
Midnight At The Oasis

上で挙げたとおり、 Maria Muldaur の名曲のカバー。
曲のはじめに、N'dea Davenportの「Midnight!」というシャウトが入っていて、爽快なアレンジとなっている。
ラジオでよくかかるのは、こちらのバージョンが多い。
Radio Edit(ショートバージョン)とエクステンド(フルバージョン)、それにRay Hayden(Opaz名義)とRoger Sanchezそれぞれの手による
二つのリミックスを収録。
ラジオでよくかかるのは、こちらのバージョンが多い。
Radio Edit(ショートバージョン)とエクステンド(フルバージョン)、それにRay Hayden(Opaz名義)とRoger Sanchezそれぞれの手による
二つのリミックスを収録。
#2 は、フルバージョンとは言いながら、やや冗長な印象。ショートバージョン(#1)でも曲は十分表現されていると思える。
サックスソロがあるのだが、どちらにもきちんと入っている。
ただ、曲のきちんとしたエンディングは、フルバージョンでしか聴けない。
ショートバージョンではフェードアウトで処理されているからだ。
リミックス二つは、どちらも原曲の輪郭を残し、大ナタを振るった感じはない。
Ray Haydenのほうは、ギターやシンセサイザーなどでフレーズを付加して奥行きを出したもの。
対しRoger Sanchezは、クラブを意識したようなハウス的感じに仕上がっている(今の耳で聴くと、古さは否めないが)。
Spend Some Time

ベースのAndrewのペンによる 、アルバムの中盤でひときわ爽やかな印象を残す曲のシングルカット。
アルバム収録バージョンよりも装飾が増え、またN'deaのコーラスも多めに入って豪華な感じになったものが収録されている。
例によって Radio Edit(ショートバージョン)とエクステンド(フルバージョン)、別々のプロデューサーによる二つのリミックスを収録。
Simonのギターソロは、フルバージョンの方にしか入っていない。また、フルバージョンの終盤で聴かれるN’deaのアカペラは、はっとさせられる。
#3のpiano mix はその名の通り、イントロからピアノをフィーチャーしてまったく印象の違うものにしている
・・・ように思われたが、それは曲の冒頭だけ(このまま行けばいいのに・・・)。
80年代的なチープな電子音を混ぜて、ハウスっぽく仕上げているものの、やはり反復の仕方などに時代を感じさせる(苦笑)。
うーん・・・惜しい。
#4のsweet club mix は、「スイート」とは名ばかりの、冒頭から無骨な機械音満載で、全く違った印象。
・・・ように思われたが、それは曲の冒頭だけ(このまま行けばいいのに・・・)。
80年代的なチープな電子音を混ぜて、ハウスっぽく仕上げているものの、やはり反復の仕方などに時代を感じさせる(苦笑)。
うーん・・・惜しい。
#4のsweet club mix は、「スイート」とは名ばかりの、冒頭から無骨な機械音満載で、全く違った印象。
調性を失わせたバックトラックにヴォーカルトラックだけを載せ、“攻めている” 感じのリミックス。
中盤からシンセソロやスクラッチなどが入るが、なかなかクール。
このシングルには別バージョンがあり、

↑のものは2枚のCDが入れられるケースになっている。
しかし入っているCDは1枚で、もう一枚はダミー(紙製のディスク)。
Spend Some Timeに限らず、この頃の彼らは、1曲につきシングルを2枚切っている。
1枚はシングル2バージョン+リミックス2バージョン(計4曲)。
もう1枚はタイトルトラック+アルバム曲のライブ音源、という仕組みだ。
↑のものは、 Spend Some Time のRadio Edit(ショートバージョン)を冒頭に、他3曲は
# Stay This Way 、# People Get Ready 、# Midnight At The Oasis のライブ音源だ。
2枚ケースは、2枚とも買った人が両方をひとつに収められるよう配慮(あるいは買わせる戦略?)したものなのだろう。
(いずれにしても、ヴァイナルはもちろんCDも売れない現在では、無用の工夫となってしまったが・・・)
中盤からシンセソロやスクラッチなどが入るが、なかなかクール。
このシングルには別バージョンがあり、

↑のものは2枚のCDが入れられるケースになっている。
しかし入っているCDは1枚で、もう一枚はダミー(紙製のディスク)。
Spend Some Timeに限らず、この頃の彼らは、1曲につきシングルを2枚切っている。
1枚はシングル2バージョン+リミックス2バージョン(計4曲)。
もう1枚はタイトルトラック+アルバム曲のライブ音源、という仕組みだ。
↑のものは、 Spend Some Time のRadio Edit(ショートバージョン)を冒頭に、他3曲は
# Stay This Way 、# People Get Ready 、# Midnight At The Oasis のライブ音源だ。
2枚ケースは、2枚とも買った人が両方をひとつに収められるよう配慮(あるいは買わせる戦略?)したものなのだろう。
(いずれにしても、ヴァイナルはもちろんCDも売れない現在では、無用の工夫となってしまったが・・・)










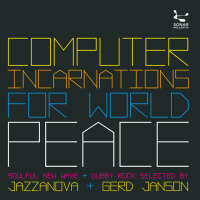

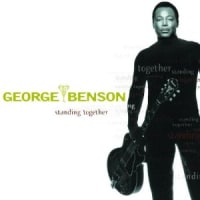



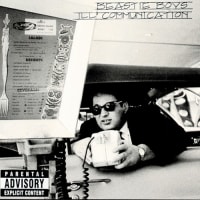


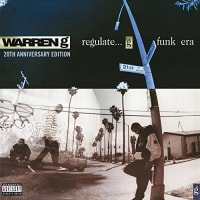
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます