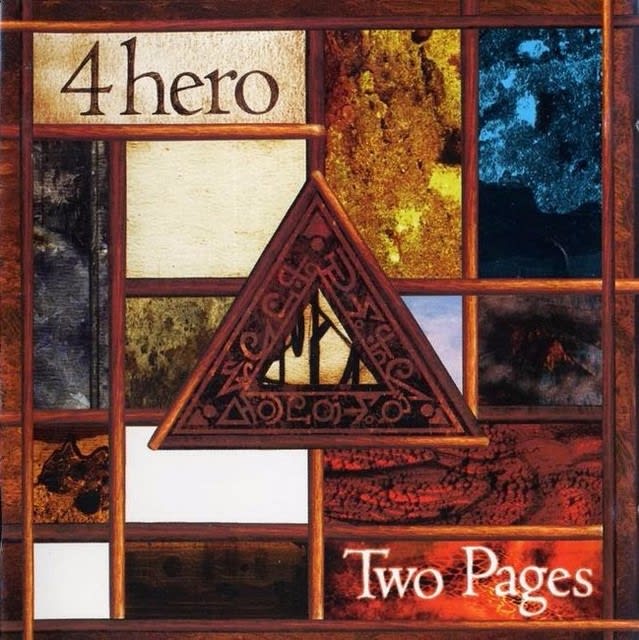JAZZANOVA と、Gerd Janson による選曲のコンピレーションアルバム。
Gerd Janson はドイツのDJ。JAZZANOVA もドイツを活動拠点とするグループなので、同郷の仲間なのだろう。
本作は、彼らが選曲したコンピレーションアルバム。
「Techno / Electronica」に分類したが、楽曲は聴けば分かる通り、バキバキのデジタルサウンドではなく
アナログシンセを多用した、いわば「レトロな」黎明期のテクノサウンドだ。
アルバムのリーフレットを見ると、楽曲の初出は70年代後半~80年代。
明らかに「そういうコンセプト」をもって作られたアルバムだと理解できる。
ヴォーカル無しの楽曲が大半にもかかわらず、どこか「人間の暖かさ」みたいのを感じることができる。
アルバムジャケットにも「Soulful New Wave + Dubby Rock」とある。
おそらく、この辺の音楽はあまりスポットが当たっていなかったんじゃなかろうか。
けれどこの雰囲気は、たしかに90年代のアシッド・ジャズに通じる。
この辺を掘り起こしたJAZZANOVA は、やはりさすがと思える。