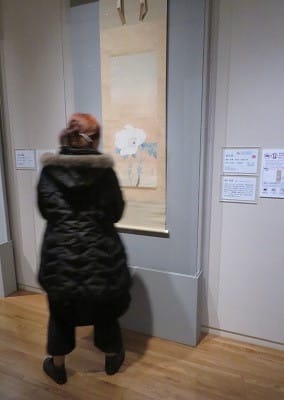京都の北西の端っこ・金閣寺の近くにある堂本印象美術館で企画展「絵になる姿」が行われています。「装い上手な少女、婦人、舞妓たち」というサブタイトルで表現されているように、京都らしい写実的で繊細な女性像をたっぷり味わえる構成に仕上がっています。
- 大正~平成に京都で活躍した画家の作品が中心、四条派の伝統の継続を感じさせる
- 和装の色彩豊かな表現が素晴らしい作品に見応え、モデルの表情と実によく調和させている
- 同時開催の館蔵レクション展「印象の女性像」では、堂本印象の画風の変化が楽しめる
近代以降の京都画壇の作品の展覧会では定評がある美術館です。建物の奇抜なデザインに負けず劣らず、中身も濃厚です。
堂本印象美術館は、入館すると建物の外壁にそって設けられているスロープを通って2Fの企画展の展示室に向かいます。このスロープも展示スペースになっており、サイズの小さい作品を間近に鑑賞することができます。三輪良平による都をどりポスター原画が見応えがあります。
【国立美術館所蔵作品総合目録検索システムの画像】 菊池契月「朝爽」京都国立近代美術館蔵
2Fの企画展示室はサイズの大きい作品が余裕をもって展示されています。菊池契月(きくちけいげつ)は幸野楳嶺の門下で竹内栖鳳の弟弟子にあたります。竹内栖鳳と並んで近代京都画壇の本家本流の写実的で清楚な画風が魅力です。「朝爽」はタイトルのようにとても爽やかなタッチに仕上がっています。女性の背後の柱に生けられた朝顔が、爽やかさをさらに強調しています。1937(昭和12)年の作品です。
【国立美術館所蔵作品総合目録検索システムの画像】 三谷十糸子「朝」京都国立近代美術館蔵
三谷十糸子(みたにとしこ)は、少女や美人画を描き続けた昭和を代表する女流画家です。1933(昭和8)年の作品「朝」は、うさぎの世話をする少女を描いています。少女の赤い着物がとても明るく、少女の元気さがストレートに伝わってきます。
【国立美術館所蔵作品総合目録検索システムの画像】 磯田又一郎「夏座敷」京都国立近代美術館蔵
菊池契月に師事していた磯田又一郎の「夏座敷」は1936(昭和11)年の作品です。座敷に冷菓子を運ぶ女中見習のような少女を描いています。青い着物がとても爽やかで、こちらも元気にあふれた作品です。
【国立美術館所蔵作品総合目録検索システムの画像】 由里本景子「娘」京都国立近代美術館蔵
由里本景子(ゆりもとけいこ)の「娘」は、花街を志した少女が三味線を師匠に習う前の様子でしょう、緊張の一瞬をとらえています。師匠の上村松園から受け継いだであろう、少女のとても真剣な眼差しの描写が印象的です。1936(昭和11)年の作品です。
三作品とも描かれたシーンは異なりますが、いずれも戦前の古き良き時代の趣を見事に今に伝えています。素晴らしい名品です。
【国立美術館所蔵作品総合目録検索システムの画像】 三輪良平「八朔」京都国立近代美術館蔵
三輪良平(みわりょうへい)は、戦後から平成にかけて活躍した日本画家です。この展覧会のチラシの表紙にも採用されている「八朔(はっさく)」は、まだ新しい2003年の作品ですが、京都国立近代美術館が所蔵している評価の定まった作品です。
八朔とは、京都の花街で毎年8/1に行われる夏の風物詩で、芸妓・舞妓が日頃世話になっている芸事の師匠にあいさつ回りをする行事です。黒の正装でびしっと決めた芸妓三人が、師匠への挨拶の順番を待っているのでしょうか、街角で佇む様子を描いています。芸妓の表情はとても充実しており、花街での仕事をとても楽しんでいるように見えます。とても華やぎのある名品です。
「はっさく」と言えば果物の方が有名ですが、元は旧暦8/1を指します。朔日とは毎月1日のことで、果物のはっさくも8/1頃から食べ始めたことが由来とされているようです。でも旬の季節とは合いません。別の由来があるのでしょうか。
2Fの企画展示室から1Fにおりると、奥の新館でコレクション展「印象の女性像」を鑑賞できます。堂本印象は、戦前までは伝統的な日本画表現だけでしたが、戦後になって西洋絵画や抽象画のような表現も行うようになります。
【堂本印象美術館公式サイトの画像】 堂本印象「木華開耶媛」
【堂本印象美術館公式サイトの画像】 堂本印象「或る家族」
「木華開耶媛」は1929(昭和4)年、「或る家族」は1949(昭和24)年の作品で、いずれも印象の代表作です。堂本印象は、ピカソのように画風の変化を味わえるとても興味深いアーティストです。
こんなところがあります。
ここにしかない「空間」があります。
美人はいつの時代も世相を示す
________________
<京都市北区>
京都府立堂本印象美術館
特別企画展
絵になる姿 -装い上手な少女、婦人、舞妓たち-
【美術館による展覧会公式サイト】
主催:京都府、京都府立堂本印象美術館、京都新聞
会期:2019年4月3日(水)~5月19日(日)
原則休館日:月曜日
入館(拝観)受付時間:9:30~16:30
※会期中に展示作品の入れ替えは原則ありません。
※この展覧会は、今後他会場への巡回はありません。
※この美術館は、コレクションの常設展示を行っていません。企画展開催時のみ開館しています。
◆おすすめ交通機関◆
地下鉄烏丸線「今出川」駅下車、3番口から「烏丸今出川」バス停で京都市バスに乗り換え、
「立命館大学前」下車、徒歩1分
JR京都駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:45分
京都駅→地下鉄烏丸線→今出川駅→烏丸今出川→市バス59系統→立命館大学前
【公式サイト】 アクセス案内
※京都駅から直行するバスもありますが、地下鉄とバスを乗り継ぐ方が、時間が早くて正確です。
※この施設には駐車場はありません。
※道路の狭さ/渋滞/駐車場不足により、健常者のクルマによる訪問は非現実的です。
________________
→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について
→ 「美の五色」 サイトポリシー
→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal