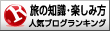東京スカイツリーのすぐ近くにあるたばこと塩の博物館に行ってきました。浮世絵や江戸絵画の蒐集軌跡をたどる「実業と美術 たば塩コレクションの軌跡」展では、企業ミュージアムとして充実した名品をたっぷりと堪能できます。
- 風俗画や浮世絵コレクションは定評通り、江戸時代の風俗画の流れをほぼ俯瞰できる
- 国営ながらも宣伝に力を入れた専売事業の歴史は、”親方日の丸”を感じさせない
- 世界のタバコと塩の歴史を学べる常設展も必見、充実した大人の社会科見学ができる
たばこは、現代では健康への影響からとても難しい事業運営に迫られていますが、嗜好品の花形として一時代を築いていたことがとてもよくわかります。そんな歴史を伝える展示はきちんと構成されています。
大阪のたばこ展覧会に出品された刻みたばこ(写真撮影OK)
たばこと塩の博物館、通称「たば塩」は、JT・日本たばこ産業株式会社が運営する企業ミュージアムです。1978(昭和53)年に渋谷で開設され、2015年に現在地に移転しました。公園通りの渋谷東武ホテルの前にあった煉瓦造りの建物を記憶している方もいらっしゃるでしょう。
日本たばこ産業は1985(昭和60)年に、国営企業であった日本専売公社が民営化される形で発足しました。昭和末期、国鉄や電電公社と共に民営化が進められていた時代です。日本では明治末から昭和末まで、たばこと塩の事業は国によって独占されていました。専売という用語は、現在30歳代までの若い世代の人にとってはすでに死後でしょう。「せんばい」とフリガナをつけた方がよいかとも思ったほどです。
JTの調査によると、日本の成人男性の喫煙率はピーク時の1966(昭和41)年に83%ありました。その後一貫して減少を続け、2018年には27%になっています。女性は1966年18%から2018年8%になっています。この数字から、たばこが嗜好品として昭和の高度経済成長期に一時代を築いていたことがわかります。
1998年にたばこのTVCMが中止になって以降は、たばこの存在感がさらに小さくなっています。企業ミュージアムは通常、最新の製品・サービスを前面に押し出してPRしますが、たばこ事業に関してはそれが事実上できません。そのため過去の活動に特化した特異な企業ミュージアムになっています。
国営企業と言うと、サービスは最悪というイメージが強いですが、たばこ事業は嗜好品を売るために宣伝にとても力を入れていました。お酒やコーヒーといった他の嗜好品と競争しないと売り上げが上がらず、国の税収にも貢献しないためです。競争原理が働いたことが国鉄や電電公社とは決定的に異なり、美術館に引けを取らない充実したコレクション形成につながります。
1933(昭和8)年の紀州徳川家の売立の様子
過去の喫煙具や喫煙風俗を描いた絵画の収集を始めたのは、1932(昭和7)年に専売公社の前身・大蔵省専売局長官に就任した佐々木謙一郎です。
キセルに詰めて喫煙する刻みたばこから紙巻たばこへと喫煙スタイルが変化する過渡期にあり、販促のためにたばこ製品や関連美術品の展覧会を頻繁に行っていたのです。当時は旧大名家からの所蔵美術品の売立ても相次いでおり、蒐集が行いやすかったという環境もコレクションの充実を後押ししました。
蒐集は日中戦争の勃発によりわずか5年ほどで終わりますが、短期間によくぞこれだけ集めた、という印象です。専売化される前にたばこ事業で巨万の富を築いた、村井吉兵衛の京都の別邸・長楽館を見た際も財力に驚かされました。たばこ事業はとてつもなく儲かる事業だったのでしょう。
【たば塩公式サイトの画像】ポスター「みのり」杉浦非水デザイン
佐々木は並行して製品の宣伝にも力を入れます。パッケージのデザインを三越の広告で名を馳せたデザイナー・杉浦非水に依頼し、斬新な商品イメージを形成することに成功します。
展示室の様子
蒐集した風俗画は江戸時代全般に渡っており、多色刷りの錦絵に至る絵画としての変遷も確認することができます。
【展覧会公式サイトの画像】 作者不詳「男女遊楽図屏風」
浮世絵が登場する以前の江戸時代前半の風俗画にも名品が揃っています。「男女遊楽図屏風」は、洛中洛外図のように生き生きとした人々の暮らしぶりが描かれています。喫煙が洒落た娯楽だったことがうかがえます。
【展覧会公式サイトの画像】 山崎龍女「縁台美人喫煙図」
山崎龍女(やまざきりゅうじょ)は、江戸時代半ばの女流絵師で、肉筆の美人画を多くのこしています。「縁台美人喫煙図」は美女が優雅にキセルを手に持つ姿を描いています。とてもかっこよく見えます。
【展覧会公式サイトの画像】 東洲斎写楽「肴屋五郎兵衛」
五郎兵衛を演じる役者は松本幸四郎です。写楽作品にしては落ち着いた印象です。幸四郎の一瞬の表情をリアルに描いたように見受けられます。
【展覧会公式サイトの画像】 風覆付き九曜文蒔絵手付たばこ盆
「風覆付き九曜文蒔絵手付たばこ盆」は、豪商が喫煙を楽しんでいた姿が目に浮かんでくるような豪華な蒔絵が目を引きます。中に置かれた磁器製の灰皿の文様とも見事に調和しています。
常設展示室「塩の世界」
たばこと塩に分けられた常設展示室もお忘れなく。塩については製法から用途まで驚きの連続でした。人間だけでなくすべての動物に塩が必要ということも知りませんでした。子供より大人の方が、”へぇ~”を連発すること間違いなしです。
こんなところがあります。
ここにしかない「空間」があります。
風俗画の舞台、江戸の暮らしを垣間見る
________________
<東京都墨田区>
たばこと塩の博物館
特別展
実業と美術 ~たば塩コレクションの軌跡~
【美術館による展覧会公式サイト】
主催:たばこと塩の博物館
会場:2F特別展示室
会期:2019年3月23日(土)~5月12日(日)
原則休館日:月曜日
入館(拝観)受付時間:10:00~17:30
※この展覧会は、撮影禁止作品以外の会場内の写真撮影が可能です。
※4/23以降の展示で一部作品/場面が入れ替えされます。
※この展覧会は、今後他会場への巡回はありません。
※この美術館は、コレクションの常設展示を行っています。
◆おすすめ交通機関◆
東京メトロ半蔵門/都営浅草線/京成線/東武スカイツリーライン「押上(スカイツリー前)」駅下車、 B2出口から徒歩12分
都営浅草線「本所吾妻橋」駅下車、A4出口から徒歩10分
東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅下車、正面口から徒歩8分
JR総武線「錦糸町」駅下車、北口から徒歩20分
JR東京駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:40分
JR東京駅(大手町駅)→メトロ東西線→日本橋駅→都営浅草線→本所吾妻橋駅
【公式サイト】 アクセス案内
※この施設には駐車場はありません。
※渋滞と駐車場不足により、健常者のクルマによる訪問は非現実的です。
________________
→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について
→ 「美の五色」 サイトポリシー
→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal