駅からウォーク 「東海道」9回目-3 2011/9/6
四日市宿へ(焼蛤)

矢田立場 ― 町屋橋 ― 富田一里塚 ― 四日市宿 ― JR四日市駅
13:40 14:00 15:15 16:35 16:50
員弁(いなべ)川に架かる町屋橋の袂に常夜灯が建っている。安永の伊勢雨宮常夜灯らしいが隣に立っている石碑には「○町屋川○○桑名郡」と書いてある。更に常夜灯には「中屋木材」とも彫ってある。これが文政元年に造られた常夜灯と云うが本当だろうか。

安永の伊勢雨宮常夜灯
常夜灯の先に江戸時代の町屋橋があったが今は無い。現在は国道1号の町屋橋を渡る。
橋の袂には両岸とも町屋橋の歴史を書いた案内板が立っているが、その中に気になる表現があった。
東海道名所図会(1797)の一部を紹介して「名物焼蛤、東冨田、小向の多所の茶店にて火鉢を軒端へ出し、松毬にて蛤を焼き旅客を饗す。桑名の焼蛤とはこれなり」と書いてある。
富田も小向もここより先にある地名で桑名方面ではない。??
後で分ったのだが、この町屋橋を渡った所に縄生の一里塚があったらしい。
尾張の宮宿の入口にあった伝馬町の一里塚が日本橋から89里目。そして縄生の一里塚が97里目になるという。その間の7つの一里塚は七里の渡しの分だとか。上手くできている。
ウーン残念! それを確認するためにも見ておきたかった。

多賀神社の常夜灯
今日は素晴らしい天気で雲一つ無い。こんな天気は街道歩きには適していないのだが、青空をバックにした、こんな物を見ると気分もスッキリする。
近くに神社など見えないが多賀神社の常夜灯らしい。伊勢に入り常夜灯に秋葉神社の文字が見られなくなったのは、伊勢神宮の影響か?
それでは近江に入るとどうだろう、秋葉山のある遠江とは親戚のような国だから。

朝明川
台風12号は紀伊半島の奈良、和歌山、三重県に甚大なる被害を出していった。ここも三重県だが被害の大きかった南部と違い余り影響は無かったようだ。それでも鈴鹿山系から流れ出る、この川などは河川敷の草がみな下流に靡いている。
川の上流に見える鉄橋はJR関西本線で、右に見える高架は伊勢湾岸自動車道だった。
冨田の一里塚はJRと三岐鉄道のガードを越した所にあった。桑名からここまで既に10km弱は歩いて来ているので、一里塚はまだかまだかと思っていたのでホットした。
だがここで気がついた。10kも歩いて一里塚無いのはおかしい、見落としてしまったのか。慌てて街道マップを戻したが見当たらない。今更あっても戻るわけには行かないと諦めたが。
家に帰り街道マップを丁寧に見たが載っていない。だが参考本には「町屋橋を渡った人家の前に「一里塚」以外は何も書かれていない碑がある」となっている。
そんな碑は見ても見なくても同じだが、HPに東海道をUPするとき一里塚の一覧表を作ろうと思っているので少々ガッカリした。尤もここまででも既に何ヶ所もの一里塚を見逃しているのだが。

冨田の一里塚
冨田小学校の入口に「明治天皇御駐輦(ごちゅうれん)跡」の石碑が立っていた。今までも明治天皇の立寄った石碑は飽きるほどあったが「御駐輦」と刻まれた石碑は少なかった。気づいたのは駿河の岩淵間の宿と遠江金谷宿の石畳、そしてここ冨田の立場の3ヶ所だった。
何故気になるかというと、天皇が乗った「輦」と言う乗物がどの様な物か知りたいと思っている。手押し車とか御輿のような物というが、実際はどんな形をした乗物だったのだろうかと興味がある。
ここの案内板には「車駕(しゃが)にて京都を出発し---」と書いてあるが、車駕の意味を調べても「天子が行幸の際に乗るくるま」ぐらいしか書いてない。

明治天皇御駐輦跡
他にもこの案内板には、焼蛤で興味を引く事が書いてあった。
「明治天皇は冨田で焼蛤をご賞味になされ---」となっている。桑名名物を何故桑名に着く前に食べるのか、これでは桑名の住民が怒ったのではないか心配になる。
焼蛤を調べていると、こんな事を書いてあるものもあった。
「冨田は焼蛤が名物の立場で、桑名はしぐれ蛤が名物」
さらに「その手はクワナの焼蛤」の解釈は、普通は「いくら上手いことを言っても、そんなことぐらいではひっかからない」とか「その手は食わぬぞ!」と食わないと桑名を引っ掛けたものとなっている。だがこんな解釈もあった
「西から来た旅人は冨田で名物焼蛤を食べたあと、桑名で再度勧められたとき「その手は桑名の焼蛤」と言ったとか。ウーンこれは説得力が有りますね。
私の解釈では桑名でも焼蛤は売ってはいたが、本場は冨田や小向だったのだと思う。
しかし冨田にも小向にも焼蛤を商っている店は目につかなかった。

力石
明治時代近くの寺を再建するとき、土台の石で力比べをしたとか。
大きい石は32貫(120kg)で、小さい方は5貫(19kg)だとか、私の力では小さい子供用の石を持ち上げる事はできるが、肩までは担ぎ上げる事は出来ないだろう。
四日市といえば私たちの年代では「公害」「大気汚染」そして「四日市喘息」など負の面を思い浮かべてしまうが、しかしご覧ください

ご覧のようにスモックなど無くすっきり晴れ渡った青空が見えてます。四日市では公害は過去のものになったのでしょうか。
今日は一日雲も無く陽射しが強いのので注意力が落ちていたのだろうか、それとも焼蛤を食べ損ねてガックリきているのか、また一里塚を見落としてしまった。
見落とした一里塚は三ツ谷の一里塚で平成13年に再建された塚だという。逃がした魚は大きいと言うが残念だった。

なが餅の笹井屋
三滝橋を渡るといよいよ四日市宿が始まる。橋の袂には名物のなが餅を商う笹井屋のお蔵のような店がある。
なが餅とは何ぞや?と調べてみたら
なが餅とは、餅の中に餡を入れて細長く伸ばして表面を焼いた焼餅のことで、分類上は焼餅で、商品名は「永餅」なのだそうだ。だからなが餅の名前は笹井屋しか使えないらしい。
このなが餅が有名になったのは藤堂高虎が足軽の頃出世払いで食べさせてもらい、後に出世をして津の城主になったとき、高虎が笹井屋の当主を召して、厚く遇したという。以来、参勤交代の折には必ず笹井屋に立ち寄ってなが餅を賞味したので、なが餅が有名になったとされる。
家康流ならば出世餅というところか。
このあたりに本陣などがあったはずだがとキョロキョロしながら歩いたが、そのような表示は見当たらなかった。出て来たの写真のような表示だった。

「すぐ 京いせ道」とか「すぐ 江戸道」と書いてある。これを見た弥次さんは
「喜多さんや、すぐ京道とあるから街道はこの道だろう」
と最初の角を曲ってしまった。
「この道は街道じゃなくて田舎道じゃないのかよー」と喜多さんがブツブツ言い出した。
弥次さんも少々不安になってきたとき前の方にお百姓が歩いていた。
「お百姓さんや チョット聞きたいのだが東海道はこの道かねー」
「東海道? これはおかしな事をお言っしゃる。お旅人さんが歩いてきた角に道しるべがあっただろうに」
「おーさ その道しるべに すぐ京道と書いてあったから、すぐ曲ってここに来たのだ」
「アハハ 四日市じゃー すぐは近くじゃなく まっすぐってことだに」
マーこんな調子になったかどうか。ともか「すぐ」とは「まっすぐ」のことらしい。
道標の立っている付近の道は江戸時代と変わっているようだが、どうも道標の指す方角が納得できなかった。

表参道 諏訪前アーケード
諏訪神社の横からは東海道はアーケードの中に続いていた。店から流れ出るクーラーの涼風が強烈な陽射しの中を歩いてきた体を冷やしてくれる。
アーケードを出ると四日市駅に通じる大通りに出る。右に行けば近鉄の駅、左はJRの駅なので当然左折してJRの駅に向う。駅まで行く間にあったマンホールの蓋で面白い図柄があったのでパチリ。

広重の描いた東海道の浮世絵の図柄を採用していた。しかもカラーで。
アーケードからJRの駅まで思っていた以上に時間が掛かった。距離もそうだが気分もだらけてきてしまったいる。
電車の予定時間は17時24分。駅に着いたのは16時50分。丁度良い待ち時間だ。トイレで上半身裸になり汗を拭い、着替えを済ませて駅の構内に。
アレー三重県一の都市なのに何となくガランとしている。乗降客も少ないし---
アッ良かった。キオスクはあった。ただ氷結は無かったので缶酎杯で乾杯!

JR四日市駅
蛇足:四日市から藤枝までの電車を紹介すると
四日市―<快速>―名古屋―<快速>―豊橋―<鈍行>―浜松―<鈍行>―藤枝
となります。豊橋から藤枝まで鈍行になっていますが、これは鈍行を選んだわけではありません。豊橋から藤枝間には快速が走っていないのです。
何故?と思いませか。もっと詳しく言えば静岡県に快速電車は走っていないのです。
イエ間違えました。ホームライナーなるものが通勤時間帯に朝2本、夜4本走っています。しかしこの電車は乗車整理券を310円で購入しなければなりません。
よって静岡県には無料の快速電車は皆無です。
その理由は明白です。静岡県にJRを脅かすような私鉄が走っていないからです。
愛知県には名古屋鉄道、三重県は近畿鉄道そして神奈川県には小田急電鉄が走っています。
JRも私企業ですので競争の原理が働いて、相手のいる場所ではサーにビスを厚くし、いない所はそれなりにする。それは仕方ない事だと諦めていました。
ところがリニア新幹線の建設資金のニュースを見てからその考えは変わった。
東京・名古屋間の建設費5兆円余をJR東海が全額自己負担で賄う計画を発表したのだ。
今までJRは私鉄との競争で大変だと思っていた。それなのにJR東海では5兆円もの資金を自己調達できるくらい内部保留金が出来ていたのだ。更に云うならばリニア新幹線は静岡県は通過しないので、その恩恵は少ない。
なら我慢する必要はない。「静岡県にも快速電車を走らせてくれ」と要求したい。
四日市宿へ(焼蛤)

矢田立場 ― 町屋橋 ― 富田一里塚 ― 四日市宿 ― JR四日市駅
13:40 14:00 15:15 16:35 16:50
員弁(いなべ)川に架かる町屋橋の袂に常夜灯が建っている。安永の伊勢雨宮常夜灯らしいが隣に立っている石碑には「○町屋川○○桑名郡」と書いてある。更に常夜灯には「中屋木材」とも彫ってある。これが文政元年に造られた常夜灯と云うが本当だろうか。

安永の伊勢雨宮常夜灯
常夜灯の先に江戸時代の町屋橋があったが今は無い。現在は国道1号の町屋橋を渡る。
橋の袂には両岸とも町屋橋の歴史を書いた案内板が立っているが、その中に気になる表現があった。
東海道名所図会(1797)の一部を紹介して「名物焼蛤、東冨田、小向の多所の茶店にて火鉢を軒端へ出し、松毬にて蛤を焼き旅客を饗す。桑名の焼蛤とはこれなり」と書いてある。
富田も小向もここより先にある地名で桑名方面ではない。??
後で分ったのだが、この町屋橋を渡った所に縄生の一里塚があったらしい。
尾張の宮宿の入口にあった伝馬町の一里塚が日本橋から89里目。そして縄生の一里塚が97里目になるという。その間の7つの一里塚は七里の渡しの分だとか。上手くできている。
ウーン残念! それを確認するためにも見ておきたかった。

多賀神社の常夜灯
今日は素晴らしい天気で雲一つ無い。こんな天気は街道歩きには適していないのだが、青空をバックにした、こんな物を見ると気分もスッキリする。
近くに神社など見えないが多賀神社の常夜灯らしい。伊勢に入り常夜灯に秋葉神社の文字が見られなくなったのは、伊勢神宮の影響か?
それでは近江に入るとどうだろう、秋葉山のある遠江とは親戚のような国だから。

朝明川
台風12号は紀伊半島の奈良、和歌山、三重県に甚大なる被害を出していった。ここも三重県だが被害の大きかった南部と違い余り影響は無かったようだ。それでも鈴鹿山系から流れ出る、この川などは河川敷の草がみな下流に靡いている。
川の上流に見える鉄橋はJR関西本線で、右に見える高架は伊勢湾岸自動車道だった。
冨田の一里塚はJRと三岐鉄道のガードを越した所にあった。桑名からここまで既に10km弱は歩いて来ているので、一里塚はまだかまだかと思っていたのでホットした。
だがここで気がついた。10kも歩いて一里塚無いのはおかしい、見落としてしまったのか。慌てて街道マップを戻したが見当たらない。今更あっても戻るわけには行かないと諦めたが。
家に帰り街道マップを丁寧に見たが載っていない。だが参考本には「町屋橋を渡った人家の前に「一里塚」以外は何も書かれていない碑がある」となっている。
そんな碑は見ても見なくても同じだが、HPに東海道をUPするとき一里塚の一覧表を作ろうと思っているので少々ガッカリした。尤もここまででも既に何ヶ所もの一里塚を見逃しているのだが。

冨田の一里塚
冨田小学校の入口に「明治天皇御駐輦(ごちゅうれん)跡」の石碑が立っていた。今までも明治天皇の立寄った石碑は飽きるほどあったが「御駐輦」と刻まれた石碑は少なかった。気づいたのは駿河の岩淵間の宿と遠江金谷宿の石畳、そしてここ冨田の立場の3ヶ所だった。
何故気になるかというと、天皇が乗った「輦」と言う乗物がどの様な物か知りたいと思っている。手押し車とか御輿のような物というが、実際はどんな形をした乗物だったのだろうかと興味がある。
ここの案内板には「車駕(しゃが)にて京都を出発し---」と書いてあるが、車駕の意味を調べても「天子が行幸の際に乗るくるま」ぐらいしか書いてない。

明治天皇御駐輦跡
他にもこの案内板には、焼蛤で興味を引く事が書いてあった。
「明治天皇は冨田で焼蛤をご賞味になされ---」となっている。桑名名物を何故桑名に着く前に食べるのか、これでは桑名の住民が怒ったのではないか心配になる。
焼蛤を調べていると、こんな事を書いてあるものもあった。
「冨田は焼蛤が名物の立場で、桑名はしぐれ蛤が名物」
さらに「その手はクワナの焼蛤」の解釈は、普通は「いくら上手いことを言っても、そんなことぐらいではひっかからない」とか「その手は食わぬぞ!」と食わないと桑名を引っ掛けたものとなっている。だがこんな解釈もあった
「西から来た旅人は冨田で名物焼蛤を食べたあと、桑名で再度勧められたとき「その手は桑名の焼蛤」と言ったとか。ウーンこれは説得力が有りますね。
私の解釈では桑名でも焼蛤は売ってはいたが、本場は冨田や小向だったのだと思う。
しかし冨田にも小向にも焼蛤を商っている店は目につかなかった。

力石
明治時代近くの寺を再建するとき、土台の石で力比べをしたとか。
大きい石は32貫(120kg)で、小さい方は5貫(19kg)だとか、私の力では小さい子供用の石を持ち上げる事はできるが、肩までは担ぎ上げる事は出来ないだろう。
四日市といえば私たちの年代では「公害」「大気汚染」そして「四日市喘息」など負の面を思い浮かべてしまうが、しかしご覧ください

ご覧のようにスモックなど無くすっきり晴れ渡った青空が見えてます。四日市では公害は過去のものになったのでしょうか。
今日は一日雲も無く陽射しが強いのので注意力が落ちていたのだろうか、それとも焼蛤を食べ損ねてガックリきているのか、また一里塚を見落としてしまった。
見落とした一里塚は三ツ谷の一里塚で平成13年に再建された塚だという。逃がした魚は大きいと言うが残念だった。

なが餅の笹井屋
三滝橋を渡るといよいよ四日市宿が始まる。橋の袂には名物のなが餅を商う笹井屋のお蔵のような店がある。
なが餅とは何ぞや?と調べてみたら
なが餅とは、餅の中に餡を入れて細長く伸ばして表面を焼いた焼餅のことで、分類上は焼餅で、商品名は「永餅」なのだそうだ。だからなが餅の名前は笹井屋しか使えないらしい。
このなが餅が有名になったのは藤堂高虎が足軽の頃出世払いで食べさせてもらい、後に出世をして津の城主になったとき、高虎が笹井屋の当主を召して、厚く遇したという。以来、参勤交代の折には必ず笹井屋に立ち寄ってなが餅を賞味したので、なが餅が有名になったとされる。
家康流ならば出世餅というところか。
このあたりに本陣などがあったはずだがとキョロキョロしながら歩いたが、そのような表示は見当たらなかった。出て来たの写真のような表示だった。

「すぐ 京いせ道」とか「すぐ 江戸道」と書いてある。これを見た弥次さんは
「喜多さんや、すぐ京道とあるから街道はこの道だろう」
と最初の角を曲ってしまった。
「この道は街道じゃなくて田舎道じゃないのかよー」と喜多さんがブツブツ言い出した。
弥次さんも少々不安になってきたとき前の方にお百姓が歩いていた。
「お百姓さんや チョット聞きたいのだが東海道はこの道かねー」
「東海道? これはおかしな事をお言っしゃる。お旅人さんが歩いてきた角に道しるべがあっただろうに」
「おーさ その道しるべに すぐ京道と書いてあったから、すぐ曲ってここに来たのだ」
「アハハ 四日市じゃー すぐは近くじゃなく まっすぐってことだに」
マーこんな調子になったかどうか。ともか「すぐ」とは「まっすぐ」のことらしい。
道標の立っている付近の道は江戸時代と変わっているようだが、どうも道標の指す方角が納得できなかった。

表参道 諏訪前アーケード
諏訪神社の横からは東海道はアーケードの中に続いていた。店から流れ出るクーラーの涼風が強烈な陽射しの中を歩いてきた体を冷やしてくれる。
アーケードを出ると四日市駅に通じる大通りに出る。右に行けば近鉄の駅、左はJRの駅なので当然左折してJRの駅に向う。駅まで行く間にあったマンホールの蓋で面白い図柄があったのでパチリ。

広重の描いた東海道の浮世絵の図柄を採用していた。しかもカラーで。
アーケードからJRの駅まで思っていた以上に時間が掛かった。距離もそうだが気分もだらけてきてしまったいる。
電車の予定時間は17時24分。駅に着いたのは16時50分。丁度良い待ち時間だ。トイレで上半身裸になり汗を拭い、着替えを済ませて駅の構内に。
アレー三重県一の都市なのに何となくガランとしている。乗降客も少ないし---
アッ良かった。キオスクはあった。ただ氷結は無かったので缶酎杯で乾杯!

JR四日市駅
蛇足:四日市から藤枝までの電車を紹介すると
四日市―<快速>―名古屋―<快速>―豊橋―<鈍行>―浜松―<鈍行>―藤枝
となります。豊橋から藤枝まで鈍行になっていますが、これは鈍行を選んだわけではありません。豊橋から藤枝間には快速が走っていないのです。
何故?と思いませか。もっと詳しく言えば静岡県に快速電車は走っていないのです。
イエ間違えました。ホームライナーなるものが通勤時間帯に朝2本、夜4本走っています。しかしこの電車は乗車整理券を310円で購入しなければなりません。
よって静岡県には無料の快速電車は皆無です。
その理由は明白です。静岡県にJRを脅かすような私鉄が走っていないからです。
愛知県には名古屋鉄道、三重県は近畿鉄道そして神奈川県には小田急電鉄が走っています。
JRも私企業ですので競争の原理が働いて、相手のいる場所ではサーにビスを厚くし、いない所はそれなりにする。それは仕方ない事だと諦めていました。
ところがリニア新幹線の建設資金のニュースを見てからその考えは変わった。
東京・名古屋間の建設費5兆円余をJR東海が全額自己負担で賄う計画を発表したのだ。
今までJRは私鉄との競争で大変だと思っていた。それなのにJR東海では5兆円もの資金を自己調達できるくらい内部保留金が出来ていたのだ。更に云うならばリニア新幹線は静岡県は通過しないので、その恩恵は少ない。
なら我慢する必要はない。「静岡県にも快速電車を走らせてくれ」と要求したい。












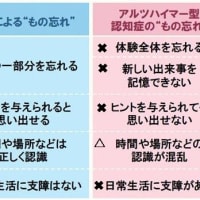




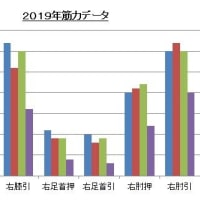
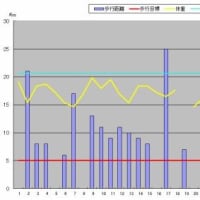
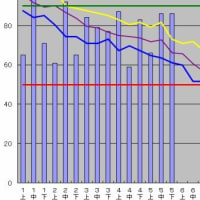
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます