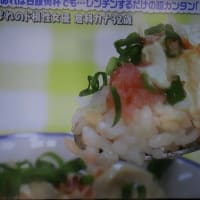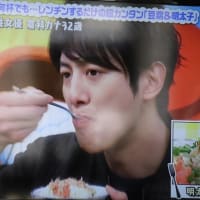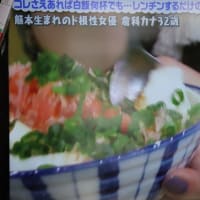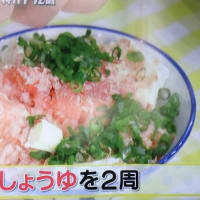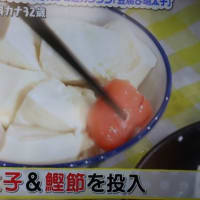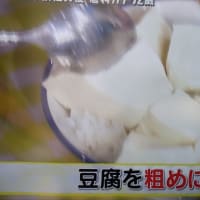生レバー禁止でこんにゃく人気…食感そっくり
(2012年6月30日14時14分 読売新聞)
6月限りで牛生レバーの提供が禁止となり、食感の似たコンニャクを代替品にする動きも出ている。
滋賀県近江八幡市の名物「赤こんにゃく」は、薄切りにすれば生レバーそっくり。同市の「水茎焼陶芸の里」のレストランでは、コース料理の中に「レバ刺し風の赤こんにゃく」を盛り込んだ。ネギを散らし、ゴマ油と塩で食べる。「見た目とのギャップや、さっぱりした味が好評です」とスタッフ。
コンニャク製造の「ハイスキー食品工業」(香川県三木町)は昨夏、トマトやイカスミの色素で加工した「マンナンレバー」を開発。業務用として居酒屋などに卸していたが、あまりの人気に、7月10日から家庭向けに60グラム358円で発売する予定だ=写真、同社提供=。同社は「カニ風味かまぼこのように食卓に定着すれば」。
★
1.私が考えた食の原則があります。
1.私が考えた食の原則があります。
(1) 住んでいる地域での近くでとれるものを食べる。(身土不二の原則)
(2) 長年食べてきたものを食べる。(継続食の原則)
(3) 先祖が食べてきたものを食べる。(先祖食の原則、日本では和食)
(4) 栄養バランスを良くする。(バランスの原則)
(5) 経済性を考える。(経済性の原則)
(6) 食性を考える。(食性の原則、人は穀物食)
(7) 安全性を考える。(安全性の原則)
(8) ハレの食とケの食(日常の食事)があり、ケの食事を大切にすべきであ る。(日常食の原則)(マスコミは晴れの食のみを取り上げている。月に1 ~2度は晴れに食良いのです。毎日になってはいけないのです。これが糖尿 病増加になっているのです。)
(9) 旬のものを食べる。(旬の原則)
(10)体質に合ったものを食べる。(体質の原則)
(11)食で何が重要かを考えて食する。(重要性の原則))
(12)主食は自給できる物でなければならない。(自給の原則)
(2) 長年食べてきたものを食べる。(継続食の原則)
(3) 先祖が食べてきたものを食べる。(先祖食の原則、日本では和食)
(4) 栄養バランスを良くする。(バランスの原則)
(5) 経済性を考える。(経済性の原則)
(6) 食性を考える。(食性の原則、人は穀物食)
(7) 安全性を考える。(安全性の原則)
(8) ハレの食とケの食(日常の食事)があり、ケの食事を大切にすべきであ る。(日常食の原則)(マスコミは晴れの食のみを取り上げている。月に1 ~2度は晴れに食良いのです。毎日になってはいけないのです。これが糖尿 病増加になっているのです。)
(9) 旬のものを食べる。(旬の原則)
(10)体質に合ったものを食べる。(体質の原則)
(11)食で何が重要かを考えて食する。(重要性の原則))
(12)主食は自給できる物でなければならない。(自給の原則)
これに最近(13)できるだけ生でたべる。
(14)「一物全体」、丸まま全体を食べること。
と言うのを追加しました。
| 日本人にとっての正しい食事とは何かー食の原則を知ることです | 2012-06-02 |
それは
「 食事の原則の一つ「生食」、生のまま食べることー漬け物、刺身の食文化 ...
blog.goo.ne.jp/.../e/72ba4b720102cba58eeb1581259b2aff - キャッシュ
2011年1月12日 – 食事の原則について以前の稿で「食事の原則の一つ「一物全体」、丸まま全体を食べること」と書いていましたが、もう一つ思い出した食事の原則が出てきました。 それは生で食べることです。 北極等で食物が育たないところでは、アザラシや ...」を見て思い出したのです。
もう一つ私のブログから
1. 食育と食事教育と食事の原則 - 正しい食事を考える会 - 楽天ブログ(Blog)
plaza.rakuten.co.jp/syokujikyouiku/diary/201007110001/ - 2010年7月11日 – 食育と食事教育と食事の原則. ... 食育と食事教育と食事の原則… (そのほか)楽天ブログ, 【ケータイで見る】 【ログイン】. 正しい政治を考える会. ホーム · 日記 · プロフィール · オークション · 掲示板 · ブックマーク · お買い物一覧. PR. カレンダー ...
私が考えた食事教育ですべきことを列挙してみます。
(1)食事の目的は何か
生きるため、健康のため、楽しむため、親睦のため、とういろいろあるが
日常食が重要でこれを主体に教えるべきと考えます。楽しみのフランス料理はあってもいいのです。しかし、それを日本人は日常食としてはいけないのです。
(2)何が食べられ、何を食べてはいけないのか、という食べ物の基本の知識
毒キノコ、ふぐの肝、農薬、食品添加物使用品、砂糖、塩、脂肪、
(3)食べられる物の中で何を食べるのか
主食はごはん、地産地消、野菜、栄養バランス、60種以上と言われるビタミン・ミネラル、旬のものを食べる
(4)経済的なものは何か(健全性)(自給と価格高、輸入か自給率向上か)
高くても国内産、健康によいもの等、大きな目で見た経済性、
(5)安全なもの、危険なものは何か(安全性)
残留農薬、ポストハーベスト、食品添加物、砂糖の過剰、塩の過剰、脂肪過多食品
(6)いつ食べるのか
1日三食、朝ごはんは大切、早寝早起き朝ごはん。
(7)食卓の揃え方(栄養バランスの良い食事とは)
一汁三菜、主食副菜主菜は3:2:1。少なくとも一汁一菜は確保を。
主役のごはんを忘れずに。
(8)費用は日常食はコストが安いもの、しかし、粗食(簡便食、手抜き料理、有り合わせ)であってはいけない。だから輸入に頼るのは腐敗防止、害虫防止策が必要になります。
外国に頼っていると食は何時でも輸出してくれるとは限らないのです。不況になったら外貨を稼げなくなり、命に関わる食糧も手に入れられなくなるのです。ですからこのことを十分経験している国は費用をかけても農業を大切にし自給率の向上を図っているのです。今安いからと飛びつくのはダンピングで自国の農業を破壊し、自国の滅亡につながるのです。結局は高くつくのです。
(9)作り方
料理法、(おいしく、新鮮なものを)
(10)どのように食べるのか
エチケット、マナー
(11)どれくらい食べるのか
必要カロリーは性別年齢、仕事量で異なる。1日1800キロカロリーとすると、
600mlの弁当箱、主食、主菜、副菜の割合は3:1:2でおよそ600キロカロリーなのでこれを三食間食なしで。間食したら食事を抑えるか、運動をする。
(12)誰と食べるのか家族団らんで、みんなと同じものを(好き嫌い無く)、
(13)何処で食べるのか
家庭で、
(14)何処で手に入れるのか外国製品を買うか、地産地消か。
外食、コンビニ・スーパーでインスタント食品。手料理か
(15)食品の知識
生産収穫方法、食べ方、料理方法、栄養素
・・・・・・
こう言う食事教育は本来家庭で教えるべき事ですが、この家庭の食の教育が破壊されてるのが日本の食の現状です。
(1)食事の目的は何か
生きるため、健康のため、楽しむため、親睦のため、とういろいろあるが
日常食が重要でこれを主体に教えるべきと考えます。楽しみのフランス料理はあってもいいのです。しかし、それを日本人は日常食としてはいけないのです。
(2)何が食べられ、何を食べてはいけないのか、という食べ物の基本の知識
毒キノコ、ふぐの肝、農薬、食品添加物使用品、砂糖、塩、脂肪、
(3)食べられる物の中で何を食べるのか
主食はごはん、地産地消、野菜、栄養バランス、60種以上と言われるビタミン・ミネラル、旬のものを食べる
(4)経済的なものは何か(健全性)(自給と価格高、輸入か自給率向上か)
高くても国内産、健康によいもの等、大きな目で見た経済性、
(5)安全なもの、危険なものは何か(安全性)
残留農薬、ポストハーベスト、食品添加物、砂糖の過剰、塩の過剰、脂肪過多食品
(6)いつ食べるのか
1日三食、朝ごはんは大切、早寝早起き朝ごはん。
(7)食卓の揃え方(栄養バランスの良い食事とは)
一汁三菜、主食副菜主菜は3:2:1。少なくとも一汁一菜は確保を。
主役のごはんを忘れずに。
(8)費用は日常食はコストが安いもの、しかし、粗食(簡便食、手抜き料理、有り合わせ)であってはいけない。だから輸入に頼るのは腐敗防止、害虫防止策が必要になります。
外国に頼っていると食は何時でも輸出してくれるとは限らないのです。不況になったら外貨を稼げなくなり、命に関わる食糧も手に入れられなくなるのです。ですからこのことを十分経験している国は費用をかけても農業を大切にし自給率の向上を図っているのです。今安いからと飛びつくのはダンピングで自国の農業を破壊し、自国の滅亡につながるのです。結局は高くつくのです。
(9)作り方
料理法、(おいしく、新鮮なものを)
(10)どのように食べるのか
エチケット、マナー
(11)どれくらい食べるのか
必要カロリーは性別年齢、仕事量で異なる。1日1800キロカロリーとすると、
600mlの弁当箱、主食、主菜、副菜の割合は3:1:2でおよそ600キロカロリーなのでこれを三食間食なしで。間食したら食事を抑えるか、運動をする。
(12)誰と食べるのか家族団らんで、みんなと同じものを(好き嫌い無く)、
(13)何処で食べるのか
家庭で、
(14)何処で手に入れるのか外国製品を買うか、地産地消か。
外食、コンビニ・スーパーでインスタント食品。手料理か
(15)食品の知識
生産収穫方法、食べ方、料理方法、栄養素
・・・・・・
こう言う食事教育は本来家庭で教えるべき事ですが、この家庭の食の教育が破壊されてるのが日本の食の現状です。
以上の食の原則から考えて生で食べることは食の原則の一つですが、しかし、それより上位の食の原則があるのです。
(2) 長年食べてきたものを食べる。(継続食の原則)→昔は牛そのものを食べていない
(3) 先祖が食べてきたものを食べる。(先祖食の原則、日本では和食)→先祖は食べていない
(4) 栄養バランスを良くする。(バランスの原則)→焼き肉店に行って、肉を主体に食べる食事はおいしさを追求して命を削っているようなもの、野菜、炭水化物を摂らないと栄養的には病気になる食事だ。
(5) 経済性を考える。(経済性の原則)→たまにはハレの食事は許されるでしょうが行き過ぎてはいけない。
(6) 食性を考える。(食性の原則、人は穀物食)ー肉食はコメや小麦が主食にできるほど取れない草原地帯の食事、家畜に草を食わして、成長させ、それを食べる。そういう食事しかできない地方の食事。人間の食事とは言えない。ライオン食、人間の食事は穀物食が基本です。
(7) 安全性を考える。(安全性の原則)→この安全性に欠けるのです。安全性が確保できる前に食べるべきではない。
(3) 先祖が食べてきたものを食べる。(先祖食の原則、日本では和食)→先祖は食べていない
(4) 栄養バランスを良くする。(バランスの原則)→焼き肉店に行って、肉を主体に食べる食事はおいしさを追求して命を削っているようなもの、野菜、炭水化物を摂らないと栄養的には病気になる食事だ。
(5) 経済性を考える。(経済性の原則)→たまにはハレの食事は許されるでしょうが行き過ぎてはいけない。
(6) 食性を考える。(食性の原則、人は穀物食)ー肉食はコメや小麦が主食にできるほど取れない草原地帯の食事、家畜に草を食わして、成長させ、それを食べる。そういう食事しかできない地方の食事。人間の食事とは言えない。ライオン食、人間の食事は穀物食が基本です。
(7) 安全性を考える。(安全性の原則)→この安全性に欠けるのです。安全性が確保できる前に食べるべきではない。
それに、何です。こんにゃくで足りるのならこんにゃくを食べるべきです。
わたしのこんにゃく案はソーメン、ラーメン、うどん、パスタ、の代替え品として糸こんにゃくを使うことです。ラーメンの半分を糸こんにゃくにしてみてください。おいしくてダイエット食です。