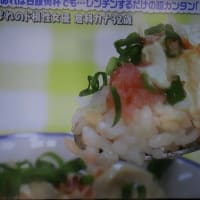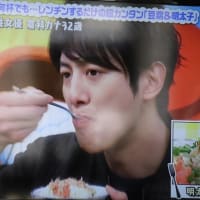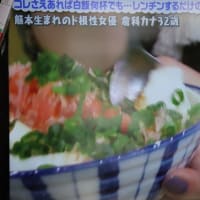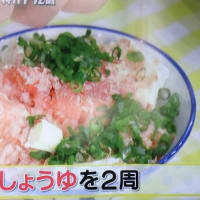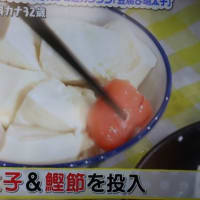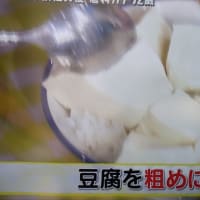食と農 改革の時、90億人の胃袋を満たせ
大転換の予兆(1)
- 2014/8/3 2:00 日本経済新聞
人は生きるために食べ、食べものは農が育む。日本の国内総生産(GDP)のうち農業は1%にすぎず、食べものは4割しか国内でまかなえない。2050年には90億人が胃袋を満たそうと競い合う世界が待っている。備えは十分か。市場の広がりを追い風にできるか。環境を守り、安全と安心をどう確保するのか。日本の食と農も変わらなければ生き残れない。
北極海に浮かぶノルウェー領スピッツベルゲン島。今年2月、岡山大教授の佐藤和広(56)は575種類の大麦の種を携えて、この永久凍土の地を踏んだ。日本から届ける初めての種だった。
目的地はスバールバル国際種子保管庫。米マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ(58)の財団による寄付などで08年に稼働した現代の「ノアの箱舟」だ。イネと麦は各15万種、トウモロコシは4万種……。世界中から集めた80万品種の種が零下17~18度で凍って眠る。
極北の地が選ばれたのは電源を失って冷却装置が壊れても永久凍土で零下4度を保てるためだ。海抜も130メートルあり津波や海面上昇に備える。
出番は戦争や干ばつ、未知の病虫害などに遭ったとき。「温暖化で南アフリカのトウモロコシ生産は30年までに3割減る」と同施設の研究者は警告する。種の多様性は究極の食糧安全保障だ。
岡山大はこれまで大麦の種を茨城県つくば市の農業生物資源ジーンバンクに預けてきた。種のほか微生物、牛や豚の受精卵など25万点超を冷蔵・冷凍して保存する世界5位の遺伝子貯蔵庫だ。
だが、水と食料が商品棚から消えた東日本大震災で食料危機への意識は一変した。震災と福島第1原子力発電所事故で「種のDNAは宇宙から注ぐ放射線で変化するほど繊細。保存場所を他にも確保した方がよいとの議論が学内で巻き起こった」と佐藤は明かす。
国連によると、世界の人口は14年の72億人から50年に96億人に増える。中国など新興国が豊かになり肉の消費や飼料穀物の輸入が急増、世界の食料需要は50年に00年比で1.6倍に拡大する。
世界の穀物生産量は1970~2010年の40年間で2倍強に増えた。今後もこのペースを保てれば食料問題は克服できる。種の多様性の保存を「守り」とすれば、収量を増やす「攻め」はバイオ技術が握っている。
地球上のあらゆる天候を再現できる場所がある。米ミズーリ州チェスターフィールド。害虫や除草剤に強く「フランケンクロップス(穀物)」とも呼ばれる遺伝子組み換え(GM)作物で世界の食料供給の未来を左右する米バイオメジャー、モンサントの研究所だ。
120の小さな部屋で温度や明るさ、湿度、雨の降る量を調節する。約1千人の科学者はトウモロコシや大豆の「遺伝子の地図」を読み解く。
日本モンサントによると、日本は穀物輸入の半分以上に当たる1600万トンの組み換え作物を輸入。主に家畜の餌として国内で使うトウモロコシの80%、大豆の83%を組み換えに頼り、人も肉を通じて口にしている。
全国農業協同組合連合会(JA全農)理事長の成清一臣(64)は輸入する穀物飼料が「ほとんどGM」と規制改革会議で認めた。米国が組み換えトウモロコシを作らなければ「日本の畜産はそれで全滅」と成清はいう。
イリノイ州モンマウスにあるモンサント試験農場を見学していた農家のマーク・シュルツ(53)はこう話す。「農業の基本的な考え方は生産性を高めてリスクを低くすることだ」。シュルツが育てた遺伝子組み換えのトウモロコシと大豆も日本に輸出されている。
輸入飼料への依存も響き、日本の12年度食料自給率は39%に下がった。中国の食肉加工会社が日本マクドナルドの「チキンマックナゲット」などに使用期限切れの鶏肉を使っていた問題の発覚も食の海外依存と安全性の揺らぎを印象づける。
農家の平均年齢66.5歳、滋賀県の面積に迫る耕作放棄地……。「90億人の食」を見据えて動く世界に比べ、日本は守りの食糧安保、攻めの生産性向上のどちらも心もとない。環太平洋経済連携協定(TPP)交渉とコメの減反廃止決定で、いよいよ追い詰められた日本の食と農が変わる兆しも見え始めた。
「車で走れば端から端まで1時間」。西部開発農産(岩手県北上市)社長の照井勝也(45)は事務所の机にB5判の紙を約60枚つなげた地図を広げた。総面積は710ヘクタール。日本の農地の平均2ヘクタールと比べ空前の規模だ。
今年だけで27ヘクタール増えた。高齢を理由に引退する農家が続出、数少ない農地の預け先として同社が頼られているからだ。
終戦後、47~50年に連合国軍総司令部(GHQ)主導の農地改革で1戸当たり約1ヘクタールの小さな農家が大量に生まれた。民主化の代償として、日本の農業の生産性と競争力は低下した。農地を西部開発農産に預けた地主は約650人。戦前の「1人の大地主と多数の小作農」とは異なる「1つの経営体と多数の地主」による新しい形で大規模化への回帰が始まった。
米コンサルティング大手A・T・カーニーは世界の外食・加工食品市場が09年の340兆円から20年に680兆円に倍増すると描く。今を逃せば日本の食と農は再生の好機を失う。(敬称略)
-
「食糧危機、技術進歩で回避できる」 (2014/8/3 2:00)
-
遺伝子組み換え あくなき追究 米種子メジャー (2014/8/3 2:00)
-
穀物の世界生産が最高に 13年度8%増 (2013/8/14 1:31)
-
世界のコメ、4分の3がアジア産 (2014/1/14 3:30)
-
アフリカでコメ需要増 世界輸入の3割 (2014/7/25 2:00)
類似している記事(自動検索)
-
(食と農)食糧危機は起きるか 技術進歩で回避可能 (2014/8/3付)
-
食と農 遺伝子組み換え あくなき追究 米の種子メジャー最前線 (2014/8/3 2:00)
-
西部開発農産、ベトナムで大規模コメ生産 (2014/5/27 6:00)
-
遺伝子組み換えカイコ、農水省が試験飼育を承認 (2014/2/6 20:30)
-
遺伝子組み換え作物、実は身近に (2014/1/12 2:00)
この記事を読んだ人によく読まれた記事
-
サイバー対策、カギ握る「善玉ハッカー」 (2014/8/3 3:30)
-
食と農 遺伝子組み換え あくなき追究 米の種子メジャー最前線 (2014/8/3 2:00)
-
食と農 「食糧危機、技術進歩で回避できる」 (2014/8/3 2:00)
-
70歳以上の医療費上限上げ、厚労省検討 (2014/8/3 1:27)