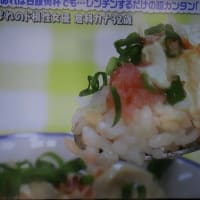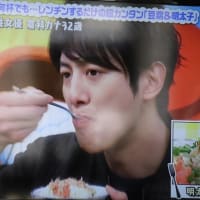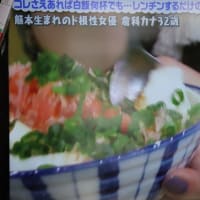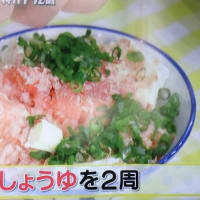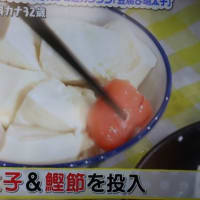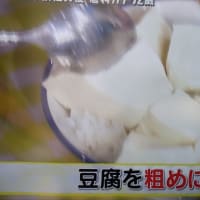「日本侵攻 アメリカの小麦戦略」 キッチンカーの謎
「キッチンカーは日本政府が行った事業ではなかったのですか?」
アメリカの小麦連合の曽根氏に、ズバリと聞いた。
「たしかに日本の厚生省の協力はありましたが、あれは当連合会の前身であるオレゴン小麦栽培者連盟が財団法人の日本食生活協会と契約して行ったわれわれの事業です。資金はアメリカ農務省から出ました。当時アメリカではPL480(Public Law 480)が制定されたばかりで、この公法にもとづいてアメリカ農産物の海外市場開拓に予算がつくようになったのです。キッチンカーについて詳しく知りたければ、日本食生活協会に行ってみたらいいですよ。厚生省の外郭団体で、たしか当時の関係者もいるはずです」
わたしたちは曽根氏の勧めにしたがって、東京・有楽町の日本食生活協会を訪ねることにした。副会長の松谷満子女史は気安く取材に応じてくれた。
「キッチンカーは、わたしどもが厚生省の後援を受けて運営しました。この協会はそもそもキッチンカーのために設立されたのです。運営資金ですか?それはもう昔の話ですから・・・」
言いづらそうなようすであったが、松谷女史は資金のほとんどがアメリカからでたものであることを認めた。
「それは信じられないほどの気前の良さでした。ピカピカの大型バスをポンと12台買ってくれたのですから。1台が400万円とか言っていました。そのほか、キッチンカーの運営には運転手さんの日当とか、ガソリン代やらで1台に1月60万円ほどかかりましたし、パンフレットもたくさん作ってくれました。そうですね、たしか6年間で1億数千万円かかったとか聞いています」
「それでは、キッチンカーはアメリカの小麦を宣伝するための事業だったのですか?」
私たちは単刀直入に聞いた。
「いやそうではありません。これはあくまで国民の栄養改善を目的に、厚生省と当協会が行なったもので、その点についてはアメリカ側も了解済みでした。粉食を奨励し、栄養改善を説けば、自然と小麦の消費は増えるわけでしょう。それがわかっているから彼らは、キッチンカーの運営をすべて私どもに任せたのです。ただ、実施する調理献立の中に最低一品だけは、小麦を使った物を入れてくれとは言われました。条件らしき物はそれだけです。キッチンカーは大変な評判を呼びましたから、アメリカの関係者も喜んだようです。バウムさんというオレゴン州の小作生産者団体の役員さんが何度も来ましたし、農務長官のベンソンという人が来てじきじきに視察し、キッチンカーに乗ってご満悦だったのをよく覚えています。どこかに写真があったと思いますが・・・」
松谷女史は古い資料を探し始めた。各地で歓迎を受けるキッチンカーの写真やそれを報じる新聞のスクラップの山の中に、ベンソン長官がキッチンカーに乗ってうどんを食べている写真があった。ハシの持ち方はぎこちないが、表情は底抜けに明るい。それにもう一枚、興味を引く写真があった。1956年5月18日、契約調印とただしがきされてある。
そこでは、あのリチャード・バウム氏が、日本食生活協会の林理事長とにこやかに握手をかわしていた。そして、その両脇では厚生省の木村事務次官と、アメリカ大使館のタモーレン主席農務官とが寄り添うように握手する二人を見守っている。日米両国の官民代表が手を取り合ってキッチンカーの事業契約を取り交わした決定的瞬間であった。当時の新聞のスクラップを見ると、いかにキッチンカーがもてはやされていたかがよく分かる。
見出しを並べると「動く台所が活躍」「走る料理教室がやってきた」「重宝がられる栄養指導車」とベタほめである。その中から典型的な報道を紹介して行こう。
「キッチンカーは日本政府が行った事業ではなかったのですか?」
アメリカの小麦連合の曽根氏に、ズバリと聞いた。
「たしかに日本の厚生省の協力はありましたが、あれは当連合会の前身であるオレゴン小麦栽培者連盟が財団法人の日本食生活協会と契約して行ったわれわれの事業です。資金はアメリカ農務省から出ました。当時アメリカではPL480(Public Law 480)が制定されたばかりで、この公法にもとづいてアメリカ農産物の海外市場開拓に予算がつくようになったのです。キッチンカーについて詳しく知りたければ、日本食生活協会に行ってみたらいいですよ。厚生省の外郭団体で、たしか当時の関係者もいるはずです」
わたしたちは曽根氏の勧めにしたがって、東京・有楽町の日本食生活協会を訪ねることにした。副会長の松谷満子女史は気安く取材に応じてくれた。
「キッチンカーは、わたしどもが厚生省の後援を受けて運営しました。この協会はそもそもキッチンカーのために設立されたのです。運営資金ですか?それはもう昔の話ですから・・・」
言いづらそうなようすであったが、松谷女史は資金のほとんどがアメリカからでたものであることを認めた。
「それは信じられないほどの気前の良さでした。ピカピカの大型バスをポンと12台買ってくれたのですから。1台が400万円とか言っていました。そのほか、キッチンカーの運営には運転手さんの日当とか、ガソリン代やらで1台に1月60万円ほどかかりましたし、パンフレットもたくさん作ってくれました。そうですね、たしか6年間で1億数千万円かかったとか聞いています」
「それでは、キッチンカーはアメリカの小麦を宣伝するための事業だったのですか?」
私たちは単刀直入に聞いた。
「いやそうではありません。これはあくまで国民の栄養改善を目的に、厚生省と当協会が行なったもので、その点についてはアメリカ側も了解済みでした。粉食を奨励し、栄養改善を説けば、自然と小麦の消費は増えるわけでしょう。それがわかっているから彼らは、キッチンカーの運営をすべて私どもに任せたのです。ただ、実施する調理献立の中に最低一品だけは、小麦を使った物を入れてくれとは言われました。条件らしき物はそれだけです。キッチンカーは大変な評判を呼びましたから、アメリカの関係者も喜んだようです。バウムさんというオレゴン州の小作生産者団体の役員さんが何度も来ましたし、農務長官のベンソンという人が来てじきじきに視察し、キッチンカーに乗ってご満悦だったのをよく覚えています。どこかに写真があったと思いますが・・・」
松谷女史は古い資料を探し始めた。各地で歓迎を受けるキッチンカーの写真やそれを報じる新聞のスクラップの山の中に、ベンソン長官がキッチンカーに乗ってうどんを食べている写真があった。ハシの持ち方はぎこちないが、表情は底抜けに明るい。それにもう一枚、興味を引く写真があった。1956年5月18日、契約調印とただしがきされてある。
そこでは、あのリチャード・バウム氏が、日本食生活協会の林理事長とにこやかに握手をかわしていた。そして、その両脇では厚生省の木村事務次官と、アメリカ大使館のタモーレン主席農務官とが寄り添うように握手する二人を見守っている。日米両国の官民代表が手を取り合ってキッチンカーの事業契約を取り交わした決定的瞬間であった。当時の新聞のスクラップを見ると、いかにキッチンカーがもてはやされていたかがよく分かる。
見出しを並べると「動く台所が活躍」「走る料理教室がやってきた」「重宝がられる栄養指導車」とベタほめである。その中から典型的な報道を紹介して行こう。