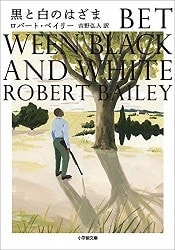父は僕の肩に手を置き「手遅れにならないうちにジェイソンを見つけなければ……」と言った。僕も父も、世界が終ろうとしていることに気づいていなかった。
1955年11月から1975年4月までおおよそ10年間続いたベトナム戦争さなかの物語で、1972年ノースカロライナ州シャーロットに元海兵隊員が刑務所から出所した。その男は、生まれ育った実家には立ち寄りもしないジェイソン・フレンチ。
バスターミナルからマリファナ吸引で退職を余儀なくされた元刑事の目撃電話を受けたのが、ジェイソンの父、殺人課刑事ビル・フレンチだった。ビルの家庭環境は、妻ガブリエル、ベトナムで戦死した長男のロバート、次男のジェイソン、そして大学受験を控えた高校生の末っ子ギビー。
どこの家庭でも何かしら問題を抱えていることが多い。フレンチ家も例外ではなかった。長男のロバートが戦死したとき、ロバートを溺愛している妻ガブリエルの一言「ジェイソンだったらよかったのに……」。この不用意な言葉が、ジェイソンを家族から離反させ悪の道へと追いやった。
両親と反目するジェイソンではあるが、弟のギビーにとっては大事な兄なのである。ジェイソンをロバートに重ねて見ているギビーで、この物語は主にギビーを中心に展開されていく。
さて、重大な事件の発端となるのがジェイソンの女友達タイラ・ノリス殺人事件。当然のように親しいジェイソンに容疑がかけられる。ジェイソンの父が殺人課刑事のビルも当然のこととして捜査からか外される。
義憤にかられるのがギビーで、なんとか犯人を突き止めたいと頭を絞る。友人のチャンスの協力や憧れの美女ベッキー・コリンズとのファーストキスからファーストセックスまで思春期の瑞々しさも織り交ぜてある。
読者にはタイラ・ノリス殺人の犯人が明らかにされている。これには黒幕がいる。レーンズワース刑務所の地下二階に君臨するXという死刑囚の男。絶大な富と力をもつ。一部の看守は勿論、刑務所長まで自由に動かせる男なのだ。
このXが冴えない中年男に見える殺し屋リースに命じたものなのだ。動機? って他愛無いもので、ジェイソン、タイラ、サラ、ギビーがドライブ中、レーンズワース刑務所の囚人護送バスに追いつき並走してタイラが裸になったりして囚人たちの劣情を刺激し侮辱したというものなのだ。
とは言っても普通に考えれば、この程度で人まで殺すかというわけで、これはXの深謀遠慮でラスト近くで明らかになる。
ジェイソンの人物像も1968年3月のソンミ村虐殺事件再来かという小隊の狂乱事態に直面して、ジェイソンらの隊が33人の死体も発見、指揮を執っていた狂乱の中尉を半殺しの目にあわせた、上官に対する殴打は軍規違反になる。
軍はレヴェンワース連邦刑務所で10年服役するか、秘密保持契約書に署名して不名誉除隊を受け入れるかを迫った。これはいわゆるもみ消しで、裏にはこのジョン・G・ラフトナー中尉が陸軍参謀長の部下ラフトナー将軍の息子ということもあって厳しい判断につながった。
しかもジェイソンを殺さない代わりに薬物中毒にして不名誉除隊とした。しかし、すべての海兵隊員たちは、ジェイソンの功績を讃えていてこんな場面がある。
シャーロットにある新兵募集の事務所。18歳になれば志願できるので、ギビーも事務所前に車を停めて考え込んでいると、片腕のない採用係が手招きした。名札にはJ・マコーミックとある。
いろいろな話の中から父や兄の話になり、父は朝鮮戦争、兄ロバートはベトナムで戦死、どこの所属だの質問からロバート・フレンチと告げると採用係は「もう一人のお兄さんは、ジェイソン・フレンチかな」と言って新聞を滑らせた。
殺人と裁判所と勾留という文字が並ぶ下にジェイソンの写真があった。ギビーが思わず「兄はあの女の人を殺していません」と言った。「信じるよ」と採用係。そして言った。
「お兄さんにメッセージを伝えてほしい。第二十六海兵師団第二大隊ジョン・マコーミック中尉からだと伝えてくれ。私のことなどお兄さんは知らないだろうが、それはどうでもいい。彼のベトナムでの行動を知る海兵隊所属の全戦闘員の気持ちだと伝えてほしい」
「なんと伝えればいいのですか?」
「これだけだ」がらんとした部屋で椅子を引いた。瞬きして涙らしきものを払い、わけが分からず言葉もなく呆然と見ている僕の前でピンと背筋を伸ばし、残った方の腕で海兵隊員だった兄に敬礼した。
こういう場面は、わたしの琴線に触れ涙ぐむのが常なのだ。先の太平洋戦争では、わたしは十代の子供で戦場の経験はないが、戦争の経験はある。空から降る爆弾と焼夷弾のザーという音は耳に残っている。焼け野原になった大阪の街に、黒こげの死体も見た。航空母艦から飛来したグラマン戦闘機のパイロットが、遊びで機銃掃射をして銭湯の壁に大きな穴をあけたことも。ついつい思い出してしまう。
その反面、甘い思春期も。ギビーとベッキーのデート。
「プリンストン大学のことは二か月前に両親から知らされた。奨学金をもらっても無理だって」とベッキー
「それはがっくりくるね。残念だ」とギビー
「それが人生よ。でもね。おかげで自分の力でなんとかできることと、できないことの違いがわかった。ここに連れてきたのはそれが理由」
「どういうことかわからないな」
「そう?」
ひんやりとした風が吹きつけ、髪が顔にかかる。彼女は僕がうろたえているのを見てほほ笑んだ。
「キスして、ギビー」
「本気?」
「二年生のときからあなたにキスしたいと思ってた」
「でも、そんなこと言ってくれなかったじゃないか……全然、知らなかった」
「でも、いまはもうわかったでしょ」
こういう会話をみていると、いつの時代も男の子はウブで、女の子のオマセは変わらない。
ベッキーが進み出たので、ぼくは彼女にキスをした。最初は軽く、やがてあまり軽いとは言えないキスまで発展した。
私がギビーなら絶対ベッキーを手放さないだろうなあと思う。こんな聡明な女性って滅多にいないからね。こういうエピソードを含みながら、家族の対立と和解を緻密な構成と文体で飽きることはない。
ただラストが気に食わない。すべてが一段落したあと、ギビーとベッキーの余情のある場面にしてほしかった。もう一つ気になることがあって、それは冒頭「僕(ギビー)も父も、世界が終ろうとしていることに気づいていなかった」のくだり。なんでわざわざこんな文言を入れたのだろうか。物語の流れから見てどうも死刑囚Xが政府機関のシンボルではないかと思ってしまう。ベトナム戦争で堕ちた政府の信用、著者は告発したかったのかも。
著者ジョン・ハートのウェブサイトより、
ジョン・ハートは、ニューヨーク・タイムズのベストセラー『嘘の王』、『ダウン・リバー』、『最後の子供』、『アイアン・ハウス』、『リデンプション・ロード』、『ザ・ハッシュ』の著者です。
連続小説で最優秀小説エドガー賞を受賞した歴史上唯一の作家であるジョンは、バリー賞、南部独立書店フィクション賞、イアン・フレミング・スチール・ダガー賞、南部図書賞、ノースカロライナ文学賞も受賞しています。
彼の小説は30の言語に翻訳され、70カ国以上で見つけることができます。元弁護人で株式仲買人であるジョンは、バージニア州の農場に住んでおり、フルタイムで執筆しています。