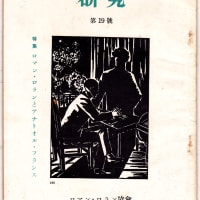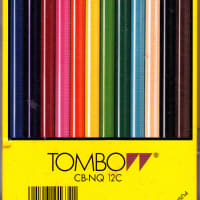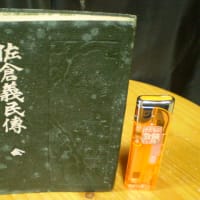次は伝馬騒動。
くりかえし昔のことを語るのは年寄りの常というけど、わたしも、新ネタを書くのがめんどうになって、昔の話を持ち出してきたのかもしれない。なにせ書いたのが8年前で、すっかり忘れてしまっています。
パソ通では、コメントが楽しくコメントを通して話が広がったり、各論に展開していくのだけど、コメントをのせるとめちゃめちゃ長くなるので、残念だけど、それはほとんどカットしました。
また、一揆の話は昔から人気がなく、すこしでも親しみやすいように、観光ガイドの形にして、藤子嬢などとふざけたガイドさんを出しておもしろおかしくしたのだけど、ごめんなさい。以下、コピー。
0 藤五郎 明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/25 00:52 コメント数:2
みなさん、こんにちは。
一揆観光の初代ガイドの藤子嬢です。
AKIさんが唐津の明和の大一揆を案内してくれたので、わたしも、同じく、
明和の大一揆を。これは、「伝馬騒動」とか「天狗騒動」などとも呼ばれて
います。
時は、明和元年(1764)12月末から翌年正月にかけて。立ち上がったお百姓は、
武蔵、上野、下野、信濃の中仙道沿いの村々から、なんと約20万人。
20万人といえば百姓一揆としては最大級でしょう。
この20万人が大挙して、江戸をめざして中山道を進軍。幕府もびっくり、お江戸
の町人もヒヤヒヤドキドキです。
原因はなんでしょう。中仙道沿いの村々に幕府が新たに課した助郷(すけごう)
役です。
街道の宿場町には、公家や幕府役人用の荷物の輸送制度として「伝馬」というの
がありました。人夫50人、馬50頭が常備してあったそうな(役人は無料で使える
特権があるそうな)。でも、年々、輸送する量は増え、「伝馬」だけではとても
用を足せない。で、そんな時には、近くの村々から、人夫や馬を徴集して、代わ
りを勤めさせたのですね。
くわしいことはわかりませんが、ま、「助郷」とは、宿場の伝馬が不足したとき
に、それを助ける村という意味くらいに考えておきましょうよ。
しかし、お百姓さんも大変ですね。。田んぼを耕したり、そのうえ、陸上輸送の
仕事までさせられるんだもの。宿場から遠く離れている村なんかも助郷に指定さ
れて、もし、人をよこせなっかったら、金を寄越せ、なんて言われたらしいわ。
まあ、固い話は、やめといて、まず一揆のスタート地点に参りましょう。
中仙道本庄宿。江戸の日本橋を起点にすると、板橋、蕨、浦和、大宮、上尾、桶
川、鴻巣 熊谷、深谷、そして10番目の宿が本庄宿になるの。今の埼玉県ね。
ふー、ここまでくるのに、もうつかれてしまったわ。やっぱり、年ね。やはり、
一揆観光のお勤めも老体にはきつくなってきちゃったわ。お客さん、今日は、
ここまでね。
藤子老嬢
RE:明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/25 13:52 06923へのコメント コメント数:1
>凄い!「内乱」といえる規模?AKIさんはこの人達のお弁当を心配してしま
>う(^^;)
弁当くらいは自前だよ。でも、足りなくなってもだいじょうぶさ。おれたち一揆
さまだから、道々、食料はだれかが提供してくれるでしょう(^^)。
>この一揆を唆したのは怪しい浪人さんかしら?
一揆の棟梁として獄門になったのは、本庄宿から南東5キロほどの所にある武蔵
国児玉郡関村(現埼玉県児玉郡美里村)の名主、兵内さん一人だから、この人が
仕掛け人だろうね。
でも、怪しい唆し浪人も、すぐそばにいて、この一揆のようすをじっと観察して
いたんだ。
名は山県大弐(だいに)。当時、上野国甘楽郡の小幡藩に身を寄せていました。
ここからも、一揆に参加したものは多かったのです。
この地方の伝説によると、この山県大弐のもとに、尊皇論者の竹内式部、藤井右
門がたずねてきて、3人でこう話し合ったということだ。
「ここの小幡藩主である織田氏は、信長公からの縁もあって朝廷の覚えもよい。
これを盟主として勤皇倒幕の軍をおこそうではないか。このように民衆の反乱が
あいついでいる現在、我々が一命を投げ打って先頭に立つなら、幕府を倒すの
は、暴風雨が枯れ木を倒すようなものだ」
でも、その2,3年後、山県、藤井は捕らえられて獄門、竹内は流罪になり、小
幡藩主織田信邦は出羽国に国替えになります(これが天童藩?)。
山県大弐は怪しい唆し浪人の先駆者だね(^^)
>助郷とは違うかもしれませんが、年貢の湊までの輸送なんかも、お百姓が自費
>でしているのですよね。大変な費用と労力なのに、ただですまそうなんてひど
>いですね。
そうよ。朝鮮からお客さんが来る、京都から公家さんが来る、とか何かある度に
助郷を徴発されたそうね。しかも、助郷を人間扱いしない柄の悪い役人もいる。
幕末になるけど、桜井常五郎という草莽の志士がいてね。この人も皇女和宮が江
戸にくる時、中山道で助郷として駕籠かつぎをしていたんだ。でも、生意気な役
人と喧嘩してね。ほんで、国を飛び出し、倒幕活動をすることになったそうだ
よ。
RE:明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/27 00:07 06934へのコメント コメント数:2
>20万人のうち死刑が一人?ということでもないのかしら。どうして獄門が一
>人なのか、
ええ!もっと百姓の首がほしいって?
さては武士の手先かあ?(^^)
この騒動で処罰されたのは、381人。名主、組頭、年寄役のもので半分を占めて
います。藤五郎みたいなスカンピンの無頼者は、はなから無視されていたのかな
あ。
獄門は兵内(ひょうない)1人。遠島3人、あと追放とかです。
一番多い処罰が過料(罰金刑)と手鎖で198人。次ぎ、役儀取り上げ119人
など。とにかく牢屋がいっぱいになって、溜りにも収容したそうだよ。獄死した
のも少なくなかったようだ。
一揆首謀者関係者の探索は火付け盗賊改がやるのかなあ?
関村の兵内さんがほんとに首謀者かどうかはわからないけども、幕府はとにかく
この兵内さんを獄門にして晒したのは事実で、地元には「義民兵内梟首の地」と
いう標識もあるようです。むろん、村人は手厚く回向し、現代でも、関村では、
「兵内おどり」というのが残っていたそうな。今、現在、まだ残っているかどう
かは知らないけど・・・。
>駕籠をかつぐって、大変なことだったと思うのです。肩の一点で駕籠と人の
>重みを支えるのですよ!こぶみたいな筋肉がなくてはできないですよね。
江戸時代の下層階級の人たちって、ええ体していたそうだね。
イギリスなんかでは、貴族がスポーツとかなんかして、立派な体をしていたそう
だけど、江戸の場合は、反対だなあ。
「黄金時代のギリシャ彫刻を理解しようとするなら、夏に日本を旅行する必要が
ある」とか「下層の者の間では、まるで体操選手を思わせるような、背が高く異
常に筋肉の発達したタイプにめぐりあう」なんて外国人も書いているようです
よ。(渡辺京ニ「逝きし世の面影」)
いなせな身のこなしというのも、やはり、しなやかで、鍛えられた身体から出て
くるものだよね。
いなせな奴というのは、最近、あまりいないなあ。としまるどんがそれに近い
ね。やっぱ、農作業で、きっと身体、鍛えているんだと思うね。
(2)明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/28 22:58 06921へのコメント コメント数:2
みなさん、こんにちは。
明和元年の秋、武蔵、上野、下野、信濃の国の中山道の宿駅に(板橋から和田宿
までの28の宿駅)に、幕府からお触れがあったそうです。
一揆の発生地、本庄宿にきたお触れは、次のようなもの。
「近年、中山道通行多くあいなり、本庄宿これまでの助郷高にては、人馬不足に
つき、このたび、村々ヘお代官両人の手代差し遣わし、村柄見分、さる戊年より
未年まで10か年、年貢割付、ならびに道中道法などこれを糾し、勤高をきめ、右
宿、助郷加え候間、心得ちがいこれなきよう、吟味うけるべきものなり。
11月 御勘定 安藤弾正
御目付 池田筑後 」
要するに、近頃、中山道の交通量が増え、今までの定助郷だけでは足らず、新た
に大幅に助郷を加えるから承知せよ、という通達です。
各宿場とも、200か村ほど新たに助郷に割り当てられるそうだ。
しかし、これらの村では、数年不作が続き、しかも、この年の春には、朝鮮使節
が来た時の接待費として100石につき3両1分2朱の税金をとられたばかり。
幕府がこの時、助郷を急増することになったのは、翌明和2年が日光東照大権現
の150年忌にあたっており、大名や公家の往来が激しくなると予想したためで
もあるそうな。
しかし、農民にとったら、たまったもんじゃあない。
「この上は、一人残らず江戸表にまかり出て、命限りに御免の御訴訟申すより
他なし」の声が高まる。
そして、ついに12月中旬のある日、次ぎのような張り紙が出る。
「来る12月16日、十条河原へ、15歳から60歳までの男子、1軒一人残らず必ず集
合されたい。もし、不参加の場合は、大勢で押しかけそのままではおかぬから覚
悟していてほしい」
さあ、集まるのだろうか?
伝馬騒動については、地元の人が書いた北沢文武「明和の大一揆」(鳩の森書
房)があります。史料としては、「民衆運動の思想」(岩波書店)に「狐塚千本
槍」という古文書が、また、日本庶民生活史料集成弟6巻(三一書房)にもいろ
いろ史料が出ています。
わたしは、北沢文武の「明和の大一揆」を参考にします。これ読みやすいですか
ら。
藤五郎 (3)明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/29 10:29 06955へのコメント コメント数:1
みなさん、こんにちはー。藤子です。
埼玉県の旅をつづけまーす。
明和元年12月16日、本庄宿の助郷に指定された村々約200村から1万人ほどが、
児玉郡の十条河原に集まってきました。ここは、県(?)の史跡になってるよう
で、農道に説明板が今でも立っているようです。まだまわりは農地ではないかし
ら。
20万一揆といわれる伝馬騒動は、この集会が始まりの合図となります。
「尚風録」という文書によると、張り紙は制札場だけでなく、立木、人の家、い
たるところに張られていたそうな。「もし、集まらなければ,焼き払うぞ」と書
かれては、一応、ぞろぞろ顔を出すよね。
さて、夜、十条河原に大勢集まったけども、唆した首謀者は姿は見せないもので
す。ただわいわいがやがやと騒ぐばかりで、まとまらない。
「尚風録」では、この時、百姓杢之助というものが、竹の先に鼻紙をさし、「東
西東西ー」とふりまわし、こういったそうだ。
「おのおの、さように動揺めされては、どんな相談もまとまらぬ。まず、静まり
候、しかるのち相談いたそう」
みんな、納得し、座る。
「今まで、ご伝馬を勤めなくても、露命をつなぎがたし。この上に、ご伝馬あい
勤めるものならば、渇命におよぶは必定なり。無二無三に御訴訟すべし。われ
は、70余歳、命を惜しいとは思わぬ。お詮議のときは、われ自ら、お咎めに出
る。」
だれかが口火をきらなくちゃいけないのよね。しかし、口火を切ったものに責任がま
わってくる。だれかが口火を切ると次々に意見がでます。次ぎのように決まります。
21日に本庄宿に再結集。その時には、各郡、各村々ごとの纏(まとい)を立
て、蓑笠を背負う。おおみそかまでに江戸に出て、大手門につめかけ、あくる元旦
に登城してくる老中、あるいは諸大名に訴訟しよう。
エイエイオー(^^)
この時の杢之助は、後、牢死しています。
兵内だけでなく、やはりいろんな人が心ならずも関わってしまうのですよね。
藤五郎
くりかえし昔のことを語るのは年寄りの常というけど、わたしも、新ネタを書くのがめんどうになって、昔の話を持ち出してきたのかもしれない。なにせ書いたのが8年前で、すっかり忘れてしまっています。
パソ通では、コメントが楽しくコメントを通して話が広がったり、各論に展開していくのだけど、コメントをのせるとめちゃめちゃ長くなるので、残念だけど、それはほとんどカットしました。
また、一揆の話は昔から人気がなく、すこしでも親しみやすいように、観光ガイドの形にして、藤子嬢などとふざけたガイドさんを出しておもしろおかしくしたのだけど、ごめんなさい。以下、コピー。
0 藤五郎 明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/25 00:52 コメント数:2
みなさん、こんにちは。
一揆観光の初代ガイドの藤子嬢です。
AKIさんが唐津の明和の大一揆を案内してくれたので、わたしも、同じく、
明和の大一揆を。これは、「伝馬騒動」とか「天狗騒動」などとも呼ばれて
います。
時は、明和元年(1764)12月末から翌年正月にかけて。立ち上がったお百姓は、
武蔵、上野、下野、信濃の中仙道沿いの村々から、なんと約20万人。
20万人といえば百姓一揆としては最大級でしょう。
この20万人が大挙して、江戸をめざして中山道を進軍。幕府もびっくり、お江戸
の町人もヒヤヒヤドキドキです。
原因はなんでしょう。中仙道沿いの村々に幕府が新たに課した助郷(すけごう)
役です。
街道の宿場町には、公家や幕府役人用の荷物の輸送制度として「伝馬」というの
がありました。人夫50人、馬50頭が常備してあったそうな(役人は無料で使える
特権があるそうな)。でも、年々、輸送する量は増え、「伝馬」だけではとても
用を足せない。で、そんな時には、近くの村々から、人夫や馬を徴集して、代わ
りを勤めさせたのですね。
くわしいことはわかりませんが、ま、「助郷」とは、宿場の伝馬が不足したとき
に、それを助ける村という意味くらいに考えておきましょうよ。
しかし、お百姓さんも大変ですね。。田んぼを耕したり、そのうえ、陸上輸送の
仕事までさせられるんだもの。宿場から遠く離れている村なんかも助郷に指定さ
れて、もし、人をよこせなっかったら、金を寄越せ、なんて言われたらしいわ。
まあ、固い話は、やめといて、まず一揆のスタート地点に参りましょう。
中仙道本庄宿。江戸の日本橋を起点にすると、板橋、蕨、浦和、大宮、上尾、桶
川、鴻巣 熊谷、深谷、そして10番目の宿が本庄宿になるの。今の埼玉県ね。
ふー、ここまでくるのに、もうつかれてしまったわ。やっぱり、年ね。やはり、
一揆観光のお勤めも老体にはきつくなってきちゃったわ。お客さん、今日は、
ここまでね。
藤子老嬢
RE:明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/25 13:52 06923へのコメント コメント数:1
>凄い!「内乱」といえる規模?AKIさんはこの人達のお弁当を心配してしま
>う(^^;)
弁当くらいは自前だよ。でも、足りなくなってもだいじょうぶさ。おれたち一揆
さまだから、道々、食料はだれかが提供してくれるでしょう(^^)。
>この一揆を唆したのは怪しい浪人さんかしら?
一揆の棟梁として獄門になったのは、本庄宿から南東5キロほどの所にある武蔵
国児玉郡関村(現埼玉県児玉郡美里村)の名主、兵内さん一人だから、この人が
仕掛け人だろうね。
でも、怪しい唆し浪人も、すぐそばにいて、この一揆のようすをじっと観察して
いたんだ。
名は山県大弐(だいに)。当時、上野国甘楽郡の小幡藩に身を寄せていました。
ここからも、一揆に参加したものは多かったのです。
この地方の伝説によると、この山県大弐のもとに、尊皇論者の竹内式部、藤井右
門がたずねてきて、3人でこう話し合ったということだ。
「ここの小幡藩主である織田氏は、信長公からの縁もあって朝廷の覚えもよい。
これを盟主として勤皇倒幕の軍をおこそうではないか。このように民衆の反乱が
あいついでいる現在、我々が一命を投げ打って先頭に立つなら、幕府を倒すの
は、暴風雨が枯れ木を倒すようなものだ」
でも、その2,3年後、山県、藤井は捕らえられて獄門、竹内は流罪になり、小
幡藩主織田信邦は出羽国に国替えになります(これが天童藩?)。
山県大弐は怪しい唆し浪人の先駆者だね(^^)
>助郷とは違うかもしれませんが、年貢の湊までの輸送なんかも、お百姓が自費
>でしているのですよね。大変な費用と労力なのに、ただですまそうなんてひど
>いですね。
そうよ。朝鮮からお客さんが来る、京都から公家さんが来る、とか何かある度に
助郷を徴発されたそうね。しかも、助郷を人間扱いしない柄の悪い役人もいる。
幕末になるけど、桜井常五郎という草莽の志士がいてね。この人も皇女和宮が江
戸にくる時、中山道で助郷として駕籠かつぎをしていたんだ。でも、生意気な役
人と喧嘩してね。ほんで、国を飛び出し、倒幕活動をすることになったそうだ
よ。
RE:明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/27 00:07 06934へのコメント コメント数:2
>20万人のうち死刑が一人?ということでもないのかしら。どうして獄門が一
>人なのか、
ええ!もっと百姓の首がほしいって?
さては武士の手先かあ?(^^)
この騒動で処罰されたのは、381人。名主、組頭、年寄役のもので半分を占めて
います。藤五郎みたいなスカンピンの無頼者は、はなから無視されていたのかな
あ。
獄門は兵内(ひょうない)1人。遠島3人、あと追放とかです。
一番多い処罰が過料(罰金刑)と手鎖で198人。次ぎ、役儀取り上げ119人
など。とにかく牢屋がいっぱいになって、溜りにも収容したそうだよ。獄死した
のも少なくなかったようだ。
一揆首謀者関係者の探索は火付け盗賊改がやるのかなあ?
関村の兵内さんがほんとに首謀者かどうかはわからないけども、幕府はとにかく
この兵内さんを獄門にして晒したのは事実で、地元には「義民兵内梟首の地」と
いう標識もあるようです。むろん、村人は手厚く回向し、現代でも、関村では、
「兵内おどり」というのが残っていたそうな。今、現在、まだ残っているかどう
かは知らないけど・・・。
>駕籠をかつぐって、大変なことだったと思うのです。肩の一点で駕籠と人の
>重みを支えるのですよ!こぶみたいな筋肉がなくてはできないですよね。
江戸時代の下層階級の人たちって、ええ体していたそうだね。
イギリスなんかでは、貴族がスポーツとかなんかして、立派な体をしていたそう
だけど、江戸の場合は、反対だなあ。
「黄金時代のギリシャ彫刻を理解しようとするなら、夏に日本を旅行する必要が
ある」とか「下層の者の間では、まるで体操選手を思わせるような、背が高く異
常に筋肉の発達したタイプにめぐりあう」なんて外国人も書いているようです
よ。(渡辺京ニ「逝きし世の面影」)
いなせな身のこなしというのも、やはり、しなやかで、鍛えられた身体から出て
くるものだよね。
いなせな奴というのは、最近、あまりいないなあ。としまるどんがそれに近い
ね。やっぱ、農作業で、きっと身体、鍛えているんだと思うね。
(2)明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/28 22:58 06921へのコメント コメント数:2
みなさん、こんにちは。
明和元年の秋、武蔵、上野、下野、信濃の国の中山道の宿駅に(板橋から和田宿
までの28の宿駅)に、幕府からお触れがあったそうです。
一揆の発生地、本庄宿にきたお触れは、次のようなもの。
「近年、中山道通行多くあいなり、本庄宿これまでの助郷高にては、人馬不足に
つき、このたび、村々ヘお代官両人の手代差し遣わし、村柄見分、さる戊年より
未年まで10か年、年貢割付、ならびに道中道法などこれを糾し、勤高をきめ、右
宿、助郷加え候間、心得ちがいこれなきよう、吟味うけるべきものなり。
11月 御勘定 安藤弾正
御目付 池田筑後 」
要するに、近頃、中山道の交通量が増え、今までの定助郷だけでは足らず、新た
に大幅に助郷を加えるから承知せよ、という通達です。
各宿場とも、200か村ほど新たに助郷に割り当てられるそうだ。
しかし、これらの村では、数年不作が続き、しかも、この年の春には、朝鮮使節
が来た時の接待費として100石につき3両1分2朱の税金をとられたばかり。
幕府がこの時、助郷を急増することになったのは、翌明和2年が日光東照大権現
の150年忌にあたっており、大名や公家の往来が激しくなると予想したためで
もあるそうな。
しかし、農民にとったら、たまったもんじゃあない。
「この上は、一人残らず江戸表にまかり出て、命限りに御免の御訴訟申すより
他なし」の声が高まる。
そして、ついに12月中旬のある日、次ぎのような張り紙が出る。
「来る12月16日、十条河原へ、15歳から60歳までの男子、1軒一人残らず必ず集
合されたい。もし、不参加の場合は、大勢で押しかけそのままではおかぬから覚
悟していてほしい」
さあ、集まるのだろうか?
伝馬騒動については、地元の人が書いた北沢文武「明和の大一揆」(鳩の森書
房)があります。史料としては、「民衆運動の思想」(岩波書店)に「狐塚千本
槍」という古文書が、また、日本庶民生活史料集成弟6巻(三一書房)にもいろ
いろ史料が出ています。
わたしは、北沢文武の「明和の大一揆」を参考にします。これ読みやすいですか
ら。
藤五郎 (3)明和の大一揆(伝馬騒動)
( 8) 99/04/29 10:29 06955へのコメント コメント数:1
みなさん、こんにちはー。藤子です。
埼玉県の旅をつづけまーす。
明和元年12月16日、本庄宿の助郷に指定された村々約200村から1万人ほどが、
児玉郡の十条河原に集まってきました。ここは、県(?)の史跡になってるよう
で、農道に説明板が今でも立っているようです。まだまわりは農地ではないかし
ら。
20万一揆といわれる伝馬騒動は、この集会が始まりの合図となります。
「尚風録」という文書によると、張り紙は制札場だけでなく、立木、人の家、い
たるところに張られていたそうな。「もし、集まらなければ,焼き払うぞ」と書
かれては、一応、ぞろぞろ顔を出すよね。
さて、夜、十条河原に大勢集まったけども、唆した首謀者は姿は見せないもので
す。ただわいわいがやがやと騒ぐばかりで、まとまらない。
「尚風録」では、この時、百姓杢之助というものが、竹の先に鼻紙をさし、「東
西東西ー」とふりまわし、こういったそうだ。
「おのおの、さように動揺めされては、どんな相談もまとまらぬ。まず、静まり
候、しかるのち相談いたそう」
みんな、納得し、座る。
「今まで、ご伝馬を勤めなくても、露命をつなぎがたし。この上に、ご伝馬あい
勤めるものならば、渇命におよぶは必定なり。無二無三に御訴訟すべし。われ
は、70余歳、命を惜しいとは思わぬ。お詮議のときは、われ自ら、お咎めに出
る。」
だれかが口火をきらなくちゃいけないのよね。しかし、口火を切ったものに責任がま
わってくる。だれかが口火を切ると次々に意見がでます。次ぎのように決まります。
21日に本庄宿に再結集。その時には、各郡、各村々ごとの纏(まとい)を立
て、蓑笠を背負う。おおみそかまでに江戸に出て、大手門につめかけ、あくる元旦
に登城してくる老中、あるいは諸大名に訴訟しよう。
エイエイオー(^^)
この時の杢之助は、後、牢死しています。
兵内だけでなく、やはりいろんな人が心ならずも関わってしまうのですよね。
藤五郎