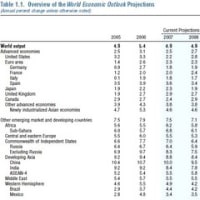☆「ノーベル賞受賞4氏 自由な論争が磨いた理論 世界に挑んだ独創の気風(産経新聞 2008.10.13 08:28)によると、昨年の取材で、南部陽一郎さんは、こう語った。
「物理を勉強しようと思った動機は湯川博士。だが当時の東大物理学科(の専攻)には、素粒子物理がなかった。『素粒子をやりたい』と教授に言ったら、『そんなの天才にしかできないぞ』といさめられたが、それを無視して朝永博士らのグループに行って話を聞いていた」。昨年、取材に応じた南部さんは、笑顔でこう振り返った。
☆今でもそういう環境ではないのだろうか?そんなの天才にしかできないぞというフレーズは格差社会をつくる優勝劣敗イデオロギー。今もあるでしょう。
☆「化学賞は意外」「クラゲ85万匹採取」下村さん語る(朝日新聞 2008年10月8日21時24分)によると、下村脩さんは米国に居続けた理由についてこう語った。
「昔は研究費が米国の方が段違いによかった。日本は貧乏で、サラリーだってこちらの8分の1。それに、日本にいると雑音が多くて研究に専念できない。一度、助教授として名古屋大に帰ったんだけど、納得できる研究ができなかったので米国に戻った」
☆21世紀金融大恐慌の影響で、米国もかつてのように研究費をだせるかどうかわからないが、日本に比べりゃあ、雑音は多くはならないだろう。ともかくこの話も今の日本では変わらないでしょう。
☆大学の話だけれど、初等中等教育の先生にもあてはまる。夢を見続けられる授業にできるだけ先生方が集中できることが、教育改革の大反省点。文科省も教育委員会もそして家庭もそういう望みを持ってくれるとよいのに。
☆そんなの理想ジャンというのは「そんなの天才にしかできないぞ」と南部さんがいさめられた当時の思考回路に通じているし、そういう雑音が子どもたちの才能をヘコませる。
「物理を勉強しようと思った動機は湯川博士。だが当時の東大物理学科(の専攻)には、素粒子物理がなかった。『素粒子をやりたい』と教授に言ったら、『そんなの天才にしかできないぞ』といさめられたが、それを無視して朝永博士らのグループに行って話を聞いていた」。昨年、取材に応じた南部さんは、笑顔でこう振り返った。
☆今でもそういう環境ではないのだろうか?そんなの天才にしかできないぞというフレーズは格差社会をつくる優勝劣敗イデオロギー。今もあるでしょう。
☆「化学賞は意外」「クラゲ85万匹採取」下村さん語る(朝日新聞 2008年10月8日21時24分)によると、下村脩さんは米国に居続けた理由についてこう語った。
「昔は研究費が米国の方が段違いによかった。日本は貧乏で、サラリーだってこちらの8分の1。それに、日本にいると雑音が多くて研究に専念できない。一度、助教授として名古屋大に帰ったんだけど、納得できる研究ができなかったので米国に戻った」
☆21世紀金融大恐慌の影響で、米国もかつてのように研究費をだせるかどうかわからないが、日本に比べりゃあ、雑音は多くはならないだろう。ともかくこの話も今の日本では変わらないでしょう。
☆大学の話だけれど、初等中等教育の先生にもあてはまる。夢を見続けられる授業にできるだけ先生方が集中できることが、教育改革の大反省点。文科省も教育委員会もそして家庭もそういう望みを持ってくれるとよいのに。
☆そんなの理想ジャンというのは「そんなの天才にしかできないぞ」と南部さんがいさめられた当時の思考回路に通じているし、そういう雑音が子どもたちの才能をヘコませる。











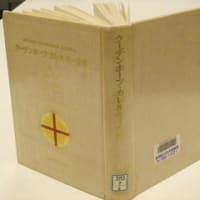


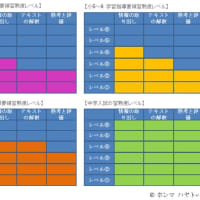
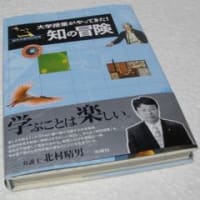
![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)
![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)