「自立」
この語は強者から弱者へ使われる。逆に使われることはない。
途上国の自立は要請される。先進国からえらそうに説教めいた調子で語られる。しかし、途上国から先進国が「わが国の資源に依存している。もっと自立しろ」と責められることはない。
正社員はフリ-タ-に自立しろと強要する。しかし、フリ-タ-が自分たちの分の給与や福利厚生をけずった分正社員はフリ-タ-に依存的だ、やめろと叫ぶことはない。たいていの場合、申し訳なさそうに俯いて「ええ、そうですね」などと語るのが精一杯だ。
あるいは、身分の高い相手の自尊心のお守りとして「ああ、そうか、そうですよね」などと、それをこれまで一度も考えたこともなかったように、幼児ぶって答えることもある。屈辱的だが、そうしなければ正社員のなかにはキレる人もいる。クビが怖ければご機嫌伺いをするしかない。いつもそうしていると、そうしたくない場面でもいつものクセがつい出てしまう。
また、自立は絶対なのか? 誰の自立なのか? その点も問われることはない。
先進国の中産階級風の生活ができること、大量生産・大量消費を問わず欧米近代文明を疑問に思わず、「給料も役職も右肩上がり」の神話を信じてやっていくこと。貧富の差に決して心を痛めないこと。豊かになれば、貧しいものに「もっと成長しろ・進歩しろ」と家父長的に傲慢に説教をすること。
どうも、それが「自立」の正体らしい。
近代的な学校教育において、先住民の文化を滅ぼすことや、「落ちこぼれ」を作ったことを祝う「進学・進級」という儀礼に何の疑問も持たない人間が、もっともよく自立を成し遂げる。
彼らは相互扶助・福祉を徹底して忌み嫌う。平和運動のミ-テイングの後、参加者の一部がいっしょにファミリ-レストランで食事をすることになった。失業者や低所得者らがコ-ヒ-一杯、あるいはおつまみメニュ-をひとつなど低額のものを注文する同じテ-ブルで、ひつまむしセットなど割高のメニュ-を注文する。サヨクでフェミニストの大学教員を中心とするグル-プは、それを貧しいものに分け与えることはなかった。また、支払いはワリカンではなく各自で、と仕切っていた。フリ-タ-やそれに準ずる身分の低い正社員たちを敵視し、さげずみ、罪悪視するまなざしがそこにあった。ひとりだけ、自分と仲のいい隣の人にメニュ-をとりわけた人もいたが、やはり同情のまなざしがあった。
その大学でフェミニストに教育を受けたお弟子さんの一人は、強硬な反福祉論者である。
彼と自分との会話を紹介しよう。ヴォイスデコ-ダ-を起こしたわけではなく、大雑把な内容を書いてある。
フェミニストの弟子 「オレはアナ-キスト。政府も法律も要らない。国があるから戦争が起こる。おかしいと思わないかい? 『同じ家族として』だの『同じ国民として』だのと言いながら、人の嫌がることをやるなんて……! ヒドイじゃないか! そんなことをして何が気持ちイイんだよォ! だから、国は廃止すべきなんだ。」
ワタリ 「え、政府を廃止する、ですって……? 」
フェミニストの弟子 「そう。町とか村とかでみんなで社会を運営すればいい」
ワタリ 「それに、国の福祉の役割はどうなるの? 例えば、失業手当とか、母子家庭手当てとか。奨学金や健康保険は?」
フェミニストの弟子 (不機嫌になってきて尊大な態度で)「そんなものは要らない。」
ワタリ「そうはおっしゃっても、例えば交通事故にあって働けなくなったり、リストラされたりしたらどうするの? 」
フェミニストの弟子 「 そんな、交通事故とか母子家庭とか失業者は、そいつらだけで集まって
福祉をした人だけが集まって村でも作ってやっていればいい」
ワタリ(半ばボ-ゼンとしながら)「何? 自分とか、家族や友達が同じ目にあってもそう言えるんですか?」
フェミニストの弟子 「当たり前。」
ワタリ 「それじゃ、あなたは、所得税は国による個人の財産権の侵害に当たるとでも?」
フェミニストの弟子 「そう! 国の税金とか年金とか、全部権利侵害だよ! あんなもの、なくなっちまえばいいんだあ!」
アメリカのリバタニアリストの考えに影響を受けたとおぼしき彼の発想は、個人や各コミュニティの「自立」を前提とした発想である。彼は「自立」という語さえ発さなかった。それは、自立が当然の前提となっていたからだ。
その後飲み会などを付き合ってわかったのだが、彼と近所に住んでいたり昔通っていた大学のよしみもあって親しくしている人たちは、みな一様に「自立」を強調する人たちだった。教師、大学教員、公務員、活動専業主婦など安定した、時間の余裕のある人たち
が大半を占めていた。
そういう人たちは、「貧しさ」をマイナスとみなし、今の文明の基準による「豊かさ」を崇拝しているようだった。たとえイラク戦争に反対しているとしても、今の生活様式=生活水準を変える気は毛頭ない。
世界に飢える人をなくすために、ほんのわずか自分たちのぜいたくを慎む気はないのだ。喜捨も所得税もすべて「悪」なのだ。そして、貧者に汚名を着せ、社会的に排除しようと試みる。
こういった勢力から「自立」という具体的なイメ-ジが不明で強迫観念じみた物言いが発せられている。
だいいち、自立したくてもできないと悩む人に対して「あなたが自立していないのは自立していないからだ。ケシカラーン。自立しろ。」と説教する同義反復にいつになったら気づくのだろう?
安価な労働力に依存して収益をあげる企業を「低賃金労働者に依存するな、自立しろ」と説教しないのはなぜだろう? 天下りする官僚を「官僚ネットワ-クと特殊法人に依存心が強すぎる。自立しろ」と批判しないのはなぜだろう?
自立という恣意的な価値観は、具体的な意味やニュアンスを忘れたまま、弱者の自己責任を追及するセリフである。
この語は強者から弱者へ使われる。逆に使われることはない。
途上国の自立は要請される。先進国からえらそうに説教めいた調子で語られる。しかし、途上国から先進国が「わが国の資源に依存している。もっと自立しろ」と責められることはない。
正社員はフリ-タ-に自立しろと強要する。しかし、フリ-タ-が自分たちの分の給与や福利厚生をけずった分正社員はフリ-タ-に依存的だ、やめろと叫ぶことはない。たいていの場合、申し訳なさそうに俯いて「ええ、そうですね」などと語るのが精一杯だ。
あるいは、身分の高い相手の自尊心のお守りとして「ああ、そうか、そうですよね」などと、それをこれまで一度も考えたこともなかったように、幼児ぶって答えることもある。屈辱的だが、そうしなければ正社員のなかにはキレる人もいる。クビが怖ければご機嫌伺いをするしかない。いつもそうしていると、そうしたくない場面でもいつものクセがつい出てしまう。
また、自立は絶対なのか? 誰の自立なのか? その点も問われることはない。
先進国の中産階級風の生活ができること、大量生産・大量消費を問わず欧米近代文明を疑問に思わず、「給料も役職も右肩上がり」の神話を信じてやっていくこと。貧富の差に決して心を痛めないこと。豊かになれば、貧しいものに「もっと成長しろ・進歩しろ」と家父長的に傲慢に説教をすること。
どうも、それが「自立」の正体らしい。
近代的な学校教育において、先住民の文化を滅ぼすことや、「落ちこぼれ」を作ったことを祝う「進学・進級」という儀礼に何の疑問も持たない人間が、もっともよく自立を成し遂げる。
彼らは相互扶助・福祉を徹底して忌み嫌う。平和運動のミ-テイングの後、参加者の一部がいっしょにファミリ-レストランで食事をすることになった。失業者や低所得者らがコ-ヒ-一杯、あるいはおつまみメニュ-をひとつなど低額のものを注文する同じテ-ブルで、ひつまむしセットなど割高のメニュ-を注文する。サヨクでフェミニストの大学教員を中心とするグル-プは、それを貧しいものに分け与えることはなかった。また、支払いはワリカンではなく各自で、と仕切っていた。フリ-タ-やそれに準ずる身分の低い正社員たちを敵視し、さげずみ、罪悪視するまなざしがそこにあった。ひとりだけ、自分と仲のいい隣の人にメニュ-をとりわけた人もいたが、やはり同情のまなざしがあった。
その大学でフェミニストに教育を受けたお弟子さんの一人は、強硬な反福祉論者である。
彼と自分との会話を紹介しよう。ヴォイスデコ-ダ-を起こしたわけではなく、大雑把な内容を書いてある。
フェミニストの弟子 「オレはアナ-キスト。政府も法律も要らない。国があるから戦争が起こる。おかしいと思わないかい? 『同じ家族として』だの『同じ国民として』だのと言いながら、人の嫌がることをやるなんて……! ヒドイじゃないか! そんなことをして何が気持ちイイんだよォ! だから、国は廃止すべきなんだ。」
ワタリ 「え、政府を廃止する、ですって……? 」
フェミニストの弟子 「そう。町とか村とかでみんなで社会を運営すればいい」
ワタリ 「それに、国の福祉の役割はどうなるの? 例えば、失業手当とか、母子家庭手当てとか。奨学金や健康保険は?」
フェミニストの弟子 (不機嫌になってきて尊大な態度で)「そんなものは要らない。」
ワタリ「そうはおっしゃっても、例えば交通事故にあって働けなくなったり、リストラされたりしたらどうするの? 」
フェミニストの弟子 「 そんな、交通事故とか母子家庭とか失業者は、そいつらだけで集まって
福祉をした人だけが集まって村でも作ってやっていればいい」
ワタリ(半ばボ-ゼンとしながら)「何? 自分とか、家族や友達が同じ目にあってもそう言えるんですか?」
フェミニストの弟子 「当たり前。」
ワタリ 「それじゃ、あなたは、所得税は国による個人の財産権の侵害に当たるとでも?」
フェミニストの弟子 「そう! 国の税金とか年金とか、全部権利侵害だよ! あんなもの、なくなっちまえばいいんだあ!」
アメリカのリバタニアリストの考えに影響を受けたとおぼしき彼の発想は、個人や各コミュニティの「自立」を前提とした発想である。彼は「自立」という語さえ発さなかった。それは、自立が当然の前提となっていたからだ。
その後飲み会などを付き合ってわかったのだが、彼と近所に住んでいたり昔通っていた大学のよしみもあって親しくしている人たちは、みな一様に「自立」を強調する人たちだった。教師、大学教員、公務員、活動専業主婦など安定した、時間の余裕のある人たち
が大半を占めていた。
そういう人たちは、「貧しさ」をマイナスとみなし、今の文明の基準による「豊かさ」を崇拝しているようだった。たとえイラク戦争に反対しているとしても、今の生活様式=生活水準を変える気は毛頭ない。
世界に飢える人をなくすために、ほんのわずか自分たちのぜいたくを慎む気はないのだ。喜捨も所得税もすべて「悪」なのだ。そして、貧者に汚名を着せ、社会的に排除しようと試みる。
こういった勢力から「自立」という具体的なイメ-ジが不明で強迫観念じみた物言いが発せられている。
だいいち、自立したくてもできないと悩む人に対して「あなたが自立していないのは自立していないからだ。ケシカラーン。自立しろ。」と説教する同義反復にいつになったら気づくのだろう?
安価な労働力に依存して収益をあげる企業を「低賃金労働者に依存するな、自立しろ」と説教しないのはなぜだろう? 天下りする官僚を「官僚ネットワ-クと特殊法人に依存心が強すぎる。自立しろ」と批判しないのはなぜだろう?
自立という恣意的な価値観は、具体的な意味やニュアンスを忘れたまま、弱者の自己責任を追及するセリフである。










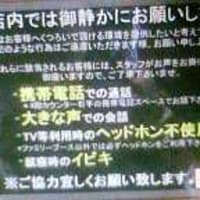

年収1000万もあるということで、人気が殺到し、採用凍結したのち、子会社嘱託員としての採用しか無くなった。郵便局も正職員の試験ははるかに難しくなり、アルバイトさえ採用が難しくなってきている。正社員にしても、自分たちが楽に入れたものだから、なぜ今のフリーターはこんなこともできないのかと思っているのだ。
正社員とフリーターの違いは、個人の能力ではなく、時代の差に過ぎない。今フリーターをしている殆どの人が、時代さえよければ、正社員や公務員だったはずだ。そのことを知らずにフリーターはわがままだと決め付ける正社員は多い。残念ながら。
そう思うよ。自分は今、失業者。ある日、会社が潰れて、整理会社(?)に移籍し、その後、退社しました。そのとき、36歳。当然、仕事はなくて(厳密にはあります。給与を含めた待遇を無視すれば)、時間雇いの仕事を5年ほど続けてきました。
「自立」という言葉はいわば凶器です。使われ方に注意しなければならんです。
私の場合、両親が健在で、母親は障害児を持つあまり好ましくない親に見られる例のように、私を保護し面倒を見ることを自分の幸せと勘違いしています。母親の健康状態が悪くなったときに、自分を道連れに心中しようとしないか心配しています(^^;
>今フリーターをしている殆どの人が、時代さ>えよければ、正社員や公務員だったはずだ。>そのことを知らずにフリーターはわがままだ>と決め付ける正社員は多い。残念ながら。
傾向分析として、いい指摘です。以前は正社員だけがしていた仕事がどんどんバイトや派遣になっている。
>仕事はなくて(厳密にはあります。給与を含>めた待遇を無視すれば)
半失業とか部分就業のことですね。自立したくてもできない給与の仕事しかないという。
フィリピンと同じように日本政府も半失業の統計をとってあらどうでしょうか? 半失業だと、社会参加しているとか、職がないより恵まれているということで、問題が隠蔽されがちなのが困りますね。
二つ以上の会社をかけもちすると、バレないように気を使わなきゃならなかったり、疲れが倍増しますよね。
>何故かここでも「攻め」とか云う発想で、労働政策
>として捉えられていないようで全く理解できませ
>ん。
自分で言うのもヘンですが、本当にそうですね(苦笑)。
ネオコン派が「自立」という言葉を面と向かって使うときの、異様な様子をどんな風に伝えればいいのでしょう。
敵意と軽蔑に満ちた表情・身振り・口調、それに人を刺し殺さんばかりの鋭い目つき。普段はユーモアに満ちた人も、シニカリストに早変わり。Aさんが失業しているからBさんの職があるのかも、といった可能性については思考停止。
そういう会話は大変神経を消耗するのですよ。で、たとえ励ますつもりにせよ、迷惑だ、と伝えたかったのが、この記事を書いた動機のひとつです。
もうひとつは、(ずいぶん複雑になりますが)自立という価値観・世界観は絶対なのか? との疑問をなげかけたかったのでした。
それから、日本の言論世界では、フリーターは心の問題として扱われがちです。そこで、心の問題に関心のある方に、こういった記事から労働問題として/政策としてのフリーター問題(という書き方が妥当かどうかは別として)を考えるきっかけにしていただきたいと考え、あえて感情の話や日常雑記的な記事を投稿しているのです。
>それゆえにそれぞれの分野で十分な分析をしてから
>社会全体で有意義な議論が必要
そうですね。
ところが、わたしはそもそも動物学者志願です。ところが、あるフリースクールで自立という価値を教えられたことがきっかけで、大学と院に行きそびれてしまいました。もう、一生動物学の大学院には行けないかもしれません。
こういうことはやはり、ネオコンから自律性の高い文科系の研究者さんが調べて報告してもらいたいのです。ところが、自分の知る限り、日本の研究者はネオコンに対する自律性が薄いようなのです。
文科系には苦手意識が強いので、文科系の大学院には行きたくないのです。もし行きたくても資金不足ですし。そのへんは悩ましいかぎりです。
>先進工業国はどこも同様な問題を抱えています。
すべての国を調べたわけではないのですが、おそらくそうでしょうね。