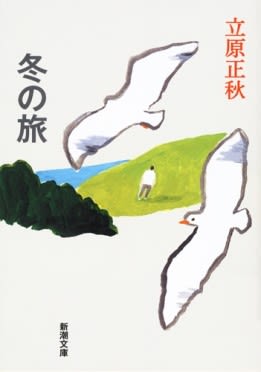時勢と個人的事情とがリンクして、なかなか遠出が出来ない。
まあそれでもようよう首都圏へ向かった。
前回の8月末に見たもののまとめも出来てないままである。
己のこの衰退をどう見るか。
…はぁぁぁ
ため息ばかりなのであった。
まあとりあえず出かけた内容を記そう。
それで先に言うとくけど「東京ハイカイ録」というわりに今回の半分は埼玉での話で、「翔んで埼玉」「なぜか埼玉」がアタマの中をぐるぐるしたな。
京浜東北線で北浦和へ。
着いたらちょっと雨が降ってたわ。まあこんなものでしょうと傘を差しながら歩きます。
今回の主目的の一つがこれ「美男におわす」展@埼玉近代美術館

詳しくはまた後日記すつもりだけど、これはわたしの中では今年の展覧会ベスト3に入るね。
「あやしい絵」「華宵ジェンダーレスなまなざし」に並んで。
一枚絵の良さ、少女マンガの美少年たち、現代アートの中の美少年、美青年…
愉しうございましたわ。
中でもJUNE表紙絵の竹宮さんの作品群。まさしく本質を衝いた作品群だった。
即ち官能性を曝け出して見る者を誘惑するという…
ときめきながら美術館を出て近所の高名なケーキ屋さんにゆくものの、土日はイートインはなし。惜しい。
それで公園で食べることにしてモンブランなど購入。
…残念、合わない。メレンゲもいいけど、わたしは基盤というか底はスポンジの方が好きなの。
相性があるから仕方ない。
さてここから都内へ向かうわけですが、神田で乗り換えればよかったのに折り損ね、新橋もスルーして、とうとう原宿まで乗ってしまった。
そこから表参道。
MAXMARAを背中にてくてく…ビリケン商会へ到着。
近藤ようこさんの「高丘親王航海記」完結記念の個展「南方綺譚」を拝見に。

アナログ絵で、背景の闇は墨によるもの。そのためにそこに色調が生まれる。その色の諧調が南方の湿気を感じさせる。
親王の原画だけでなく「女の顔を持つ虎」「ジャカルタ辺りで暮らす日本人の女と西洋人の女の対話」「寄り集う人魚たち」の絵があり、それらは完売していた。めでたいことである。
今回の展覧会のタイトルはマルグリット・ユルスナール「東方綺譚」から。
あれはよい短編集でした。
「高丘親王」では一枚絵として眺めたいコマがいくつかあって、それらは天上から降る花を伴った情景であったりし、むしろこれを風呂敷などにすればよいのではないかと思った。
つまり人形手の更紗を思い起こさせたのだ。
…ということを近藤さんに話すと「えっ風呂敷」と笑われた。
いやいや、ええと思いますよ。
ホホホホホ
ご本は色々と手元に賜り物があるので今回は一筆箋を二種、それから見かけた植木金矢絵はがきセットも購入。
ここでタイムアップ。
さらばでござる。
またの再会を約束して、わたくしは日本橋へ。
地下鉄から上がったら丸善で綺麗な建築本の展示があるのを知って見に行く。
なんだかよいものを色々と見てからさくら通りへ出てぎょっ…えらく大きい区域が更地になっておった。
そうか…
新幹線に乗り大阪へ。
まだ府中市美術館、弥生美術館、汐留美術館、たばこと塩の博物館、東京オペラシティなどなど行くべきところがあるのでなんとか会社と病院の合間を縫って出かけたいと思います。
今回はここまで。
まあそれでもようよう首都圏へ向かった。
前回の8月末に見たもののまとめも出来てないままである。
己のこの衰退をどう見るか。
…はぁぁぁ
ため息ばかりなのであった。
まあとりあえず出かけた内容を記そう。
それで先に言うとくけど「東京ハイカイ録」というわりに今回の半分は埼玉での話で、「翔んで埼玉」「なぜか埼玉」がアタマの中をぐるぐるしたな。
京浜東北線で北浦和へ。
着いたらちょっと雨が降ってたわ。まあこんなものでしょうと傘を差しながら歩きます。
今回の主目的の一つがこれ「美男におわす」展@埼玉近代美術館

詳しくはまた後日記すつもりだけど、これはわたしの中では今年の展覧会ベスト3に入るね。
「あやしい絵」「華宵ジェンダーレスなまなざし」に並んで。
一枚絵の良さ、少女マンガの美少年たち、現代アートの中の美少年、美青年…
愉しうございましたわ。
中でもJUNE表紙絵の竹宮さんの作品群。まさしく本質を衝いた作品群だった。
即ち官能性を曝け出して見る者を誘惑するという…
ときめきながら美術館を出て近所の高名なケーキ屋さんにゆくものの、土日はイートインはなし。惜しい。
それで公園で食べることにしてモンブランなど購入。
…残念、合わない。メレンゲもいいけど、わたしは基盤というか底はスポンジの方が好きなの。
相性があるから仕方ない。
さてここから都内へ向かうわけですが、神田で乗り換えればよかったのに折り損ね、新橋もスルーして、とうとう原宿まで乗ってしまった。
そこから表参道。
MAXMARAを背中にてくてく…ビリケン商会へ到着。
近藤ようこさんの「高丘親王航海記」完結記念の個展「南方綺譚」を拝見に。

アナログ絵で、背景の闇は墨によるもの。そのためにそこに色調が生まれる。その色の諧調が南方の湿気を感じさせる。
親王の原画だけでなく「女の顔を持つ虎」「ジャカルタ辺りで暮らす日本人の女と西洋人の女の対話」「寄り集う人魚たち」の絵があり、それらは完売していた。めでたいことである。
今回の展覧会のタイトルはマルグリット・ユルスナール「東方綺譚」から。
あれはよい短編集でした。
「高丘親王」では一枚絵として眺めたいコマがいくつかあって、それらは天上から降る花を伴った情景であったりし、むしろこれを風呂敷などにすればよいのではないかと思った。
つまり人形手の更紗を思い起こさせたのだ。
…ということを近藤さんに話すと「えっ風呂敷」と笑われた。
いやいや、ええと思いますよ。
ホホホホホ
ご本は色々と手元に賜り物があるので今回は一筆箋を二種、それから見かけた植木金矢絵はがきセットも購入。
ここでタイムアップ。
さらばでござる。
またの再会を約束して、わたくしは日本橋へ。
地下鉄から上がったら丸善で綺麗な建築本の展示があるのを知って見に行く。
なんだかよいものを色々と見てからさくら通りへ出てぎょっ…えらく大きい区域が更地になっておった。
そうか…
新幹線に乗り大阪へ。
まだ府中市美術館、弥生美術館、汐留美術館、たばこと塩の博物館、東京オペラシティなどなど行くべきところがあるのでなんとか会社と病院の合間を縫って出かけたいと思います。
今回はここまで。