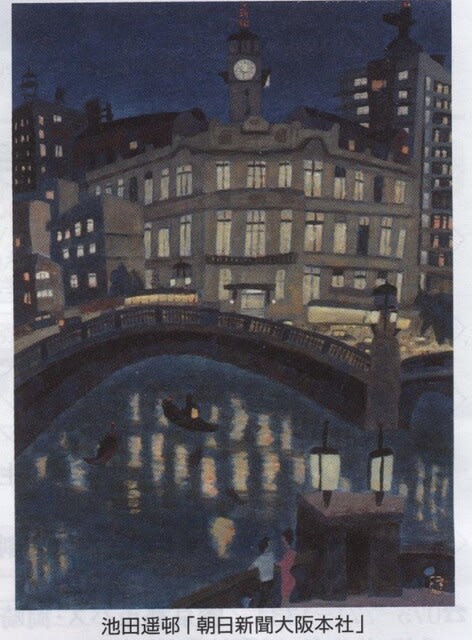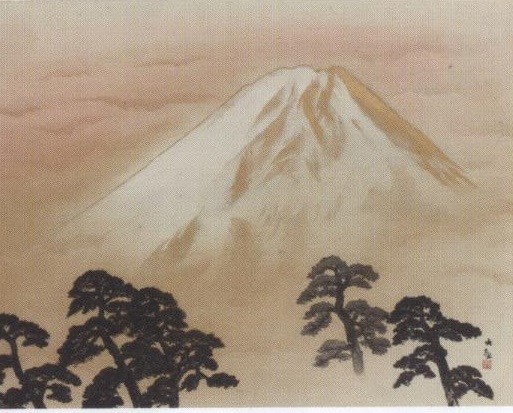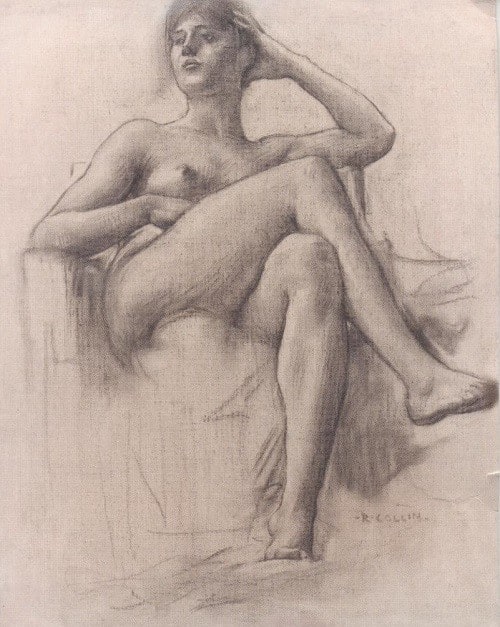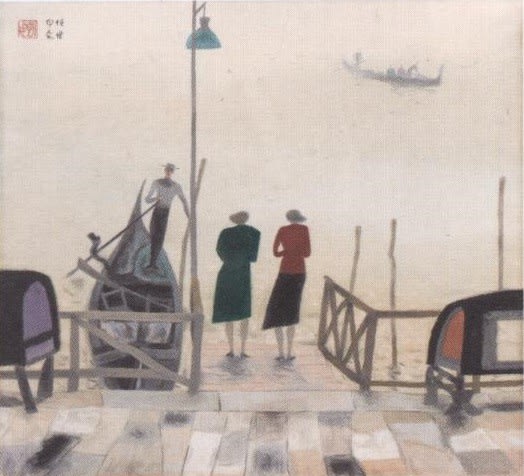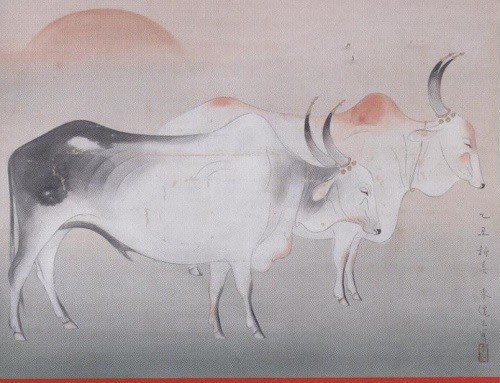続き。

小磯良平 薔薇 1955
丁度労働者の絵や抽象表現も始まりだしてたかな。その時代でもこうした重厚な薔薇の絵を描いている。
この翌年から小磯は武田薬品の薬用植物園に咲く花々をその機関誌に描くようになる。
川口軌外 柘榴1 1939 ナマナマシイ爆ぜ方の柘榴。スペインのボデゴンを思い出させる。

杉山寧 鯉 1959 エメラルド色の水中に泳ぐ白い鯉。しぃんとした光景。後のスタイルがこの頃すでに確立されている。
川西英 薔薇 1958頃 白に青の濃い背景に黄色と赤の薔薇。明るくていいなあ。
栗原忠二 芍薬 1923 ふわっとした花びらの質感がよく出ている。綺麗な花。
ここで肖像画が並ぶ。
宮本三郎 村山長挙氏 1944.12.14
東郷青児 姉妹(村山美知子、富美子) 1944
どちらも水彩画でそれぞれの画家の特性が出ている。全く知らない人々なので画家の仕事以外は何もわからない。
ただ、姉の方が柔らかく、妹の方がしっかりめなのはやはり「姉と妹」らしくて面白い。
山下摩季 富士越龍 1960 横長の画面に広がる龍。竜のまとう空気感のようなものが伝わる。
ここからは近世絵画
花鳥図屏風 18世紀 三段に分かれている。一番上は金地、中辺りが飛ぶ鳥、下には花々やその蜜を吸う鳥などがえがかれている。雀が可愛い。
葛飾北斎日肉筆画帖 1835 最晩年の仕事なのだが、力の衰えは感じない。

鷹が可愛い。これはアタマをかいているのかもしれない。なんとなくちょっと甘えてるようにも見えて、そこが可愛い。猛禽でも可愛いものは可愛い。
伝・円山応挙 菜花に猫図 19世紀 これは好きな絵で以前から絵葉書をめでている。かわいいなあ。菜の花だけでなく菫も咲いていて、ねこもにゃあとした顔つき。
蝶々はいないね。いたら吉祥画になるのかな。

伝・応挙 歌仙図 文屋、遍照、業平の三人がいた。
渡邊南岳 観桜美人図 枝垂桜を愛でる二人。一人は女中だろうか。
黒田稲皐 群鯉図 1823 この人の絵も仲間入りか。鯉狂いの絵師。府中市美で見た時にはギョッとしたな、魚だけに。←金カムの尾形のようなことを言う。
原在中 鯉図 1832 これは前々からここで見ていた。二匹の鯉を腹を合わせるようにして括ってる。
たぶん鯉こくにでもするんだろうなあ…
原在泉 立雛図 明治のお雛様図。
伝・狩野探幽 戯画図巻 なんか野原で宴会してるんだが。
猩々と陶淵明と人麻呂(人丸)

西行にお酌するのは牛若丸?酒呑童子の横には婆さんの小町、もう一人の名が読めない。

給仕するのは鬼たちかな、よく働くがおこぼれちょうだいもいるな。

将軍塚絵巻模本 17-19世紀 この元本は高山寺のか。前にも他で見ているな。
塚を拵えようと働く人々。田村麻呂だったかな。そういえばわたし将軍塚行ったことないわ。
今はもう後期開催中なので展示替えされた分を見に行きたいと思う。

小磯良平 薔薇 1955

丁度労働者の絵や抽象表現も始まりだしてたかな。その時代でもこうした重厚な薔薇の絵を描いている。
この翌年から小磯は武田薬品の薬用植物園に咲く花々をその機関誌に描くようになる。
川口軌外 柘榴1 1939 ナマナマシイ爆ぜ方の柘榴。スペインのボデゴンを思い出させる。

杉山寧 鯉 1959 エメラルド色の水中に泳ぐ白い鯉。しぃんとした光景。後のスタイルがこの頃すでに確立されている。
川西英 薔薇 1958頃 白に青の濃い背景に黄色と赤の薔薇。明るくていいなあ。
栗原忠二 芍薬 1923 ふわっとした花びらの質感がよく出ている。綺麗な花。
ここで肖像画が並ぶ。
宮本三郎 村山長挙氏 1944.12.14
東郷青児 姉妹(村山美知子、富美子) 1944
どちらも水彩画でそれぞれの画家の特性が出ている。全く知らない人々なので画家の仕事以外は何もわからない。
ただ、姉の方が柔らかく、妹の方がしっかりめなのはやはり「姉と妹」らしくて面白い。
山下摩季 富士越龍 1960 横長の画面に広がる龍。竜のまとう空気感のようなものが伝わる。
ここからは近世絵画
花鳥図屏風 18世紀 三段に分かれている。一番上は金地、中辺りが飛ぶ鳥、下には花々やその蜜を吸う鳥などがえがかれている。雀が可愛い。
葛飾北斎日肉筆画帖 1835 最晩年の仕事なのだが、力の衰えは感じない。

鷹が可愛い。これはアタマをかいているのかもしれない。なんとなくちょっと甘えてるようにも見えて、そこが可愛い。猛禽でも可愛いものは可愛い。
伝・円山応挙 菜花に猫図 19世紀 これは好きな絵で以前から絵葉書をめでている。かわいいなあ。菜の花だけでなく菫も咲いていて、ねこもにゃあとした顔つき。
蝶々はいないね。いたら吉祥画になるのかな。

伝・応挙 歌仙図 文屋、遍照、業平の三人がいた。
渡邊南岳 観桜美人図 枝垂桜を愛でる二人。一人は女中だろうか。
黒田稲皐 群鯉図 1823 この人の絵も仲間入りか。鯉狂いの絵師。府中市美で見た時にはギョッとしたな、魚だけに。←金カムの尾形のようなことを言う。
原在中 鯉図 1832 これは前々からここで見ていた。二匹の鯉を腹を合わせるようにして括ってる。
たぶん鯉こくにでもするんだろうなあ…
原在泉 立雛図 明治のお雛様図。
伝・狩野探幽 戯画図巻 なんか野原で宴会してるんだが。
猩々と陶淵明と人麻呂(人丸)

西行にお酌するのは牛若丸?酒呑童子の横には婆さんの小町、もう一人の名が読めない。

給仕するのは鬼たちかな、よく働くがおこぼれちょうだいもいるな。

将軍塚絵巻模本 17-19世紀 この元本は高山寺のか。前にも他で見ているな。
塚を拵えようと働く人々。田村麻呂だったかな。そういえばわたし将軍塚行ったことないわ。
今はもう後期開催中なので展示替えされた分を見に行きたいと思う。