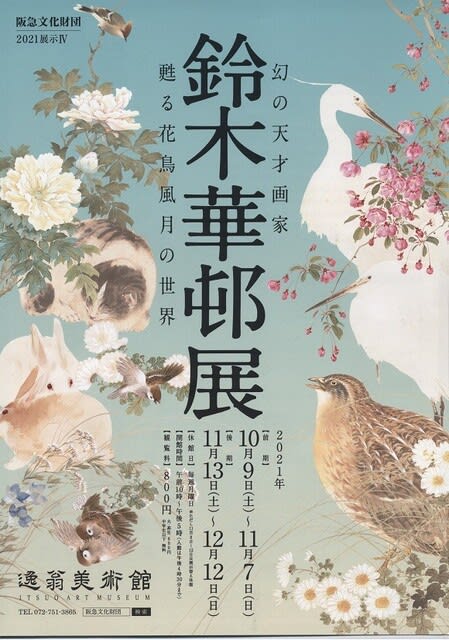2021年の正月から三月まで放送された「PUI PUI モルカー」はたちまち多くの人の心を掴み、自分の愛モルカーを夢見る人が生まれた。
わたしは二話から見始めたが、放送中からの大ヒットによる再放送などもあって、すぐに全話を見ることが叶った。
結果として、わたしもモルカーの飼い主・運転手さんになりたくて仕方ない一人になった。
夏には映画化もされ、わたしもプイプイ言いながら観に行き、貰ったプイプイ鳴くモルカーのポテトをプイプイ言わせた。
本もグッズもたくさん出た。
欲しいものを手に入れたし、モルカーを愛する人々が描く二次創作もたくさん世に出たので、節度を弁えつつ皆さんで共に楽しんでいる。
もう本当にモルカーには夢中になっている。
今回、心斎橋パルコで「PUI PUI モルカーTOWN」展が開催され、わくわくしながら出向いた。

嬉しい限りよ。
有料入場者にはランダムでキラキラシールが渡される。
わたしはチョコちゃんのが当たった。
全シールはこちら。

みんな可愛いなあ。
わたしは特にテディとシロモが好きだが、他にもポン太、ごましおといったモルカーも大好き。
そう、箱推しなんですね。モルカーと言うだけでみんな大好き。
モルカーはそれぞれ個性がある。好きなものも違うし、見た目も違う。
でもやっぱりモルカーは可愛くていとしい。たよりになるモルカーも多い。
このみっしり具合いいなあ。

左端の緑色はワサビ。キュウリ好きのモルカー。その左上にいるゴミ収集モルカーが、ごみだけでなく人参も載せていることに今回気づいた。
その上にはDJモルカーもいる。

モルカータウンの再現をバチバチ撮る。

人もモルカーも普通に存在する街。

双子のテンテンとトントンが交差点にいる。

行き交うモルカーたちを鳥瞰する。

モルカーはタイヤでパタパタ走る。

ポテト、テディ、シロモ。

「魔法天使もるみ」ポスターがある。ヲタロード。

DJモルカー活躍中 聴衆にはゾンビと原始人も。

アビーのヒーロー志願 駐モル禁止マークも。

撮影の様子

どの街角にもモルカーはいる。

誰にでも優しいハンバーガーモルカー。思えばゾンビはタダ食いだよなあ。

小柄なジーニーがあんな隙間にいた。寿司モルカー(えび)、ワサビも。
「アキラ」ならぬ「モルカー」ポスター。

ビルの屋上で危機一髪な冒険モルカー。でもちゃんとポリスも来てくれている。
左のビルの屋上にはタイムモルカーの背中が見える。博士の開発した機材を乗せている。

タイムモルカーと博士。

にぎやかでなにより。

映画ポスター

「モルミッション」でテディが「アキラ」の金田のバイクアクションをやってたが、思えば見里監督は映画「アキラ」上映より後に生まれているのですねえ…

モルカーの後ろ姿は可愛い。とはいえこれはシーナ。花に話しかけるがその後ぱくっ。

悪人たち。そっと猫もいる。

資料色々


武装テディ


映像コーナー
シロモが強盗に乗っ取られてプイプイ泣きながら走るシーン



第一話ラストシーン

つづく。
わたしは二話から見始めたが、放送中からの大ヒットによる再放送などもあって、すぐに全話を見ることが叶った。
結果として、わたしもモルカーの飼い主・運転手さんになりたくて仕方ない一人になった。
夏には映画化もされ、わたしもプイプイ言いながら観に行き、貰ったプイプイ鳴くモルカーのポテトをプイプイ言わせた。
本もグッズもたくさん出た。
欲しいものを手に入れたし、モルカーを愛する人々が描く二次創作もたくさん世に出たので、節度を弁えつつ皆さんで共に楽しんでいる。
もう本当にモルカーには夢中になっている。
今回、心斎橋パルコで「PUI PUI モルカーTOWN」展が開催され、わくわくしながら出向いた。

嬉しい限りよ。
有料入場者にはランダムでキラキラシールが渡される。
わたしはチョコちゃんのが当たった。
全シールはこちら。

みんな可愛いなあ。
わたしは特にテディとシロモが好きだが、他にもポン太、ごましおといったモルカーも大好き。
そう、箱推しなんですね。モルカーと言うだけでみんな大好き。
モルカーはそれぞれ個性がある。好きなものも違うし、見た目も違う。
でもやっぱりモルカーは可愛くていとしい。たよりになるモルカーも多い。
このみっしり具合いいなあ。

左端の緑色はワサビ。キュウリ好きのモルカー。その左上にいるゴミ収集モルカーが、ごみだけでなく人参も載せていることに今回気づいた。
その上にはDJモルカーもいる。

モルカータウンの再現をバチバチ撮る。

人もモルカーも普通に存在する街。

双子のテンテンとトントンが交差点にいる。

行き交うモルカーたちを鳥瞰する。

モルカーはタイヤでパタパタ走る。

ポテト、テディ、シロモ。

「魔法天使もるみ」ポスターがある。ヲタロード。

DJモルカー活躍中 聴衆にはゾンビと原始人も。

アビーのヒーロー志願 駐モル禁止マークも。

撮影の様子

どの街角にもモルカーはいる。

誰にでも優しいハンバーガーモルカー。思えばゾンビはタダ食いだよなあ。

小柄なジーニーがあんな隙間にいた。寿司モルカー(えび)、ワサビも。
「アキラ」ならぬ「モルカー」ポスター。

ビルの屋上で危機一髪な冒険モルカー。でもちゃんとポリスも来てくれている。
左のビルの屋上にはタイムモルカーの背中が見える。博士の開発した機材を乗せている。

タイムモルカーと博士。

にぎやかでなにより。

映画ポスター

「モルミッション」でテディが「アキラ」の金田のバイクアクションをやってたが、思えば見里監督は映画「アキラ」上映より後に生まれているのですねえ…

モルカーの後ろ姿は可愛い。とはいえこれはシーナ。花に話しかけるがその後ぱくっ。

悪人たち。そっと猫もいる。

資料色々


武装テディ



映像コーナー
シロモが強盗に乗っ取られてプイプイ泣きながら走るシーン



第一話ラストシーン

つづく。