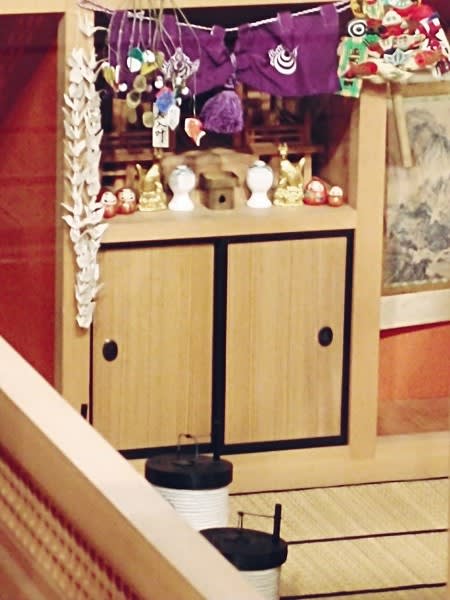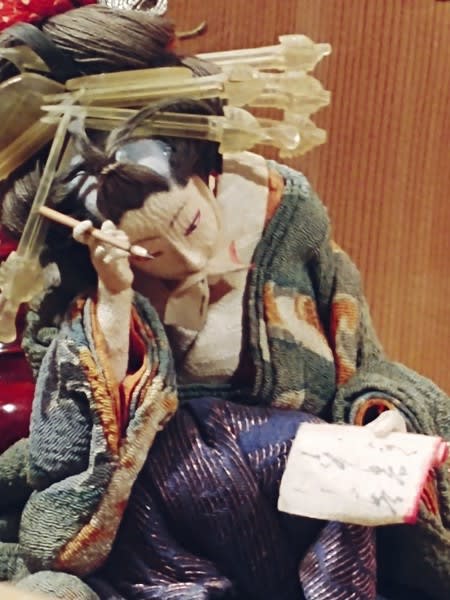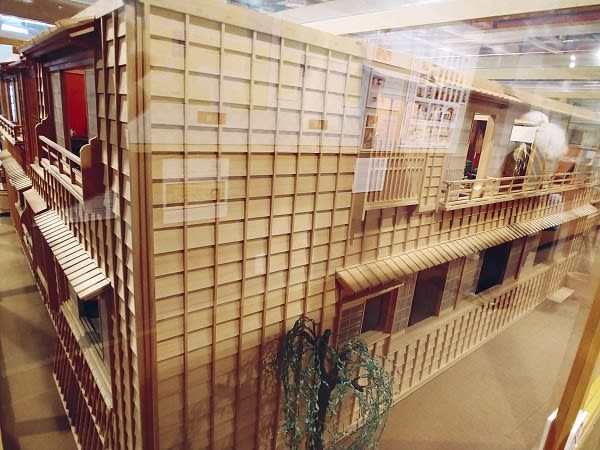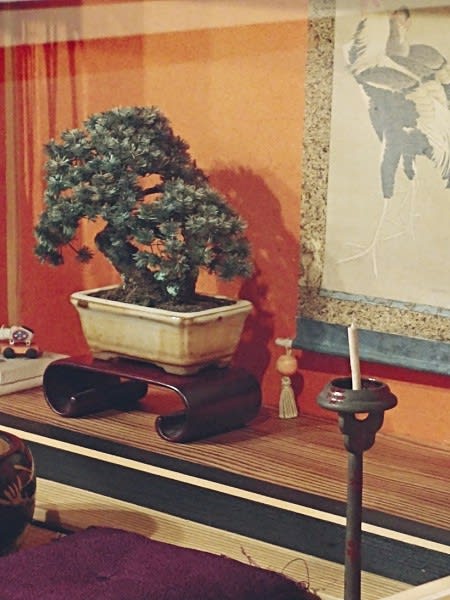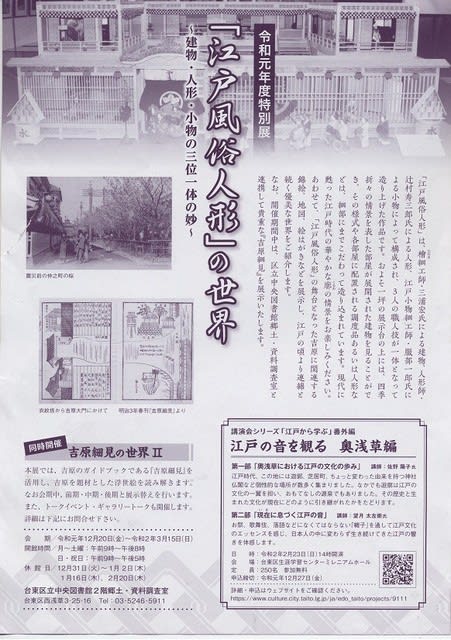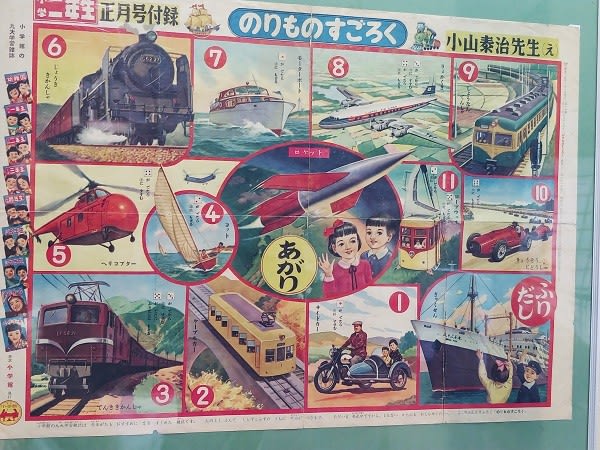大阪市立美術館の「フランス絵画の精華」展に行った。
このタイトルといえば1989年夏に京都国立近代美術館で開催されたのがある。
あの展覧会は正式名を「ル・サロン(1667-1881)の巨匠たち フランス絵画の精華」といい、サロンに出品された作品群を集めたものだった。
詳しくはこちら
その時にフランスのロココ、新古典主義、ロマン主義作品を見たのだ。
なので今回の展覧会と方向性は等しい。
そのためになつかしさが湧き出して、この暑い中、コロナも怖いが天王寺へ出向いた。
高校くらいまではこうした様式のはきはきした表現が好きだったのよ、あいまいなものより。
今はまた違うけれど…
今回の展覧会についてはサイトから引用する。
「本展では、フランス絵画の最も偉大で華やかな3世紀をたどります。17世紀の「大様式」と名づけられた古典主義から、18世紀のロココ、19世紀の新古典主義、ロマン主義を経て、印象派誕生前夜にいたるまでの時代です。ヴェルサイユ宮殿美術館やオルセー美術館、大英博物館、スコットランド・ナショナル・ギャラリーなど、フランス、イギリスを代表する20館以上の美術館の協力のもと、油彩画、素描あわせて約80点の名品が集結しました。」
第I章 大様式の形成、17世紀:プッサン、ル・ブラン、王立絵画彫刻アカデミー
アンブロワーズ・デュボワ (本名 アンブロシウス・ ボサールト)フローラ 油彩、カンヴァス 148×137 東京富士美術館
中央にくつろぐフローラがいて、周囲に4人のアモルたち。花は全て瓶や鉢に生けられている。いずれも灰色がかった青磁。左上にはどこかの門とその周囲が描かれている。
このフローラの姿態をみると、白衣観音のそれを思い出す。艶めかしくも尊い。
ジョルジュ・ド・ラ・ トゥール 煙草を吸う男 1646年? 油彩、カンヴァス 70.8×61.5 東京富士美術館
さすがラ・トゥール、ぼあっと灯りが。松明からキセルの火を採る横顔。襟が高く袖は赤い。「ふーっ」とする口元。
ニコラ・プッサン 55歳の自画像 1649年 油彩、カンヴァス 79.2×65.7 ベルリン国立絵画館
人のことは言えんがおっちゃんである。けっこう満足気。
ニコラ・プッサン コリオラヌスに哀訴する妻と母 1652-1653年頃 油彩、カンヴァス 116×196 レザンドリー、ニコラ・プッサン 美術館

右側にローマ風の被り物の男と懇願する女たち。左端にはアテナめいた女もいる。
ニコラ・プッサンのこういう群衆の絵、好きだな。
ジャック・ブランシャール バッカナール 1636年 油彩、カンヴァス 138×115 ナンシー美術館
バッカスのための祭儀は色々あるなあ。左端には赤目の豹がいる。タンバリン叩く女もいる。かれらに歌舞音曲は必須。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) 小川のある森の風景 1630年頃 油彩、カンヴァス 99×149 東京富士美術館
これは前提として「アモールとプシュケー」の物語があり、捨てられて溺れていたプシュケーが救われたシーンらしい。「どうしたどうした」とばかりに来る人々。ロバもいる。森の右端には小川に至る滝も見える。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) 笛を吹く男のいる風景 1630年代 油彩、カンヴァス 49×39 ナンシー美術館
牛がいる。「アストレ」という物語がブームになってから、牧歌的な恋を描いたものが流行ったそう。牧童と羊飼いの娘の恋。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) ペルセウスと珊瑚の起源 1673年 油彩、カンヴァス 100×127 ホウカム・ホール、レスター 伯爵 コレクション

これは画像小さいからわかりにくかろうが、左に結構「え゛っ」な情景がある。
アンドロメダを救ったペルセウスはメデューサの首を切ってもいて、その首の血から出たペガサスを愛馬にし、メデューサの蛇髪を運ぶペルセウスだが、ちょっと一旦置きまして、とした途端首の血が出てきてあちこちを石にする。
それを見た海のニンフたちが海藻を下敷きにと持ってきたら…あらあら不思議、たちまちサンゴになりました。
というサンゴの由来を語る絵になっている。
右端にはモネがよく描いたエトルタの岩みたいなのがある。
そして中央の水面に映る月。

フィリップ・ド・ シャンパーニュ キリストとサマリヤの女 1648年 油彩、カンヴァス (円形、方形の カンヴァスの四隅 を付彩)114×113 カーン美術館

キリスト「水くれい」
女「え゛っ ああ」
見得が決まったような二人、なにやら阿吽の呼吸まで感じる。
青と黄色の衣の対比もいい。
ピエール・パテル エジプト逃避途上の休息 1658年 油彩、カンヴァス 41.5×61.5 トゥール美術館、ルーヴル 美術館より 寄託
右に廃墟、左に円柱の残り。崩れかけ。その下に一家。
なんとなく武田泰淳「わが子キリスト」を思い出したな…
ローラン・ド・ラ・イール 笛を吹く男のいる風景 1648年頃 油彩、カンヴァス 106.5×131.5 リール美術館
こちらは奥に羊飼い。日本だと十牛図のバリエーションになるのかもしれない。
ニコラ・ミニャール リナルドとアルミーダ 1650年代半ば 油彩、カンヴァス 152×198.5 東京富士美術館
十字軍遠征を舞台にした物語「エルサレム解放」の恋人たち。なかよし。ちんまいアモルもいる。十字軍なのでへいもいるが、赤い鸚鵡がけっこう印象深い。
マチュー・ル・ナン あるいは「ゲームの 画家」 いかさま師(かつて「カード 遊び の人びと」と 呼ばれた) 油彩、カンヴァス 65×81 ランス美術館、ルーヴル 美術館より 寄託
真剣にカード見る男の背後でサマの仲間が合図を送るところ。
あきませんなあ、博打なんか負けるためにやるようなもんです。
ピエール・ミニャール 眠るアモルの姿の トゥールーズ伯爵 1682年 油彩、カンヴァス 91×134 ヴェルサイユ宮殿美術館
ニコラの弟。 これはルイ14世の子で、赤ん坊をアモルに見立てた絵。だかに矢羽も描かれる。
すやすや眠るこの幼子。いわゆる「871069」鼻天向くの子で、こんな小さいうちから既にある種の尊大さが出ている。
ウスタシュ・ル・シュウール 病人たちをいやす聖ルイ 1654-1655年 油彩、カンヴァス 192×126 トゥール美術館
ルイは王様。フランスでは聖別された王様は病人を癒す力を持つ、と信じられていたそう。
これあれだ、金枝篇だな。病人たちは青色がかったような石灰みたいな色。
シャルル・ル・ブラン スブリキウス橋を守るホラチウス・ コクレス1643-1645年頃 油彩、カンヴァス 122×172 ロンドン、ダリッジ 絵画館
戦闘シーンなんだけど、橋を守るというと「遠すぎた橋」とか長板坡とか思い出すのよ。あとロンビエン橋な…
シャルル・ル・ブラン キリストのエルサレム入城 1688-1689年 油彩、カンヴァス 153×214 サン=テチエンヌ近現代美術館、 ルーヴル美術館より寄託
基督は青い衣。群衆は犬連れてる人が多いな。
「駆け込み訴え」のあのシーンが蘇る…
続く。
このタイトルといえば1989年夏に京都国立近代美術館で開催されたのがある。
あの展覧会は正式名を「ル・サロン(1667-1881)の巨匠たち フランス絵画の精華」といい、サロンに出品された作品群を集めたものだった。
詳しくはこちら
その時にフランスのロココ、新古典主義、ロマン主義作品を見たのだ。
なので今回の展覧会と方向性は等しい。
そのためになつかしさが湧き出して、この暑い中、コロナも怖いが天王寺へ出向いた。
高校くらいまではこうした様式のはきはきした表現が好きだったのよ、あいまいなものより。
今はまた違うけれど…
今回の展覧会についてはサイトから引用する。
「本展では、フランス絵画の最も偉大で華やかな3世紀をたどります。17世紀の「大様式」と名づけられた古典主義から、18世紀のロココ、19世紀の新古典主義、ロマン主義を経て、印象派誕生前夜にいたるまでの時代です。ヴェルサイユ宮殿美術館やオルセー美術館、大英博物館、スコットランド・ナショナル・ギャラリーなど、フランス、イギリスを代表する20館以上の美術館の協力のもと、油彩画、素描あわせて約80点の名品が集結しました。」
第I章 大様式の形成、17世紀:プッサン、ル・ブラン、王立絵画彫刻アカデミー
アンブロワーズ・デュボワ (本名 アンブロシウス・ ボサールト)フローラ 油彩、カンヴァス 148×137 東京富士美術館
中央にくつろぐフローラがいて、周囲に4人のアモルたち。花は全て瓶や鉢に生けられている。いずれも灰色がかった青磁。左上にはどこかの門とその周囲が描かれている。
このフローラの姿態をみると、白衣観音のそれを思い出す。艶めかしくも尊い。
ジョルジュ・ド・ラ・ トゥール 煙草を吸う男 1646年? 油彩、カンヴァス 70.8×61.5 東京富士美術館
さすがラ・トゥール、ぼあっと灯りが。松明からキセルの火を採る横顔。襟が高く袖は赤い。「ふーっ」とする口元。
ニコラ・プッサン 55歳の自画像 1649年 油彩、カンヴァス 79.2×65.7 ベルリン国立絵画館
人のことは言えんがおっちゃんである。けっこう満足気。
ニコラ・プッサン コリオラヌスに哀訴する妻と母 1652-1653年頃 油彩、カンヴァス 116×196 レザンドリー、ニコラ・プッサン 美術館

右側にローマ風の被り物の男と懇願する女たち。左端にはアテナめいた女もいる。
ニコラ・プッサンのこういう群衆の絵、好きだな。
ジャック・ブランシャール バッカナール 1636年 油彩、カンヴァス 138×115 ナンシー美術館
バッカスのための祭儀は色々あるなあ。左端には赤目の豹がいる。タンバリン叩く女もいる。かれらに歌舞音曲は必須。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) 小川のある森の風景 1630年頃 油彩、カンヴァス 99×149 東京富士美術館
これは前提として「アモールとプシュケー」の物語があり、捨てられて溺れていたプシュケーが救われたシーンらしい。「どうしたどうした」とばかりに来る人々。ロバもいる。森の右端には小川に至る滝も見える。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) 笛を吹く男のいる風景 1630年代 油彩、カンヴァス 49×39 ナンシー美術館
牛がいる。「アストレ」という物語がブームになってから、牧歌的な恋を描いたものが流行ったそう。牧童と羊飼いの娘の恋。
クロード・ロラン (本名 クロード・ジュレ) ペルセウスと珊瑚の起源 1673年 油彩、カンヴァス 100×127 ホウカム・ホール、レスター 伯爵 コレクション

これは画像小さいからわかりにくかろうが、左に結構「え゛っ」な情景がある。
アンドロメダを救ったペルセウスはメデューサの首を切ってもいて、その首の血から出たペガサスを愛馬にし、メデューサの蛇髪を運ぶペルセウスだが、ちょっと一旦置きまして、とした途端首の血が出てきてあちこちを石にする。
それを見た海のニンフたちが海藻を下敷きにと持ってきたら…あらあら不思議、たちまちサンゴになりました。
というサンゴの由来を語る絵になっている。
右端にはモネがよく描いたエトルタの岩みたいなのがある。
そして中央の水面に映る月。

フィリップ・ド・ シャンパーニュ キリストとサマリヤの女 1648年 油彩、カンヴァス (円形、方形の カンヴァスの四隅 を付彩)114×113 カーン美術館

キリスト「水くれい」
女「え゛っ ああ」
見得が決まったような二人、なにやら阿吽の呼吸まで感じる。
青と黄色の衣の対比もいい。
ピエール・パテル エジプト逃避途上の休息 1658年 油彩、カンヴァス 41.5×61.5 トゥール美術館、ルーヴル 美術館より 寄託
右に廃墟、左に円柱の残り。崩れかけ。その下に一家。
なんとなく武田泰淳「わが子キリスト」を思い出したな…
ローラン・ド・ラ・イール 笛を吹く男のいる風景 1648年頃 油彩、カンヴァス 106.5×131.5 リール美術館
こちらは奥に羊飼い。日本だと十牛図のバリエーションになるのかもしれない。
ニコラ・ミニャール リナルドとアルミーダ 1650年代半ば 油彩、カンヴァス 152×198.5 東京富士美術館
十字軍遠征を舞台にした物語「エルサレム解放」の恋人たち。なかよし。ちんまいアモルもいる。十字軍なのでへいもいるが、赤い鸚鵡がけっこう印象深い。
マチュー・ル・ナン あるいは「ゲームの 画家」 いかさま師(かつて「カード 遊び の人びと」と 呼ばれた) 油彩、カンヴァス 65×81 ランス美術館、ルーヴル 美術館より 寄託
真剣にカード見る男の背後でサマの仲間が合図を送るところ。
あきませんなあ、博打なんか負けるためにやるようなもんです。
ピエール・ミニャール 眠るアモルの姿の トゥールーズ伯爵 1682年 油彩、カンヴァス 91×134 ヴェルサイユ宮殿美術館
ニコラの弟。 これはルイ14世の子で、赤ん坊をアモルに見立てた絵。だかに矢羽も描かれる。
すやすや眠るこの幼子。いわゆる「871069」鼻天向くの子で、こんな小さいうちから既にある種の尊大さが出ている。
ウスタシュ・ル・シュウール 病人たちをいやす聖ルイ 1654-1655年 油彩、カンヴァス 192×126 トゥール美術館
ルイは王様。フランスでは聖別された王様は病人を癒す力を持つ、と信じられていたそう。
これあれだ、金枝篇だな。病人たちは青色がかったような石灰みたいな色。
シャルル・ル・ブラン スブリキウス橋を守るホラチウス・ コクレス1643-1645年頃 油彩、カンヴァス 122×172 ロンドン、ダリッジ 絵画館
戦闘シーンなんだけど、橋を守るというと「遠すぎた橋」とか長板坡とか思い出すのよ。あとロンビエン橋な…
シャルル・ル・ブラン キリストのエルサレム入城 1688-1689年 油彩、カンヴァス 153×214 サン=テチエンヌ近現代美術館、 ルーヴル美術館より寄託
基督は青い衣。群衆は犬連れてる人が多いな。
「駆け込み訴え」のあのシーンが蘇る…
続く。