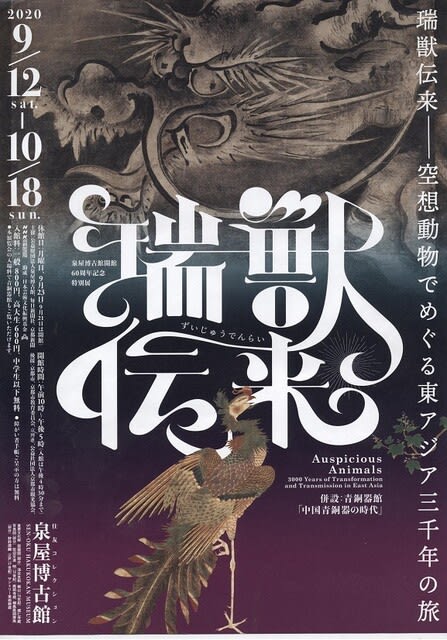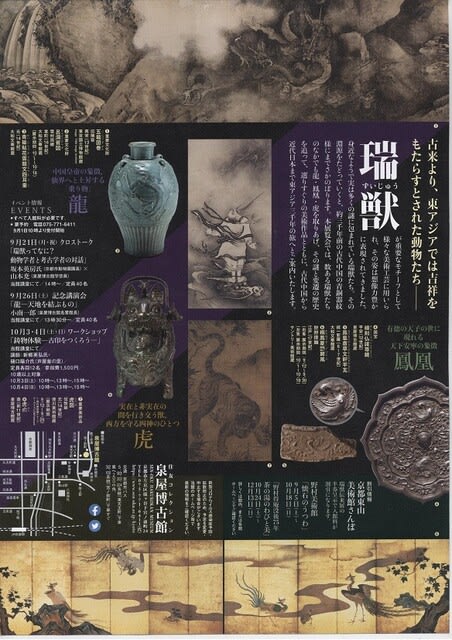弥生美術館で蠱惑的な展覧会「奇想の国の麗人たち」が開催されている。
メインヴィジュアルは御正伸である。

かれの展覧会も数年前に開催されている。
この傾向の展覧会は以前に「魔性の女」展がある。
当時の感想はこちら
「魔性の女」挿絵展 1
「魔性の女」挿絵展 2
弥生美術館は挿絵作品がコレクションの主体なので、他の美術館にはない面白さがある。
外連味といえば外連味なのだが、そこが魅力なのだ。
一目で心を掴むことが大事な挿絵・口絵にはそれ自体に既に魔性と文芸性とが同居している。それが「奇想」でもある。
そしてそこに現れた麗人たちの前にわれわれは跪くことになる。
わたしは12/26に訪ねた。
年の瀬の押し迫った最中にこの展覧会を主目的として出かけたのだ。
友の会会員としてだけでなく、決して見逃してはならぬ展覧会なのだ。
須藤しげる「春の女神」から始まる展示。
1933.4少女倶楽部。領巾が綺麗な装束。白い蝶がひらひら。
そしていよいよ。
化生のいきものから始まる。
異類婚で最も数の多いのが狐である。
華陽夫人、妲己、玉藻の前の系譜だけでなく、哀れにゆかしい葛の葉の物語は長く人口に膾炙した。
創作物でもこれは男性だが「きつね三吉」などがある。
黒地の着物がある。
一つは狐の嫁入り行列の図。もう一つは山川秀峰の「葛の葉」を写したとおぼしき図様のもの。秋草の野を往く女(=狐)
どちらも拵えた人の遊び心を伺わせる着物である。
葛の葉は芝居になる以前から五大説経の一つにも数えられたり、瞽女歌にもあった。
秋元松代の傑作「元禄港歌」はその「葛の葉」をライトモチーフにし、更に舞台で実際に瞽女役の演者に三味線で弾き語りをさせた。
わたしなどは亡くなった藤間紫の歌声が今も耳に残る。
他にも本当の瞽女さんの歌を録音したものを武蔵野吉祥寺美術館の斎藤真一展で聴いてもいる。
橘小夢の玉藻の前が二点。
以前の展覧会のメインヴィジュアルとなった、影が狐のものと、モノクロで狐が一人くつろぐものと。
几帳の向こうで笑う。几帳も春をモチーフとした小綺麗な装飾がついている。屏風もそう。
・雀
意外なことに雀が来た。そう、「舌切り雀」。講談社の絵本で鴨下晁湖の絵。
これについてはこちらに色々と書いたのでご参考までに。
講談社の絵本原画展 2016年秋
紹介されていたのはおじいさんが雀娘と梅見するシーン。椿や松も綺麗に咲く。
まん丸に近い雀のアタマのついたヒトガタに鮮やかな色合いのおべべ。
雀の変化というとこれ以外思い浮かばないなあ。
・蛇 蛇の化身または化生するのは大概女ということになつてゐる。
いきなり旧仮名遣いになってしまうくらい昔から変わらない。
蛇おばさんというマンガもあったなあ。蛇男といえば伊黒さんくらいか。蛇柱の。でも彼は蛇に変身するのではなく、蛇の親友・鏑丸と行動を共にしているので蛇ではない。
そういえば萩尾望都さんの「マージナル」の何話かに「へびおとこ」がいたな。
さて蛇女の話。
やっぱり王道は安珍清姫。
国会図書館のデジタルコレクションからもパネル展示あり。
出てたのは日高川を行く舟をにらみつける清姫。
そして橘小夢のペン画の安珍清姫。蛇体に巻き付かれる全裸の安珍。もう絶望しかない顔。
かれのヘアの表現が少しばかりアールヌーヴォー風にも見えた。
安珍て受くさいのよね。
現代の画家・加藤美紀さんの描く「日高川」もある。呼吸も描かれていてそれが゜おどろおどろしい。
次に現れたのは上田秋成「雨月物語」蛇性の淫
小夢の肉筆画もある。真名児のにんまりした顔。髪を弄りながら。
まさかの玉井徳太郎の挿絵もあった。これは小学館の少年少女世界の名作文学47巻の「雨月」の挿絵らしい。
ただここでは物語は子供の頃に豊雄が蛇をいじめたが為に仕返しをされそうになったものの、今の豊雄が可愛くて蛇は仕返しを止めて、という設定らしい。
「今の豊雄は可愛い。仇討ちが出来なくて困っている」とのこと。侍女まろや共々態度が大きい。
・人魚
これも確かに妖しい。
山岸凉子さんの「八百比丘尼」の掲載されたプチフラワーが出ている。
(偶然ながら右ページにはカムイ伝の宣伝)
この「八百比丘尼」は人魚が実は宇宙人でエネルギー補給の為に地球で、というなかなか怖い話なんだよな。
人魚で怖いというと、諸星大二郎「サイレン」もそう。それから人魚で鵜飼するのもあった。
いやいや、もおほんまに怖い。
福井の空印寺縁起のパネル展示もある。このお寺は旅に疲れた八百比丘尼が入定した洞穴があるそう。
絵にはナマズに乗る女、カメに乗る爺さん、まな板に乗る人魚などなど。
とある人からこの軸を貰ったというのがまたミステリアスな。
アマビエも出た。これも人魚の仲間なのか。
海から来るものは不思議だものなあ。
小夢 水妖 サンゴなどが巻き付く蛇体。色々とバージョンがあるようだ。

表情も凄い。

さてここで江戸の戯作登場。
山東京伝「箱入娘面屋人魚」なるふざけた話。なんと近年映画化までされてるらしい。
国会図書館のデジタルコレクションには絵入本がある。
顔の次にすぐ魚の胴というのも怖いな。
しょっぱなに「まじめな口上」と題した序文と作者の絵があること自体ふざけてますがな。
簡単に記すと、乙姫の男妾・浦島太郎は魚と浮気して一女をもうけて困っている。
漁師の平二がその子を拾う。口に筆咥えて絵を描いたりするうち、義足のついたぱっちをはかせて「魚人」うおんど という源氏名で見世に出す。しかし顔は綺麗でも生臭くて客は逃げ出し、ついに「なめ料」で稼ぐことになる。これは人魚を舐めたら若返るということで、色事なしに侍も女客も並ぶほどの人気となる。
やがて人魚も一皮むけてヒトになり、ついには「勘平殿に似たやうな」いい男と和合し、「二人は今も生きてゐる」そうで、「深川の八幡で御開帳ありし玉手箱は即ちこれなり」とオチがつく。
20ページほどだし読みやすいよ。絵は豊国。
いよいよ水島爾保布「人魚の嘆き」登場。谷崎も若い頃は西洋賛美でした。
この挿絵は中公文庫版の「魔術師・人魚の嘆き」で全編見れます。
肉付きのいい人魚。

ここにはないが、清方「妖魚」もいいのですよ。
高橋葉介の人魚の話もとんでもなく異妖。
ぜひ。
・霊魂
今回の展覧会のメインヴィジュアルとなったのが御正伸の「葵」
二人の女の醸し出すただならぬ雰囲気が怖い怖い…
実は最初に見たとき、女が二人いるとはわからなかったのだ。
日本では六条御息所が生霊の代表。光君の正妻・葵上をはじめ色々と。
与謝野晶子の源氏では新井勝利の挿絵。これはカラー版の河出ので11点がある。
平家物語は怨霊オンパレード。ここでも御正伸の油彩画が。
75年「残霊」 青と緑の使い方が怖い。対する弁慶の強さすら呑み込まれそう。
伊藤彦造も「平家」を描いている。これも「少年少女文学全集」。
同じシリーズでは「耳なし芳一」をペン画で描いたのと大物のカラー画がある。
「牡丹灯籠」小夢のモノクロ画。5点ある。
・やってくる二人の女・蚊やりをする新三郎・蚊帳の外にいるお露・凄い顔の新三郎とお露・お米。
怖いよねえ…
実は三遊亭圓朝のそれより先に瞿佑のそれを読んだのよね。講談社少年少女向け本「怪談」で。
しかも辰巳四郎のおぞけを振るう挿絵がまた…棺から出る二本の腕とか、棺の外にはみ出る男の着物の裾とか…
2014年には岩崎書店から佐竹美保さんの絵で刊行されてるが、骸骨が新三郎に添い寝する絵がなかなか怖い。
・両性具有の神々
ここでは男装の天照と弟の素戔嗚との「誓約」うけひが行われたことから始まる。
下って人の時代となり、女装して熊襲を討つ日本武尊、三韓征伐で男装する神功皇后がいる。
やがて白拍子として男舞を見せる静御前、出雲阿国の紹介がある。
異装することで通常でない力を得るという信仰があったのだ。
展示にはないが、大本教の出口王仁三郎が中国大陸に行ったとき、かれは女装しての旅だった。
歌舞伎なども現行の形になって以後「女形」の存在がある。
更にそこで敦盛の女装、天狗小僧の女装が現れ、お嬢吉三、弁天小僧がいる。
白洲正子「両性具有の美」などはそのことについて詳しい。
長くなりすぎるので一旦ここまで。
メインヴィジュアルは御正伸である。

かれの展覧会も数年前に開催されている。
この傾向の展覧会は以前に「魔性の女」展がある。
当時の感想はこちら
「魔性の女」挿絵展 1
「魔性の女」挿絵展 2
弥生美術館は挿絵作品がコレクションの主体なので、他の美術館にはない面白さがある。
外連味といえば外連味なのだが、そこが魅力なのだ。
一目で心を掴むことが大事な挿絵・口絵にはそれ自体に既に魔性と文芸性とが同居している。それが「奇想」でもある。
そしてそこに現れた麗人たちの前にわれわれは跪くことになる。
わたしは12/26に訪ねた。
年の瀬の押し迫った最中にこの展覧会を主目的として出かけたのだ。
友の会会員としてだけでなく、決して見逃してはならぬ展覧会なのだ。
須藤しげる「春の女神」から始まる展示。
1933.4少女倶楽部。領巾が綺麗な装束。白い蝶がひらひら。
そしていよいよ。
化生のいきものから始まる。
異類婚で最も数の多いのが狐である。
華陽夫人、妲己、玉藻の前の系譜だけでなく、哀れにゆかしい葛の葉の物語は長く人口に膾炙した。
創作物でもこれは男性だが「きつね三吉」などがある。
黒地の着物がある。
一つは狐の嫁入り行列の図。もう一つは山川秀峰の「葛の葉」を写したとおぼしき図様のもの。秋草の野を往く女(=狐)
どちらも拵えた人の遊び心を伺わせる着物である。
葛の葉は芝居になる以前から五大説経の一つにも数えられたり、瞽女歌にもあった。
秋元松代の傑作「元禄港歌」はその「葛の葉」をライトモチーフにし、更に舞台で実際に瞽女役の演者に三味線で弾き語りをさせた。
わたしなどは亡くなった藤間紫の歌声が今も耳に残る。
他にも本当の瞽女さんの歌を録音したものを武蔵野吉祥寺美術館の斎藤真一展で聴いてもいる。
橘小夢の玉藻の前が二点。
以前の展覧会のメインヴィジュアルとなった、影が狐のものと、モノクロで狐が一人くつろぐものと。
几帳の向こうで笑う。几帳も春をモチーフとした小綺麗な装飾がついている。屏風もそう。
・雀
意外なことに雀が来た。そう、「舌切り雀」。講談社の絵本で鴨下晁湖の絵。
これについてはこちらに色々と書いたのでご参考までに。
講談社の絵本原画展 2016年秋
紹介されていたのはおじいさんが雀娘と梅見するシーン。椿や松も綺麗に咲く。
まん丸に近い雀のアタマのついたヒトガタに鮮やかな色合いのおべべ。
雀の変化というとこれ以外思い浮かばないなあ。
・蛇 蛇の化身または化生するのは大概女ということになつてゐる。
いきなり旧仮名遣いになってしまうくらい昔から変わらない。
蛇おばさんというマンガもあったなあ。蛇男といえば伊黒さんくらいか。蛇柱の。でも彼は蛇に変身するのではなく、蛇の親友・鏑丸と行動を共にしているので蛇ではない。
そういえば萩尾望都さんの「マージナル」の何話かに「へびおとこ」がいたな。
さて蛇女の話。
やっぱり王道は安珍清姫。
国会図書館のデジタルコレクションからもパネル展示あり。
出てたのは日高川を行く舟をにらみつける清姫。
そして橘小夢のペン画の安珍清姫。蛇体に巻き付かれる全裸の安珍。もう絶望しかない顔。
かれのヘアの表現が少しばかりアールヌーヴォー風にも見えた。
安珍て受くさいのよね。
現代の画家・加藤美紀さんの描く「日高川」もある。呼吸も描かれていてそれが゜おどろおどろしい。
次に現れたのは上田秋成「雨月物語」蛇性の淫
小夢の肉筆画もある。真名児のにんまりした顔。髪を弄りながら。
まさかの玉井徳太郎の挿絵もあった。これは小学館の少年少女世界の名作文学47巻の「雨月」の挿絵らしい。
ただここでは物語は子供の頃に豊雄が蛇をいじめたが為に仕返しをされそうになったものの、今の豊雄が可愛くて蛇は仕返しを止めて、という設定らしい。
「今の豊雄は可愛い。仇討ちが出来なくて困っている」とのこと。侍女まろや共々態度が大きい。
・人魚
これも確かに妖しい。
山岸凉子さんの「八百比丘尼」の掲載されたプチフラワーが出ている。
(偶然ながら右ページにはカムイ伝の宣伝)
この「八百比丘尼」は人魚が実は宇宙人でエネルギー補給の為に地球で、というなかなか怖い話なんだよな。
人魚で怖いというと、諸星大二郎「サイレン」もそう。それから人魚で鵜飼するのもあった。
いやいや、もおほんまに怖い。
福井の空印寺縁起のパネル展示もある。このお寺は旅に疲れた八百比丘尼が入定した洞穴があるそう。
絵にはナマズに乗る女、カメに乗る爺さん、まな板に乗る人魚などなど。
とある人からこの軸を貰ったというのがまたミステリアスな。
アマビエも出た。これも人魚の仲間なのか。
海から来るものは不思議だものなあ。
小夢 水妖 サンゴなどが巻き付く蛇体。色々とバージョンがあるようだ。

表情も凄い。

さてここで江戸の戯作登場。
山東京伝「箱入娘面屋人魚」なるふざけた話。なんと近年映画化までされてるらしい。
国会図書館のデジタルコレクションには絵入本がある。
顔の次にすぐ魚の胴というのも怖いな。
しょっぱなに「まじめな口上」と題した序文と作者の絵があること自体ふざけてますがな。
簡単に記すと、乙姫の男妾・浦島太郎は魚と浮気して一女をもうけて困っている。
漁師の平二がその子を拾う。口に筆咥えて絵を描いたりするうち、義足のついたぱっちをはかせて「魚人」うおんど という源氏名で見世に出す。しかし顔は綺麗でも生臭くて客は逃げ出し、ついに「なめ料」で稼ぐことになる。これは人魚を舐めたら若返るということで、色事なしに侍も女客も並ぶほどの人気となる。
やがて人魚も一皮むけてヒトになり、ついには「勘平殿に似たやうな」いい男と和合し、「二人は今も生きてゐる」そうで、「深川の八幡で御開帳ありし玉手箱は即ちこれなり」とオチがつく。
20ページほどだし読みやすいよ。絵は豊国。
いよいよ水島爾保布「人魚の嘆き」登場。谷崎も若い頃は西洋賛美でした。
この挿絵は中公文庫版の「魔術師・人魚の嘆き」で全編見れます。
肉付きのいい人魚。

ここにはないが、清方「妖魚」もいいのですよ。
高橋葉介の人魚の話もとんでもなく異妖。
ぜひ。
・霊魂
今回の展覧会のメインヴィジュアルとなったのが御正伸の「葵」
二人の女の醸し出すただならぬ雰囲気が怖い怖い…
実は最初に見たとき、女が二人いるとはわからなかったのだ。
日本では六条御息所が生霊の代表。光君の正妻・葵上をはじめ色々と。
与謝野晶子の源氏では新井勝利の挿絵。これはカラー版の河出ので11点がある。
平家物語は怨霊オンパレード。ここでも御正伸の油彩画が。
75年「残霊」 青と緑の使い方が怖い。対する弁慶の強さすら呑み込まれそう。
伊藤彦造も「平家」を描いている。これも「少年少女文学全集」。
同じシリーズでは「耳なし芳一」をペン画で描いたのと大物のカラー画がある。
「牡丹灯籠」小夢のモノクロ画。5点ある。
・やってくる二人の女・蚊やりをする新三郎・蚊帳の外にいるお露・凄い顔の新三郎とお露・お米。
怖いよねえ…
実は三遊亭圓朝のそれより先に瞿佑のそれを読んだのよね。講談社少年少女向け本「怪談」で。
しかも辰巳四郎のおぞけを振るう挿絵がまた…棺から出る二本の腕とか、棺の外にはみ出る男の着物の裾とか…
2014年には岩崎書店から佐竹美保さんの絵で刊行されてるが、骸骨が新三郎に添い寝する絵がなかなか怖い。
・両性具有の神々
ここでは男装の天照と弟の素戔嗚との「誓約」うけひが行われたことから始まる。
下って人の時代となり、女装して熊襲を討つ日本武尊、三韓征伐で男装する神功皇后がいる。
やがて白拍子として男舞を見せる静御前、出雲阿国の紹介がある。
異装することで通常でない力を得るという信仰があったのだ。
展示にはないが、大本教の出口王仁三郎が中国大陸に行ったとき、かれは女装しての旅だった。
歌舞伎なども現行の形になって以後「女形」の存在がある。
更にそこで敦盛の女装、天狗小僧の女装が現れ、お嬢吉三、弁天小僧がいる。
白洲正子「両性具有の美」などはそのことについて詳しい。
長くなりすぎるので一旦ここまで。