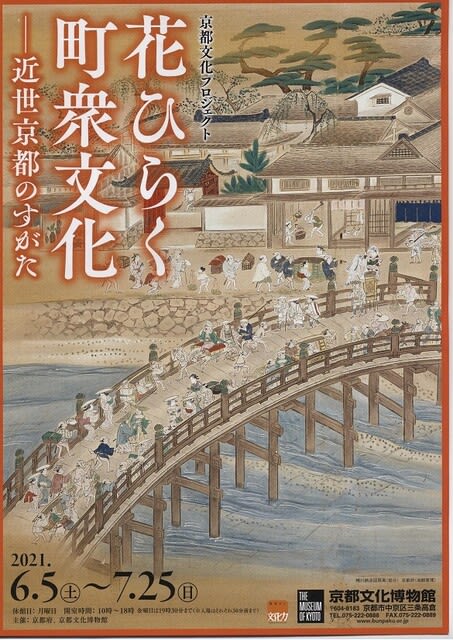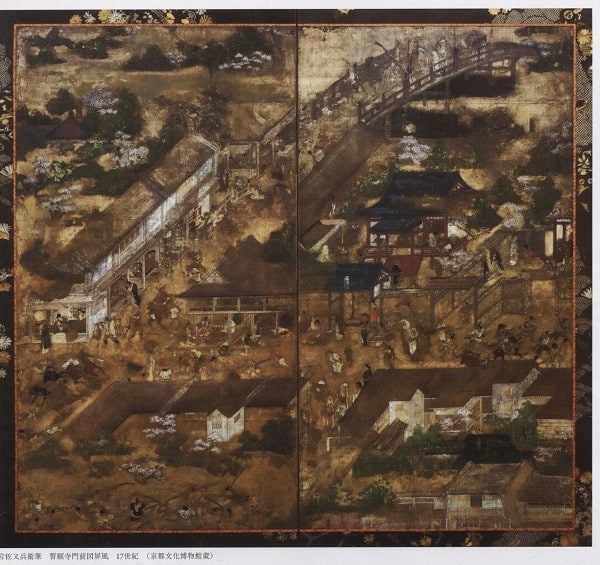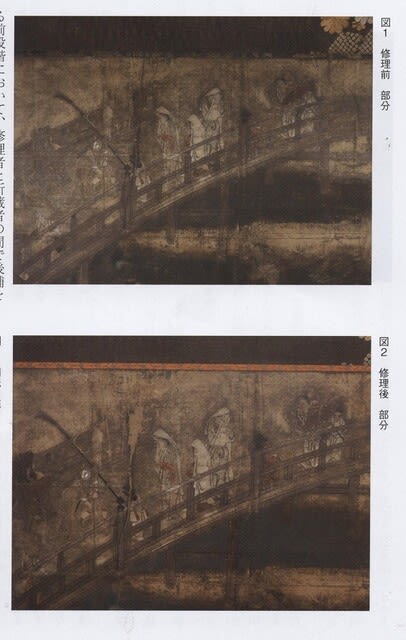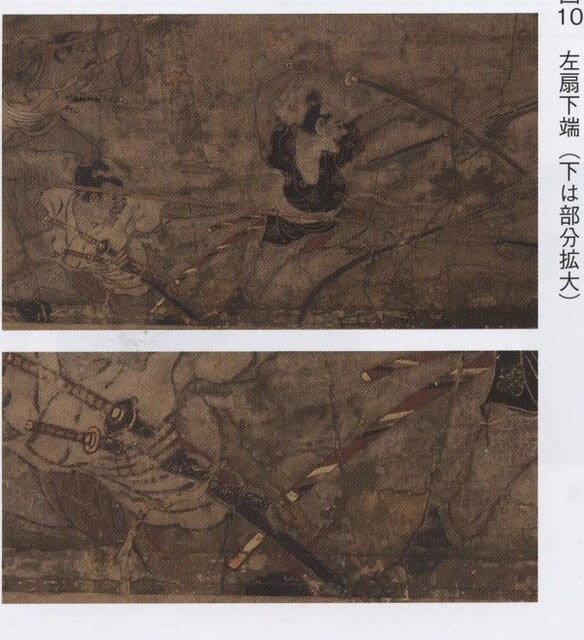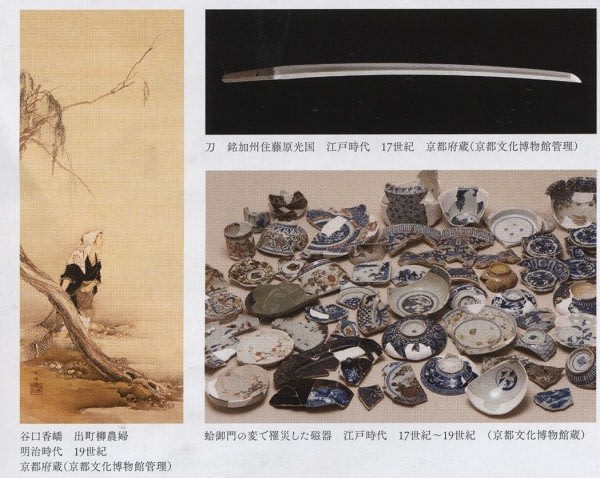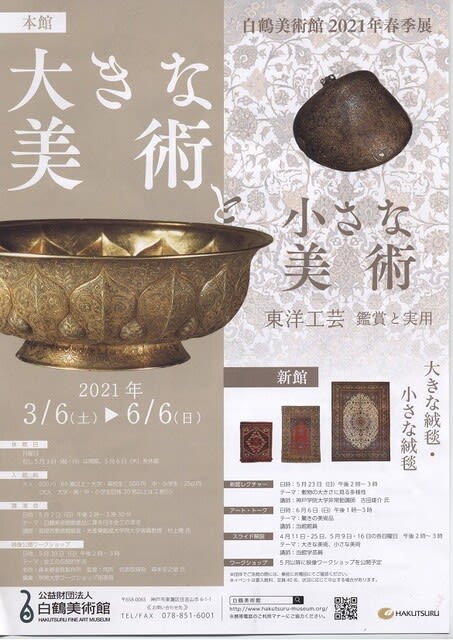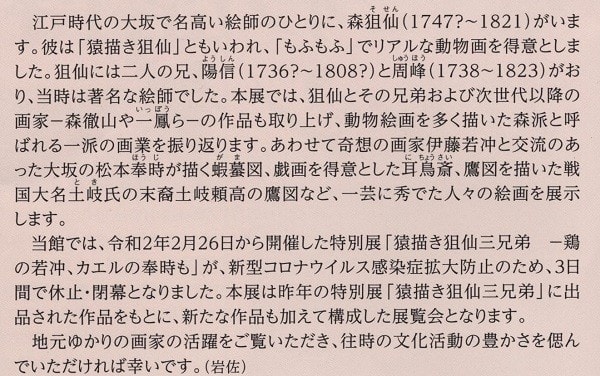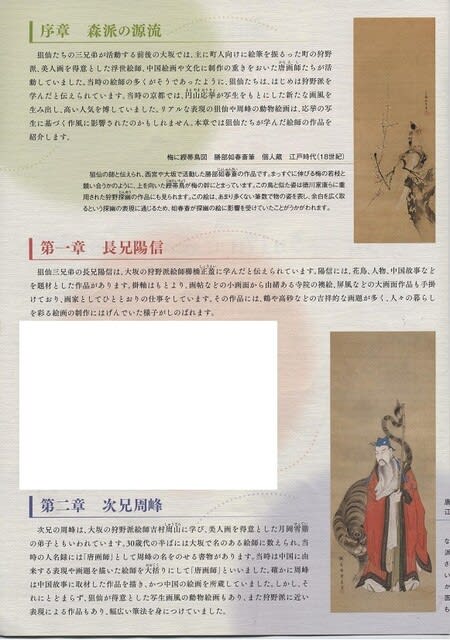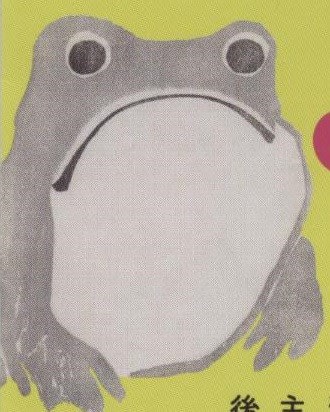弥生美術館で70年代後半から80年代初頭にかけて大人気の「おとめちっく」の立役者の一人・田渕由美子展が開催されている。
日本の少女雑誌の歴史の中で「なかよし」「りぼん」は派閥が分かれていて、たまにどちらも好きと言う少女もいるが(わたしとかな)、大抵はどちらかに寄る。
その「りぼん」で短編マンガ、イラスト、付録に大活躍した田渕由美子の原画が展示されているわけだが、あの当時から田渕由美子ファンのわたしは行ける日を数えて待ち、とうとう朝からおとめちっくな世界に浸ることが出来た。

彼女は長期連載を持たない人ではあるが、読者の心に深い印象を残す作家である。
代表作と呼ばれる「フランス窓便り」の昔から、たいへん丁寧で繊細な絵柄と、こだわりのある植物描写、素敵な小物が心に活きている。
彼女は兵庫県に生まれ、豊中市で育ったとある。これはもうたいへんよくわかる。
わたしは豊中生まれの豊中育ち、先祖代々の土着民だが、兵庫の阪神間と昔で言う南摂あたりの地には非常に親しさを感じている。これはわたし一人の感性ではないだろう。
手塚治虫は豊中生まれだが、宝塚育ちである。同じだと言っていい。
北摂の人間を「阪急王国」の住民と言う巧い表現をした人がいるが阪急王国は兵庫県の東部分にも及ぶのである。
そして彼女の2000年代の自伝的な風味のある作品「大阪マウンテンブルース」を読むと、色々と思い当たることもある。また早稲田大学へ入学したことにもいくつかの予想がわく。
さて本題に戻り、作品の展示からうけたわたしのときめきを記してゆく。
改めて言うが、これはわたしの感想なので、展覧会レポではないのである。
展覧会レポはわたしなどではなく、もっと知性と理性のある方々が書いてくださるものなのだ。
・初期作品から
「雪やこんこん」 既にもう物語の展開も表現も後の田渕さんを彷彿とさせる。
こんな初期からずっとあのしなやかで魅力的な感性が活きていたのだ。
可愛くて、綺麗で、センスのいい、あの世界。
田渕さんの特徴として、大学生活を舞台にした作品が多いことが挙げられる。
今回の展示でのご本人の言葉などから、マンガ家デビューが早かったことから大学進学を考えなかったと知った。しかし周囲、就中編集者さんからの言葉で早稲田へ進んだそうで、結局それが本当によかったのだ。
また、進学を考えないといった北摂の女子高校生が現役で早大合格と言うだけで、どれほど田渕さんが「勉強のできる人」なのかがわかる話でもある。
ちょっと飛ぶが、日本橋ヨヲコさんの「少女ファイト」でもマンガ家志望の少年に対し、編集者さんが進学を良い言葉で勧めていて、これもとても印象に残っている。
「ライム・ラブ・ストーリー」 これも読んで印象に残っている。片思いの男性の気を惹くためにと、友人にごり押しされて、スケスケのシースルーを着たものの、やはり恥ずかしくて天気がいいのにレインコートを着て出向いたヒロイン。
当時シースルーは知っていたが、下着だという認識を持っていたのでびっくりした。
小学生のわたしはこの作品を読んで、シースルーはちょっと…と思うようになった。
今この原画を見て、展示に該当シーンはなくても印象深いシーンだったので、脳裏に展開されていった。
作中、陸奥A子さんへの私信が壁ポスターとして貼られていた。昭和の頃はこうしたちょっとしたおまけのようなものがわりと少女マンガにはあった。
ファンには嬉しいおまけなのである。
田渕さんの作品にはやさしい男しかいない。
1990年代の女性誌での連載以外には皆無である。
わたしは基本的にラブコメは受け入れられない体質である。
恋愛の成就が目的である作品には本当に関心がないが、田渕さんの作品だけは別で、繰り返し読み続けるのは、出てくる男性にやさしさがあり、女性をバカにしない性質が見えるからだと思う。
暴力もなく、女性にきちんと向き合う男性がいるという点でも、田渕さんの作品は輝く。
「クロッカス咲いたら」 この頃からはっきりと作画の中の植物の魅力が大きくなったように思う。いわゆる「花を背負った」キャラが描かれているのではなく、葉っぱや木花が背景に活きているのだ。その植物の描写に深く惹かれた。
今見ても本当に初々しい。葉っぱがやさしくて、風を感じる作画なのである。
「やさしい香りのする秋に」 素敵。着ているカーディガンも綺麗。日常を丁寧に生きている感じがある。
「フランス窓便り」 三人の娘のオムニバスもの。葉っぱもフランス窓のある建物も、なにもかもが素敵。この背景だけでときめく。
他人と勘違いされる杏、美大生でスモーカーの茜、大人っぽい詮子(みちこ)。それぞれの恋愛譚。
田渕さんによると、全然フランス窓とは無縁だったそうで、和も和だったとやら。
今でこそ和の建物、民家への目も優しくなったが、この時代は和に対してはあまり…
ところで他の作品、後の「桃子について」でもそうだが、けっこうスモーカーの女性が多いな。
当時は何も思わなかったが、田渕さんのキャラのタバコはどんな意味を持つのだろう。
…案外ご本人がタバコ好きなのかもしれないし、背伸びを意味するのかもしれないし、と考えることはいくらでも出てくる。
尤も、同時代のりぼん掲載の一条ゆかり作品「ハスキーボイスでささやいて」にはヘビースモーカーのマニッシュなミュージシャンが登場する。ボーイッシュではない、マニッシュなのである。そしてこの作品の彼女のそのスタイルが実は騒動の種となるのだが。
「あなたに」 ああ、これは今のわたしからすれば「こらっ」だな。だけど、それでも作画と感性に惹かれるのだ。
「ブルー・グリーン・メロディ」 1979.1月号 この作品が欧米物の最後だという。ああ、これは好きな作品で「林檎ものがたり」に収録されているが、大体同時期に読んだ弓月光「ラクラクBF獲得法」でも同じような指南書のせいでトラブルと誤解が生まれる話があり、子供心に「こういう文書は処分しないとヤバいな」と強く思ったものだ。
マンガでいろんなことを学んできたが、料理以外のノウハウ本に無関心なのはこの時からだ。
なお「ラクラク」は同時期に刊行された「ぶーけ」誌の冒頭の目玉たる再録で読んだのだ。
そして「ブルー…」での指南書とは正確にはノウハウ本ではなく、探偵社の所長が拵えた余計な文書なのである。
箱入りのお嬢さんが一人暮らしを始め自立しようとする。その父親が心配し、彼女の監視・保護を探偵社に頼んだことから話が動き始めるのだ。
カット絵がある。それだけでもムードがある。描かれた人の背景や性格はわからないのに、何か惹かれる。
今わたしは学生時代以来の長髪なのだが、根底には田渕さんの描く素敵な長髪への憧れがあると思う。そしてわたしはこの髪で今なら田渕さんの描く素敵な世界の住人になれるような錯覚を懐いている。
この妄想は手放せない。ヘア・ドネーションのための既定の長さにカットする日までは。
「りぼん」表紙絵のいくつかが並んでいた。
77.12月号 クリスマスプレゼントを期待して、ちょっと欲深くとても大きな靴下を手にする少女と、その背後の窓から中の様子を見ているサンタさん。
この号の掲載作品は
陸奥A子「そりの音さえ聞こえそう」、千明初美「涙が出ちゃう」、佐伯かよの「思い聖夜」。
他に連載陣の一条ゆかり「砂の城」、坂東江利子「ちょいまちミータン」、みを・まこと「キノコ💛キノコ」…懐かしくて涙出そう。
千明さん、どうされているのだろう…
78年10月号 太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、一条ゆかり「砂の城」金子節子「オッス美里ちゃん」、陸奥A子「歌い忘れた1小節」
この頃は「ミリちゃん」ものでしたか。今思っても「歌い忘れた1小節」はいいタイトルだなあ。「おとめちっく」を体現しているよ。
79年4月号 これにポスターにもなった「菜の花キャベツがささやいて」が掲載されているが、この号はわたしもよく覚えている。
清原なつの「桜の森の満開の下」、太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、金子節子「オッス! Gパン先生」、佐伯かよの「ハローマリアン」、一条ゆかり「砂の城」…
清原さんの「桜の森の…」はタイトルはそれだが別に安吾の作品とは無縁だ。わたしはこちらを先に知った。この作品は後に初期作品集のメインタイトルにもなった。
清原さんは「飛鳥昔がたり」がいちばん好きだが、どの作品にもふんわりしたものとせつなさとがあった。ああ「花岡ちゃんの夏休み」もよかったなあ。
79年10月号 太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、金子節子「オッス! Gパン先生」、佐伯かよの「ハローマリアン」、一条ゆかり「砂の城」
80年5月号 一条ゆかり「ときめきのシルバースター」、太刀掛秀子「まりの、君の声が」、久保田律子「たんぽぽ空へ」
この頃はもうあの「砂の城」「花ぶらんこ」も連載終了し、お二方の次の連載はそんなに重いものではなくなっていた。
「まりの」では今は懐かしきカセットテープに吹き込まれた声が次の下宿者にエールを送っていたのだったかな。
…わたしもこの頃までだったなあ、「りぼん」「なかよし」を読んでいたのは。
この頃のわたしは「少年ジャンプ」で「リングにかけろ」に熱狂し、「花とゆめ」で「はみだしっ子」にハラハラしていたのだ。
同時代の「なかよし」の紹介もあった。
「キャンディキャンディ」「おはようスパンク」「わんころべえ」がある。
みんな面白かったなあ。諸事情により二度と「キャンディキャンディ」が世に出ないのは非常に残念だ。近年になりわたしは家から偶然「キャンディ」全巻を発掘し、ちょっと言葉もなくなった。
田渕さんの一枚絵の良さは表紙絵だけでなく付録にも生かされている。
色んな付録がずらりと並ぶ。陸奥A子さんの「スペースファイル」79年6月号 は今も手元にある。
付録、もろに「おとめちっく」と書いてあるねえ。

トランプ、レターパット、ノート…
へんなたとえかもしれないが、歌手で言えば「りぼん」はユーミン、「なかよし」は中島みゆきのようなものだと思っている。
「林檎ものがたり」の紹介がある。これもオムニバス。
田渕さんの言葉によると、物語としては三話目がいちばんよいようだが、それぞれ面白く読んだものです。
第一話表紙 セピアとチェック柄と赤の配置がとても素敵。
そうそう、三話目のヒロインの名字が「納所さん」で、この作品からこの名字を知ったのだった。あと野草を食べるということも。
単行本表紙絵 胸のリンゴがとても存在感がある。

この作品集には前述「ブルー・グリーン・メロディ」も入る。
そして「菜の花キャベツがささやいて」で〆なのだが、今回の展示で初めてこの作品が「風色通りまがりかど」の続編だと知った。
「菜の花キャベツ」では学生結婚した周さんと林子の間の色々あることが描かれていたが、二人の住まうビンボーくさいアパートは田渕さんの最初の下宿がモデルだと知り、にやりとなった。
この作品を知ってから数年後にわたしは今東光「春泥尼抄」を読み、そこで阿倍野のアパートの様子が「菜の花キャベツ」のそれと同じだと思ったものだ。
つまりある一定年代までは東京も大阪もこういう形態のアパートが少なくなかったということなのだ。
単行本裏表紙には林子のイラストが載る。

「夏からの手紙」 ああ、ゆで卵をおでこで割る二人。そう、同じことをする二人の話で、男子の方がテスト用に鉛筆を削りコロコロと…それを彼女にそっと渡して転校してゆくのだよな。この作品を読んでからわたしも鉛筆の下に〇Xとか入れたなあ。←青春というより思春期。
「あの頃の風景」は81年2月号の付録だそう。今この原画を見て「ををを」になった。
この作品は未読なんだけど、小6の調理実習メニューが懐かしくて…
目玉焼き、ほうれん草のバター炒め、粉ふき芋。
これ、わたしも小学校の時拵えましたよ。豊中市の小学生の定番なのかな。
「つかの間の午後」83年4月号 これはまた大人っぽい物語だなあ。大学教員と再婚する若い女…年の差が大きいのとか色々考えるね。
ちょっと違うけど「みいら採り猟奇譚」を思い出すわたしはもう「おとめちっく」から遠く離れたなあ。
ポーリー・ポエットそばかすななつ 「赤毛のアン」を好きだったというのを知り、それを踏まえてこの作品を見ると、ファブリックや建物の佇まい、町の在り方にも納得する。
そしてこの話自体は「ブルー・グリーン・メロディ」の別バージョンだという感想をどこかで見て、なるほどとも思う。
布の質感、レンガの表面、そんなものが感じられる絵。
やがて子育てで一線を退き、表紙絵だけを世に贈るようになる田渕さん。
80年代のカラー絵は水彩画ではない。カラーインクを使用する。
時代に沿った画風に変ってゆく…
コバルト文庫の仕事もされていたのか。おお、「赤毛のアン」の挿絵も。
今から思うと80年代の絵は、なかじ有紀さんの「学生の領分」とも共通するものがあるなあ。特に髪型がね。
そして95年「チュー坊がふたり」エッセイマンガを連載された。
これは掲載誌は読んでないが、単行本が98年に刊行されてから読んで、非常に嬉しかった。
「子育てが一段落して復活されたんだ」
この嬉しさと言うのはちょっと言葉に出来ない。
YOUNG YOUなどで陸奥さんが復活されたときもそうだった。
「りぼん」の少女たちが真っ当な成長を遂げた姿がここにある、と思った。
これについては以前弥生美術館で開催された陸奥A子展でも書いている。当時の感想はこちら
陸奥A子+ふろく展
「桃子について」が世に出たとき、とても嬉しかった。
わたしの手元にあるのは新装版である。おしゃれしている桃子。

彼女と付き合う相手の青年がやっぱり田渕由美子世界のヒトで、これもすごくうれしかった。桃子自身は翻訳の下請け作業をして、とても多忙で、しかしあまり収入は良くない。最初に好きになった相手は、自分の妹と結婚する。その痛手を隠して桃子は妹一家に誠実に向き合う。
やがて自分より年下のまだ学生の山男の青年とようやく付き合い始めて、そこから諸々の揺れがあり、生活苦もなんとかなり、未来が開けてくる。
ほっとした。
作中でテート・ギャラリー展に行くのがまたリアルで。
そうそう、わたしも見に行った見に行った、と嬉しく思いもした。
こちらは裏表紙

ところで田渕さんは水彩画を好む理由についても語っている。
そこでは「たよりなさのある水彩」と表現している。
ああ、なんだかわかるなあ。田渕さんの繊細な絵にはやはり水彩絵の具がいいもの…
20世紀末から21世紀初頭にかけて田渕さんは連載作品を何本も出す。嬉しい。
短編もよかった。
「NO.ブランド」 素敵な表紙絵。


収録の「外は白い雪」は男の都合のよさにちょっと腹が立つのだが、ここに出てくる古い洋館がとても素敵で、わたしが近代洋風建築が好きな要因には田渕さんの作品も関わっているかもしれない、と今になって考えたりしている。
そしてこの作品集ではりぼん時代から一歩進んでラブシーンがあるが、その中でもタイトルの「NO.ブランド」のそれはかなり笑えるのだった。理由は読んだらわかるので書きません。ぜひご一読を。わははははは。
「オトメの悩み」 少女小説家・黒田笑さんの年下の編集者青年とのモダモダした話。
いやもう連載当時わたしも気になって気になって…なんだか知人を応援する心持だった。
丁度同世代だったのだ、この頃の田渕さんの作品のヒロインの大半は。
なのでわたしにもなにかこう…えへんえへん、もうかなり前なんだな。
そうだ思い出した。今回展示には出ていなかったが、京都・嵯峨野へ青年を案内する話を昔読んだがあのタイトルは何だったかな。着物を着て案内する娘さん。
それで下宿に来た青年の名が「日野」か「壬生」だったので、日野菜とか壬生菜とか呼ばれていたな。こういうところに大阪の人間の明るい感性を感じるのよ。
ラストに「大阪マウンテンブルース」の紹介が来た。

帰宅後、再読し直す。やっぱりせつないのと「ううう」となるのがある。
冒頭、ものすごく良くわかる。
そう、豊中辺りでは夕日は六甲山に沈むのよ。わたしの見る夕日も六甲山へ沈む。
ああ田渕さん、1970年も2021年の今も、その辺りは変わってないですよ。
裏表紙 いい男だなあ

休筆されてからもだいぶ経つ。もう描かれないそうだ。でも、描いてほしいと思う。
思うのはわたしの、わたしたちファンの勝手な気持ち。
今回の展覧会で改めて田渕さんの世界に浸ることが出来て本当に良かった。
やっぱり好きです。
6/27まで開催中。
日本の少女雑誌の歴史の中で「なかよし」「りぼん」は派閥が分かれていて、たまにどちらも好きと言う少女もいるが(わたしとかな)、大抵はどちらかに寄る。
その「りぼん」で短編マンガ、イラスト、付録に大活躍した田渕由美子の原画が展示されているわけだが、あの当時から田渕由美子ファンのわたしは行ける日を数えて待ち、とうとう朝からおとめちっくな世界に浸ることが出来た。

彼女は長期連載を持たない人ではあるが、読者の心に深い印象を残す作家である。
代表作と呼ばれる「フランス窓便り」の昔から、たいへん丁寧で繊細な絵柄と、こだわりのある植物描写、素敵な小物が心に活きている。
彼女は兵庫県に生まれ、豊中市で育ったとある。これはもうたいへんよくわかる。
わたしは豊中生まれの豊中育ち、先祖代々の土着民だが、兵庫の阪神間と昔で言う南摂あたりの地には非常に親しさを感じている。これはわたし一人の感性ではないだろう。
手塚治虫は豊中生まれだが、宝塚育ちである。同じだと言っていい。
北摂の人間を「阪急王国」の住民と言う巧い表現をした人がいるが阪急王国は兵庫県の東部分にも及ぶのである。
そして彼女の2000年代の自伝的な風味のある作品「大阪マウンテンブルース」を読むと、色々と思い当たることもある。また早稲田大学へ入学したことにもいくつかの予想がわく。
さて本題に戻り、作品の展示からうけたわたしのときめきを記してゆく。
改めて言うが、これはわたしの感想なので、展覧会レポではないのである。
展覧会レポはわたしなどではなく、もっと知性と理性のある方々が書いてくださるものなのだ。
・初期作品から
「雪やこんこん」 既にもう物語の展開も表現も後の田渕さんを彷彿とさせる。
こんな初期からずっとあのしなやかで魅力的な感性が活きていたのだ。
可愛くて、綺麗で、センスのいい、あの世界。
田渕さんの特徴として、大学生活を舞台にした作品が多いことが挙げられる。
今回の展示でのご本人の言葉などから、マンガ家デビューが早かったことから大学進学を考えなかったと知った。しかし周囲、就中編集者さんからの言葉で早稲田へ進んだそうで、結局それが本当によかったのだ。
また、進学を考えないといった北摂の女子高校生が現役で早大合格と言うだけで、どれほど田渕さんが「勉強のできる人」なのかがわかる話でもある。
ちょっと飛ぶが、日本橋ヨヲコさんの「少女ファイト」でもマンガ家志望の少年に対し、編集者さんが進学を良い言葉で勧めていて、これもとても印象に残っている。
「ライム・ラブ・ストーリー」 これも読んで印象に残っている。片思いの男性の気を惹くためにと、友人にごり押しされて、スケスケのシースルーを着たものの、やはり恥ずかしくて天気がいいのにレインコートを着て出向いたヒロイン。
当時シースルーは知っていたが、下着だという認識を持っていたのでびっくりした。
小学生のわたしはこの作品を読んで、シースルーはちょっと…と思うようになった。
今この原画を見て、展示に該当シーンはなくても印象深いシーンだったので、脳裏に展開されていった。
作中、陸奥A子さんへの私信が壁ポスターとして貼られていた。昭和の頃はこうしたちょっとしたおまけのようなものがわりと少女マンガにはあった。
ファンには嬉しいおまけなのである。
田渕さんの作品にはやさしい男しかいない。
1990年代の女性誌での連載以外には皆無である。
わたしは基本的にラブコメは受け入れられない体質である。
恋愛の成就が目的である作品には本当に関心がないが、田渕さんの作品だけは別で、繰り返し読み続けるのは、出てくる男性にやさしさがあり、女性をバカにしない性質が見えるからだと思う。
暴力もなく、女性にきちんと向き合う男性がいるという点でも、田渕さんの作品は輝く。
「クロッカス咲いたら」 この頃からはっきりと作画の中の植物の魅力が大きくなったように思う。いわゆる「花を背負った」キャラが描かれているのではなく、葉っぱや木花が背景に活きているのだ。その植物の描写に深く惹かれた。
今見ても本当に初々しい。葉っぱがやさしくて、風を感じる作画なのである。
「やさしい香りのする秋に」 素敵。着ているカーディガンも綺麗。日常を丁寧に生きている感じがある。
「フランス窓便り」 三人の娘のオムニバスもの。葉っぱもフランス窓のある建物も、なにもかもが素敵。この背景だけでときめく。
他人と勘違いされる杏、美大生でスモーカーの茜、大人っぽい詮子(みちこ)。それぞれの恋愛譚。
田渕さんによると、全然フランス窓とは無縁だったそうで、和も和だったとやら。
今でこそ和の建物、民家への目も優しくなったが、この時代は和に対してはあまり…
ところで他の作品、後の「桃子について」でもそうだが、けっこうスモーカーの女性が多いな。
当時は何も思わなかったが、田渕さんのキャラのタバコはどんな意味を持つのだろう。
…案外ご本人がタバコ好きなのかもしれないし、背伸びを意味するのかもしれないし、と考えることはいくらでも出てくる。
尤も、同時代のりぼん掲載の一条ゆかり作品「ハスキーボイスでささやいて」にはヘビースモーカーのマニッシュなミュージシャンが登場する。ボーイッシュではない、マニッシュなのである。そしてこの作品の彼女のそのスタイルが実は騒動の種となるのだが。
「あなたに」 ああ、これは今のわたしからすれば「こらっ」だな。だけど、それでも作画と感性に惹かれるのだ。
「ブルー・グリーン・メロディ」 1979.1月号 この作品が欧米物の最後だという。ああ、これは好きな作品で「林檎ものがたり」に収録されているが、大体同時期に読んだ弓月光「ラクラクBF獲得法」でも同じような指南書のせいでトラブルと誤解が生まれる話があり、子供心に「こういう文書は処分しないとヤバいな」と強く思ったものだ。
マンガでいろんなことを学んできたが、料理以外のノウハウ本に無関心なのはこの時からだ。
なお「ラクラク」は同時期に刊行された「ぶーけ」誌の冒頭の目玉たる再録で読んだのだ。
そして「ブルー…」での指南書とは正確にはノウハウ本ではなく、探偵社の所長が拵えた余計な文書なのである。
箱入りのお嬢さんが一人暮らしを始め自立しようとする。その父親が心配し、彼女の監視・保護を探偵社に頼んだことから話が動き始めるのだ。
カット絵がある。それだけでもムードがある。描かれた人の背景や性格はわからないのに、何か惹かれる。
今わたしは学生時代以来の長髪なのだが、根底には田渕さんの描く素敵な長髪への憧れがあると思う。そしてわたしはこの髪で今なら田渕さんの描く素敵な世界の住人になれるような錯覚を懐いている。
この妄想は手放せない。ヘア・ドネーションのための既定の長さにカットする日までは。
「りぼん」表紙絵のいくつかが並んでいた。
77.12月号 クリスマスプレゼントを期待して、ちょっと欲深くとても大きな靴下を手にする少女と、その背後の窓から中の様子を見ているサンタさん。
この号の掲載作品は
陸奥A子「そりの音さえ聞こえそう」、千明初美「涙が出ちゃう」、佐伯かよの「思い聖夜」。
他に連載陣の一条ゆかり「砂の城」、坂東江利子「ちょいまちミータン」、みを・まこと「キノコ💛キノコ」…懐かしくて涙出そう。
千明さん、どうされているのだろう…
78年10月号 太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、一条ゆかり「砂の城」金子節子「オッス美里ちゃん」、陸奥A子「歌い忘れた1小節」
この頃は「ミリちゃん」ものでしたか。今思っても「歌い忘れた1小節」はいいタイトルだなあ。「おとめちっく」を体現しているよ。
79年4月号 これにポスターにもなった「菜の花キャベツがささやいて」が掲載されているが、この号はわたしもよく覚えている。
清原なつの「桜の森の満開の下」、太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、金子節子「オッス! Gパン先生」、佐伯かよの「ハローマリアン」、一条ゆかり「砂の城」…
清原さんの「桜の森の…」はタイトルはそれだが別に安吾の作品とは無縁だ。わたしはこちらを先に知った。この作品は後に初期作品集のメインタイトルにもなった。
清原さんは「飛鳥昔がたり」がいちばん好きだが、どの作品にもふんわりしたものとせつなさとがあった。ああ「花岡ちゃんの夏休み」もよかったなあ。
79年10月号 太刀掛秀子「花ぶらんこゆれて」、金子節子「オッス! Gパン先生」、佐伯かよの「ハローマリアン」、一条ゆかり「砂の城」
80年5月号 一条ゆかり「ときめきのシルバースター」、太刀掛秀子「まりの、君の声が」、久保田律子「たんぽぽ空へ」
この頃はもうあの「砂の城」「花ぶらんこ」も連載終了し、お二方の次の連載はそんなに重いものではなくなっていた。
「まりの」では今は懐かしきカセットテープに吹き込まれた声が次の下宿者にエールを送っていたのだったかな。
…わたしもこの頃までだったなあ、「りぼん」「なかよし」を読んでいたのは。
この頃のわたしは「少年ジャンプ」で「リングにかけろ」に熱狂し、「花とゆめ」で「はみだしっ子」にハラハラしていたのだ。
同時代の「なかよし」の紹介もあった。
「キャンディキャンディ」「おはようスパンク」「わんころべえ」がある。
みんな面白かったなあ。諸事情により二度と「キャンディキャンディ」が世に出ないのは非常に残念だ。近年になりわたしは家から偶然「キャンディ」全巻を発掘し、ちょっと言葉もなくなった。
田渕さんの一枚絵の良さは表紙絵だけでなく付録にも生かされている。
色んな付録がずらりと並ぶ。陸奥A子さんの「スペースファイル」79年6月号 は今も手元にある。
付録、もろに「おとめちっく」と書いてあるねえ。

トランプ、レターパット、ノート…
へんなたとえかもしれないが、歌手で言えば「りぼん」はユーミン、「なかよし」は中島みゆきのようなものだと思っている。
「林檎ものがたり」の紹介がある。これもオムニバス。
田渕さんの言葉によると、物語としては三話目がいちばんよいようだが、それぞれ面白く読んだものです。
第一話表紙 セピアとチェック柄と赤の配置がとても素敵。
そうそう、三話目のヒロインの名字が「納所さん」で、この作品からこの名字を知ったのだった。あと野草を食べるということも。
単行本表紙絵 胸のリンゴがとても存在感がある。

この作品集には前述「ブルー・グリーン・メロディ」も入る。
そして「菜の花キャベツがささやいて」で〆なのだが、今回の展示で初めてこの作品が「風色通りまがりかど」の続編だと知った。
「菜の花キャベツ」では学生結婚した周さんと林子の間の色々あることが描かれていたが、二人の住まうビンボーくさいアパートは田渕さんの最初の下宿がモデルだと知り、にやりとなった。
この作品を知ってから数年後にわたしは今東光「春泥尼抄」を読み、そこで阿倍野のアパートの様子が「菜の花キャベツ」のそれと同じだと思ったものだ。
つまりある一定年代までは東京も大阪もこういう形態のアパートが少なくなかったということなのだ。
単行本裏表紙には林子のイラストが載る。

「夏からの手紙」 ああ、ゆで卵をおでこで割る二人。そう、同じことをする二人の話で、男子の方がテスト用に鉛筆を削りコロコロと…それを彼女にそっと渡して転校してゆくのだよな。この作品を読んでからわたしも鉛筆の下に〇Xとか入れたなあ。←青春というより思春期。
「あの頃の風景」は81年2月号の付録だそう。今この原画を見て「ををを」になった。
この作品は未読なんだけど、小6の調理実習メニューが懐かしくて…
目玉焼き、ほうれん草のバター炒め、粉ふき芋。
これ、わたしも小学校の時拵えましたよ。豊中市の小学生の定番なのかな。
「つかの間の午後」83年4月号 これはまた大人っぽい物語だなあ。大学教員と再婚する若い女…年の差が大きいのとか色々考えるね。
ちょっと違うけど「みいら採り猟奇譚」を思い出すわたしはもう「おとめちっく」から遠く離れたなあ。
ポーリー・ポエットそばかすななつ 「赤毛のアン」を好きだったというのを知り、それを踏まえてこの作品を見ると、ファブリックや建物の佇まい、町の在り方にも納得する。
そしてこの話自体は「ブルー・グリーン・メロディ」の別バージョンだという感想をどこかで見て、なるほどとも思う。
布の質感、レンガの表面、そんなものが感じられる絵。
やがて子育てで一線を退き、表紙絵だけを世に贈るようになる田渕さん。
80年代のカラー絵は水彩画ではない。カラーインクを使用する。
時代に沿った画風に変ってゆく…
コバルト文庫の仕事もされていたのか。おお、「赤毛のアン」の挿絵も。
今から思うと80年代の絵は、なかじ有紀さんの「学生の領分」とも共通するものがあるなあ。特に髪型がね。
そして95年「チュー坊がふたり」エッセイマンガを連載された。
これは掲載誌は読んでないが、単行本が98年に刊行されてから読んで、非常に嬉しかった。
「子育てが一段落して復活されたんだ」
この嬉しさと言うのはちょっと言葉に出来ない。
YOUNG YOUなどで陸奥さんが復活されたときもそうだった。
「りぼん」の少女たちが真っ当な成長を遂げた姿がここにある、と思った。
これについては以前弥生美術館で開催された陸奥A子展でも書いている。当時の感想はこちら
陸奥A子+ふろく展
「桃子について」が世に出たとき、とても嬉しかった。
わたしの手元にあるのは新装版である。おしゃれしている桃子。

彼女と付き合う相手の青年がやっぱり田渕由美子世界のヒトで、これもすごくうれしかった。桃子自身は翻訳の下請け作業をして、とても多忙で、しかしあまり収入は良くない。最初に好きになった相手は、自分の妹と結婚する。その痛手を隠して桃子は妹一家に誠実に向き合う。
やがて自分より年下のまだ学生の山男の青年とようやく付き合い始めて、そこから諸々の揺れがあり、生活苦もなんとかなり、未来が開けてくる。
ほっとした。
作中でテート・ギャラリー展に行くのがまたリアルで。
そうそう、わたしも見に行った見に行った、と嬉しく思いもした。
こちらは裏表紙

ところで田渕さんは水彩画を好む理由についても語っている。
そこでは「たよりなさのある水彩」と表現している。
ああ、なんだかわかるなあ。田渕さんの繊細な絵にはやはり水彩絵の具がいいもの…
20世紀末から21世紀初頭にかけて田渕さんは連載作品を何本も出す。嬉しい。
短編もよかった。
「NO.ブランド」 素敵な表紙絵。


収録の「外は白い雪」は男の都合のよさにちょっと腹が立つのだが、ここに出てくる古い洋館がとても素敵で、わたしが近代洋風建築が好きな要因には田渕さんの作品も関わっているかもしれない、と今になって考えたりしている。
そしてこの作品集ではりぼん時代から一歩進んでラブシーンがあるが、その中でもタイトルの「NO.ブランド」のそれはかなり笑えるのだった。理由は読んだらわかるので書きません。ぜひご一読を。わははははは。
「オトメの悩み」 少女小説家・黒田笑さんの年下の編集者青年とのモダモダした話。
いやもう連載当時わたしも気になって気になって…なんだか知人を応援する心持だった。
丁度同世代だったのだ、この頃の田渕さんの作品のヒロインの大半は。
なのでわたしにもなにかこう…えへんえへん、もうかなり前なんだな。
そうだ思い出した。今回展示には出ていなかったが、京都・嵯峨野へ青年を案内する話を昔読んだがあのタイトルは何だったかな。着物を着て案内する娘さん。
それで下宿に来た青年の名が「日野」か「壬生」だったので、日野菜とか壬生菜とか呼ばれていたな。こういうところに大阪の人間の明るい感性を感じるのよ。
ラストに「大阪マウンテンブルース」の紹介が来た。

帰宅後、再読し直す。やっぱりせつないのと「ううう」となるのがある。
冒頭、ものすごく良くわかる。
そう、豊中辺りでは夕日は六甲山に沈むのよ。わたしの見る夕日も六甲山へ沈む。
ああ田渕さん、1970年も2021年の今も、その辺りは変わってないですよ。
裏表紙 いい男だなあ

休筆されてからもだいぶ経つ。もう描かれないそうだ。でも、描いてほしいと思う。
思うのはわたしの、わたしたちファンの勝手な気持ち。
今回の展覧会で改めて田渕さんの世界に浸ることが出来て本当に良かった。
やっぱり好きです。
6/27まで開催中。