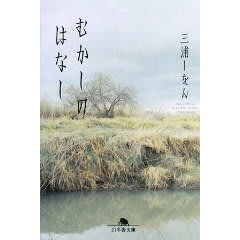『光』 三浦しをん著
重厚なミステリー小説だ。これまでの爽やかな作品とは違い新たな著者を見た気がした。
天災ですべてを失った中学生の信之。共に生き残った幼なじみの美花を救うため、彼はある行動をとる。二十年後過去を封印して暮らす信之の前に、もう一人の生き残り・輔が姿を現す。あの秘密の記憶から、今、新たな黒い影が生まれようとしていた…。
小さな島から端を発した事件が20年の歳月を経て新たな不幸と愛憎を生む、でもそこに存在するのは、ドロドロの悪意ではなく冷たく澄みきった邪悪さ。
もやもやしたものをもやもやしたまま投げかけてくるから、後味が悪いが、気持ちは悪くならない。暴力的で怖さを感じるのに、どこか清涼感があるのがたまらなく好き。
なんか、キツめの炭酸水を呑んだイメージ。独特の文体のせいかもしれない。
登場人物については少しながらの不満が残る。
女優になるほどの美形なはずの美花は少しも想像できない。美花のためなら冷酷になれる信之の秘密に隠された性格も同様。輔はただ気持ち悪いだけ(子供の時も大人になった時も)。でも信之の妻、南海子はこの作品の主人公といっても過言ではないぐらい想像できた。世間で一番この手の主婦が多いからだろう。
怖いのは、南海子の視点から見た夫と家族の描写。
島の記憶をすべて封印し、穏やかな家庭を持ったようにみえる信之が心に抱える闇。わからないながらもそれを感じ取って脅え、でもなにもできずに漠然とした不安を抱えて生きている南海子。彼女の苛立ちや恐怖が手に取るように伝わってきて、心底怖いと思った。幼い娘にあたってしまうところなどは本当にリアルで、誰にでもあり得ることのような気がしてゾッとする。
著者は「夫婦」という単位を基本的に居心地の悪いもの、気味の悪いものと感じているような気がする。擬似家族、「家族的なもの」に向けるまなざしは優しいのに、いわゆる「普通の家族」に対してすごく突き放した感じがある。それと、人間は基本的にわかりあえないものだという所を常に出発点にしている感じもある。
ちょっと前の桐野夏生小説に似ているなぁ。
でもこの作品でまた、いろいろなことが気づかされたのでそれで良し。
重厚なミステリー小説だ。これまでの爽やかな作品とは違い新たな著者を見た気がした。
天災ですべてを失った中学生の信之。共に生き残った幼なじみの美花を救うため、彼はある行動をとる。二十年後過去を封印して暮らす信之の前に、もう一人の生き残り・輔が姿を現す。あの秘密の記憶から、今、新たな黒い影が生まれようとしていた…。
小さな島から端を発した事件が20年の歳月を経て新たな不幸と愛憎を生む、でもそこに存在するのは、ドロドロの悪意ではなく冷たく澄みきった邪悪さ。
もやもやしたものをもやもやしたまま投げかけてくるから、後味が悪いが、気持ちは悪くならない。暴力的で怖さを感じるのに、どこか清涼感があるのがたまらなく好き。
なんか、キツめの炭酸水を呑んだイメージ。独特の文体のせいかもしれない。
登場人物については少しながらの不満が残る。
女優になるほどの美形なはずの美花は少しも想像できない。美花のためなら冷酷になれる信之の秘密に隠された性格も同様。輔はただ気持ち悪いだけ(子供の時も大人になった時も)。でも信之の妻、南海子はこの作品の主人公といっても過言ではないぐらい想像できた。世間で一番この手の主婦が多いからだろう。
怖いのは、南海子の視点から見た夫と家族の描写。
島の記憶をすべて封印し、穏やかな家庭を持ったようにみえる信之が心に抱える闇。わからないながらもそれを感じ取って脅え、でもなにもできずに漠然とした不安を抱えて生きている南海子。彼女の苛立ちや恐怖が手に取るように伝わってきて、心底怖いと思った。幼い娘にあたってしまうところなどは本当にリアルで、誰にでもあり得ることのような気がしてゾッとする。
著者は「夫婦」という単位を基本的に居心地の悪いもの、気味の悪いものと感じているような気がする。擬似家族、「家族的なもの」に向けるまなざしは優しいのに、いわゆる「普通の家族」に対してすごく突き放した感じがある。それと、人間は基本的にわかりあえないものだという所を常に出発点にしている感じもある。
ちょっと前の桐野夏生小説に似ているなぁ。
でもこの作品でまた、いろいろなことが気づかされたのでそれで良し。