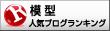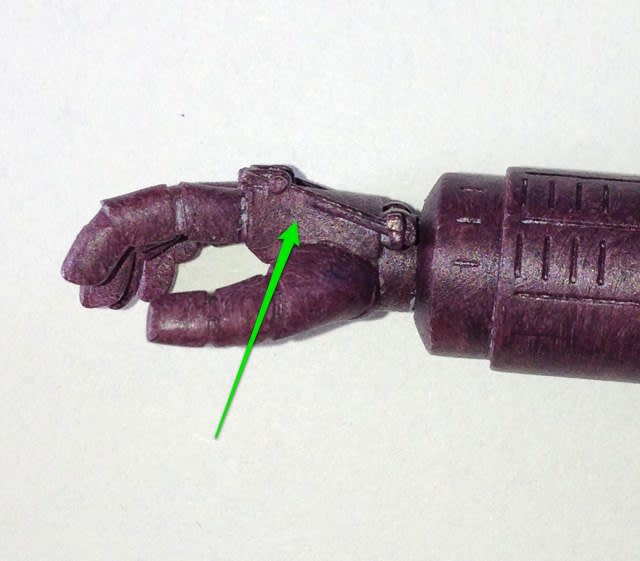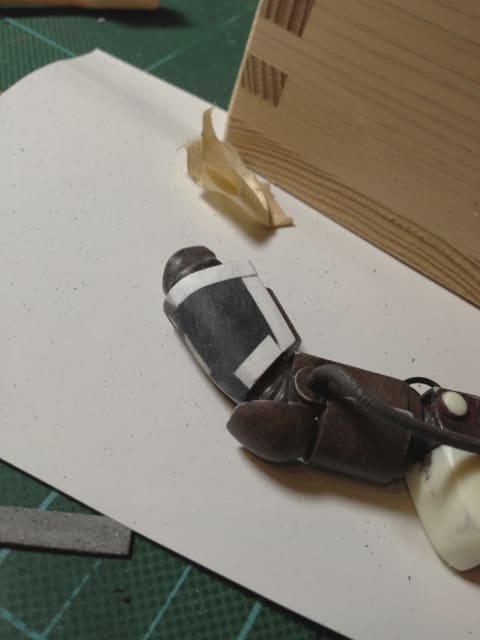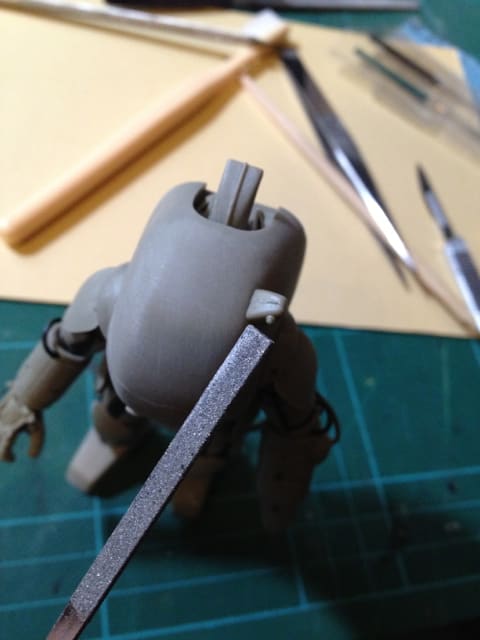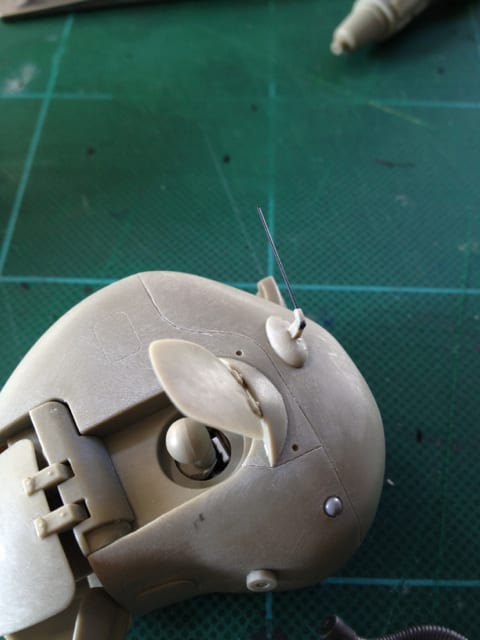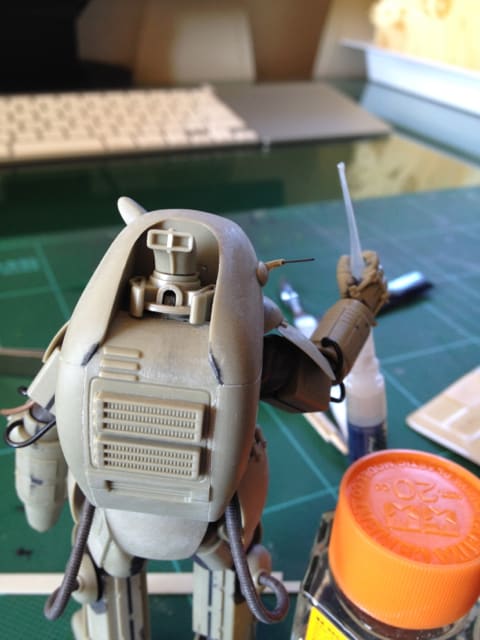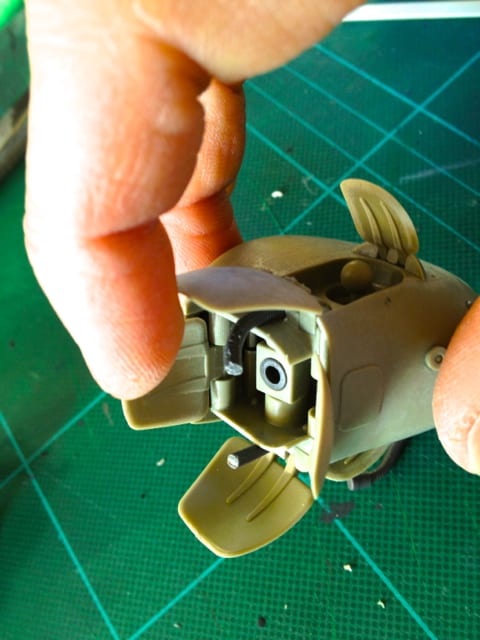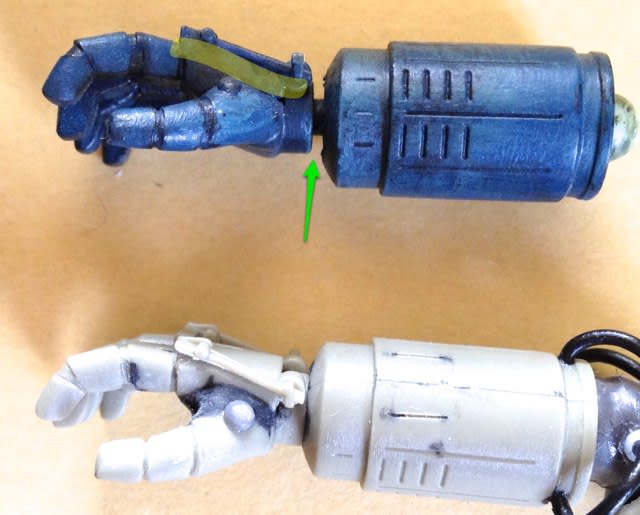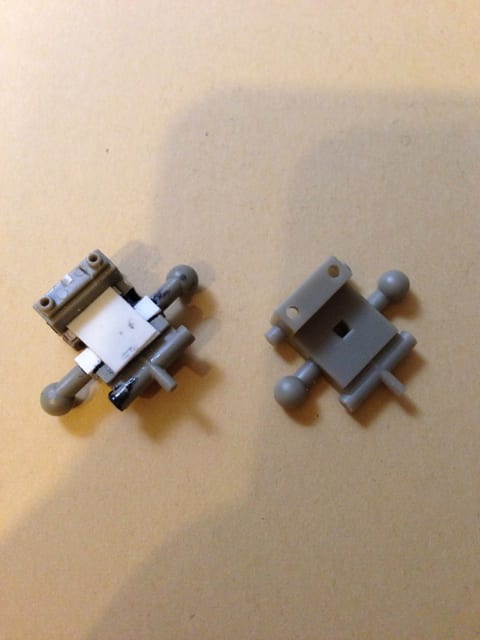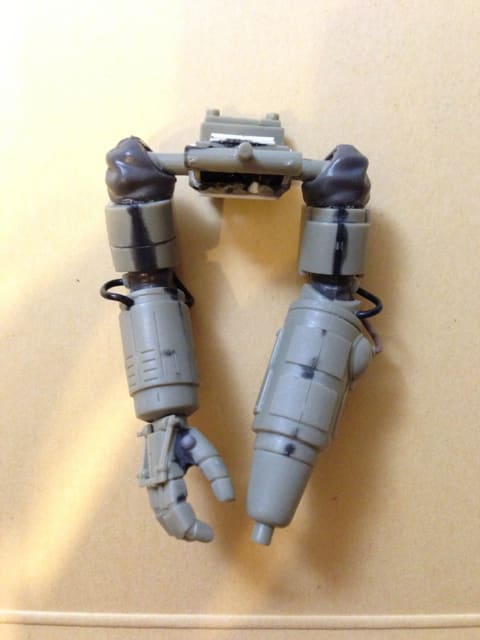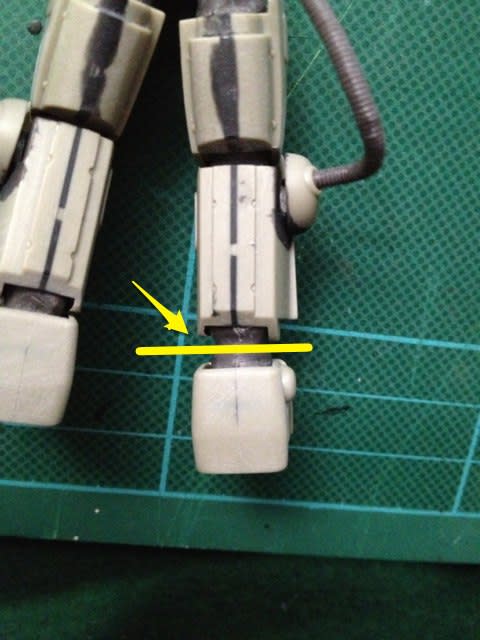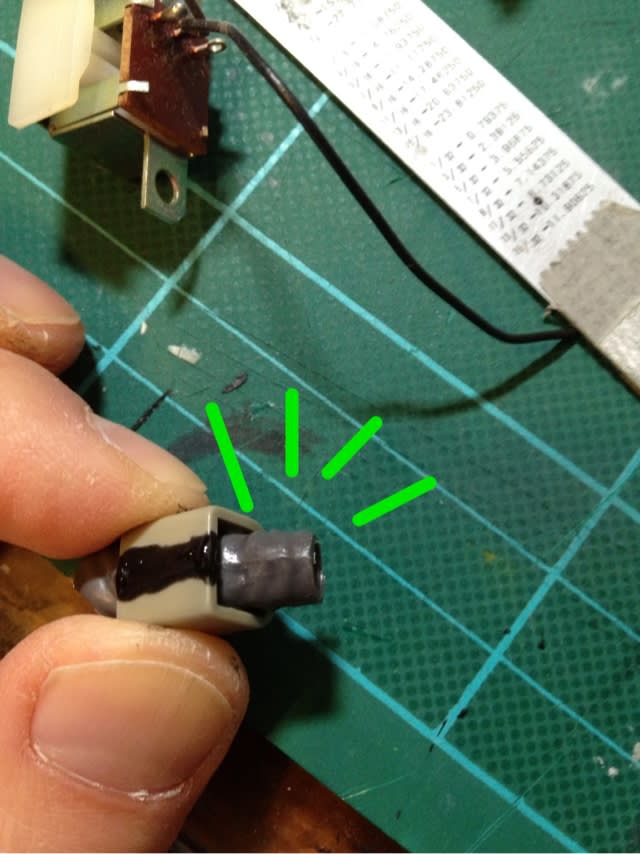ポーラーベアは前回でおしまい。
アーケロンにもどってきました。

このキット、どうも上半身と下半身に一体感が感じられないのです。
ポーラーベアを加工中もアーケロンは机においていて、なんとなく頭の片隅で考え続けていたのですが、腰の前面の装甲が小さい気がしてきました。
検証。

日東グスタフの装甲を貼ってみました。
これはちょっと大きすぎるけど、なんか見えてきた気がしない?
装甲板は、横山先生のオリジナルモデルでは、ピンポン玉が使用されています。
ファンのあいだでは有名な話なわけですが、実践している人は意外と見ないですね。プラスプーンを使っている人は時々いらっしゃいますが。
マシーネラーは締まり屋が多い?w

先ほどのグスタフの装甲をあてがってあたりをとります。

ノコギリで大ざっぱに切り出します。

ハサミで余白をていねいに切りとります。
(昔料理番組で聞いて、へぇと思った話なのですが、日本人はハサミを活用していない民族だそうです。例えば料理、朝食にほうれん草の油炒めでも作ろうかというとき、包丁だとまな板を準備しなくてはいけないですが、フライパンの上でチョキチョキやれば時間短縮、洗い物も減って合理的とか。これってプラモでも当てはまるなあと、以来ハサミを積極的に使うようにしています)

グスタフのと基本おなじかたちで左右幅をへらしてみました。

ほら!断然いいんじゃない?
さっそく貼りつけます。

本来の装甲の上に貼っちゃいます。
下端が見切れていたので切り落しました。
もう少し手前に持ってきたいので、丸めたセロテープを貼って、、、

その上から黒瞬着を盛ります。

べチョッ!

宙に浮いた状態で固定されました。
...............................................................................

股関節の位置が高すぎる気がします。
素立ちの時は気になりませんが、足を大きく開いたポーズをとらせると、股が裂けたようで怖い、、、。
ので、ポリキャップの輪切りを挟みこんで微調整。
ビフォー/アフターを載せようと思ったのですが、画像では微妙すぎて伝わらないのでやめました(泣)
(人によっては真逆に、足の長さが気になって股関節位置を上げているケースも多いですね。
自分が胴長短足だから気になるのだろうか、、、)

もういいだろう。工作はこれでおしまい!