先日、母校のことをフォローする(庇う)文章を更新した。
ハンドルネームでツイッターのバッシングにいそしむ「ウルトラスーパーデラックスマン」(©藤子・F・不二雄)なみなさん、石をぶつける相手が欲しければ、まずワカキコースケまでどうぞ! ボクはフリーランスで無力だから潰しやすいし、リスクがなくていいですよ~! と丸腰で立ったつもりだったのだが。
反応ゼロ。
なんか、がっくりきてしまった。マジンガーZをたすけたいのに、そもそも敵キャラに相手にされないボスボロットの気分。
よくよく考えると(考えなくても)、バリューのない人間なんて足を引っ張る対象にならないし、まずもって、存在そのものが目に留まっていないんだ。ひとり上手もいいところだった。
精進します。
それでも、試写で見た映画の話を、誰のためでもなく。
『樹海のふたり』
2013 同作製作委員会 監督 山口秀矢
7月6日よりユーロスペースほか全国順次ロードショー
配給 アーク・フィルムズ 宣伝 フリーマン・オフィス
http://www.jukai-futari.com/
おもしろい成り立ちの映画だ。
まず監督の山口秀矢は、テレビ・ドキュメンタリーの大ベテラン。劇映画は初めてだという。
初めてとはいえ、現場、という1点に基準を置けば、若手インディーズ映画監督20人分のキャリアがある、大変な方である。へっぽこ構成作家の立場としては、制作プロ「ドキュメンタリー・ジャパン」出身で「えふぶんの壱」の設立者と聞くだけで、キーンと緊張してしまい、恐れ多くて傍にも寄れない。しかもプロフィールをよく読むと、黒木和雄に師事していたという。
そして撮影はやはりテレビ・ドキュメンタリーの大ベテランでありつつ、是枝裕和作品の共働でおなじみの山崎裕。
富士の樹海にカメラを持って張り込み、自殺志願者を説得する姿を撮影するディレクター2人組の話なので、おそらく自分達の仕事の経験から膨らんだストーリーなのではないかと思っていたら、違った。モデルがいた。
プレスシートによると、監督は、そういう切り口の取材で人の人生に立ち入るしんどさを抱えている後輩2人と出会ってインスピレーションを感じ、映画にする着想を得たのだそうだ。
おもしろい成り立ちというのは、ドキュメンタリーと劇との往還がつくりや視点の基本になっている点はもちろん、監督が、自分とは違うモチーフを追ったディレクター達をモデルに、ダブル主人公にしていることだ。ストレートな心情投影の人物にしていない。
この、『樹海のふたり』が持つやや複雑な厚みは、監督が黒木和雄に師事していたと聞くと、ずいぶん腑に落ちるところがある。
黒木和雄も、ある意味では分かりにくい映画作家だった。他の作家のテーマに題材を求めることで、自分のロマンを託す以上の想念が生まれるのを待つようなところがあった。黒木がドキュメンタリー出身であることの「らしさ」は、出来上がった映画の具体的な演出や手法より、企画の考え方のほうに顕著に出ている、というのが僕の印象。
『樹海のふたり』も、そうだ。長年の自身のドキュメンタリーへの思い(或いは蓄積や自負)に拠らない、頼らないストーリーにすることで、骨太な展開になっている。
死のイメージに覆われた樹海で、心身ともにとりこまれそうになった2人が、なんとか抜け出す。その時、イメージの位相が変わり、樹海の持つ本来の意味が浮かび上がる。理屈とストーリーの結構がしっかり噛みあった、ドーンとした骨組みによる最終提示が、とても良かった。
この映画に関しては、そこが伝われば一番だな、と思う。
せっかくなので、このあとはこの映画をめぐる想念を続けて書く。
ドラマの部分では登場人物の了解が観る人よりも早いところが少なからずあり(タテに置いても倒れない封筒のくだりなどはさっぱり呑み込めなかった)、面白いエピソードたっぷりなのに置いていかれる、惜しいところがある。
青春の燃やしそこねと格闘する2人の熱い生硬さは、1970年代のATG映画をほうふつとさせる懐かしい特長、とも言えるのだが、インパルスという、まさに今のカンどころで生きているコンビが演じているため、最初はかなり違和感がある。
つまり、『樹海のふたり』はそういう映画なのだ、と了解し慣れるまでに時間がかかる。
映画はディティールの集積物なので、こまかいところに何度も引っかかると、作り手の描くことがどんなに深くても好感を持ちにくくなるところがある。
ただでさえ僕は、80年代のポスト・モダンの文脈の世代。テーマなど無くても快楽的によどみなく画面を見せ切れる監督こそが真の映画作家なのだとアルフレッド・ヒッチコックやハワード・ホークス、マキノ正博を称揚する評価軸で洗礼を受けているので、体質的にはピタッとはこなかったのである。(そういえば当時の「シネアスト」の感覚では、黒木和雄ですらキツかったっけ)
でも、前述したように、底にある大きな骨組みは素晴らしいと思った。水面が描く波紋は決して好みではないズレをどう咀嚼すればよいのか、しばらくは分からなかった。要するに、ゴリゴリのシネフィルにも目を向けてもらえるポイントを見つけあぐねた。
ところが、『樹海のふたり』の数日後に、たまたま『80年代アメリカ映画100』(芸術新聞社)をめくり、デヴィッド・クローネンバーグの映画に一貫しているのは「精神と肉体の変容」(渡部幻)だとする解説を読んで、なるほどー、と感心しているうち。
そうか、『樹海のふたり』もだよ! と急にスルスル解けた気がしたのだった。
クローネンバーグの『ビデオドローム』と『樹海のふたり』は、途中まで似ている。
かたや、内面の空虚を抱えながらバイオレンスネタを探すテレビマンが、幻覚の世界にズブズブはまっていく話。こなた、生活の重荷を抱えながら樹海で番組ネタを探すテレビマンが、死の森と共鳴しそうになる話。
2人は白骨死体を何度も見て、慣れていく。やがて街へ下り、家にもどるほうが億劫になりかける。(このあたりになると、インパルスにノリのいい演技を禁じた効果がてきめんに出てくる。もともと2人のコントにはイヨネスコ的な演劇性があったっけ、と気づく)
1人は認知症の父親を、もう1人は自閉症児の息子を持っている。この設定が上っ面ではなく、映画の芯に直接関わっている。
2人はふつうの精神状態=シャバッ気のなかで生きているときは、家族を負担に感じている。しかし、樹海のなかで死の世界にとりこまれかけたとき、家族を重荷ではなく、別の精神世界で生きる者として再発見する。『ザ・フライ』のように蠅男にも、『イースタン・プロミス』のように刺青だらけにもならないけれど、気持ちの置き場所を変えることで「ニュー・フレッシュ」(クローネンバーグの言う「新人間」)になっていく。
まあ、だからといって、監督本人に聞いたとしても、「クローネンバーグ? 別に参考にはしていない」と答えがおそらく返ってくるだろう。
山口秀矢の演出がクローネンバーグを思わせるか、という話とは別。
いわゆる「相似」や「想起」ではなく、僕の場合は「テコ」なのだ。
僕自身が、『樹海のふたり』をテコにして考えたことで今ふたつ、みっつほどよく分からない存在だったクローネンバーグがずいぶん近くなったし、また、クローネンバーグをテコにすることで、『樹海のふたり』の良さをもう少し深く咀嚼できた、だけのこと。
ただ、テコの支点と力点は、まるで関係なく見えるもの同士だったほうがより面白いのだ。
シネフィルさんによっては、こうした発想法がカンに触る人もいるらしいのだが、まあ仕方ない。知的遊戯のひとつの方法と、ご理解いただきたい。
最後に助演陣について。
きたろうや烏丸せつこが良いのは当然として、不意打ちなのは、遠藤久美子だった。
「むかしはよく出てた元気印アイドル」だったエンクミが、かわいらしくてはかなげで、しかし母性をたっぷり湛えた女優になっていて、息詰まるほどでした。
















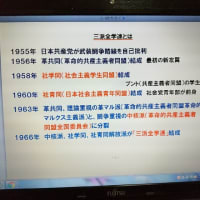
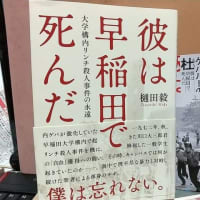

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます