少しまえがき
このブログの前回更新となる、「深田晃司に聞く~『LOVE LIFE』を中心に(Ⅰ)」
https://blog.goo.ne.jp/wakaki_1968/e/01e32390ee3ef69574fec50594105ea2
の続きです。できれば、前回も読んでいただければありがたいです。
非常に長いインタビュー記事になりましたが、これはもともと長い記事にしたい意向が僕にあり、深田晃司氏にもそうおねがいして快諾してもらえた結果です。
かつては、映画監督のインタビューは長いものほど印象的であることが多く、映画ファンだった頃は、そんな記事が載った雑誌や本を古書店で見つけると得した気分になりました。そういう、オールドスクールの時代の記事を再現したかったわけです。
具体的には、1970年代のキネマ旬報社『世界の映画作家』シリーズ中のロングインタビューや、白井佳夫のインタビュー集『監督の椅子』(81・話の特集)を深田晃司でカバーさせてもらった、という感じでしょうか。
(構成協力:繁田実和)
暴力反対イコール暴力を描かない、には必ずしもならない
― そこで聞いてみたいのが、深田晃司の映画のなかにある暴力性なんです。そこをどう意識して、どうコントロールしているのかなと思っていて。
深田 そうですねえ、暴力性……。直接的な描写はビンタ位なんですけどね。いや、ビンタも十分暴力ですけど。ああ、でも『椅子』はあれか。
― 子どもが酔って寝ている母親の彼氏をトンカチで殴り殺す。そもそも、その男の母親に対する暴力への仕返しなんだけど。
深田 ひどい話ですよね。あれはウィークリーマンションを借りて撮影したので、畳の上に血糊をぶちまけるわけにはいかないからどうしようとなって。考えた末に、透明のビニールシートを敷いてから撮影したんですよね。あれは我ながら賢かったなと思う(笑)。
― 血糊の作り方なんか、どこで教わったの?
深田 自分も全然知らなくて。手伝ってくれていた友人が美術スタッフの仕事をしていたんで、彼にやってもらったんです。
― 『椅子』はバイオレンスが突出した特例として、いつも深田映画のなかで暴力性は裏側に潜み、たまに見え隠れするような形であると感じています。特に『淵に立つ』は、実はいまだに深田映画のなかでは苦手で……八坂役の浅野忠信が怖いのよ。彼の持つ悪意が、いつ剥き出しになるか分からなくて。
深田 そうですか。浅野さんの表現する怖さは、確かに脚本で想定していた以上でしたね。
『LOVE LIFE』では、公開までネタバレ禁止をお願いしているところがあるので話すのが少し難しいんですけど、冒頭から数十分は、とにかくどれだけ見る人の注意をその後に起こるある暴力から逸らすかが勝負だったんです。そこにいきなり、何の伏線もなく不幸がやってきて、それまで積み上げてきた展開を断ち切るという。そこの狙いは『淵に立つ』も当初は同じで、日常のなかに暴力的なものが、何の前触れもなく侵入してくることを考えていたんです。
ただ、『淵に立つ』の場合は、浅野さんが画面の中に登場するだけで不穏な、何か起りそうな雰囲気が匂い立つから(笑)。浅野さんに出演いただけると決まった時点で、方向性を変えたんです。それはそれで満足しているんですけど。
― なるほど、『淵に立つ』もやはり例外的だったと。先ほど伺ったように、他の深田映画で出てくる直接的な暴力はビンタ位のものです。しかし、いきなり出てくるビンタの場面だって怖いからね。
『LOVE LIFE』では二回出てきますね。ひとつは、二郎の同僚である先輩と後輩がとぼけたやりとりをしていて、先輩が後輩の頭をはたく。もうひとつは、葬式の時にずっと行方知れずだったパクさんが現れて妙子の頬を叩く。それぞれの意図を聞かせてほしいです。

深田 『LOVE LIFE』では、今さっきの話の繰り返しになりますが、自然災害のような、悪意の介在しない世界が生来的に持つ暴力性、生きることや死ぬことの無目的な予測不可能性みたいなものを描きたかった。例えばこうして楽しく取材を受けていても、終わって外に出た途端に自分は車に轢かれて死んでしまう可能性はありますよね。そういう、伏線も理由も何もなく訪れる不幸を描きたかったんです。
私たちは規則正しい日常を送ることで、生の予測不可能性から目を逸らしてだましだまし生きています。しかし、日常は突然破られたり思いもよらない方向に進みます。その、呆気なさをできるだけ正確にスクリーンを通じて観客と共有するには、どうしたらいいのだろうと考えました。
多くの映画がそうであるように、私たちは生活においても予定調和を望みます。今回はその予定調和を突然断ち切る必要があるので、脚本にまずは様々なミスリードとなるような予定調和を仕掛けました。伏線をいろいろと入れて登場人物を増やして、複数のエピソードが同時に進む流れを作ったんです。
その一環として先輩と後輩のコメディ的な、ステレオタイプのコントのような描写を入れたりしていたので、頭をはたくのも、漫才やコントのツッコミのようなつもりでした。それが、職場の上下関係のなかでのパワハラを連想させてしまうということですよね?
― うん。申し訳ないけど、深田晃司監督の映画の中にこんな場面がある、とショックを受ける人は、いるだろうと思う。僕自身、見ていて少しドキッとしました。あれ、数年前なら特に気にならなかったかもしれないんだけどね。はたきかたがパチンッて、大きいのよ。
深田 確かに、思った以上に痛そうでしたよね。後輩のキャラクターがふてぶてしい感じだったので、あれ位のベタなツッコミは大丈夫かなと思って、見過ごしたのかもしれない。すいません、なんか。
― 二郎さんの職場の平和さを描きたい意図であったなら、了解できるんです。もしも先輩が一方的に言うだけで後輩が委縮しているような関係なら、ああいう演出はしなかったと思いますから。
深田 『さようなら』以外は全部ビンタの場面があるんですよね。たぶん最低限の、一番短い時間でシンプルに描ける突発的な暴力性として、自分の中でビンタが使いやすいんだと思います。
― それは、例えばディスコミュニケーションの状態を一番端的に表現できるということ? 葬式の場面だと、パクさんが怒り悲しみ、そのパニック状態をどう表現してよいのか分からなくて、つい妙子を叩いてしまったわけですよね。
深田 そうですね。怒りなどの感情の昂ぶりを抑制できずに暴力に至ってしまう。そういうことは、良くはないけどあるものなのだろうなと思います。
自分は身の回りや、映画の製作現場のなかで暴力が起きることに反対ですが、といって暴力を描かないのは違うという考え方です。それは世の中に、現に存在しているから。これは、バルザックがロマン主義の時代の作家で、ロマン主義的な価値観の人物達が小説の中に登場しつつ、彼らを非常に冷徹で、即物的な目から描くことでレアリズムの先駆となったこととも通じると思うんです。作家が自らの視点で同時代を描こうとすれば、当然、その視界には作家の主義や思想と相反することも入り込む。もちろん、何をモチーフにするかの取捨選択自体も作り手の作家性のひとつではありますが、暴力に反対していることイコール暴力を描かない、には必ずしもならないんです。
― それはよく分かります。自分はあらゆるハラスメントに反対だから、自分の映画のなかで暴力的な場面はNGにする。そういう選択もひとつの姿勢だけど、それがある種の隠蔽に繋がってしまうかもしれないことは、注意しなくちゃいけない。
深田 どれもケース・バイ・ケースなので慎重に話す必要があるんだけど……アメリカ映画の場合だと、強い女性がヒロイックに活躍するエンタテインメントが近年多いですよね。それ自体は「女性は弱く守られるもの」というこれまでの社会が求めてきたジェンダーステレオタイプを払拭するひとつのアクションとして悪くないのだけど、でもその爽快な表象ばかりが強調されてしまうと、現実にまだまだ根深く存在している女性差別を覆い隠してしまう形にフィクションが機能してしまうかもしれない。
人種についてもそうで、アメリカ映画は白人の主人公の上司が黒人という場合が多い。雇用機会などの配慮そのものは素晴らしいんだけど、そういうイメージを流布する映像の力に対して自覚的にならないと、現に存在する人種差別を覆い隠す、ガス抜きに映画が加担してしまうことにもなる。十代の頃で誰のテキストかも分からないのですが、そう論じている文章を読んだことがあって、なるほどなと、それが妙に記憶に残っているんです。
社会に対して理想像を持つのと、今この現実に対してカメラを向けるのは全く違うことで、重要なのはその現実を作家がどう描くかです。例えば、無理矢理セックスさせられた女性がそれをきっかけに男と恋愛に落ちてハッピーエンドなんて物語が仮に肯定的に描かれたとすれば、それは作り手の思想抜きには語れないはずです。『LOVE LIFE』では、パクが久々に再会した妙子の頬をひっぱたいたのをきっかけに二人の関係が復活していくんだけど、理不尽な暴力を受けたことに対して妙子がパクに抗議をし謝罪を求める場面は、どうしても外してはならなかった。
― 妙子がパクに「叩かれて痛かったよ」と言う夜の場面。なあなあにはしない、妙子のフェアな人柄の表現にもなっていました。
深田 男女を撮れば作り手のジェンダー観が映し出されるし、家族を撮れば家族観が反映される。作品というのはどれも、その作家の考え方を世界にフィードバックするものだと思っています。世に出る以上は、それは社会に影響を与えていくので、そこはきちんと、作り手は覚悟を持って自分自身の思想や哲学と向き合っていく必要があると思います。
会話の作り方は、めちゃめちゃ現代口語演劇の影響を受けている
― そこで、改めて聞いておきたいのが、深田晃司が平田オリザから受けた影響です。
僕、ずいぶん前に一度だけ、平田オリザさんが関わる仕事をしたことがあるの。ある教科書出版社の国語教材づくりの一環で、平田さんと谷川俊太郎さんの対談の進行を作ったことがあって。
深田 へえ。平田さんは谷川さんの大ファンだから、嬉しい仕事だったでしょうね。
― え、そうなの? 知らなかった。なんか谷川さんの前でも淡々とされていたから……(笑)。
まあいいや、とにかくその対談の平田オリザさんの発言でよく覚えているのが、会話と対話は日本ではゴッチャにされがちだけど違うものなんだという話だったんです。会話は基本的に関係性に乗っかったもので、「あれ取って」「これやっといて」で通じるし、同時に甘えも生じる。一方の対話は、自分はこれこれこう思っている、と親しい仲であっても言葉にして伝えること。
妙子が、パクさんに殴られた後で初めて会って、まずは「あの時は痛かったよ」と伝えてイーブンにしてから再び関係を作り出すのは、まさに平田オリザの言うところの対話だ、と思ったんですよ。それは多分、深田晃司のどの映画の根っこにもある。それで影響を聞いてみたいんだけど。
深田 映画の中の会話の作り方は、めちゃめちゃ平田さん、というか現代口語演劇の影響を受けていると思います。
これは映芸ダイアリーズ時代にもよく話したことですけど……映芸ダイアリーズ時代と言って何人が分かってくれるかな(笑)。とにかく僕は当初、演劇が嫌いでした。シネフィルにありがちなことでしょうが、映画以外の表現を基本的に見下す偏狭な映画至上主義者なところが以前の自分にはあって、演劇に色目を使っているような映画は軒並み否定していたんです。オーソン・ウェルズはいいけどローレンス・オリヴィエは認めないみたいな(笑)。
それに、学生時代に友人に誘われて見に行った舞台のほとんどがつまんなくて、みんなどうしてこんな大仰な演技をしているんだろうとしんどくて。ところが、『椅子』に出てくれた井上三奈子さんがその後で青年団に入ったんですね。公演があるから見に来て、と言われて見たものがとんでもなく面白くて。
本当に日常会話だけなんです。いわゆる〈セミパブリックな空間〉である、待合室みたいな場所を行き交う人達がただ言葉を交わす。簡単に本音をさらけ出すようなセリフは一つもないんだけど、でも、会話のやりとりからなんとなくこの人は寂しいのかもしれない、こういうことを考えているのかもしれない……と様々な想像ができる会話の作りになっていて、それが凄いと思った。
でも、よく考えてみれば、エリック・ロメールや成瀬巳喜男だってそもそもそういう映画じゃないかと気付いたんです。意味のないような日常会話から本音が透けて見えるような、さらに言えば本音を語っているらしき台詞が、その人自身にさえ本当に本心かどうか分かるわけはないという領域。ヌーヴェルヴァーグへの憧れで作られた自主映画は当時からよくあったけど、どうしてもフランスの素敵な恋愛映画のパロディの範疇に収まってしまう印象だった。でも、ロメールと現代口語演劇を足して二で割ったら新しいものができるんじゃないか、とその時は真剣に考えましたね。
2003年位からはもう青年団の追っかけみたいな感じで、公演は片っ端から見ました。その影響をもとに『Home Sweet Home』という、バラバラになっていく家族を描く中編を2004年に作ったんだけど、結論としてはあまり咀嚼し切れていない、満足のいく作品にはならず。それで、2005年にたまたま募集を見かけて青年団の演出部に入ったんです。
― 本腰を入れて青年団の演劇の勉強をしてみよう、平田オリザから吸収してみよう、ということ?
深田 まあ、そうですね。一応、新人研修みたいな期間が一年間あって、俳優と一緒に学ぶんですけど、予算書の書き方や著作権まで教わるのが目から鱗でしたね。
もちろん劇作についても学んで、そこで、自然なセリフや不自然な会話について知りました。会話は登場人物の関係性で成り立っているので、その関係性を無視せず、お互いの持つ情報量とコンテクストを意識しなければならないという。
例えば、銀行員の一家の朝食の場面で、娘が父親に言うセリフが「最近、銀行の仕事はうまくいってるの?」なのは、まるでダメなわけです。父親が銀行員なのは家族全員にとって自明のことなのにそんな情報を不自然に出すのは、作り手がお客さんにその設定を伝えたいからでしかないから。伝えたいなら、別の方法で父親が銀行勤めであることを分からせなければいけない。もちろんケース・バイ・ケースですが。
― それはよく分かるし、でも、プロでもなかなか難しいのもよく分かります。
深田 会話で何かを組み立てる、という技術に関しては現代口語演劇の発達の仕方は物凄いと思います。 その点において特に圧倒された平田さんの作品は『隣にいても一人』。ある男女が、朝目覚めたらなぜか夫婦になっていたという話です。
平田さんは、不条理劇には二つの類型があると指摘していて、ひとつは何かを待っているけれど来ない。もうひとつは朝起きたら何かになっていた、だと。要はベケットの『ゴドーを待ちながら』とカフカの『変身』ですよね。『隣にいても一人』はその後者、『変身』をモチーフにした中編の舞台です。
で、この二人のもとにやはり男女が駆け付ける。それぞれ男の兄と、女の姉です。この二人は実際に夫婦なんだけど、離婚調停中なので、一体どういうことかと慌てていて、関係を持ったということか?と聞く。しかし男女は、目が覚めたらお互いに夫婦と認識してしまっていたんだ、と答えざるを得ない。始まってから10分ほどの間に、これだけの複雑な状況と関係性を、平易な会話のみ、説明のための不自然なセリフ一切なしで伝えるんです。これは本当に、勉強になりました。
― 僕が平田オリザの演劇に触れたのは、それこそ映芸ダイアリーズ時代にあなたから「青年団の芝居を見てくださいよ」と言われたおかげです。そうかーと思って、『マッチ売りの少女たち』や『ヤルタ会談』、『ソウル市民』などを初めて続けて見た。
(注:『マッチ売りの少女たち』『ヤルタ会談』は2011年春のこまばアゴラ劇場〈平田オリザ・演劇展vol.1〉。
『ソウル市民』は同年秋の吉祥寺シアター)
だから、あなたが2020年にオンラインの国際映画祭のために作った『ヤルタ会談 オンライン』も、とても面白く見ましたよ。
深田 恐縮です。あれはなんだか、勢いで作ったというものですけど。
― 戦勝国が戦後処理について話し合った、あれだけ入り組んだ歴史的な協議を、噛み砕いて噛み砕いて、それこそ日常的な雑談にまで落とし込んで、互いの利害という協議の真の目的をエッセンスとして露わにしていく。改めて、ああいうユニークな形で平田オリザさんの劇に触れると驚きますね。怖い位。
深田 平田さんは、ああいう会議コメディものなら幾らでも書けるそうです。
― ははあ。
深田 自分が初めて見たのも『忠臣蔵・OL編』。青年団のなかでは傍流のようなコメディから入ったんですよ。
芝居を撮るというより、人間を撮る
― 平田オリザさんの話を伺ったうえで『LOVE LIFE』に戻ります。今回、重要な登場人物であるパクさんがろう者である。ここでまた、会話と対話に対するあなたの意識が深まっていると感じました。
僕もここ数年の間に理解をしたばかりのことなんだけど、手話って、相手をよく見て話さないといけないんだよね。表情もランゲージのうちだから。
深田 そうそう、そうなんですよね。聴者は、手話は手だけで行うものと思いがちなんですけど、表情も重要な言語なんです。同じ言葉が、眉の動きの違いで疑問形になったりする。おそらく、聴者の俳優や演出家が手話を表現するときに抜け落ちてしまいやすいところだと思います。
― 役所で妙子と二郎とパクさんが、生活保護などの条件について話し合う場面。妙子が二郎の説明を手話でパクさんに伝えているんだけど、その時二人は、お互いの目と目をしっかり見ながら話している。二郎がそこに入っていけないのは、なんとも悲しくていい場面、いい演出でしたね。妙子と二郎が一緒に暮らしているのに、いつの間にか目と目を合わせて話さないようになっている、という気配付けがすでにあるから。
深田 はい。三角関係においてあの場面が、二郎のほうがマイノリティになる瞬間、ということは意識していました。
― 二郎さんに対してホロッとくるもんね。今までの深田映画なら、ああいうところはもう少しシニカルな描き方だったと思います。子どもとオセロをやっても勝てない凡庸な男・夫の醜い嫉妬みたいな。それが今回は、どうして俺はこんなにがんばっているのに妙子とうまくいかないんだろう……という二郎さんの辛さのほうが先に迫ってくる。
深田 ああ、そう言ってもらえると。
― これはどういう変化でしょうね。凡庸な男に対するシンパシイみたいなものが生まれている、というのは。永山絢斗さんの演技が、平凡な二郎の平凡なりに精一杯なところを魅力的に表現していることは、もちろんあるとして。
深田 今までだってああいう男性をあえて辛辣に描こうと考えていたわけではないんですよ。もしも古舘寛治さんなら、ふてぶてしく演じて逆に観客に憎まれていたかもしれない(笑)。それはそれで見てみたいですが。
― 演出についてもお聞きしたいです。というのも『LOVE LIFE』を見て、僕が強烈に重ね合わせるように思い出したのは、ロベルト・ロッセリーニなんです。特に『ヨーロッパ一九五一年』や『イタリア旅行』。
深田 『イタリア旅行』は最近見直したんですよ。『ヨーロッパ一九五一年』は高校の時に見たきりですね。
― 『ヨーロッパ一九五一年』は、息子を失った母親が心の穴を埋めるために共産主義者と会ったり教会に通ったり、いろんなことを試す話。『イタリア旅行』だって、二郎と妙子っぽいでしょう?
深田 確か、それで見直してみたのかな。参考になるかと思って。『イタリア旅行』は最後の祭りの場面がね。ああいう群衆の場面は無条件にグッときますね……まあ、ふつうに見たくて見たんですね(笑)。
― でね、『ヨーロッパ一九五一年』を今見ると、この映画ではイングリット・バーグマンの芝居をちゃんと撮るぞ、とロッセリーニが腹を据えているのがよく伝わってくる。その一点集中振りが凄いんです。
あなたは、前はずいぶんエリック・ロメールの影響を指摘されてきたでしょうけど、まず芝居をしっかり撮る、画角や構図は後から付いてくる、というあり方にどんどんなってきている気がするんです。ストーリーもそうだけど、そういう、シンプルに俳優の演技に向き合う姿勢からも、バーグマン時代のロッセリーニを連想したんですよね。
深田 そう言ってもらうのはありがたいけど、どちらかと言えば芝居をというより、人間を撮る、という気持ちでいます。
基本的に、カメラは目線の高さにするのが自分の中でかなり原則になっています。それに映画のサイズは現在のところヨーロピアン・ビスタを選択しているんですけど、本当は一番好きで、人間を撮るのに一番気持ちのいいサイズだと思っているのはスタンダードなんです。人間の両脇に景色がヘンに余らなくて、人間がモチーフであることをハッキリさせられる。
(注:画面の横縦比は、ヨーロピアン・ビスタが1.66:1。スタンダードは1.33:1が基本。4:3とも)
― でも演劇の劇場の場合、客席から見れば多くの舞台は言ってみればワイド画面ですよね。上にある空間も含めて舞台であって、その空間の中に常にロングショットで人が立っている。それはそれで僕は好きだけど、あなたはその空間を詰めて考えたいというのは、面白いですね。
深田 逆に言えば、自分の映画はクローズアップもほとんどありません。できるだけバストショット以上寄らないと決めているんです。演出上の意図で例外はもちろんありますけど。よく言うのは、自分の映画は基本的に三人称の視点にしたいと。クローズアップにするとその原則から逸脱してしまう。三人称の視点にしたいのは、関係性を描きたいからなんです。
― そう言われると、深田映画はいつもそうですね。それは小津安二郎のような、禁則的なルールに近いのかしら。
深田 偉大すぎる名前なので同じとはとても言えませんが、自分なりに原理主義的なところはあるかもしれない(笑)。カメラの位置は目線の高さで、と事前にスタッフに伝えますからね。カメラマンのほうの判断で違うアングルにカメラを置かれた時でも、戻してくださいとお願いすることは多いです。
これを最初にイチ映画ファンとして意識したのは、ハワード・ホークスの〈透明なカメラ〉ですね。カメラが常に目線の位置にあることで、カメラの存在が透明になるという。その撮り方が凄く好きで。
(注:蓮實重彥がホークスの映画をよく「嘘のような透明さ」「強靭な透明さ」などと評していた。
透明とは何かというと、「彼ら(ホークスやウォルシュなど)の才能は、むしろキャメラの存在を意識させないまでにショットの
独走を禁じることに発揮されていたのだといってよい」(『ハリウッド映画史講義』)。
深田はその記憶から「透明なカメラ」という独自の理論を作り出している)
ロメールだって仰角や俯瞰のショットはほとんどなくて。やっぱり、ベースにあるのはモチーフとカメラの関係性だと思うんです。モチーフとカメラをきちんと向き合わせることが自分のやりたい演出だと言ってもいい。技巧的なショットを撮るとカメラとモチーフの関係性が濁ってしまう、ぶれてしまう気がするんですね。だから基本的には、カメラはモチーフの正面にきちんと据えることにしています。
― とても面白いお話です。それだけ禁欲的にカットを積み立てたうえで、先ほども聞いた『LOVE LIFE』や『本気のしるし』の海辺の場面のように、ドーンと、風景の中に人間が溶け込むほどのロングショットを入れ込むんですね。
深田 ロングショットはねえ、難しいですよね。いいロングショットを撮りたいなといつも思うんですけど。一方で自主映画の時代から、風景の誘惑というものをよく考えます。
― 風景の誘惑?
深田 凄くいい空間や、雄大な風景を見るとね、つい引きたくなっちゃうんですよ(笑)。でも本当にその雄大な風景はこの映画に必要なのか、と自問自答したほうがいい。そこで捉える必要があるのが人物ならば、いい風景を構図から排除してでも人物を撮るべきなんです。
実際、風景の誘惑に負けて引いた画が、実はそんなに強くないケースは多いと思います。自分も風景に感動してロングで撮って、後でカットすることになる場合はちょくちょくあります。
いずれ誰もが死ぬし、人の死に直面する
― ここまで伺ってきて、いろいろ面白い発見がありました。特に、あなたが〈苦しみは理不尽に訪れる〉ということを自分の映画の重要なテーゼにしているのが。なので、そこについてもう少し伺いたい。
とつぜん訪れる不幸、具体的には死は、作劇においてとても慎重さが必要になると思うんです。なぜならそれは、お話を劇的にするために、あるいはその人物を強引に退場させるために……と便利に扱うようになると、とめどもなくなってしまうから。
深田 宮崎駿が手塚治虫を強く批判している文章があるんですよね。手塚治虫が亡くなってから出た雑誌の追悼特集。読んだことありますか?
― ないです。
(注:COMIC BOX1989年5月号「ぼくらの手塚治虫先生」特集に掲載された、宮崎駿のインタビュー
「手塚治虫に「神の手」をみた時、ぼくは彼と訣別した。」)
深田 漫画の神様・手塚先生に愛情、尊敬、感謝の念を捧げる文章が溢れるなかで、宮崎駿が深い愛憎の念を語っていて凄いんですよ。手塚治虫のアニメーション作家としての資質や見識を徹底的に批判しているんですけど、そのなかで宮崎駿は特に、手塚治虫の作品に感動させるために登場人物を殺す傾向があることを問題視しているんですね。そこに気付いた時に、少年時代からの手塚の影響と訣別したという。
― ははあ……。あなたはそれだけ意識的だから、映画の中で人が死ぬ=作劇のうえで死なせることに関しては、人一倍慎重なはずだと思っているんですよ。そのうえで、理不尽に訪れる死を一度ならず描いている。
深田 そこは自分なりに慎重に向き合ってから、ゴーサインを出しているつもりですが、もちろん批判もあるだろうことは覚悟しています。
これだけは自分にとって確実な、普遍的なことだ、と信じられるものを描きたいと当初から考えていて、結局残るのは〈人も自分もいつか理由もなく死ぬ〉〈人間は孤独である〉の二つなんです。言葉にすると陳腐に聞こえると思うんですけど、結局はこれに行き着いてしまう。映画美学校に入って最初に書いた企画のタイトルが「メメント・モリ」だったという、なかなか香ばしい思い出もある位で(笑)。
でも、いずれ誰もが死ぬし、自分の死に直面する。死という自然現象を認識してしまったヒトは、それ以後死の暗闇と向き合い続けなくてはいけなくなりましたし、死をいかに前向きに受容していくかに苦心してきた。死は無意味でも終わりでもないという強烈な幻想を人類に与えてきたのは宗教ですが、死を描いた芸術作品は宗教的背景の濃淡に関わらず、死について想いを巡らす時間を人類に与え続けてきたわけです。生きている間に自分の死を体験することはできないけど、人間は何らかの作品を通して死を仮想体験していくことでだんだんと心を死に慣れさせてきたとも言えると思います。
表現者がそんなセラピーみたいなことを考えながら死を描く必要はまったくありませんが、少なくとも自分にとっては切実なモチーフですし、それを描くだけの最低限の言い訳としてこういったことを考えています。私達の生活にとつぜん、何の前触れも伏線も理由もなく訪れる死をそのまま、等身大のままでスクリーンのなかに持ち込むにはどうすれば良いのだろう、といつも考え続けています。
信仰を失ってしまった人間の哀しみ、苦しみ
― その、とつぜん訪れる不幸に対して、『LOVE LIFE』のなかで特に強い反応を示すのが、妙子の義母にあたる二郎の母親・明恵(神野三鈴)です。明るく温和な人柄の女性であり、おそらく自分でもそういう社会的な賢明さの持ち主であることに自信があったのに、動揺する事態が起きた時、それが崩れる言動をしてしまう。
僕はたまたま、明恵役の神野三鈴さんが出演していた2012年の三谷幸喜演出版『桜の園』を見ていたのもあって、神野さんの複雑な演技に感心しました。正確には、自分のなかにある矛盾を持て余した人の平凡さを巧みに表現されている、と言うのかな。
深田 言っていることや行動と本心にズレが出てしまう役回りは、ずいぶん担ってもらっていたと思います。妙子のことは本当に親身になって考えているんだけど、つい傷つけるようなことを言ってしまう。

『椅子』2001©深田晃司
― 明恵はその後、教会に通い出すようになります。信仰に目覚めたわけではなく、自分の杖になるものが欲しくなって。あなたの映画では修道女がよく出てきますし、今も、死についてのお話のなかに宗教が出てきたので、深田晃司の持っている宗教観について聞いておきたいのですが。
深田 はい、宗教観。
― あなたの映画では修道女がよく出てきますよね。一方で、僕が深田映画からよく連想するのは能なんです。異界との交通の場である水辺に成仏できない者が幽霊や鬼になって現れて、現世の者と交渉するのが能の基本でしょう。東西の何かが、いつも和洋折衷となって滲み出ている印象です。
深田 和洋折衷と言ったら、ある意味今の日本人全員がそうならざるを得ない暮らしをしているんじゃないでしょうか。
宗教観について答えるなら、まず自分自身は無宗教です。特定の信仰は持っていないです。ただ、信仰を持ってないゆえの生きづらさはいつも感じています。
自分は今更何かの信仰を持つことはできないけれど、人類に対して宗教が果たしてきた役割はめちゃめちゃ大きいと思っています。これから言うことは、カルト的な団体の評価とはまた別のこととして聞いてほしいんですが。
人間はそもそも生きること自体が苦しいというか、解決できない問題ばかりなんですよね。大抵の動物なら感じずに済む、いつか死ぬことへの不安や孤独に人間は囚われてしまうわけで。そんな、どんなに考えても答えを出せない問題に、宗教は何かしらの答えをくれる。地獄も天国も結局、死によって今ある生が断絶してその後は何もない、無に還る恐ろしさから救われたいという思いが根源にあるし、その幻想にリアリティを与えていると思うんですね。もちろん宗教は政治装置でもあるので、必ずしもそれだけではありませんが。孤独という問題に対しても、信仰を持つことで神様が主体にある、常に神様が隣にいるような世界のなかに入っていけるわけで、それだけでひとつの救いにはなるでしょう。
近代は、かつて宗教と一体化していたはずの科学や哲学が独立し発展をして、人類に大きな影響を与えるようになって、信仰を背景にしたスピリチュアルな思考は、相対的に力を弱めていった。ところが人間の、本当に解決困難な悩みや苦しみに対して、科学が答えを出してくれるかといったらそうは出してくれないんですよね。人間がなぜ死ぬかについて、その生物学的なプロセスを解明できるようになっても、死んだ後自分はどうなるのかとか、死がもたらす不安や苦しみに対して何か答えを与えてくれるかと言ったら、そんなことはない。まあ、薬で和らげることはできますが。
科学が沈黙するしかない多くの苦しみに答えを与えてくれるものとして、宗教はやはり大きな存在だったんだと思います。しかも、死は生きる不安の原因のひとつであるとともに、同時にその不安から解放してくれる唯一の希望かもしれない点も、人間の世界観のまた恐ろしいところで。
といって素朴な、純粋な信仰心になかなか戻ることのできない現代人にとっては、哲学などがより重要になってくるわけですけど、信仰ほどには圧倒的な、合理性を超えた「神の力」で苦しみに答えを与えることはできない。結局、現代においても宗教や信仰が一定の強い影響力を持ち続けるのは、科学や哲学がなかなか人を死への恐れや孤独の焦燥、存在の不安のようなものから救う役割を代替えし切れないからですよね。
信仰によって救われる人はたくさんいるし、それは簡単に否定できることではない。自分自身はいわゆる神様の存在を信じてはいないけれど、信仰心を持つ人が「神様は存在する」と言うのは、それはその人にとって全く正しいことだし、彼らにとって神様は「実在」しているのだと思う。そういった人間の思いを利用することである種の宗教が搾取を行なってきたのもまた事実で、それがまた難しいところですが。
『LOVE LIFE』のなかで描いた信仰は、登場人物にとって死の不安や孤独を忘れさせてくれるレイヤーの一枚という位置付けです。そのレイヤーは人によっては、家族であったり仕事であったりするし、趣味かもしれない。でもそういうレイヤーをある時パッと剥ぎ取られてしまったり、そこからこぼれ落ちてしまったり、あるいは特に理由はなくとも不意に、ああ、自分はひとりなんだなとか、なんで生きてるんだろうとか思ってしまう瞬間のほうに自分は関心があるんです。
― とても興味深いお話でした。でも、無宗教だとおっしゃっていたけど、今のお話をよく伺うと、それこそ仏教的ではないかという気もします。
深田 ああ、なるほど。自分も一応は仏教系の大正大学出身ですからね。一般学部の歴史学科だったから、仏教についてちゃんと教わったわけではないんだけど。
― 僕は最近になって仏教のにわか勉強をしたので、あなたの個人を突き詰めて考えようという姿勢に、例えば禅宗である臨済宗の教えに通じるものを感じるんです。解脱のためならば何者にも惑わされるな、仏に逢ったら仏を殺したっていいんだという。仏教のなかでもかなりハードコアの部類だとは思うんだけど(笑)。
深田 それは凄いな。でも、個であることを受け入れるかどうか以前に、信仰を失った人間にとっては、その時点で個の荒野に放り出されること自体が過酷ではないでしょうか。生きることに目的はないし、死ぬことにも意味はない。そんななかでどうやって平静を装いながら1秒1秒を過ごしていくのか自体が、かなりのハードモードだと思うんです。
だから家族や夫婦、恋愛、それに宗教などの存在によって個の苦しみを忘れながら生きることを自分は全く否定していないです。むしろ忘れたまま生き抜いてそのまま死ねたら、どんなに幸せなことだろうと思う。でも人によっては、死や孤独への不安を不意に思い出してしまう瞬間は訪れるわけで。自分はそっち側の人間なので、そっち側から見えている世界を描くしかない。今でもごまかしごまかし生きているというのが実感です。よく40年も生きていられたな、と思います。
だから二郎のお母さん、明恵も、信仰を本当に信じられる日が死ぬまでに訪れたらいいな、間に合えばいいな……とは思っていますね。
過剰な女性観、男性観から一度抜け出さなくては
― そうだ、さっき『椅子』と『LOVE LIFE』の共通項について伺った時、深田映画にはベランダがよく出てくることについて後で聞くと言っておいて、そのままにしていました。
『椅子』の少年は、罰のためにベランダに出されて部屋に入れてもらえないんだけど、そこから外を見つめて、いろいろなものを見つける。『自転車と音楽』の子どももベランダに追い出されているんだけど、同じようにベランダにいる子と連帯を始める。
『LOVE LIFE』では、さらにベランダが重要な場所になります。妙子と、妙子の義母にあたる二郎の母親・明恵(神野三鈴)が、部屋で会う時は互いに配慮し合っているのに、ベランダで二人きりになった時は心の奥に閉まっていた話をする。それに妙子とパクさんが、無邪気にふざけ合う場面もベランダ。
深田晃司にとってベランダはどんな場所なんでしょう。解放区か聖域のような意味を持っているのか。
深田 ベランダ……うーん、これも精神分析の領域かな(笑)。
― 一応はベランダも〈セミパブリックな空間〉ではあるでしょう。
深田 確かに。部屋の一部ではあるんだけど、外の世界ともつながっている。物語の転機として、非常に使いやすい空間であると自分が思っていることは間違いないですね。多分、『裏窓』とかもそうですし、ルビッチの映画でもアパートの窓と窓を隔ててのショットとかがあって、いいなあと思ってきた、その影響も強いと思います。
― 妙子とパクさんがベランダで心を寄せ合っている姿を、二郎が見てしまう場面も辛いね。そう、やっぱり二郎さんが見ていて気の毒になる。
深田 いやあ、そうなんですけどね。でも、あんまり二郎さんに同情が集まるようになるのも嫌だったので、それで二郎も、妙子に対して秘密があることにしたんです。
この手の物語は、例えばファム・ファタールに代表されるような、女性に振り回される男性を同情的に描く場合が凄く多いと思うんですよね。男性だけが常に安全な道徳圏内にいるという。それはいかがなものか、というのもあって。それで、みんな等しく誰かを裏切っている構造にしたんです。
― 日本映画専門チャンネルの番組「監督深田晃司にまつわるいくつかのこと」のなかで、筒井真理子さんが「深田監督はそのセリフを言うのが男か女かを考えずに書くそうです」と、それを知ってとても感心したことをコメントしていました。
深田 それは今でもかなり意識していることですね。矛盾したことを言うようですけど、ジェンダーがそれぞれの立場によって受けている社会的な抑圧や差別自体は忘れちゃいけないし、その点においては男女平等であるとは全く思っていません。
ただ、自分のなかには様々なフィクションを受容してきたことによる過剰な女性観や男性観、思い込みに近いものがどうしようもなく積み重ねられています。ここからは一度は意識的に抜け出さなければいけないと思っているので、個々のキャラクターを描く時には、性別をなるたけ意識しないようにしているんです。自分の場合はそれ位までやって、ようやく程良くなるんだと思っています。

https://lovelife-movie.com/



















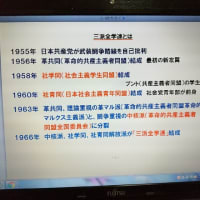
唐突ではございますが、若木さんが10年以上前に執筆された
「あんにょん由美香」のレビューが印象に残っている者です。
『お前らイカもの好きの笑うはな、嗤うって書くんだ。嗤うな!
人ががんばってるこっけいな姿を見て、嗤うな!』
この文が自分の思考・行動の指針の基になっていると言っても過言ではありません。
真摯な言葉をありがとうございました。
自分の書いたものを覚えてくれている人がいること、咀嚼してくださったこと、すなおに
うれしいです……