連日、蒸し暑うございますな。
今日は本ブログで書いた『標的の村』(昼の回)、『恋する神様~古事記入門~』(レイト)の、ともに初日です。
どちらもポレポレ東中野。当劇場の回し者みたいですが、今回は偶然です! ただ、打率は高いよね。
ともあれ、お出かけの際はこまめな水分補給、ぜひ、お気をつけください。
当ブログを覗いてくださる方へのサービスとして、ひとつ納涼小噺を。
妻が泊りがけの同窓会旅行に出かけ、自宅でひとりで寝ていたある男性。
「暑くて寝苦しくて、夜中にひどく喉が乾いた。水を一杯飲もうとベッドを出たんだ。
すると、キッチンの隅にぼんやりと人影が立っている。
電気は消しているし、ねぼけているから、最初はカミさんも起きだしたのかと思い込み、疑いもなくキッチンに入った。
あれ、待てよ今日は旅行に……と気づいた途端、身体中に鳥肌が立ったね。
恐る恐る見ると、ぼんやりとした影も、立ったままこっちを見ているのが分かる。なのに、その影には、顔が無いんだ。
『……!』
声も出ないし、足が竦んで動けない。なにかして身を守らなきゃと、震える手を振り回すと、カミさんが冷蔵庫に入れ忘れて、一日置いたまんまの生卵のパックがあった。
卵をひとつ掴んで、エイッと投げつけた。
当たったはずなんだけど、影はピクリとも動かない。
必死でぶつけたよ、生卵を。もうひとつエイッ。もうひとつ、エイッ……。
そしたら影が、生まれてこのかた聞いたことのない不気味な唸り声をあげた。そして、ゆっくりと、こう言ったんだ。
『キミがわるい』」
版権フリーです。ただし、すべった際の責任は当方は一切負いかねますので何卒ご了承ください。
『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』
2013 「SGC」運営委員会 監督 小沼雄一
8月17日よりシネ・リーブル池袋ほかにてロードショー
製作・配給・宣伝 S・D・P
http://sgc-movie.info/
まあ、まずは公式サイトの画像や予告編動画を、しげしげ、しげしげと眺めてください。
街では目のやり場に困る(エスカレーターで前に立たれるとさらに困る)女子高生の生脚、ひざこぞう、ふくらはぎがこれでもかとばかりに。
これこそ納涼。
原作は青山裕企の、あの『スクールガール・コンプレックス』シリーズ。
写真集の映画化、なのである。
〈女子高生〉という社会的記号性を伴う存在を、記号そのものとして撮るところからハミ出す揺らぎにドギマギしてしまい、大きな書店に行っても、この人の写真集はいつも買えずに帰る繰り返しだ。
去年の秋に出た『パイスラッシュ』に至っては、一体なんてところに目をつけるんだ! けしからん! と風紀委員のように義憤にかられつつ、周りに人がいないことを確かめてからガン見して、やっぱり買えずに帰ってゴメンナサイ。こんど、購入します。
揺らぎとは、すなわち聖と性が同義になる瞬間の(そして掴まえたと思った瞬間消えてしまうものをスチールに残そうとした)美であり、形而の上と下の接点。こちらの妄想の精度を突き詰める厳しいレッスンでもある。妄想は、やるからにはマジメにやらねばならない。愛は真摯な妄想からしか生まれない。
写真集の映画化はつまり、読者がいるだけある妄想の中から、作り手が代表してそのひとつを具体化してみた、という提示となる。
映画を見て、自分の頭の中でふくらんでいる「SGC」とは違う! こんな意見があって当然。むしろ、それしか無くたっていい。ただしそれは不満ではあっても、批判としては成立しない。『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』の作り手には、愛があるからだ。愛のある妄想は、自分のソレとは違ってたとしても、尊重しないといけないんだよ。
愛はなくてももっとかわいく、パーツをさらにエロく、を作り手は、できるのに選ばなかった。完全妄想の園に生きる彼女達にも青春が、痛みがあることをドラマでちゃんと描きたいと願い、涙と汗のナラタージュによって「SGC」を逸脱している。でも、ハートは原作から離れていない。
青山裕企は『〈彼女〉の撮りかた』(12・ミシマ社)で、クラスメートの女の子達を純粋な存在と思っていた思春期こじらせ体験を飄々と披露した後、100%純粋な女の子は存在しない。けれど、100%不純な女の子も存在しない。といったことを書いている。
映画化によってストーリーが付け加えられると、そのエッセンスの部分は確かにより具現できるのだ。そして作り手は「ちゃんと」自分達の妄想の原点である1980年代の青春映画体験を濾過して、映画をこさえている。
監督・小沼雄一、脚本・足立紳と年齢の近い僕は、見ていてもう、ジョン・ヒューズ、斉藤由貴の『女たち』三部作、角川三人娘、大林宣彦の尾道三部作、キティフィルムなどの記憶が走馬灯のように浮かんできて、ワーッ、やってるなー……となった。
ただしそれは、似ているシーンがあるという相似の話ではない。実際、具体的にはどれにも似ていない。そういうものを夏休みの映画館で見たときの甘酸っぱいあこがれ、感傷、気分そのものをうまく形にできないか、と楽しみながらまさぐったのだろうと思われる。その気配が伝わるから、画面上は似ていなくても、いろいろ思い出したのだ。中原俊の『櫻の園』(91)はどうかと言うと、これはずいぶん本作と似ているから、全く意識していないはずはない気がする。が、小沼と足立がこれを見たのは、もう〈映画=100%あこがれの世界〉の年齢を過ぎてからだろう。こうなると、ちょっと先の文脈と違ってくる。
小沼雄一はかなりのシネフィルでもあるらしいから、若い女性しか出てこない世界観作りの参考に、レオンティーネ・サガンの『制服の処女』(31・仏=独)を見ていますか? と聞いても、顔色一つ変えず「もちろん」と答えそうな気がする。そういう人が、クエンティン・タランティーノのような、一見センスはいいようだけど実は即物的な貼り付けとは別のアプローチをした、という話。
しかし、小沼と足立がどれだけ意識していたかどうかは別として、『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』が、大島渚の『戦場のメリークリスマス』(83)と構造が通じることには、僕はけっこうカンゲキした。
・ある閉鎖的空間が舞台。(ジャワ島の俘虜収容所/地方の、おそらく私立の女子高校放送部)
・登場人物の性の徹底。(全員男性/ほぼ全員女性)
・安定していた集団を乱す来訪者の登場。(新たな俘虜セリアズ/途中入部のチアキ)
・統率者が来訪者に魅せられ、個の欲求を募らせることで集団は揺れる。(開戦前はインテリだった収容所長ヨノイ/ちょっとマジメすぎる部長マナミ)
・揺れる要因にふくまれる音楽の要素。(セリアズの記憶にある美声を持つ弟と、クリスマスの行事/朗読劇に抜擢したくなるチアキの声)
・劇的爆発を招来する来訪者と統率者の身体的接触。(どちらも……アレ)
・すでに空間に終わりが来ることは予告された物語。(3年後に日本は敗戦/朗読劇は3年生最後の部活)
比較は、単にこじつけではない、と思う。
公開当時はもちろん全く気付かないまま繰り返し見たが、『戦メリ』は、大島のモチーフのいったんの集大成(集団が生むシステムと個が持つ無垢の相克)だった。
初期の代表作『太陽の墓場』(60)で、愚連隊を破滅させていくのは、セリエズと弟が一緒になった人物→「歌がうまくて気の優しい弟」(佐々木功)。
釜ヶ崎のドヤ街から俘虜収容所、中央集権国家そのものまで打倒するように描いて反響を呼び時代を席巻しながら、しかし大島のコアな部分は、無垢へのあこがれにあった。ちゃんと全作を見て研究とかしたわけじゃないけど、僕はそう、直感で捉えている。
そうでないと、『儀式』(71)の、あの少年少女達の三角ベースの場面になぜあれほど胸をかきむしられるのか、説明できない。
あらゆる支配構造、権力とそれを承認する精神を崩壊させたあと、大島は荒野を描かなかった。
「そこにランナーがいることにする」子ども同士の約束事によって成り立つ、三角ベース。その永遠の風景だけは記憶の中に残る。『儀式』をはじめとする先鋭的だった時代の大島映画はどれも難渋で、批評を本格的にやりたい若い人も手こずるようだが、実は表象論とは逆で、「透明ランナー」の存在を認め、観客とのルールの共有を求めることが大島渚の優しさ、モラルだ。僕なんかの場合は、『儀式』を見てそう感じた途端、パーッと身体に入ってポロポロ泣いた。
そして、『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』。
映画で描かれている世界は人工物、観念の少女達であるとあらかじめ知らせる記号的構造のなかで、現実と通じる関係の綾、校外=社会の影響から彼女達の生を輝かせ、さらに、象徴的な恒常(まさに三角ベースをやっている真っ最中といえる)の青春像へと立ち返らせる。
なかなか実はかなり手間のかかる作業を経ながら、無垢へのあこがれに向かっている映画なのだ。そのため、小沼雄一の映画を見ると、ちょくちょく大島渚を思い出す。『nude』(10)の時もそうだった。
やはり、フィルモグラフィの大半はみていないくせに、小沼雄一はそろそろ(フットボールでいうと)ワールドカップに向けた日本代表候補合宿に召集されていいはず、と前から僕は思っている。
今のところ、小沼雄一の初期の代表作と言えるのは『AKIBA』(06)。メイド喫茶で働く女の子が、なついてくるが面倒のかかる子を放っておけない心理をヒリヒリと描いたものだった。メイド喫茶ブームに当て込んで作ってるのに、仕上がりはほとんど社会派だった。
欠損を補い合う(ゆえにキツい)関係の緊張劇は、『結び目』(10)では男女の性別が神によって分かれる創世神話に基づいての恋愛ドラマになり、『nude』では田舎から出る子、残る子の訣別となる。一転して『都市霊伝説 クロイオンナ』(12)では、姉妹の愛憎がホラーの軸となる。
どれも企画の出どころも脚本も違う。なのに、小沼雄一の映画では女性2人のドラマが目立つ。
去年の秋、『都市霊伝説 クロイオンナ』の試写で小沼さんにあいさつした時(お会いするのは確か2度目だった)、そのことに触れて、冗談半分に「何かオブセッションがあるんじゃないですか?」と聞いたら、
「あ、そうかな、そういえぱ……。いま準備中なのも女の子2人の話なんですよ。言われてみると、うーん」
と、ちょっと困らせてしまった。『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』を見ている途中で、ああ、あの時言ってた新作がこれか、と気づいたのだった。
戸惑った返事は、ホントだったのかもしれないし、プロの映画監督ならではのおとぼけだったかもしれない。
ただ、『スクールガール・コンプレックス ―放送部篇―』は、ここまで長々と書いてきたように、もし小沼にオブセッション(作家としての確固としたモチーフといってもいい)があったとしても、そこのみに拘泥していない普遍的な良さがあったという話に戻るのだ。
さよならだけが青春だ。
要はそう言っている、夏休みのあいだに見ておきたい、卒業を控えた夏の少女たちの映画。現代の「たけくらべ」。
ここらへんのストイックな人生観照の精神は、足立紳(『MASK DE 41』(04・村本天志)は僕のゼロ年代邦画ベストテンの1本)の脚本が注入している部分も大きいと思われる。



















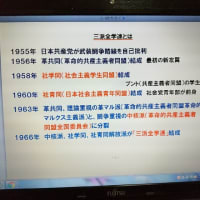
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます