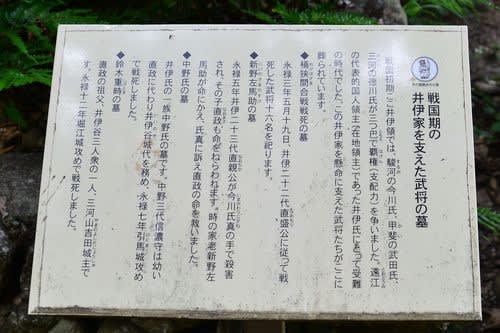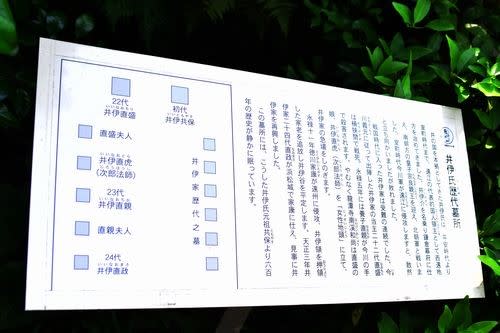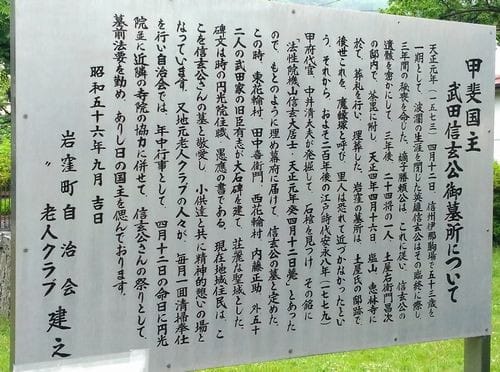1582年6月2日に起こった本能寺の変は明智光秀の緻密な作戦のもとに遂行された。1582年5月29日織田信長は僅かな供回りとともに安土城から上洛し、本能寺に宿泊した。翌6月1日夕方5時頃光秀は13000の兵とともに丹波の亀山城を出陣し、毛利攻めを行う羽柴秀吉の援護に向かった。当時織田信長の軍は五つの方面に分けれれている。滝川一益関東方面軍、柴田勝家北陸方面軍、織田信孝四国討伐軍、羽柴秀吉中国方面軍、明智光秀近畿方面軍である。織田信長のすぐ近くで大軍を有していたのは光秀のみ、6月1日午後9時頃光秀は重臣を集めて謀反の計画を語ったという。応仁の乱以降京都の町は城塞都市と化していた。そのため光秀はあらかじめ町の門戸を開かせて行軍しやすいように図っている。そして1982年6月2日午前4時頃、信長に気づかれることなく本能寺を包囲し終えた光秀は一斉攻撃を命じた。戦いは僅かな時間で終わったが次の標的は信長の嫡男織田信忠である。この時織田家の代表は嫡男に移っており、信忠が正当な後継者であった。僅か1時間ほどの戦闘で信忠を討ち取った。
緻密な計画を練った光秀の出自は定かではない。早くから室町幕府の足利義昭に仕えていた。その後信長に能力を見出されて、比叡山焼き討ちなどの武功を挙げて、近江の要衝・坂本城を任されるほど信長から厚い信頼を得ている。1583年光秀は丹波攻めの総司令官に抜擢される。丹波が平定されれば中国の覇者・毛利攻略の足掛かりとなる。この平定によって光秀は家中随一の称号を得たのである。丹波平定の光秀の居城は黒井城、標高は380m、周囲8km、重臣斎藤利光に命じて大土木工事を施した城である。光秀は築城術に秀でていたことがわかる。
光秀の出自は不明であるが、江戸時代初めに編纂された「当代記」によると、当時67歳であったという。老い先短い光秀は変の理由についての手紙を後継者に出している。また川角太閤記によると、光秀軍の生き残りの証言では、老後の思い出に一夜たりとも天下の思い出をなすべき、とある。変の後、午後1時頃光秀は京から近江へ進軍し攻略平定にとりかかった。秀吉の長浜城や丹羽長秀の佐和山城を攻略し、6月4日には平定し終えると、6月5日光秀は信長の安土城に入城した。この素早い動きにより大和の筒井順慶や若狭の武田元明を味方につけた。6月7日安土城にいる光秀のもとに朝廷の勅使が派遣されてきている。つまり、安土城にある財宝を確保して朝廷をも味方につけたのである。また上杉、北条、毛利、長曾我部に密使を派遣して連携を求めたと考えられる。次に京の庶民に対して免税を実施、信長親子の死に際して人々は喜び天下が定まったといわれる。光秀は天下人になるための所要日数を100日と見積もっていた。
丹波三大城のひとつ黒井城

ところが、光秀の配下であり姻戚関係にあった細川藤孝が協力を拒否、髷を切り謹慎を表明する。また、摂津の武将たちも去就を明らかにしていなかった。こうした武将たちに書状を送って味方につけようとした。1982年6月9日、秀吉軍がすでに姫路まで到着しているという。
秀吉は備中の高松城を総大将として攻撃中であった。高松城は毛利輝元の家臣・清水宗治の城で周囲を沼で覆われた攻めにくい城であったが、秀吉は水攻めにより兵糧の補給を絶ち、落城させた。この反乱により織田信長が横死したことが毛利元就の耳に入れば、毛利側が強気になり秀吉の和平交渉は潰れてしまう。光秀は乱後に毛利元就に知らせるべく使者を送ったが、秀吉側に捕まり毛利側よりも先に秀吉側に伝えられた。これにより織田信長の死という弱点を毛利に知られること無く和平交渉は進められ、即座に退陣することができたのである。毛利元就は織田信長が明智光秀とともに、秀吉に加勢すべく攻めてくるものと思い込んでいたから、吉川元春、小早川隆景を中心とした毛利は所領の半分を織田家に差し出す条件で講和に応じたのである。毛利側が織田信長の死を知らされたのは和平の翌日で紀州雑賀衆の海路によるものと思われる。秀吉は講和を結ぶと直ちに東へ引き返すべく行動した。毛利家に知られること無く講和を結ぶことができたのは、軍師・黒田官兵衛の手柄であるが、織田信長の嫡男・信忠が光秀により自害させられたことも後になって秀吉に運をもたらす。そして、光秀と同じく秀吉も各地の武将たちに書状を送っている。ところがその内容は、信長様窮地を脱出したとのこと。つまり信長は生きているとの偽情報を流し、味方につけようとしたのである。
1862年6月9日、光秀は京の下鳥羽に出陣、信孝を討つために大阪へ向かおうとしていた。しかしこのとき光秀に味方していた大和の筒井順慶が参陣を拒否、すでに順慶は秀吉と通じていたのである。一方、秀吉は播州の姫路城を出発すると、それを知った光秀は迎え撃つべく山崎へと向かった。このとき摂津の武将たちも秀吉に加勢、光秀軍1万に対して秀吉軍は3万数千となっていたのである。秀吉軍よりも早く山崎に到着した光秀軍は大山崎の狭隘な地区を流れる小泉川を防衛ラインとして、大山崎の出口に陣を構えた。また淀城や勝竜寺城の防備を固めた。一方の秀吉軍は天王山と川に挟まれて細長い陣形にならざるを得ない。かくして光秀は大軍の利を封じた。しかし大坂の信孝と合流した秀吉軍は弔い合戦という大義名分を得た。決戦開始は6月13日午後4時頃、戦いは光秀の思い通りの展開であったが、秀吉軍の別動隊が湿地帯を抜けて光秀軍の側面をついてきた。この奇襲により光秀軍の左翼が崩れ光秀本陣に迫った。激闘は数時間で終わり、光秀は夜陰にまぎれて近江の坂本城を目指す途中で、農民に竹で突かれて重症を負い切腹したという。