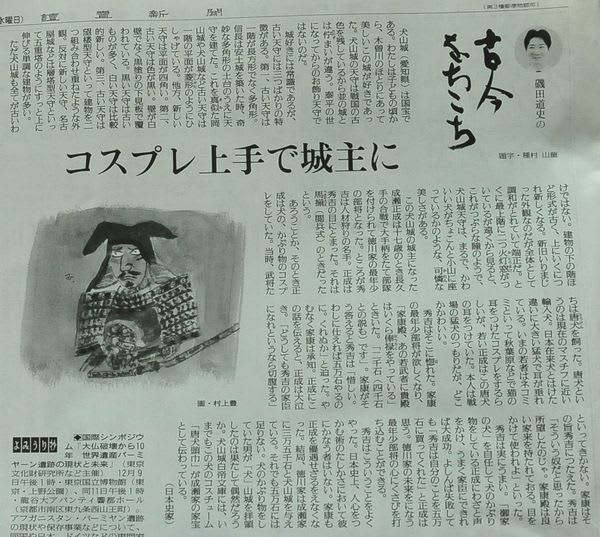年の瀬の12月に久しぶりに高台寺に行った。紅葉の季節ともなると清水寺、嵐山と並んで大変な人混みになるのであるが、この日は12月23日。駐車場もほとんど空いた状態で静寂さを感じるには絶好の時期であった。高台寺は秀吉・ねねの方だけではなく、幕末の志士ゆかりの地でもあり、近くには八坂の五重塔や一念坂・二寧坂・産寧坂があり、さすがにこの周辺は賑わっていた。坂の名はその字の通り安産を念じたところかたきている。ねねには子は授からなかったが、子の誕生を念じて清水寺に参拝していたことが由来だとされている。
”ねね” とはもちろん豊臣秀吉の正妻・北政所のことであるが、高台寺を建立したのはこのねね殿である。 出家後の高台院からその寺名はきている。 実は高台寺のすぐ近くに豊国廟があり、阿弥陀ヶ峰の山頂、約500段にも及ぶ石段を登ったところにある豊臣秀吉の墓である。秀吉亡き後豊臣政権は長続きをせず、大阪夏の陣で遺児・秀頼と淀殿の自害によって豊臣氏は滅亡し、豊国廟も荒廃していったという。 秀吉亡き後の高台院26年間の人生は苦悩に満ちていたものだったらしい。 豊国廟への山道を通い続けて菩提を弔い、出家後高台院と称して後半生をひっそりと過ごした寺が高台寺なのである。 平成10年には秀吉400年を記念して現在のねねの道が整備されて観光地として人気の高い場所となっている。 秀吉が眠る阿弥陀が峰に近い閑静な場所を高台院は探していたが、高台寺のある場所にはもともと別の寺があり、徳川家康が助力をしてその寺を立ち退かせて土地を手に入れるようにはからっている。 高台寺の建設には秀吉子飼の武将である福島正則、加藤清正、浅野長政が推進し、1606年に完成した。家康はねねに大変好意的で、ねねも家康を支持していた。 秀吉子飼の家臣がねねにも仕えていたことから、家康にとってねねは大きな存在であった。 高台寺の建立には秀吉が晩年をすごした壮大な伏見城の建物を移築している。 高台寺の表門には加藤清正が寄進した伏見城の薬医門が使われ方丈にも伏見城の一部が使われている。 ねねが亡くなるまで住まいとした建物は、伏見城で日常的に使っていた化粧御殿と呼ばれる豪華な建物であったという。
26歳の百姓の子・秀吉が12歳年下の足軽の娘に恋をして求婚を受け入れられたのは前田利家の助力があったといわれている。 政略結婚があたりまえの時代にあって、秀吉とねねは恋愛結婚であった。 しかし秀吉の死後は大阪城から退却し、大阪城には伏見城から淀殿と秀頼が移り、豊臣家の後継者である秀頼を生んだ淀殿の力は大きくなっていく一方で、正室でありながら自分の地位を明け渡したねねは寺領5百石の大寺に移った。高台寺の方丈には本尊の釈迦如来像が安置され、秀吉とねねの位牌がおかれている。 秀吉は豊国社に祀られていたが、徳川家康が政権をにぎると豊国社に対して破却命令をだして廟墓を別の場所に移すというものであった。 この命令にねねは二条城に駆けつけて家康に直訴したという。 豊国社全体の破却は免れたが、残った建物は朽ち果てることとなる。 静かな余生を過ごしたいと願っていたねねにとっては衝撃的で、苦悩は続く。 こうした苦悩を和らげていた思われる茶室が境内にはある。 傘亭と時雨亭である。 どちらも桃山時代の千利休好みのもので伏見城からそっくりそのまま移築させたらしい。 ねねは大阪夏の陣ではここ時雨亭から大阪を眺めて、大阪城の落城を知り涙ぐんでいたという。 時雨亭・傘亭から石段を降りたところに霊屋というお堂があり、ここはねねが眠る廟所になっている。 内陣の須弥壇の左右に秀吉とねねの坐像が置かれ、その下の棺にねねの遺骸が葬られている。 そして霊屋の内陣は金色の蒔絵で荘厳され、高台寺蒔絵と呼ばれる桃山時代を代表するものである。ねねは、この蒔絵が気に入り自分の廟所と定めた霊屋を蒔絵で飾ったのである。 晩年病気がちであったねねは1624年に眠るように化粧御殿で息をひきとった。現在の高台寺の塔頭である園徳院のあたりにあった化粧御殿は焼失していて存在しない。 園徳院は高台寺前のねねの道に面したところにあり、当時の面影として枯山水の庭だけが残っている。 高台寺は権力や威光を放つのではなく、ひっそりと佇み人の気持ちを和ませてくれる寺なのである。