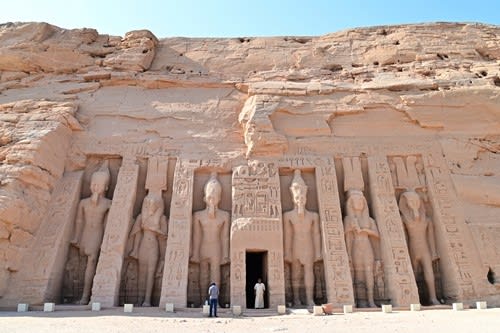【BC3500】 インダス文明(文章を持たないため解読されていない)はドラヴィダ人による文明と言われている。
・インダス →シンドゥー(水の意味) →ヒンドゥー
【BC2600 ドラヴィダ人】
・モヘンジョダロ@シンド地方 /
・ハラッパー@ハンジャーブ地方
などはドラヴィダ人という先住民による遺跡には水道施設が発達し、数多くの青銅器は出土されている。
【BC1500 アーリア人侵攻】
・アーリア人(インド・ヨーロッパ語族)がカイバル峠を越えて侵攻
農耕を営み、鉄器文明を発達させながら周辺の原住民を奴隷化させた
この時、バラモン教(経典はヴェーダ:ヒンドゥー教の原始宗教)が成立
バルナ制による階級差別が始まる。
これは現在のカースト制度(ポルトガル人が「カスタ」と呼んだのが語源)の原型である。
・奴隷化された原住民の間では仏教文化が始まり、階級差別を否定し始める。
・またアレクサンドロス大王の侵入により新しい支配層が誕生し複数の宗教とバラモン教が融合
・ヒンドゥー教が形成されて、カースト制は浸透していった。
・輪廻転生の教え
・改革は根付かない -- 共産主義は広まらない
・イスラム教とは対極-- 人生は一度 非差別民族(アウト・カースト)に広まる
・インドの古典法であるマヌ法典
・ヒンドゥー教の3大神・ブラフマーは体の部位から階級によって人間を創造したという
・頭からはバラモン、
・胸からはクシャトリエ、
・腹からはバイシャ、
・手足からはシュードラが創造されたという。
・現在カースト制による差別はは法令で禁止されている。
・しかしながらインド人に色々と聞いてみると、実際に差別は存在し社会に悪影響を与えているらしい。
・例えばインド人の名前にカースト制の名残りである階級がすぐにわかるという
・階級が高い部下は絶対に階級が低い上司のいう事は聞かない。
【カースト制度】
・ところでこのカースト制度は上位から
「バラモン」:神聖な職に就けたり、儀式を行える司祭
「クシャトリヤ」:王や貴族など武力や政治力を持つ王族・戦士
「ヴァイシャ」:一般製造業などに就ける所謂市民
「シュードラ」:農牧業や手工業など生産に従事する広汎な大衆
の4段階に分かれているというが、実はそうではない。
・そもそもバルナ制に入っていない人々、アウト・カーストが居る。
それを「アチュート」といい、「不可触民」ともいう。
現在約1億人(約8%)もの人々がアチュートとして暮らしている。
最近ではアチュートの人権を求める動きがあるという。
しかし現実は1950年にカースト制が法的に廃止されたにもかかわらず、
血統・地域・職業に応じて細分化され、何千、何万に分かれて現存する。
これをジャーティーといいインドからカースト制度がなくならない最大の理由である。
・ジャーティーが家紋となって分かれており、同じ家紋であれば同じ苗字となる。
つまり苗字から階級が推測できるのである。
また、結婚は同じ階級同士で行うので肌の色からの推測も可能。
例えば白い肌であるほど階級は高い傾向にある。
・インドにはメソポタミア文明の時代から、浄・不浄の考え方が根強く存在する。
例えばバラモン身分の人が不可触民をひき逃げしても問題にならないし、
不可触民の女性が暴行を受けても問題にもならないという現状があるという。
不可触民に生まれやアンベートカルは身分差別を撤廃する活動を行う。
【差別部落問題】 では日本ではどうかというと、戦国時代から江戸時代にかけて行われた身分制度・士農工商があり、その下の位置に穢多、非人などの身分があったというが、これは間違い。農工商も上下関係ではなく横並びであり、穢多、非人も上下ではなく横並びだったらしい。現在はというと、被差別部落問題などで残っているのは事実であるが、それが理由で自由に職に付けないとか、正当に昇進できないということはない。
【英に於ける階級制度】 次はイギリス。いまなお階級制度が存在し、国民の誰もが意識し自分自身がどの位置にいるのかを自覚している。ただし法律化されているわけではないし、上下の階級間に、支配・被支配の関係があるわけでもない。ただ、階級はかなり明確に存在していて、異なる階級同士の交流は少ない。成功して裕福になることはできても、階級を変えることは非常に難しいという。その階級はおおむね5段階区分が一般的で、上流階級(UPPER CLASS)、上位中流階級(UPPER MIDDLE CLASS)、中位中流階級(MIDDLE MIDDLE CLASS)、下位中流階級(LOWER MIDDLE CLASS)、労働者階級(WORKING CLASS)
【BC317 アレクサンドリアによる侵攻による団結】
マウリア朝 今まで分立していた小さな国がひとつにまとまった時代がマウリア朝。それはアレクサンドリアによる侵攻が原因である。チャンドラグブタが建国、3代目のアショーカ王BC304-BC232は数多くの残虐行為により領土を広げたが、上座部仏教に帰依、ダルマに基づく統治を行い、仏典結集(釈迦の説法集)が行われた時代でもある。
【1世紀頃 北部クシャナ朝、南部はサータヴァーハナ朝】
クシャナ朝 インド北部にはクシャナ朝、南部はサータヴァーハナ朝が栄えた。北部にはシルクロードによる交易でプルシャプラを首都とするガンダーラ王国が栄え、アレクサンドロス大王による侵攻によってギリシャ文化の影響を受けたガンダーラ美術が栄えた。また3代目カニシカ王(在位2世紀中頃)は大乗仏教(ナーガールジュナ)を成立させた。大乗とな皆という意味。一方戒律が厳しい方を小乗仏教。で、3世紀頃にササン朝ペルシャのシャーブール1世の侵攻により滅びた。
南は海を越えてローマ帝国と交易が始まった。こうして東西の文化が入り交じり、ギリシャ文化の影響を大いに受けたことはローマの金貨が出土していることからもわかる。西遊記にでてくる三蔵法師は天竺を目指して旅をするが、この天竺とはガンダーラのことではなく、インドのこと。インドはブッダが生まれ、仏教が生まれた地。かくして三蔵法師は多くの経典を中国に持ち帰った。

【375- 純インド化に返ったグプタ美術】 イラン系クシャーナ族を排除
グプタ朝 多神教であるヒンズー教(経典はマヌ法)がグプタ朝(チャンドラグプタ1世、2世)で発達する。ヒンドゥー教とはバラモン教と民間信仰が融合した多神教で、カースト制は肯定。輪廻思想が重要であり、西洋の様に詳細な歴史を残そうとはしない。中国からの高僧が文字に残す歴史がある。
【7世紀】 西遊記・三蔵法師でお馴染みのヴァルダナ朝
【1206】 奴隷王朝Byアイバク
【1521】 マゼランが到着したモルッカ諸島は香辛料の最重要地域、当時ポルトガル人が既に治めていた
【1526 トルコ系イスラムのムガール帝国が成立】
パーニーパットの戦いでバーブルがロディー朝(イブラヒーム王)を破り
ムガル帝国を建国(イラン:イスラム少数+インド:ヒンドゥー多数+モンゴル)
【1526 ムガル帝国繁栄と滅亡】
初代 : バーブル1483-1530---ムガール帝国の創始者、父親はサマルカンド--ティムールの末裔、母親はジンギスハンの末裔。
→ ティムール帝国サマルカンド政権(ウズベク族が侵攻)を逃げ出して、ティムール復興を目指す
インドのロディー朝を打倒(パーニーパットの戦い)
モンゴル帝国再建が目的:モンゴル---ムガル
少数のイスラム系バブールが大多数のヒンドゥー教徒を治めるのは困難
2代 : フマユーン1508-1556---アフガン人による侵攻でイラン(サファビー朝)に逃亡
3代 : アクバル1542-1605 ---イランに父親フマユーンを引き取りに行くことでサファビー朝と親交(ペルシャ文化流入)
ムガル帝国の公用語はペルシャ語
シズヤ廃止しイスラムとヒンドゥーを融和(懐柔)
中央集権的統治(マンサブダール制:階級制)を行う
これはイクター制に似ていて禄を官僚に与えて徴税権をを給与として受け取る
80%以上のヒンドゥー教徒から税金が入ってこないので質素倹約
都をアグラに移す
4代 : ジャハン・ギール1569-1637---文化に熱中するバカ息子
5代 : シャージャハーン1592-1666---ムムターズ・マハル1595-1631を妃とするバカ息子
総大理石の壮大な墓を妃のために建造した
建設開始は1632年、完成は1653年。これがタージマハルである。
フマユーン廟@ニューデリーを真似て建造
シャージャハーンの墓はヤムナ川挟んで黒大理石でタージマハルと同様に建設を開始
しかし建設の途中で3男によってアグラ城に幽閉される。かくして財政難を招く


6代 : アウラングゼーブ帝1618-1707---ムガール帝国の衰退を招いたシャージャハーンの三男
贅沢禁止の厳格なスンニ派。
長男次男は父親と同じく悪政を敷いたため争って殺害、父親を幽閉した。
アウランガバードという都市を造営
バスコ・ダ・ガマがカルカッタに漂着して商品経済が浸透するが、財政は苦しくジズヤ税を復活。
すると反乱が起きて英も侵略してきた。英はアンボイナ事件などで蘭と対立しインドに目を向けたが次は仏と対立する。カーナティック戦争、プラッシー戦争で勝利して仏は撤退すると徴税権を得て支配力を高めた(カルカッタ、ボンベイ、マドラス)。ここで東インド会社のインド人傭兵が鉄砲の薬包問題で反乱を起こして1858年にムガル帝国は滅亡、東インド会社は解体となる。
【1623】 アンボイナ事件:
オランダ領・アンボイナ島(モルッカ諸島)にある英国東インド会社をオランダが襲撃して商館員を皆殺しにする
これによって英香辛料貿易は頓挫し、オランダが利権を独占
1521年マゼランが到着したモルッカ諸島は香辛料の最重要地域、当時ポルトガル人が既に治めていた。1580年、ポルトガルは世界の王者スペインに併合。ところが1588年スペイン艦隊が英に敗れ、スペインが衰退するとオランダが台頭。1595年英東インド会社設立(エリザベス1世のレヴァント会社の後押し)の2年後にはオランダ東インド会社が設立された。お互い競争するが、香辛料では利益は薄かった。かくして英蘭は1619年に休戦協定を結ぶ。こんなときにアンボイナ事件は起こった。当時日本は英との交易を見限りオランダと交易していた。そして浪人たちの多くは蘭領に出稼ぎにいく。1623年日本人浪人はモルッカ諸島で英の傭兵として城壁を調査、すると蘭側はこれを不審に思って拷問する。蘭クーン総督の暗殺計画を暴露したということで惨殺(無実の罪だろう)。これによって英はモルッカ諸島を撤退し、平戸の英商館も1623年に閉鎖。以降ここは20世紀迄蘭の植民地となる。禍根を残したことで、この30年後に蘭英戦争が起こった。

【1877 ビクトリア女王がインド帝国の女王即位】 東インド会社は解体となり、インド総督府が分割統治を行う。
【インドの哲学は梵我一如】 ヴェーダ最大の哲人・ヤージュニャヴァルキアBC750-700頃? 「ブラフマン(世界)とアートマン(自分)が同一だと知った人間は苦悩から解放されて究極の心理に到達する」 対して釈迦は「アートマンは存在しない」つまり目的を見失って踊らされていませんか?と言った。この釈迦の死後、仏教組織は大混乱する。そうしたなかで戒律に厳しい上座部仏教と多くの人に開かれた大乗仏教(ナーガールジュナ)に分かれた。そこで生まれた空の哲学から「0」の概念が生まれた。「色即是空・空即是色」これは全てのものは実体がない・・・という意味である。しかし物事が存在すると思ってしまうことを「分別知」という。これさえも無い・・無分別知を悟ることが究極の悟り。。。