
先のネタでは、チンパンジーの赤ちゃんと現代人の骨格その他が似ている事からさもチンパンジーの幼形成熟(ネオテニー)で在るかと取られる文章になっている。勿論、その可能性も皆無では無いが、それでは直立二足歩行の獲得へ得心のいく説明が得られない。
そもそも幼形成熟(ネオテニー)とは、数年前にTVのコマーシャルに使われた両生類のウーパールーパー(アホロトール)に代表される。本来、両生類とは、幼形期はえら呼吸をし、成体になると肺呼吸に移行する。両生類のウーパールーパー(アホロトール)はサンショウウオの幼生の姿のまま性的に成熟し繁殖が可能となった幼形成熟(ネオテニー)である。変態に必要なホルモンが先天的に欠如していて、本来なら成体は水中生活の出来ない構造となってしまうが、アホロトールは全生活史を水中のみで過ごす為の適応と考えられている。だが、アホロトールも陸生が可能な環境が整えば、完全に変態を終えて成体は陸生のサンショウウオになってしまう。
実は、昆虫類でも、両生類でも多くのネオテニーは見つかっているが、哺乳類以上では具体的なネオテニーの証拠は見つかっていない。にも拘わらず、人類は大型類人猿のネオテニーで在るとする説が有力である。
1920年にルイ・ボルクと云うアムステルダム大学で解剖学の研究者が、「人類ネオテニー説」を提唱した。ヘッケルの「個体発生は系統発生をくりかえす」という有名なテーゼ(人の胎児は、胎内で単細胞生物から魚類・両生類・は虫類・哺乳類と進化系統樹の進化の過程を辿って生育していく)から、系統樹上の遺伝情報を持っているが、その殆どを成体では使っていない。解剖をしていて胎毛がビッシリ生えた胎児を見て・・・、系統樹上の近しい類人猿の解剖もした上で、ヒトの歯が小さいこと、乳歯がしばしば存続することなど16種類の違いに気がついて、このような特徴はヒトが成人としての特徴よりも乳児や幼児の特徴を保存しようとしているのではないかと考え「ヒトは性的に成熟したサルの胎児なのでる!」と記した。ルイ・ボルクの主張は画期的だった。サルの個体発生では一時的にしか現れない特徴がヒトでは保存されている事、サルの成長に比べてヒトの成長はひどくゆっくりしている事、そこにはアロメトリー(生物学的な諸量を生物の大きさ. で整理したときに導かれる関係=プロポーションの事)も働いている事、そうだとすれば哺乳類中でヒトのように成長速度を遅らせた生物が言葉や知性をもつようになったのは、ひょっとしたらネオテニーの“おかげ”だったのではないかということ、これらのことを一挙に吐露したからだ。
その後、「人類ネオテニー説」は手を変え品を変え、あらゆる分野で誠しやかに語られるようになる極端な物では類人猿が未成熟な幼体を放置していた群体から人類の祖先が産まれたなどと言う眉唾な意見も飛び交った。未成熟な幼体を放置すると早晩死んでしまうのは当然の事であるのに・・・。
同時進行で人類進化の道筋を探す発生考古学者も、ダーウィン進化論に基づくミッシングリンクを探す事に躍起になっていた。人の祖先が類人猿(チンパンジーかオラウータンに分かれる前の前類人猿)だとして、その900万年前から300万円前のホモ・ハビルス迄の間の進化の過程である中間体の化石探しに務めたが見つからない。この間の中間体を見つければ大発見になると数々の偽造や粉飾もされた。全地球上で探しても見つからないミッシングリンクはダナキル地塁のアクアテイックエープ水棲原人である。
ダーウィン進化論で説明が出来ない事には、例えば、キリンの祖先の化石は見つかっているが首が伸びれば他の類似の草食動物と生存権を争う食料を他の草食動物の届かない高い樹木に求める事が出来るという適者適存ルールで、キリンの首は伸びたとする。だが、中途半端に首の長いキリンの中間体は見つかっていない。
そんな生物が居たか居ないのか判らないが、見つかっていない事が居なかった証拠にはならないと云うのはダーウィン進化論者の意見だが、もし中間体の生物が居れば低地の草は食べられないし高い木の葉も食べられない、地面近くの水も飲めない随分不便な生き物だったと想像されるが、それらが生存して遺伝形質を進化させるに必要な期間生存して繁殖を続けていた筈であるが、化石発掘が進めば進むほどミッシングリンクとされる中間体の生育していた筈の年代は狭まって来、ついにキリンの祖先と現在のキリンと同じ位首の長いキリンの祖先の化石が同じ年代の同じ地層から発掘されるに至っては、同時に首の短いキリンと首の長いキリンが生存していた事になっている。その年代の地層には勿論、中間体の化石は無かった訳です。生物進化は、想像以上に素早いのかも知れない。
ここで前類人猿から前人類を繋ぐミッシングリンクが見つからない事がキリンと同じと云うのも極論だが、徐々に進化するのではなく、ある時を境に前類人猿から前人類が産まれ始めた・・・それを必然とする環境の変化が在ったとする考えが「人類ネオテニー説」と手を結んだ。
勿論、ダーウィン進化論では前類人猿から前人類への進化は「サバンナ説」で説明されている。それまでは樹上で生活していた前類人猿が、地球規模の気象変動で熱帯雨林が減少しアフリカ大陸大峡谷地帯東側は乾燥し灌木で覆われた草原と成り、 華奢で頭の良い前類人猿は熱帯雨林を追われて新しい環境に適応する為に、移動に直立歩行を体得し、食性も果実から肉食に変化して狩人になっていった・・・としている。
だが、それでは直立二足歩行に移行した事、体毛を失い代わりに皮下脂肪を蓄えた事、言語を発達させた事、1920年にルイ・ボルクが見つけた16種類の違いが発生した説明は困難だろう。
1950年海洋生物学者サー・アリスター・ハーデイが、人類に特有な形態学的・生理学的な特徴の大部分は、陸生の哺乳類ではユニークだが、かつて陸を捨てて水棲に戻った哺乳類に共通する特徴が顕著だと発表した。
進化のプロセスの中では、海から産まれた生物が爬虫類・鳥類・哺乳類等が陸生から水棲に回帰した例は枚挙に暇がない。7000万年前の鯨やイルカ等が哺乳類では最古参だが、5000万年前には草食有蹄類の象の仲間が海牛類ジュゴン、マナテイに進化し初め、2500万年前には熊に近い種の哺乳類のオットセイ、アシカ、セイウチ、そして、犬に近い種が水棲に回帰したアザラシ等が知られている。これら水棲に回帰した陸生哺乳類達は当初から水棲に適応して居らず、その長い進化の過程で水棲への適応度を増していったと考えられている。
人類の祖先も或る時期、水棲(半水棲)生活を余儀なくされる環境の変化を受けたから直立歩行・無毛・皮下脂肪・涙・(向かい合わせの)性交・言葉等の類人猿との違いの総てに説明が付くとしている。
ワシントンDC海軍調査研究所レオン・PリュミエールJRは、それは中新世末期のアフリカ森林地帯のどこかで起こったと想定して、一群の類人猿がかなりの長期間にわたり他と隔絶されたとし、隔離状態は鮮新世の終わりか更新世の始めに解消したと考えた。何故なら、数百万年の空白の後、初期前人類の化石がこの時期以降から各所で発掘されるからである。
地質的地理的年代的に条件に沿う場所が見つかった。アフリカ・プレートとユーラシア・プレートがぶつかり合って地殻変動を起こしていた期間のある時期(670万年前~540万年前の可能性もある)に、現在のエチオピア北東部海岸線にあたるダナキル地塁(マイクロプレート)が大陸から離れて島(ダナキル島)となっていた可能性があり、この島に取り残された類人猿は森林が減っていくなかで周囲の海に頼る半水棲生活を強いられたのでは無いかと書かれている。
人類が、類人猿とは異なる形態の中で、水棲生物の形態に似ているモノがある。
(1)人間は類人猿と比べると体毛が少なく、皮下脂肪で体温維持をしている。 又、人間の毛の生える向きは、泳ぐときに流れる水の向きに一致するという。
(2)人間は、向かい合ってセックスを行なう。水生生物では一般的だという。
(3) 生まれてすぐの赤ちゃんは、水の中で泳ぐ。筋力も器用さでも人類の胎児より上である筈の類人猿の新生児は泳げない。
他にも、涙、言語能力の進化、直立歩行も半水棲生活に適応した類人猿が人類の祖先であるとすると上手く説明が成り立つそうだ。半4つ足歩行の類人猿が海に入り呼吸する為に頭を海面上に出す直立二足歩行を獲得した。又、海での生活が他の類人猿にない「涙」を体内の塩分調整の為に発達させた。他の類人猿に無い上唇の「人中」は、水中を潜る際、呼気が漏れるのを防ぐため上唇を鼻に密着させて鼻の穴を塞いだ名残り。人中という溝があることで、ちょうど、ジャストフィットする。(子供が遊びでするけど、大人には難しい?)又、ピアニストには邪魔な水かきも類人猿には無い事から爬虫類時代や両生類時代の名残というより水棲生活時代の名残かも知れない。
又、他の前類人猿は後退を続ける熱帯雨林を追って移動したが、もし適応が進まぬままに草原地帯に居残ってそこで新たな進化を遂げたとしたら化石が発見されるだろうし、数百万年間の間前人類の化石が一切発見されない事からもダナキル地塁のみで類人猿から前人類へと進化を遂げたと考える方が自然かも知れない。
(が、この現在の海面から100m低いダナキル砂漠では、それこそ全世界の研究家が前人類の化石を血眼になって探しているが水棲原人の生活痕跡は見つかっても肝心の前人類の化石は見つかっていない)
エレイン・モーガンの著作である「進化の傷あと身体が語る人類の起源」の中でも、興味深い論文が紹介されている。それは、アメリカ・メリーランド州のアメリカ癌研究所の研究チームによりまとめられた論文で、後に「ネイチャー」誌にも同内容の論文が発表された。論文の概要は、霊長類のヒヒは内在性C型ウィルスのDNAを遺伝子中に持っている。このウイルスに感染するとウイルスのRNAがその動物の細胞内でDNAに組み込まれて親から子へ伝えられていくが、ヒヒの場合はすでに発病しなくなっている。このウイルスが猛威を振るった時期には、他の霊長類に感染して発病したと考えられるが、今は感染力がなくなっている。調査結果によると、現在アフリカに住む全てのサルと類人猿からこのウイルスに対する抗体が発見されたが、アフリカ以外(南アメリカやアジア)を原産とする霊長類はこの抗体を持っていないことがわかった。ここで特異な点は、人類だけは、アフリカの原住民も含めて、この抗体を持っていなかったことである。そうすると、人類はアフリカ以外の地で進化し、このウイルスの脅威がなくなってからアフリカ大陸へ戻ってきたと云う結論が導き出される。


少なくても150万年から300万年前程度の間、一群の類人猿が大陸での本来の生活に戻れず上昇する海面下に沈むダナキルの島々(火山)に取り残され、半水棲を余儀なくされたのではないか。そこで海水が浸入して島々に孤立したダナキルの類人猿達は食糧確保と捕食者から逃れてさ迷うことになる。多くの仲間や陸上動物が死に絶える中で、かろうじて少数の猿人は浅瀬や水中に逃れ食餌しながら活を求めた。頻繁に起こる噴火は彼等に火と礫の知恵を与え、少ない食料の加工を思いつかせたのかもしれない。水中に出入りする暮らしは適応によって現在ヒト科と呼ばれる進化を急速に成し遂げてゆく。彼等はいまのアザラシやペンギンのようなコロニイを造って少なくても一日6時間以上を水中で暮らしていたのだろう。175万年前には陸橋でアフリカ大陸と繋がり、この時点で環境が悪化したダナキルからアフリカ大陸に移動し大地溝帯に沿って南下したのだろう。この年代以降には前人類の化石がアフリカ大陸で発見されている。
さて、このダナキル火山に取り残された類人猿がネオテニー(幼形成熟)に依って急激に変わる環境に適応していったとする訳です。考えてみれば、人類ほどゆっくりと発育する哺乳類はない。チンパンジーの子供は生まれてすぐに母親にしがみついて移動できる。それに比べて人類の胎児は歩く事も適わない。まるで人類の新生児はチンパンジーの未熟児なのかも知れない。「個体発生は系統発生を繰り返す」、と言うけれど、大脳の発達などをみると、まるで人類は個体発生によって系統発生が完結する(進化で獲得した機能の発現を意図的に遅延させている)戦略をとっているように思えます。止むを得なき理由に依って、或いは意図的戦略によってか…。この遅延性の原因は何だろう。
人類の新生児は、産まれてすぐに水中に投じても泳げるらしいしロシアでの研究では息継ぎも出来るらしい。だが、10ヶ月経った後では泳げないらしい。幼体成熟の必然性は当にココにあるのでは無いだろうか?これこそが人類が進化の過程で半水棲生活を100万年弱おくっていた証なのだろうか?類人猿の未熟児として産まれた方が、身体能力に勝る類人猿の新生児として産まれるより、半水棲生活への適応が上手く働いたという事なのかも知れない。
『哺乳類は最終的に達する体重の30%で性的な成熟期に達するのに対し、ヒト以外の霊長類は60%をやや下回る体重で、またヒトは約60%の体重で性成熟する。大部分の哺乳類では脳は胎児期の終わりに形成されるが、霊長類は出生後までかかる。チンパンジーでは出生時の脳は大人の脳の容積の40%までしか発達しておらず、ヒトではわずか23%に過ぎない』(『科学10大理論』学研出版より)
そもそも幼形成熟(ネオテニー)とは、数年前にTVのコマーシャルに使われた両生類のウーパールーパー(アホロトール)に代表される。本来、両生類とは、幼形期はえら呼吸をし、成体になると肺呼吸に移行する。両生類のウーパールーパー(アホロトール)はサンショウウオの幼生の姿のまま性的に成熟し繁殖が可能となった幼形成熟(ネオテニー)である。変態に必要なホルモンが先天的に欠如していて、本来なら成体は水中生活の出来ない構造となってしまうが、アホロトールは全生活史を水中のみで過ごす為の適応と考えられている。だが、アホロトールも陸生が可能な環境が整えば、完全に変態を終えて成体は陸生のサンショウウオになってしまう。
実は、昆虫類でも、両生類でも多くのネオテニーは見つかっているが、哺乳類以上では具体的なネオテニーの証拠は見つかっていない。にも拘わらず、人類は大型類人猿のネオテニーで在るとする説が有力である。
1920年にルイ・ボルクと云うアムステルダム大学で解剖学の研究者が、「人類ネオテニー説」を提唱した。ヘッケルの「個体発生は系統発生をくりかえす」という有名なテーゼ(人の胎児は、胎内で単細胞生物から魚類・両生類・は虫類・哺乳類と進化系統樹の進化の過程を辿って生育していく)から、系統樹上の遺伝情報を持っているが、その殆どを成体では使っていない。解剖をしていて胎毛がビッシリ生えた胎児を見て・・・、系統樹上の近しい類人猿の解剖もした上で、ヒトの歯が小さいこと、乳歯がしばしば存続することなど16種類の違いに気がついて、このような特徴はヒトが成人としての特徴よりも乳児や幼児の特徴を保存しようとしているのではないかと考え「ヒトは性的に成熟したサルの胎児なのでる!」と記した。ルイ・ボルクの主張は画期的だった。サルの個体発生では一時的にしか現れない特徴がヒトでは保存されている事、サルの成長に比べてヒトの成長はひどくゆっくりしている事、そこにはアロメトリー(生物学的な諸量を生物の大きさ. で整理したときに導かれる関係=プロポーションの事)も働いている事、そうだとすれば哺乳類中でヒトのように成長速度を遅らせた生物が言葉や知性をもつようになったのは、ひょっとしたらネオテニーの“おかげ”だったのではないかということ、これらのことを一挙に吐露したからだ。
その後、「人類ネオテニー説」は手を変え品を変え、あらゆる分野で誠しやかに語られるようになる極端な物では類人猿が未成熟な幼体を放置していた群体から人類の祖先が産まれたなどと言う眉唾な意見も飛び交った。未成熟な幼体を放置すると早晩死んでしまうのは当然の事であるのに・・・。
同時進行で人類進化の道筋を探す発生考古学者も、ダーウィン進化論に基づくミッシングリンクを探す事に躍起になっていた。人の祖先が類人猿(チンパンジーかオラウータンに分かれる前の前類人猿)だとして、その900万年前から300万円前のホモ・ハビルス迄の間の進化の過程である中間体の化石探しに務めたが見つからない。この間の中間体を見つければ大発見になると数々の偽造や粉飾もされた。全地球上で探しても見つからないミッシングリンクはダナキル地塁のアクアテイックエープ水棲原人である。
ダーウィン進化論で説明が出来ない事には、例えば、キリンの祖先の化石は見つかっているが首が伸びれば他の類似の草食動物と生存権を争う食料を他の草食動物の届かない高い樹木に求める事が出来るという適者適存ルールで、キリンの首は伸びたとする。だが、中途半端に首の長いキリンの中間体は見つかっていない。
そんな生物が居たか居ないのか判らないが、見つかっていない事が居なかった証拠にはならないと云うのはダーウィン進化論者の意見だが、もし中間体の生物が居れば低地の草は食べられないし高い木の葉も食べられない、地面近くの水も飲めない随分不便な生き物だったと想像されるが、それらが生存して遺伝形質を進化させるに必要な期間生存して繁殖を続けていた筈であるが、化石発掘が進めば進むほどミッシングリンクとされる中間体の生育していた筈の年代は狭まって来、ついにキリンの祖先と現在のキリンと同じ位首の長いキリンの祖先の化石が同じ年代の同じ地層から発掘されるに至っては、同時に首の短いキリンと首の長いキリンが生存していた事になっている。その年代の地層には勿論、中間体の化石は無かった訳です。生物進化は、想像以上に素早いのかも知れない。
ここで前類人猿から前人類を繋ぐミッシングリンクが見つからない事がキリンと同じと云うのも極論だが、徐々に進化するのではなく、ある時を境に前類人猿から前人類が産まれ始めた・・・それを必然とする環境の変化が在ったとする考えが「人類ネオテニー説」と手を結んだ。
勿論、ダーウィン進化論では前類人猿から前人類への進化は「サバンナ説」で説明されている。それまでは樹上で生活していた前類人猿が、地球規模の気象変動で熱帯雨林が減少しアフリカ大陸大峡谷地帯東側は乾燥し灌木で覆われた草原と成り、 華奢で頭の良い前類人猿は熱帯雨林を追われて新しい環境に適応する為に、移動に直立歩行を体得し、食性も果実から肉食に変化して狩人になっていった・・・としている。
だが、それでは直立二足歩行に移行した事、体毛を失い代わりに皮下脂肪を蓄えた事、言語を発達させた事、1920年にルイ・ボルクが見つけた16種類の違いが発生した説明は困難だろう。
1950年海洋生物学者サー・アリスター・ハーデイが、人類に特有な形態学的・生理学的な特徴の大部分は、陸生の哺乳類ではユニークだが、かつて陸を捨てて水棲に戻った哺乳類に共通する特徴が顕著だと発表した。
進化のプロセスの中では、海から産まれた生物が爬虫類・鳥類・哺乳類等が陸生から水棲に回帰した例は枚挙に暇がない。7000万年前の鯨やイルカ等が哺乳類では最古参だが、5000万年前には草食有蹄類の象の仲間が海牛類ジュゴン、マナテイに進化し初め、2500万年前には熊に近い種の哺乳類のオットセイ、アシカ、セイウチ、そして、犬に近い種が水棲に回帰したアザラシ等が知られている。これら水棲に回帰した陸生哺乳類達は当初から水棲に適応して居らず、その長い進化の過程で水棲への適応度を増していったと考えられている。
人類の祖先も或る時期、水棲(半水棲)生活を余儀なくされる環境の変化を受けたから直立歩行・無毛・皮下脂肪・涙・(向かい合わせの)性交・言葉等の類人猿との違いの総てに説明が付くとしている。
ワシントンDC海軍調査研究所レオン・PリュミエールJRは、それは中新世末期のアフリカ森林地帯のどこかで起こったと想定して、一群の類人猿がかなりの長期間にわたり他と隔絶されたとし、隔離状態は鮮新世の終わりか更新世の始めに解消したと考えた。何故なら、数百万年の空白の後、初期前人類の化石がこの時期以降から各所で発掘されるからである。
地質的地理的年代的に条件に沿う場所が見つかった。アフリカ・プレートとユーラシア・プレートがぶつかり合って地殻変動を起こしていた期間のある時期(670万年前~540万年前の可能性もある)に、現在のエチオピア北東部海岸線にあたるダナキル地塁(マイクロプレート)が大陸から離れて島(ダナキル島)となっていた可能性があり、この島に取り残された類人猿は森林が減っていくなかで周囲の海に頼る半水棲生活を強いられたのでは無いかと書かれている。
人類が、類人猿とは異なる形態の中で、水棲生物の形態に似ているモノがある。
(1)人間は類人猿と比べると体毛が少なく、皮下脂肪で体温維持をしている。 又、人間の毛の生える向きは、泳ぐときに流れる水の向きに一致するという。
(2)人間は、向かい合ってセックスを行なう。水生生物では一般的だという。
(3) 生まれてすぐの赤ちゃんは、水の中で泳ぐ。筋力も器用さでも人類の胎児より上である筈の類人猿の新生児は泳げない。
他にも、涙、言語能力の進化、直立歩行も半水棲生活に適応した類人猿が人類の祖先であるとすると上手く説明が成り立つそうだ。半4つ足歩行の類人猿が海に入り呼吸する為に頭を海面上に出す直立二足歩行を獲得した。又、海での生活が他の類人猿にない「涙」を体内の塩分調整の為に発達させた。他の類人猿に無い上唇の「人中」は、水中を潜る際、呼気が漏れるのを防ぐため上唇を鼻に密着させて鼻の穴を塞いだ名残り。人中という溝があることで、ちょうど、ジャストフィットする。(子供が遊びでするけど、大人には難しい?)又、ピアニストには邪魔な水かきも類人猿には無い事から爬虫類時代や両生類時代の名残というより水棲生活時代の名残かも知れない。
又、他の前類人猿は後退を続ける熱帯雨林を追って移動したが、もし適応が進まぬままに草原地帯に居残ってそこで新たな進化を遂げたとしたら化石が発見されるだろうし、数百万年間の間前人類の化石が一切発見されない事からもダナキル地塁のみで類人猿から前人類へと進化を遂げたと考える方が自然かも知れない。
(が、この現在の海面から100m低いダナキル砂漠では、それこそ全世界の研究家が前人類の化石を血眼になって探しているが水棲原人の生活痕跡は見つかっても肝心の前人類の化石は見つかっていない)
エレイン・モーガンの著作である「進化の傷あと身体が語る人類の起源」の中でも、興味深い論文が紹介されている。それは、アメリカ・メリーランド州のアメリカ癌研究所の研究チームによりまとめられた論文で、後に「ネイチャー」誌にも同内容の論文が発表された。論文の概要は、霊長類のヒヒは内在性C型ウィルスのDNAを遺伝子中に持っている。このウイルスに感染するとウイルスのRNAがその動物の細胞内でDNAに組み込まれて親から子へ伝えられていくが、ヒヒの場合はすでに発病しなくなっている。このウイルスが猛威を振るった時期には、他の霊長類に感染して発病したと考えられるが、今は感染力がなくなっている。調査結果によると、現在アフリカに住む全てのサルと類人猿からこのウイルスに対する抗体が発見されたが、アフリカ以外(南アメリカやアジア)を原産とする霊長類はこの抗体を持っていないことがわかった。ここで特異な点は、人類だけは、アフリカの原住民も含めて、この抗体を持っていなかったことである。そうすると、人類はアフリカ以外の地で進化し、このウイルスの脅威がなくなってからアフリカ大陸へ戻ってきたと云う結論が導き出される。


少なくても150万年から300万年前程度の間、一群の類人猿が大陸での本来の生活に戻れず上昇する海面下に沈むダナキルの島々(火山)に取り残され、半水棲を余儀なくされたのではないか。そこで海水が浸入して島々に孤立したダナキルの類人猿達は食糧確保と捕食者から逃れてさ迷うことになる。多くの仲間や陸上動物が死に絶える中で、かろうじて少数の猿人は浅瀬や水中に逃れ食餌しながら活を求めた。頻繁に起こる噴火は彼等に火と礫の知恵を与え、少ない食料の加工を思いつかせたのかもしれない。水中に出入りする暮らしは適応によって現在ヒト科と呼ばれる進化を急速に成し遂げてゆく。彼等はいまのアザラシやペンギンのようなコロニイを造って少なくても一日6時間以上を水中で暮らしていたのだろう。175万年前には陸橋でアフリカ大陸と繋がり、この時点で環境が悪化したダナキルからアフリカ大陸に移動し大地溝帯に沿って南下したのだろう。この年代以降には前人類の化石がアフリカ大陸で発見されている。
さて、このダナキル火山に取り残された類人猿がネオテニー(幼形成熟)に依って急激に変わる環境に適応していったとする訳です。考えてみれば、人類ほどゆっくりと発育する哺乳類はない。チンパンジーの子供は生まれてすぐに母親にしがみついて移動できる。それに比べて人類の胎児は歩く事も適わない。まるで人類の新生児はチンパンジーの未熟児なのかも知れない。「個体発生は系統発生を繰り返す」、と言うけれど、大脳の発達などをみると、まるで人類は個体発生によって系統発生が完結する(進化で獲得した機能の発現を意図的に遅延させている)戦略をとっているように思えます。止むを得なき理由に依って、或いは意図的戦略によってか…。この遅延性の原因は何だろう。
人類の新生児は、産まれてすぐに水中に投じても泳げるらしいしロシアでの研究では息継ぎも出来るらしい。だが、10ヶ月経った後では泳げないらしい。幼体成熟の必然性は当にココにあるのでは無いだろうか?これこそが人類が進化の過程で半水棲生活を100万年弱おくっていた証なのだろうか?類人猿の未熟児として産まれた方が、身体能力に勝る類人猿の新生児として産まれるより、半水棲生活への適応が上手く働いたという事なのかも知れない。
『哺乳類は最終的に達する体重の30%で性的な成熟期に達するのに対し、ヒト以外の霊長類は60%をやや下回る体重で、またヒトは約60%の体重で性成熟する。大部分の哺乳類では脳は胎児期の終わりに形成されるが、霊長類は出生後までかかる。チンパンジーでは出生時の脳は大人の脳の容積の40%までしか発達しておらず、ヒトではわずか23%に過ぎない』(『科学10大理論』学研出版より)













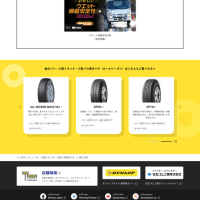













こんな所にも出ている(笑)
成長のスピードで寿命も決まるんやろね。
ん~ 神秘的や。
店主様、一つだけお願いがございます
あの骨を返していただけ・・・・・(爆)
人類は海に回帰するんですかねぇ?
思わずジャック・マイヨールやイワン・ソープが頭を過ぎりました。
σ(^-^)は泳ぎが苦手ですが(汗)
ネオテニーですか・・・・・
ちょっと引き込まれてしまいましたよ~
進化論も面白いですね
#今日は忙しくて日中1回もMacBookを開く機会が無かった・・・(/_;)
左のチンパンジーの新生児・・・結構、男前だと思いますが・・・。私には、顎が在るのが羨ましいです。
> 海を眺めて落ち着く事が多い訳がわかったような。
ですよね~。生命は海から産まれた・・・から、では少々遠すぎる気がしていましたが、こんな最近の事だったのなら、海は第二の故郷なのかも知れませんねぇ。
子供の頃「海のトリトン」を見ていて、何だか自分もトリトン族の様な気分に浸っていましたが、ヒトは過去の一時期にはトリトン族だったのカモね。
> 成長のスピードで寿命も決まるんやろね。
> ん~ 神秘的や。
じじさん、素晴らしい発見です。その通りです。象の赤ちゃんは産まれたら、すぐに歩けます。ですが、お母さんのお腹の中には650日(2年弱)居る訳です。ユックリ成長するから象も寿命が長いのかもね。
> あの骨を返していただけ・・・・・(爆)
陰茎骨に変わるのがプロテーゼでしょうか?組織にはチャンと入り込むスペースが空っぽで準備OKだそうで、埋め込むと何時でも臨戦態勢らしいですよ。お一つ如何でしょう?
なかなか進化論も面白いでしょう?
このネタは、私の妻が大好きで・・・眠れない時に話をねだります。(5分未満で爆睡ですが)
大陸プレートの移動も、人類の進化の速度も、ヒトの寿命では測れない程ユックリなので実感として涌きませんが、人類は益々手足が長くなり小顔になっていくそうです。細かい骨は一体化していき簡素化されて来ているそうです。私など進化から取り残された現代の原人なのかもね。
それと、このホモ・ハビルスからクロマニョン人迄の間は、大脳の発達が加速していて、クロマニョン人は現代人よりも大きな脳の体積をもっていました。立花隆「電脳進化論(朝日新聞社)」では、ハードウエアの進歩はクロマニョン人で終わり、現代人はソフトウエア(脳の使い方の)進化が続いていると記しています。
どうやら、私なんかは進化から取り残された感が強いですが・・・。
> ん~ 神秘的や。
動物の寿命って、心臓の停止とともに終わりが来ますよね
その心臓が生涯鼓動する心拍数はみな同じくらいって聞いたことがあります。
ネズミも人間も象も鯨も
ネズミは鼓動がめっちゃ早く1分間に600~700拍、
人間は40~60、象は20拍/分くらいだそうです
でも、どの心臓も誕生して動き始めてから止まるまで約15億回ほど拍動するそうですよ。
ポンプ(心臓)の耐久性はみな同じってことですかね
あと、心拍数の速さで感じる時間の流れも違うし、動きも違ってきますよね
ネズミなんか10倍くらい早いから、人間の動きなど1/10のスローモーションに見えるんじゃないでしょうか。
逆に象から見れば、人間は自分達の倍速で動くせせこましい動物に見えてると思います。
(聞いたことないけど)
なので、約束しても時間の観念も違うそうな
人間が1年後に会いましょう!
って言ったら、ネズミにとっては10年後みたいに思えてもう生きてるかどうかさえ判らない。
象にしたら、半年くらいにしか感じてないってことです。
随分前にこんな話しを聞いたことがあるのですが、すごく面白くて今でもはっきり覚えてますよ
私も聞いた事があります。
動物の寿命÷心周期=15億
動物の寿命÷呼吸周期=3億
動物の寿命×体重1kg当たりのエネルギー消費(W)=15億(J)ジュール
又、更にそれの上をいく話では、それぞれの人間の寿命も計算で出るというモノも在ります。それに因ると、安静時の心拍数を数えると自分の寿命が判ると云います。(一般の動物より甘いのは、人間には医学があるから・・・です)
寿命(分)=20~23億(拍)÷ 1分当たりの心拍数
自分はタバコも吸わず深酒もせず健康に留意している人は23億を、酒もタバコも不摂生の限りを尽くしていると云う命知らずは20億を、自分の1分間当たりの心拍数を数えて割ると、その人の寿命が分で計算できます。
安静時の心拍数は、大体36~120拍/毎分の範囲でしょうから、人の寿命は31年~120年となる様ですネ。(自分で計算すると、ついつい最初の数字をオマケしたくなるので客観的に、ね。)
ついつい計算してしまうと・・・何だか不幸な気持ちになるので止めましょうね。
でもゴールは知らない方がじじはええかも。
店主様の計算もせんときますね。
幼い時はゆっくりな一年が年を重ねると早くなるでしょ。
5歳は5分の1年、50歳は50分の1年だからかな?難しい事は不得意なじじやから
みんなと一緒に笑って楽しくすごしますね。