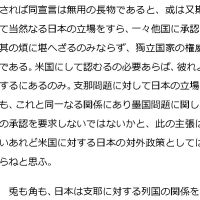菊池寛著『二千六百年史抄』
目次
序
神武天皇の御創業
皇威の海外発展と支那文化の伝来
氏族制度と祭政一致
聖徳太子と中大兄皇子
奈良時代の文化と仏教
平安時代
院政と武士の擡頭
鎌倉幕府と元寇
建武中興
吉野時代
足利時代と海外発展
戦国時代
信長、秀吉、家康
鎖国
江戸幕府の構成
尊皇思想の勃興
国学の興隆
江戸幕府の衰亡
勤皇思想の勃興
勤皇志士と薩長同盟
明治維新と国体観念
廃藩置県と征韓論
立憲政治
日露戦争以後
勤皇志士と薩長同盟
明治維新に活躍した勤皇の志士の中でも、その忠誠や志操が、何等報いられずして、中途で斃れた人が、何と多いことであらう。吉田松陰、久坂玄瑞(くさかげんずゐ)、田中河内介、真木和泉、梅田雲浜、頼三樹三郎、有馬新七、松本奎堂(けいだう)、河上弥市、吉田稔麿(としまろ)、藤田小四郎、武田伊賀、入江九一、坂本龍馬、中岡慎太郎、その他無数である。
これらの人々は、生き延びてゐたならば、その人物に於て、その功業に於て、伯爵や侯爵を授けられた維新の功臣達と、何の遜色もなかつたであらう。殊に、これ等の人の中でも、藩論に背いて行動した人や、徒手空拳で奮起した人や、神官や処士などで大事のために奔走した人達は、何の政略味もない純忠至誠の人々で、その悲壮な最期に対して、最大の敬意を表せざるを得ないのである。
50有余歳の高齢で、いはゆる天誅組に参加し、戦敗れて刑死した国学者 伴林光平(ともばやしみつひら)などの日記を見ると、耿々(かう/\)たる忠誠が、殆んど報いられてゐないやうな気がして、気の毒に堪へないのである。
しかし、これらの人々こそ、真に明治維新の大業の礎石となった人々で、明治、大正、昭和と3代の恩沢に恵まれてゐる我々が、決して忘れてはならない人々だらうと思ふ。
かういふ人達に比べれば、尊皇討幕の大義名分が、全国を風靡した後、各藩の方針も定まり、それに依って行動した人達などは、仕事も楽であり、一身の栄達も思ひのまゝだったのだから、功臣であると同時に成功者であったわけだ。
明治維新の初期を彩った、各地の討幕反幕の行動を挙げると、井伊直弼の首を挙げた桜田事件、閣老安藤対馬(つしま)を要撃して傷(きずつ)けた坂下門事件、薩藩内部の同士討であるが、京都に、武装蜂起を企てた伏見寺田屋事件、中山忠光の大和義挙、澤宣嘉(さはのぶよし)、平野国臣らの生野義挙、そして元治元年(1864年)の禁門戦争(蛤(はまぐり)御門の変)などがある。
これらのアンチ幕府運動の結果、果して彼等の期待したやうに幕府の勢力は地を払ったであらうか。
成程、歴史の歩みは寸時もその歩調をかへず、その根本に於いては幕府の声威は日々に衰勢を見せてゐるが、表面に現はれたこれらの事件の結果は、必ずしも勤皇運動の伸張を意味するものではなかった。
元治元年(1864年)の禁門戦争の結果は、いよ/\この反動的な時勢の動きを、露骨に示してゐる。凡そ無分別な長州勢の禁裡に対する発砲は、今まで勤皇運動の総本山とも云ふべき長州藩に対して、ハツキリと朝敵の烙印を押しつけた。勤皇側の公卿の参朝停止、これは有名な七卿落ちとなって、惨憺たる急進派の敗北である。
京都の市中は、今や勤皇の志士は全く屏息(へいそく)して、所司代の役人や、会津桑名の藩士、さては新選組の浪士たちが、肩で風をきって、闊歩してゐる。
更に、幕府は朝廷に請うて、長州征伐の師を起し、藩主毛利父子を謹慎させ、その封土から10万石を削らうとしてゐる。
これらのことを大観すると、明らかに幕府勢力の復活といふことが云へると思ふ。尊皇攘夷の代りに、今や公武合体といふスローガンが尤もらしく振りまはされ、幕府は朝廷を擁して、天下の諸侯に昔日の威を以て臨まうとしてゐる。明らかに、頽勢挽回である。
これは一体どうしたのであらう。これでは今まで夥(おびたゞ)しく流された勤皇志士の犠牲の血は、全く無駄ではなからうか。
各藩の志士の中の頭のよい者は、かうした逆効果に反省して、今までのやり方の失敗に漸次気がつく者が出てきた。
桜田事件、寺田屋事件、大和、生野義挙、蛤御門の変、水戸天狗党の擾乱――こう並べて考へてみると、それらの討幕テロの企てには共通した誤りがあった。
つまり、彼等は有志として蜂起し、擾乱を企てただけで、その背後に、少くともその成功を確信させるだけの実力を持たなかったことである。自分たち同志だけで、先づ事を起せば、天下は自然に動いて、討幕が出来ると、簡単に考へてゐたことである。やせてもかれても、幕府はそんなに脆く崩壊しはしない。
この誤りを再びくり返さず、討幕の大理想を実現する方法は、たった一つしかないのである。それは、もつと実力ある者が一致して、幕府に当ることである。バラ/\ではダメなのである。
つまり志を同じくする雄藩が、今までの種々の行きがかりを水に流して、この際大同団結し、同盟を結ぶことである。もつと簡単に云ふならば、薩藩と長藩の同盟である。
なるほど、今や薩長は仇敵の間柄と云ってもよい。長州兵の精鋭は、蛤御門の戦ひで、薩摩軍の銃火にかゝつて、沢山死んでゐる。薩奸会賊と云ふのは、当時の志士の標語であって、薩摩は会津と同じく、佐幕の張本人と目され、その評判のわるいこと甚だしい。
薩藩はしかし、果して佐幕であらうか。断じて否だ。たゞ長州や勤皇急進論者のやうに、過激でなかっただけだ。その耿々たる勤皇精神に於ては、一歩も譲るものではなかったのである。目的は同じであるが、その手段に於て、異っていただけなのである。それから封建の世だけに、藩と藩との間の対立嫉視もある。彼等は一藩を以て一国とし、互ひに対峙してゐたのである。
しかし、大体のコースとして、薩摩と長州とは、それ程深刻に憎み合はなければならぬ理由はないのだ。西国の雄鎮として、共に率先して勤皇の大義を唱へた両藩の先覚者の間に、それほど深刻な敵愾心(てきがいしん)があるとは思へない。話せば分るのである。
こゝ四五年の間の不幸な行きがかりを捨てゝしまへば、両藩の妥協は可能だし、提携も出来る。
たゞ、薩摩でも長州でも、かう気づいてゐたが、責任ある当局者は、自分で先に言ひ出すわけにはゆかないのだ。
この時、両藩の間に橋渡しをして、その提携の糸口を開いてやったのが、土佐勤皇党の俊英、坂本龍馬と中岡慎太郎であった。
慶応元年(1865年)5月6日、馬関へ長藩の巨頭桂小五郎(木戸孝允)を引っぱり出し、薩摩藩の代表、西郷隆盛に会はした。
そして、薩長が互に肚の探り会ひをして、なか/\木戸、西郷の会見がまとまらないと、彼はかう云って怒鳴った。
「何がわが藩の面目、体面、名誉だ。もういゝ加減にしないか。あんた等は、まだ封建制度の幽霊を背負つてゐるか。此の大きな日本を何故忘れてゐるか。同じ日本の土地の上に、位牌知行を立て合ひ、わが藩、わが主人と、区別を立てて何になる。西郷も桂も、これ程馬鹿とは思ってゐなかったよ。」
さう言って、西郷に直(ぢか)談判をして、この薩長秘密攻守同盟を締結させたのである。慶応2年(1866年)1月21日のことである。
しかも此の秘密同盟は、77万石と36万石の大藩が、漫然と一緒になったのではない。この両藩を代表するに足る、西郷と木戸が、腹心を披瀝しあって、討幕の役割を分担することを決めたのだ。
その他に、土佐藩、越前藩、宇和島藩等の各藩も、これを機に一つに固まらうとしてゐる。
坂本龍馬を仲介とする、西郷吉之助、桂小五郎両人の晴れやかな握手は、正に維新大業の出発点といってよい。皇政復古運動の進展は、こゝに一段と拍車をかけられたのである。
明治維新と国体観念
慶応3年(1867年)12月9日、明治天皇小御所に出御、諸卿諸侯を召見し給ひて、皇政復古のことを諭告し給うた。こゝに於て、明治維新のことは、一まづ形の上では成ったのである。
この復古の大号令に先立つこと2箇月、徳川慶喜は土佐の山内容堂の建白により、10月14日に、政権奉還の表を奉ってゐる。
薩長の攻勢はいよ/\激しく、このまゝでは幕府の瓦解は免れ難き情勢となった。この時慶喜将軍は土佐派の公武合体、公議政治論を採って、大政奉還と先手に出たのである。これでは如何に幕府打倒といきり立ってゐる薩長と雖も文句がつけられないのである。
しかし、薩長派の西郷、大久保、木戸たちは、たゞに大政奉還だけでは、ダメだと達観した。200有余年の旧習に汚染した人心を振起するためにも、幕府にはどうしても武力を以て一撃を加へ、天下の人心を一新しなければ、新時代は来ないと見てとったのだ。
板垣退助などは「馬上でとった徳川の天下だから、馬上でなければ奪(と)れぬ」と痛言してゐた程である。
そして彼等は、さま/″\の挑戦的行動をとって、幕府側を怒らせようとした。江戸薩摩邸の焼打などそれだ。こゝに於て、衰へたりと雖も、幕府は依然として幕府だ。大坂に退いて謹慎してゐる慶喜をめぐって、幕臣の激昂は渦をまき、伏見鳥羽の一戦となって爆発、こゝに一箇年余に亙る戊辰戦争の幕は切って落されたわけである。
この薩長主戦派のやり方は、充分に理由はあったけれど、しかし考へてみれば、ずい分危険な権道だったとも云へよう。
若(も)し慶喜が本当に肚を据ゑて、佐幕派の藩士を集めて、反薩長の旗幟(きし)を掲げて起(た)ったならばどうであつたであらうか。
当時フランスは、ナポレオン3世の命を承けた公使ロセスが、積極的に幕府援助に乗り出してゐるのである。金も六百万弗(ドル)貸さう。軍事顧問も派遣すると言った張り切り方である。
だから慶喜が、突如として大政奉還の挙に出ると、公使ロセスはすっかり呆れ、また驚いてしまった。
「300年も天下太平を齎(もたら)した徳川家が、兵戈(へいくわ)も交へずして、こんなに簡単に政権をなげ出すとは、不思議千万である。欧羅巴(ヨーロツパ)には、こんなバカ/\しい政変は嘗(かっ)てない。」と、福沢諭吉に語ったといふ。
が、慶喜は、フランスの援助を拒絶したし、血気に逸る旗本の将士を慰撫し、あくまでも絶対無抵抗主義をとつて、慶応4年(明治元年、1868年)4月11日には、本拠江戸城をも官軍に引渡し、郷国水戸に退いて、弘道館の一室に退隠しているのである。
慶喜は烈公斉昭の子で、水戸学の精神で、幼時から育て上げられてきた人だ。皇政復古は皇国本来の姿で、これは歴史の必然だと観じていたのだ。薩長の専恣は、固より好むところではなかったが、わが皇室が中心となって、これからの日本は世界に乗り出してゆかねばならぬと信じていたことは、決して勤皇の有志と違ふものではなかった。
たゞ将軍といふ立場が、今まで歴史を逆行させる役目を担はせてゐたのである。水戸に退いて、はじめて、慶喜は、一日本人としての自分と、そしてその立場を得て、静かに時勢を眺め得るに至ったといへよう。
攻められる慶喜に此の感懐があったとすれば、攻める薩長側にも、称揚さるべき佳行があった。
フランスが幕府に力を貸したのと同じやり方で、英国の薩長援助は公然の秘密であった。英国公使パークスは、機会ある毎に、薩摩に説いて、幕府及びその背後にあるフランスを打倒すべくすゝめ、その為めにはどんな援助でもするからと、もちかけてゐる。
これに対して、薩長の領袖、西郷吉之助は何と答へてゐるか。
「戦争のことはとに角、日本の政体変革のことは、われ/\日本人だけで考へるべき問題である。外国の援助を受けるは面目ない。」とキツパリと断ってゐるのである。
慶喜といひ、西郷といひ、わが国体といふ点にいたつて、その両極端の立場にも拘はらず、期せずして一致したわけである。外国をある程度まで利用しようと考へたであらうが、その国政干渉は一歩たりとも許さなかったし、近づけもしなかった。そこに維新史を流れる、日本人独得の力強い信念の流れを見るのである。以夷制夷(いゝせいゝ)など、所詮、日本人には出来ない芸当なのであらう。
あれほどに激湍(げきたん)渦を捲いた、維新の政治史に於て、われ/\は此の日本歴史に特有な美談佳話を探さうとするならば、他にもいくつも挙げられるだらう。
伏見鳥羽の戦争がまさに一触即発といふ時、大坂城に在る慶喜のもとへ、岩倉卿から一使者が遣はされた。孝明天皇御一年忌に際し、慶喜に対して献金のことを申出でたのである。恐懼した慶喜は、勘定奉行に命じて、直ちに5万両を朝廷に奉ってゐるのである。
想へ、京都は今や薩長の精兵によって充満し、幕兵一掃といきり立ってゐる時である。大坂城は、江戸から上った竹中陸軍奉行の大軍によって守られ、京都に対して、一戦に及ばんと、陣容を整へてゐる最中である。これらの物々しい空気の中にあって、大坂城と京都御所を結んで、一脈清冽の気の相連(つらな)ってゐるのを見る、われ/\日本人は如何に幸福であらうか。
伏見鳥羽の一戦に朝廷に汚名を着た、徳川慶喜に対する処断は、当時諸説紛々で、初めの中は死刑論が圧倒的に多かった。薩長の諸将は慶喜を憎むこと甚だしく、ぜひこれを誅戮(ちゆうりく)して、刑典を正さねばならぬと主張する者が多かったのである。
この時に於て、明治天皇は三條実美(さねとみ)を召されて、徳川家の旧勲を失はざるやうに処置せよ、との有難き宸翰(しんかん)を賜うてゐる。
これらの聖恩が、たゞに徳川氏をしてその家祀を全うせしめたばかりでなく、明治維新の大業をして容易に成就せしめた所以(ゆゑん)なのである。
戊辰奥羽諸藩の処断に於ても、詔(みことのり)して今日の乱は九百年来の弊習の結果であると、大いに藩主等の罪を恕(じよ)し、今後親しく教化を国内に布き、徳威を海外に輝かさんことを欲する旨を、告げたまうた。恐懼(きようく)の限りである。
この洪大無辺の聖恩があったればこそ、維新の戦乱も容易に鎮定されたのである。慶喜、西郷などの立派な国体観などもさることながら、一たび、明治天皇の御洪大なる大御心に思ひ及ぶ時、明治維新史の花を観る心持がするのである。
廃藩置県と征韓論
明治元年(1868年)の鳥羽伏見の戦ひで始まった維新戦争は、翌2年(1869年)函館の幕軍が降伏して、一段落となり、輝かしい天皇親政の御世となったが、しかし天皇親政の障害となるものは、徳川幕府だけではなかった。
討幕の急先鋒となった薩長二藩をはじめ、全国無数の大小各藩も、一君万民の理想のためには、やがて廃滅せらるべき運命に在ったのである。
討幕のために奔走した勤皇諸藩の主従が、幕府の廃滅はやがて諸藩の廃滅となることを、意識してゐたかどうか、それはかなり疑はしい。幕府の代りに朝廷を戴いて、討幕の功績に対する恩賞をも受け、旧幕時代以上の威福を擅(ほしいまゝ)にしようと考へてゐた者も、絶無とは云ひがたいであらう。従つて、明治4年(1871年)の廃藩置県までは、新興日本は非常なる危機にあったと云つてもよい。一歩あやまれば建武中興の二の舞が演ぜられたかも知れないのだ。
この形勢を、ハツキリと認識してゐたのは、大久保利通である。明治2年(1869年)4月、岩倉具視(ともみ)宛の書簡に、
「即今、内外の大難、危急存亡の秋(とき)切迫すること間髪を容れず、抑々(そも/\)昨年来一時の平和の形をなすと雖(いへど)も、大小藩主 各(おの/\)狐疑を抱き、天下人心 恟々然(きよう/\ぜん)として、その乱れること百万の兵戈(へいくわ)動くより恐るべし……」
と喝破してゐる。
たゞ、当時の各藩は、水戸の天狗騒動で、武田耕雲斎が、わづか数百の兵力で、中部日本を押し通るのを、傍観してゐたのでも分るやうに、軍備的に無力であったのと、天皇親政の中央集権的情勢が天下を風靡してゐたので、利害的にも、人情的にも、至難と思はれた廃藩置県が、見事に断行されたのである。
西郷隆盛が、
「お互に数百年来の御鴻恩、私情に於ては忍び難きことに候(さふら)へども、天下の大勢かくの如く、全く人力の及ばざるところと存じ候」
と、述懐してゐるのを見ても、当時の実情が分り、その局に当った岩倉、大久保、西郷、木戸等の苦衷は察せらるべきである。が、この廃藩置県をはじめ、廃刀令、徴兵令その他明治政府の革新政策に対する武士階級の不平不満が、やがて、西南戦争その他の変乱となつて、勃発してゐるわけである。
明治6年(1873年)の征韓論に就いての廟議の紛糾は、当時の重臣間に於ける文治派と武断派との意見の対立ではあるが、武断派の思想的背景としては、西洋文明の輸入に快からざる保守主義的傾向、攘夷思想の変形である国権論、武士階級の撤廃に対する不満、薩長専制に対する不平などが横(よこた)はってゐることを見逃すことが出来ない。
偶々(たま/\)、岩倉大使と共に欧米を巡遊して、その燦然たる文明の諸施設に驚嘆し、殖産興業に依る富国強兵の大策を、土産(みやげ)として帰朝した大久保利通の眼には、征韓派の主張は、時代知らずの書生論としか映らなかったのであらう。彼が、断乎として反対したのは当然であらう。
が、当時の征韓論は、たとひそれが当時の情勢から云へば無謀であったとしても、やはり発展的日本民族の気魄であって、この気魄があればこそ、後年日清、日露の大戦勝となったのである。
が、この征韓論の決裂に依って、多くの反対勢力を野に放った明治政府は、爾後数年間、苦難の道を歩まねばならなかつた。
現在でも、学生間では、歴史的人物としては、第一に人気があると云はれる西郷隆盛の、生前に於ける大衆の輿望は想見すべきで、その西郷を魁首とした薩軍の蹶起は、明治政府にとっては、現在の我々が想像する以上の危機であったのである。
が、大久保を中心とする政府は、よくその措置を誤らず、徹底的に之(これ)を鎮定して、明治政府の基礎を確立すると共に、新興日本から不平分子を一掃したのである。後年の立憲政治も、この安定した国情の上に築かれたのである。
討幕から廃藩置県までの立役者は、西郷隆盛であるが、廃藩置県以後、変乱時代を通じて、その文明政策に依つて、近代日本を築いた大立物は、大久保利通である。
立憲政治
明治時代に創始された立憲政治の起源は、維新当初の五箇条の御誓文である。いな、御誓文は、当時すでに実行されて、各藩選出の徴士(ちようし)、貢士(こうし)が、後年の代議士のやうに国政に参与してゐたのである。たゞ、この公議政治がよく理解されず、政治の運行が円滑に行かないので、薩長の政治家達が、強力な藩閥政府をつくり上げてしまったたのである。
が、既に、公議政治の何物であるかを知った国民が、藩閥政府の専横を見るにつけ、国民参政の要求をなすのは、当然であった。殊に、征韓論で破れた板垣退助が、立志社を組織し、国会開設の建白を成すや、人心が翕然(きふぜん)として集り、自由民権運動が、天下を風靡した。
が、五箇条の御誓文に依り、憲法を制定し、立憲政治を行ふといふことは、明治天皇の叡慮であったと拝察してよい。
されば、明治12年(1879年)の夏、アメリカのグラント将軍が来朝するや、明治天皇は、将軍を浜離宮に召されて、政治上の事を、いろ/\御下問になったが、
将軍の、
「承るところに依れば、日本にも国会開設の議論がある由、いづれ憲法を御制定になることと存じますが、何事も忌憚なく言上せよとの御沙汰であるから、申上げます。日本の憲法は日本の歴史及び習慣を基として、御起草あそばさるゝことこそ最も願はしく存じます。」
と、いふ意見が、よほど御思召(おんおぼしめし)に叶ったやうであり、同年末には、立憲政治に就いて、山県有朋、黒田清隆、山田顕義(あきよし)、伊藤博文、大隈重信などの各参議に対して、意見の提出をお求めになって居られる。
この時の大隈の意見が、あまりに急進的であったため、大隈は廟堂から追はれて、後年の改進党を組織したのである。されば、憲法制定、立憲政体の実施については、政府に於ても、明治天皇の大御心に依ってその大方針が確立してゐたのであるから、当時に於ける自由民権運動の騒ぎは、藩閥政府の強権に対して、不平分子が国会開設の名を利しての抗争とも見るべきであらう。
憲法の調査起草に率先して当ったのは、伊藤博文であるが、その主旨とするところは、英仏流の憲法ではなく、わが国体を基礎とする「日本の憲法」であった。伊藤は、憲法調査のために外遊し、憲法学者、独逸(ドイツ)のグナイスト、墺国のシュタインに教へを聞き、仏蘭西(フランス)、英吉利(イギリス)を歴訪して、参考資料を蒐(あつ)めて帰った。
当時の最高知識たる井上毅(こはし)は、金子堅太郎、伊東巳代治を率ゐて、その起草に惨憺たる苦心をしたのである。
元来、憲法は、欧洲に発達したもので、民主的色彩の強いものである。それを日本に採用するについて、伊藤は渾身の努力を傾け、日本精神の根柢をなす、皇室中心の忠君思想を盛って、日本独得の憲法を起草したのである。
明治21年(1888年)4月、憲法草案は、明治天皇の御前に奉呈された。天皇は、その草稿を御嘉納あそばされ、新たに枢密院を設けられ、国家の元勲と練達の士とを集めて、逐条御諮詢、その審議を聞召(きこしめ)さるゝこと8箇月に及んだ。その間の御励精は、かしこき極みであった。
かくて、明治22年(1889年)2月11日、紀元の佳節を期して、わが万世不磨の大典は全国に発布されたのである。
日露戦争以後
明治6年(1873年)に、その時を得ずして、開花しなかつた征韓論の精神が、その時を得て花を開き、実を結んだのが、日清戦争であり、東洋に於ける日本の位置を確立した戦争である。しかも、戦勝日本の実力を築いたものは、大久保利通に依つて指導された殖産興業に依る富国強兵政策であった。それと同時に、民意に基づく国民戦争を行ふについて、立憲政治がいかに有力であるかを示したのである。
当時、官民朝野の反目甚だしく、国会開設以来、議会は闘争場の観があったが、一旦開戦となると、国民は斉(ひと)しく起つて、渾然たる一体となり、広島で開かれた臨時議会は、僅かに五分間で、当時としては厖大なる臨時軍事費一億五千万円を可決したのである。
当時の新聞雑誌を見ても、国民の一致団結は、涙ぐましいくらゐであり、純粋素朴な愛国的感情が随処に、ほとばしってゐるのである。精動運動を必要とするやうな現代の国民は、愧死(きし)してもいゝくらゐである。
日清戦争に依って、東洋に於ける位置を確立した日本は、その発展途上の宿命として、露西亜(ロシア)と、衝突せねばならなかつた。
これは、当時としては、喰ふか喰はれるかの一大抗争であつた。
日清戦争の終局に於て、三国干渉の首謀者として日本の遼東半島領有を放棄せしめた露西亜(ロシア)は、逆に旅順、大連を獲得し、まさに満洲を軍事的に占領し、更に朝鮮へも南下しようとしてゐるのである。もし、この形勢を甘受せんか、日本もやがて、彼の勢力下に蹂躙されたかも知れないのだ。
これより先、日本は、日清戦争の苦き経験に教へられて、日英同盟を締結し、専心露西亜(ロシア)に備へてゐたのである。
果然、明治37年(1904年)2月8日、旅順に於て、第一戦の砲火が交へられた。開戦当初は、作戦当局にも確固たる勝算はなく、国家自衛のための決戦であったが、戦争の結果は、海陸共に戦勝を重ね、遂に敵の戦意を挫折せしめたのである。
講和談判の結果は、国民の期待通りではなかったが、結局露国は満洲を断念し、その東方政策を放棄し、日本は代って満洲に大陸発展の第一歩を踏み入れたのであるから、実に満足すべき大成功と云ってよいので、一に大陸及び黄海、日本海に血を流した同胞の犠牲のおかげである。
日清、日露両役を通じて、明治天皇が、軍国の御政務に御精励遊ばされた御様子は、畏れ多き極みで、幾多の御製を拝してもその一端を拝察することが出来るが、2箇年の歳月を経た日露戦争後には、戦前まで、漆黒であらせられた御頭髪が、半白にならせ給うたとの事で、恐れ多くも、6年後の御大患は、この戦争中の御過労に起因するとも云はれてゐるのである。
国家の如何なる大事変に際しても、何人(なんぴと)よりも先に御軫念(ごしんねん)遊ばされるのが、上御一人であることを思ふとき、我々は三思して日本国民たる多幸を思ひ、奉公の誠を尽くすべきだと思ふ。
日露戦争に依つて、世界に於ける日本の位置は、確立せられたが、第一次欧洲大戦に際しては、聯合国側に参戦して、東亜の安定勢力たる実力を十二分に発揮した。
この辺から、日本は世界史の舞台に登場したわけで、ロンドン及びワシントンの軍縮会議などは、日本の涯(かぎ)りなき発展に対する欧米列強の嫉視的工作であると云ってもいゝと思ふ。
昭和6年(1931年)の満洲事変は、日本が世界歴史をリードしようとしはじめたことを意味してゐる。満洲の一角に上つた現状打破の波紋は、旧勢力に依る国際聯盟を無力化し、伊太利(イタリー)、独逸(ドイツ)等の活躍となり、世界新秩序形成の口火となったとさへ思はれるのである。
今や、わが日本は、世界新秩序の一角たる東亜新秩序建設に従事してゐる。「無賠償、無割譲」といふ道義的和平条件を正面に立てて、東亜諸民族の恒久平和の楽土を建設するために戦ってゐるのである。
その目的は宏遠であると共に、日本始まつて以来の難事業である。しかし、この大業が達成せられるかどうかは、日本の国運をも、左右しかねないのである。
我々は、先祖以来二千六百年来の皇恩を思ひ、現在日本国民たるの多幸を思はば、一致団結、今次の大業のために、身命を捧げ、以て二千六百年 肇国(てうこく)以来の皇謨(くわうぼ)を扶翼し奉るべきであると思ふ。