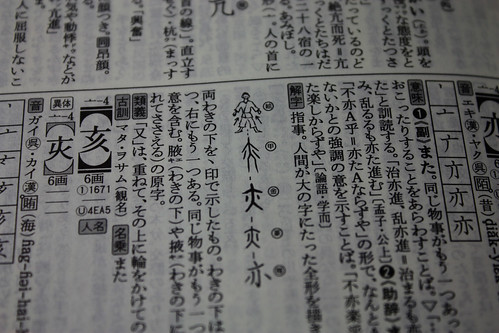なんか久しぶりに『十二国記』を読み返してみた。
なんか久しぶりに『十二国記』を読み返してみた。小野 不由美という作家のシリーズで、これをきっかけにいくつか作品を読んでみた。だけど私見では本シリーズ以外はあまりにつまらないんだよな。「なぜアルジャーノンを書けたんですか?」「それは俺が教えてもらいたい」というダニエル・キイスの話を思い出したりする(笑)。否、自ら「パスティーシュ」を意識し始めて下らなくなった清水義範かな。
そんな現在の状況にひきずられて引いてみたのは「王」。
『新漢和大字典』によると「王」は「会意文字」。「手足を広げた人が、天と地の間に立つさま」だそうな。『漢字海』によれば「指事文字」。「天下が帰着し、服し往く対象である」。ま、『漢辞海』にはよくわからんことが往々にして書いてある(笑)。で、『日本語漢字辞典』はなんと「象形文字」。「鉞の刃を下に向けた形」だそうな。
ようするに「王」という漢字が古く、出自がわからないってことなのかな。そういえば OED のように初出を明らかにする漢字辞書ってのはないのかな。きっとありそうな気もするけれど。
月の影 影の海〈上〉 十二国記 講談社X文庫―ホワイトハート
posted with amazlet at 09.03.31
小野 不由美
講談社
売り上げランキング: 11816
講談社
売り上げランキング: 11816
おすすめ度の平均: 

 素晴らしい!
素晴らしい! 命を棄てる程の絶望
命を棄てる程の絶望 ありじごく
ありじごく 夢中になった
夢中になった 誰でもおもしろいと思えるわけじゃない
誰でもおもしろいと思えるわけじゃないアルジャーノンに花束を (ダニエル・キイス文庫)
posted with amazlet at 09.03.31
ダニエル キイス
早川書房
売り上げランキング: 1126
早川書房
売り上げランキング: 1126
おすすめ度の平均: 

 脳科学の未来を考える。
脳科学の未来を考える。 「人間らしさ」の一つの答え
「人間らしさ」の一つの答え 人間としてあるべき姿とは?
人間としてあるべき姿とは? 矛盾と不安を抱え、真摯に生きる
矛盾と不安を抱え、真摯に生きる ルビ付きを読みました
ルビ付きを読みました