平成27年9月 2泊3日飛騨高山温泉~下呂温泉旅行へ

台風が18号・19号とダブルで接近中、梅雨前線も日本列島を覆いかぶさっていて、天候が心配の中での
出発となりました。北千住6時に待ち合わせです。
12時30分、最初の目的地、新穂高ロープウェイに到着。

天候が悪いので、園のテーブルは、かたされていました。無料の足湯は、屋根つきなので、入っている方がいました。

頂上のライブ映像が流れています。

只今の山頂気象情報も展示されています。
悪天候ですが、せっかく来たので、ロープウェイに乗ることにしました。



山の天気は、変わりやすいといいます。山頂は、もう少し雲が切れていればいいのにと思いながら、、、。

山頂は、思っていた以上に雨風が、強く残念でした。

今度で4回目の新穂高ロープウェイでしたが、今回も絶景を見ることができませんでした!
「北アルプス大橋」へ寄ってみました。悪天候です。こちらでも絶景には程遠い景色でした。



天気が良ければ北アルプス大橋からこのような絶景が見られるそうです。

昼食は、高山ラーメンを食べました。
「高山ラーメン」は、醤油ベースのスープで、ねぎ・メンマなどのシンプルな具、細く縮れた麺が特徴です。スープも丼の中にたれを入れてそれにスープを溶くのではなく、スープとたれを一緒に混ぜて煮込みます。
お蕎麦に近い気がしました。あっさりしていてラーメンが苦手な私でも美味しくいただけました。

飛騨高山温泉は、弱アルカリの美肌効果ありの温泉でした。
「高山陣屋」江戸幕府が飛騨高山を管理するために作らせた代官所(陣屋)。


飛騨高山のシンボルの橋、「宮川中橋」。


古い町並みは、当時の面影を残しながらのお店が建ち並んでいます。

「舩坂酒造」のれんをくぐると、中庭がありここで、枡酒がいただけます。

テーブルの上には、お酒をいただく方の為に塩が置いてあります。
私たちは、無料の試飲でご満悦!

小京都高山の町並。気になるお店はたくさんありましたが、「大のや醸造」で、赤みそと糀(こうじ)味噌をお土産にしました。

高山は、落ち着いた風情ある良い町でした。またゆっくりと見て回りたいですね!

高山観光では、今朝の雨が嘘のように青空の中で、散策出来ました。
これから郡上八幡を通って下呂温泉へむかいます。
道の駅「ななもり清見」で、これからのコースチェックです。
途中、「道の駅」を寄りながらのんびりと思っていましたが、台風の影響の為、道すがらの「道の駅」は、すべて休業中でした。
下呂温泉に早めに入ってのんびりしました。
下呂温泉は、有馬温泉・草津温泉と並ぶ日本三名温泉です。
アルカリでとろーとしていて、お肌にいい感じです。
今朝も雨でしたが、10時チェックアウトの時間には、青空が見えてきました。


今日は、妻籠宿~寝覚の床へむかいます。

「馬籠宿」


石畳が敷かれた坂道の宿場町です。


石畳の坂道の両脇には、お土産物屋が並びます。

五平餅、おやきは食べ歩きで、美味しく頂きました。
お土産は、御菓子司「澤田屋」で、小豆、栗で作ったお菓子を買いました。


「中山道」は、はじめ「中仙道」と書かれていたが、本州の中部山岳地帯を貫いている道路ということから、享保元年(1716)以降、「中山道」と書き改め、やはり「なかせんどう」と読まれた。
江戸と京都を結ぶ重要な街道で、その延長は百三十二里(約550km)、ここには69の宿場が置かれた。(案内板より)
中山道は、木曽路をはじめ、峠道が多いので人馬の往来は困難でした。参勤交代の大名は、東海道の154家に対し中山道は、34家でした。
しかし往来が少なく大河もなく、氾濫に伴う渋滞も少なかったことから、将軍家に献上する宇治茶の茶壷道中や、将軍家に輿入れの皇女和宮など中山道を利用した。

ここ中山道で、二人で、何をしているのかと思ったら?

石が剥がれていたのを定位置になおしていました。いいこと(仕事)しましたね!



石畳を歩いて行くと展望台があります。

台風の影響で、雲の流れが速いです。

「木曽路はすべて山の中である」島崎藤村の『夜明けまえ』の書き出しを思い出します。
島崎藤村は、ここ中山道・馬籠生まれです。


天候が刻々と変わる中、馬籠宿も雨に降られることなく歩くことが出来ました。良かったです!
「寝覚の床」は、木曽川の水流によって岩が浸食されてできた地形。
「寝覚の床」は、浦島太郎が竜宮城から帰ってきた後の伝説が残っています。


絶景です。



浦島太郎が、竜宮城・乙姫からもらった玉手箱をこの地で開け、白髪のおじいさんになってしまい、びっくりして眼がさめた。
眼をさましたというこてで、ここを寝覚という。



中央にある「浦島堂」は、浦島太郎が弁財天像を残したといわれています。

足場が悪く、「浦島堂」までは、行けません!

展望台から見たときは、岩伝いに楽そうに行けるように見えましたが、足場がないので、危険です。
駐車場に戻った時は、山歩きしたように汗びっしょりでした!

これから東京に帰ります。
今は、こんなにいい天気です。

梅雨前線と台風の影響を受けながらの旅行でした。帰りに寄った、諏訪湖インターでは、
左側は雨、右側は晴天で、まぶしいほどの光がさしていました。

飛騨高山温泉と下呂温泉 ゆっくりつかってリフレッシュしてきました。
観光時は、雨に降られず、散策を楽しめたのは、よかった!

「寝覚の床」

「馬籠宿の萩」































































































































































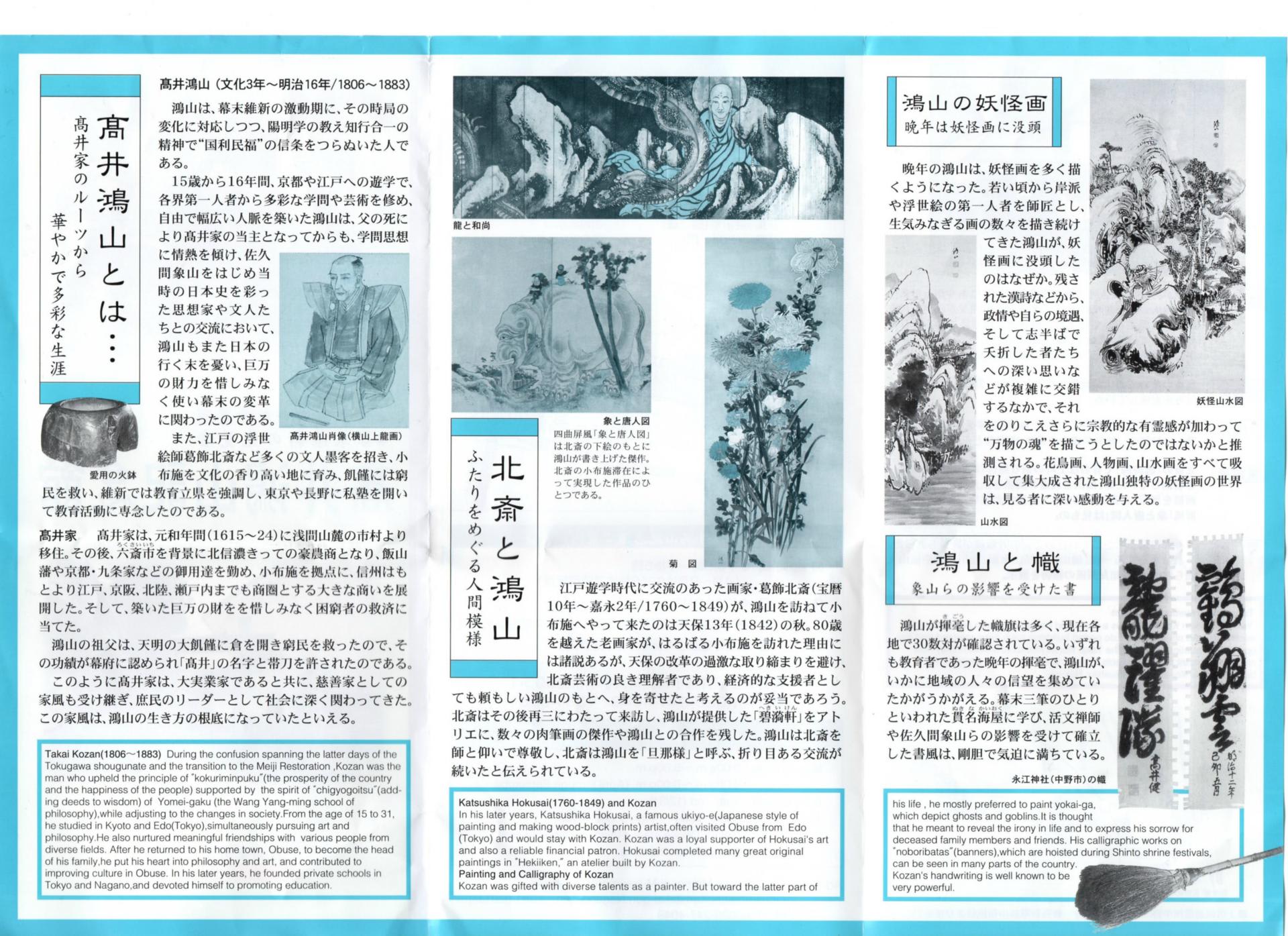





















































































































 「奥の院」
「奥の院」


 「最上川」
「最上川」

 紅葉の時期は、このように見事だそうです。 「鳴子峡の紅葉」鳴子温泉旅館組合HPより
紅葉の時期は、このように見事だそうです。 「鳴子峡の紅葉」鳴子温泉旅館組合HPより













 「須賀の滝」
「須賀の滝」 樹齢1000年、樹の周囲は10mの巨杉
樹齢1000年、樹の周囲は10mの巨杉


















