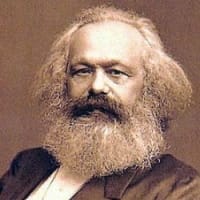本ブログ 総目次へ戻る
「日本経済の将来を展望する」もずいぶん長くなってしまった。ここで少々まとめてみたい。
- 国民経済計算によると2012年から賃金総額(*)は増え続けている。増加の原因を、もう一つの賃金に関する統計である賃金構造基本統計調査から探ってみると増加の重要な要因は勤続年数の上昇にあった。賃金の上昇に一番必要なもの、それは安定した雇用環境である。
- ところがGDPの成長率は賃金総額の増加率を下回っている。賃金の上昇が消費に回っていない。
- 1997年から2021年までの消費支出の伸び率の平均は0.2%であり、2013年の消費増税を前にした駆け込み需要と2021年のコロナ禍の影響という両極端を除外すると0.1%という結果となる。いずれにせよ誤差の範囲であってこの間消費は全く動かなかったということだ。
- 原因は可処分所得の低迷にある。賃金総額はようやく1997年の水準に戻ったかどうかというときに社会保険料は1997年の1.52倍になっている。社会負担控除後の賃金は1997年からマイナス7%となっているうえに、この間消費税は5%から10%になっている。
- 一方企業の税負担は減り続けている。特に資本金10億円以上の大企業の実効税負担率は1991年の58%から2021年の18%と激減している。
- 家計に重く企業に軽い税・社会負担となっているのは、利益を確保したいという企業側の思惑と政府が結託しているためである。
- しかしその結果、総需要は伸び悩み、利益を確保したいという思惑と裏腹に国内での企業の持続的利益確保は難しくなっている。
- 企業負担を軽くしたにもかかわらず資本の海外逃避は進んだ。需要のないところから需要のある所へ資本が移動するのは極めて自然なことである。企業負担の軽重は資本の海外逃避(投資)とはあまり関係はなかったのである。
- 1997年から始まった日本経済の長期停滞はいまだに続いている。いまや没落する日本というのが前提になってしまっているが、長期停滞には明確な原因(*)があり、明確な原因がある以上、宿命などではなく克服できる課題に過ぎない。
- それでも日本経済の底が抜けなかったのは高齢化の進行によって年金を媒介とした再分配が進んだからである。その社会保障の財源を家計にだけ押し付けてことが消費低迷の原因である。
*賃金総額には社会保険料の企業負担分も含まれる。社会保険料が上昇すると増えることになる。
*明確な原因は、経済全体が債務償還に傾き過ぎていることと、再分配構造の歪みにより総需要が伸び悩んでいることである。
以下続く