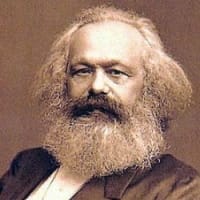雇用の増減は投資の増減によるのだが
消費性向があまり変化しないとすれば総雇用・総所得は投資量の関数となる。すなわち雇用の増減は投資の増減によることになる。
所得の増減によって消費も増減するが、その増減は所得の増減ほどではない。つまり消費の増加分は所得の増加分より小さい。消費の増加分÷所得の増加分を限界消費性向と呼ぶ。消費をC、所得をYとすれば、⊿C/⊿Yが限界消費性向である。限界消費性向は1より小さく、かつ所得が増えるほど小さくなるだろう。ここまでは理論の前提となる観察的事実である。
さらに投資をIとすると
⊿Y=⊿C+⊿I、つまり所得の増加分は消費と投資の増加分に等しく、消費と投資の増加分だけ所得が増加するということである。ここまでは異論のある人はいまい。問題はなぜ投資が増えないのか、という点である。この章もなぜ投資を増やすのが困難なのかの解明に充てられている。
この式⊿Y=⊿C+⊿Iは、
消費が1単位増えれば所得がそれに対応して何単位増えるか。
投資が1単位増えれば所得がそれに対応して何単位増えるか。
ということを表している。と同時にその逆の関係:所得1単位の増加に対して消費、投資がそれぞれ何単位増加するかをも表している。等式ですから。
ケインズは、
- 所得1単位の増加に対して消費が何単位増加するかを限界消費性向と呼び、
- 投資1単位の増加に対して所得が何単位増加するかを投資乗数と呼んでいる。
おわかりのように限界消費性向と投資乗数は逆の向きを持っている。その理由は消費が投資の原資である貯蓄を決め、投資が所得を決めるという循環構造が存在するからである。この循環構造の中では向きは同じとなる。消費⇒貯蓄⇒投資⇒所得⇒消費である。この循環の中で⊿所得⇒⊿消費が限界消費性向、⊿投資⇒⊿所得が投資乗数と呼ばれているのだ。新古典派・現代正統派は忘れがちであるが、この循環が回っていけば必ず経済は成長する。なぜなら労働過程を内包しているからだ。
それはさておき
⊿Y=⊿C+⊿Iという等式は⊿Y=k⊿Iという式に書き換えることができる。このk=⊿Y÷⊿Iを投資乗数とすると限界消費性向は1―1/kとなる。これは⊿Y=⊿C+⊿Iと⊿Y=k⊿Iの二式から⊿C/⊿Yを求めただけなので各自計算してみてください。
この節はケインズの論考の進め方から離れた方が分かりやすいと思われる。ケインズはkをもとに議論を進めているが限界消費性向をpとして投資乗数の逆数をqとして議論を進めることも可能である。
⊿Y=⊿C+⊿I 両辺を⊿Yで割ると
1=(⊿C+⊿I)/⊿Y
⊿C/⊿Y+⊿I/⊿Y=1 これは p+q=1ということである。
qはk:投資乗数の逆数なのだから当たり前だ。ここで限界消費性向:pが大きいほど(1に近づくほど)投資上場数の逆数:qは小さくなり、1/qである投資乗数kは大きくなる。またpが小さいほどqは大きくなりその逆数であるkは小さくなる、ということもわかる
ケインズは、限界消費性向:pが大きい社会は小さい社会より貧しいだろう。貧しい社会は限界消費消費性向が大きいほど投資乗数は大きくなり、逆に限界消費性向の小さい豊かな社会ほど投資乗数は小さくなる。ということを主張している。このことは、もし仮に限界消費性向が小さくしかも完全雇用状態ではない社会において完全雇用を目指して投資を行おうとした場合に、その額が認めがたいほど巨大なものになることを示している。実はこの投資乗数の低下こそ世界が「格差の拡大」という形で貧困を抱え続けなければならない大きな理由の一つなのだ。
これだけでは全くわからないだろうということでケインズは数値モデルのようなものを持ち出してくる。
もっとも単純な前提を導入する
- 500万人の雇用が生み出す総所得をYとする。1人当たりが産み出す所得をXとする。
- Y=X×Nという一次関数の関係が短期では成り立つ。Nは雇用量。
- このとき消費性向は1とする。つまり生産したものは100%消費されるということである。
- 追加雇用10万人の追加生産物はその99%が消費される。以下10万人の追加雇用ごとに消費性向は1%ずつ下がっていくとする。仮定で重要なのはこの限界消費性向低下だけである。
- 完全雇用状態のときの雇用は1000万人とする。
このような前提から以下のような表が得られる

1のケース:雇用によって生み出される所得は全て消費され投資の原資すら存在しない。
2のケース:追加の雇用から生み出される所得の99%は消費され1%が投資に回される。生産物はかたぱっしから消費されるので投資先を見つけるのも容易である。
3のケース:前提から追加の雇用から生み出される所得の98%は消費され1%が投資に回される。このような社会では例え投資が半減しても失われる雇用は10万人に届かない。
4、5のケース:投資額が82から41へと半減すると、雇用は120万人失われる。これは900万人の13.3%にあたり由々しき事態となる。
それぞれのケースで投資乗数=⊿所得/⊿投資を計算すると100、50、約3.6、2.5、2となり限界消費性向が低下する前提では投資乗数も低下していく。これは雇用を維持・拡大するための投資額が、投資乗数の低下に反して増大することを示している。2のケースでは10万人の雇用を増やすために0.1の投資でよかったのに6のケースでは127.5の投資が必要になってくるということだ。
6のケースで限界消費性向が50%のとき消費性向は872.5÷1000=87.25%である。現代日本の消費性向は60%台前半だから、限界消費性向は50%を大きく下回っていると見なくてはならない。すなわち不安定雇用(失業+非正規)をなくすためにはケインズの時代よりはるかに大きな投資が必要ということなのだ。
投資の乗数効果がないのだからケインズの一般理論はもう古いという極めて単純な言い方をしばしば見かけるが、投資の乗数効果が鈍ってくるのは一般理論では織り込み済みだ。
豊かになるほど完全雇用達成は難しい
ここからケインズが導き出す結論は、投資(公共投資)の影響は深刻な不況のとき、非自発的失業が大量に存在しているときは、投資が雇用に及ぼす影響は大きい(失業対策として効果的)ということである。
使われない貯蓄は、何かに使ってしまったほうがいい。利益を生むかどうか、という問題、回収とか金利とかの問題ではないのだ。投資は必ず総所得を増やすから。一方豊かになるほど、完全雇用に近づくほど投資の乗数効果は減少する。消費性向が小さくなるほど完全雇用の実現と賃金水準の上昇によって社会全体を豊かにすることは難しくなる。このあと「穴を掘って埋める」という議論が登場するが、この議論を現代に置きなおして解釈するのは示唆に富む。
37:第10章 穴を掘って埋めるとは? 最も流布した一般理論への誤解
資本主義の非営利化
豊かになるほど、投資の機会が、特に営利を目指した投資の機会は減少する。その結果投資先を失った余剰資金が蓄積していく。資本主義のこの段階こそ資本主義が「社会化」するための前提条件である。非営利でなおかつ全ての人々の効用につながるような投資の機会は、いくらでも存在するが、この段階になって初めて人々はその原資を手に入れたのだから。ここから資本主義の非営利化という表現自体が矛盾するような課題が登場してくる。現代の様々な問題の根底にはこの「資本主義の非営利化」という課題が存在しているのである。