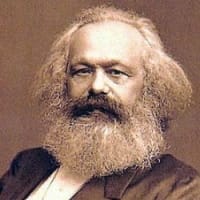重商主義の国家主義的性格と戦争好きについて 第23章続き
私の批判の全重量はかくして、私を育み私が何年ものあいだ教えてきた自由放任学説の理論的基礎の不十分さに――利子率と投資量は最適水準に自己調整され、それゆえ貿易収支に拘泥するのは時間の無駄だとする考えに向けられる。われわれ経済学者の一団が、何世紀ものあいだ実際的な経世済民術の主目的であったものを、おこがましくも子供じみた妄執だとあげつらう過ちを犯してきたのはいまや明らかだからである。
この誤った理論の影響下でロンドンのシティは、均衡を維持するために、想像しうるかぎりでの最も危険な手法、すなわち銀行割引率を固定的な外国為替相場に連結させるという手法を徐々に編み出していった。
つまり、国内利子率を完全雇用と見合う水準に維持するという目標は完全に放擲されたのである。国際収支を無視することは実際問題として不可能であるから、国際収支を調整する手段は発達したが、国内利子率のほうはそれを保護する代わりに盲目的な力の作用に委ねることになってしまった。
為替相場を維持するために公定歩合を調整することは現代でも行われている。バブルの生成と崩壊がその証である。今では調整のしようもないのであるが。ドル相場維持のために日本の金融財政当局が過剰流動性を発生させ、以後長くバブルの発生とその後遺症に痛めつけられる。
ケインズにとって重商主義者たちは「実践的知恵の格率に行き着いた人々」であった。ここからケインズはヘクシャー教授の大著を引用しながら、重商主義の実践的知恵の格率を救い出そうとする。
この項は、ヘクシャーの引用、コメント、ケインズのコメントが入れ子になっており、かつ昔のイギリス人が大勢出てくるので読みづらい。読みづらいがなかなか面白いので是非読んでいただきたい。塩野谷訳はケインズの原文から受ける印象より硬いのでお勧めはしない。
大きくは4点である。
- 重商主義者は利子率には自己調整的性格はなく、利子率は貨幣量と流動選好に依存することを知っていた。重商主義は貿易収支によって貨幣量(金)を増加さえようとする政策である。
- 重商主義者は近隣窮乏化政策の誤りを知っていた。「貿易を増やそうとするあまり、国を害してまで他国より安値で売ろうとしてはならない。需要が少ないことと貨幣が乏しいことが安値の原因、物の値段を安くするのであるから、商品がたいそう安いからといって貿易が伸びる筋合いのものではない。ゆえに反対の場合、すなわち貨幣が豊富で、商品が需要の増加によって高価になっている場合には貿易は増加する(ジェラルド・マーネリス、1622」
- 重商主義者は「〔過剰な〕財貨への恐怖」を論じ貨幣不足が失業の原因だと考えた最初の人たちである。このような考えを、二世紀の後、古典派はたわごとにすぎないと一蹴することになる。
- *「〔過剰な〕財貨への恐怖」って何?原文では財貨=goodsである。商品の過剰である。原文の文脈では、輸入によって商品はあふれ、貨幣量は減少し、失業が蔓延することを言っている。
- *間宮、塩野谷両氏ともなぜ財貨と訳したのかわからない。財貨では金銭と品物になってしまい、すぐ次の貨幣不足と整合性がない。その前に出てくる金や銀の財宝を溜め込むことと理解したのかもしれない。
- 重商主義者はその政策が国家主義的で戦争に向かう傾向にあることはちゃんとわかっていたし、実際にそうなった。
第4点が重商主義の最大の問題である。実際に17世紀からずっと貿易戦争は実際の戦争になってきた。では自由放任にすれば戦争はなくなるのか?
ここからケインズは来るべき戦争を防ぐための提言に入る。重商主義が戦争を引き起こすのは他に手段がなかったからである。戦争以外に貨幣量を増加させ、利子率を引き下げ、公共当局が然るべき投資をできるようになった現在(1936年)戦争は防げるというのがケインズの信念である。
残念ながら防ぐことはできなかったが、第二次大戦後は経済学者も政策当局者もみなケインズの提言を採用した。
その後ケインズ反革命が起こったが、ケインズ反革命を放置すると戦争の危機は収まらない。
該当箇所を引用する。例の誤訳箇所なので筆者訳にしてある。
国際通貨システムというものがもつこの不可避の帰結(筆者注:国家主義と戦争)を容認した彼らのあっけらかんとした無頓着はたしかに批判されてょい。けれども知的な面で見ると、彼らのリアリズムは、不動の国際金本位制と国際金融における自由放任を主張する現代の論者――こうした政策こそが最も平和を促進すると信じている論者の混乱した思考に比べればはるかにましである。
それというのも、通貨が収縮する傾向にあり、関税が相当の期間にわたって多少なりとも固定化され、そのために国内の貨幣流通量と利子率が主として国際収支により決定されるような経済、戦前のイギリスがそうだったのであるが、そのような経済では、隣国を犠牲にして貿易黒字と貨幣金属の分捕り合戦をする以外、当局は国内の失業と闘う正統的手段をもたないからである。
歴史上、一国の利益を隣国の利益と相反させるのに、国際金本位制(あるいは、それ以前の銀本位制)ほど有効な方式は存在しなかった。というのは、国際金本位制は一国の繁栄を競争的な販路獲得と競争的な貴金属への渇望とに直接依存せしめたからである。幸運な偶然によって金と銀の新たな供給がいくぶん増えたときには、分捕り合戦はいくらか和らぎはしたであろう。だが富が増加し限界消費性向が逓減するにつれて、合戦は徐々に共食いの様相を呈するようになった。正統派経済学者の常識はみずからの誤った論理を正すに足るほどのものではなく、彼らの演じている役回りは昨今の舞台では悲惨なものであった。苦境を脱出しようと必死の努力を試み、そうした中で、これまで自主的な利子率を不可能にしていた縛りをかなぐり捨てた国もあったというのに、これらの経済学者は、以前の足枷を回復することが全般的回復に至る必須の第一歩だと説いていたのだから。
一般理論以降の世界では何をすればいいのかは分かっているのだ
本当をいえば逆が正しい。必要なのは、国際的顧慮に煩わされることのない自主的利子率の政策、そして最適な国内雇用水準に向けた国家的な投資計画の政策である。このような政策はわれわれ自身とわれわれの隣人たちを同時に救うという意味で、二重の恩恵をもたらすだろう。しかも国際的規模で経済的健康と強さ――国内雇用水準で測ってもいいし、国際貿易量で測ることもできる――を回復しようとしたら、すべての国が一丸となって、同時にこうした政策を追求することである。
- (原注)この真理に対して国際労働事務局(International Labour Office)が、最初はアルバート・トーマスの下で、次いでH・B・バトラー氏の下で、一貫して賛意を表明してきたことは、戦後に創設された数ある国際機関の意見表明の中でもとりわけ傑出している。
- ここで「以前の足枷」というのは金本位制に復帰すること。
- 国際的顧慮に煩わされることのない自主的利子率の政策、そして最適な国内雇用水準に向けた国家的な投資計画の政策にILOが一貫して賛成していたことは傑出している。今も日本以外のナショナルセンターは反緊縮を訴えているのだが。