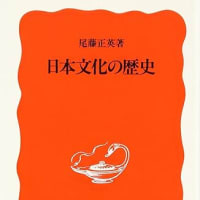ポートアイランドが作られ始めた1966年、神戸が日本国復興にあわせるように日本の貿易の出入り口として発展して、今までの不当では不足した分を補おうと計画された。この時点で神戸港はNY、ロッテルダムを抜いて世界一の貿易量となっていたという。ポートアイランドの埋め立てに使われた土の量は8000万立方メートル、一ノ谷から神戸の街の上をベルトコンベアで運ばれ、海の上をバージが運んだ。ポートアイランドが完成した1981年、博覧会ポートピアが開催された。「魅力ある未来都市」、これがテーマであった、先端の流行や文化を取り入れ、古いものは未練なく捨て去る神戸を象徴するような博覧会であった。
金星台という展望台が諏訪山の山の端にある。ここからは神戸の街が一望できる。明治7年にこっkでフランス人ジャン線が金星を観察したことから命名された。ここに記念碑がもう一つ建つ。海軍営之碑、勝海舟の海軍操練所跡であり、坂本龍馬たちが住んだ寄宿舎の横には折れ鳥居があった。戦後道路工事の邪魔になるとあっさり撤去された。我が国海軍濫觴の地、と刻まれた水飲み場の石は戦後、これも取り除かれたらしい。
金星台の麓には異人館地帯があった。その海洋気象台の下に中華同文学校があり、その一角に中華会館があった。孫文もそこには立ち寄ったという。さらに東に200メートル行くと移民館があった。戦前の移民はここから送り出された。石川達三の蒼茫に登場するお夏や孫市などのような惨めな人たちだっただろう。戦後は移民も明るく送り出された。移民館から東に行くとトーアロードがある。ドイツ語で門を意味する”Tor”が語源だとか。
布引と六甲は対照的な山だ。布引は布のようにながくひいて流れ落ちる滝にその名の由来がある。布引の茶店に美人三姉妹がいた。松、福、三番目の名前は不明であるそうだ。お福に恋したのがポルトガルの海軍士官モラエス、日本に惚れ込み日本人になりたかったという。しかしお福は胸の病気でしんでしまう。傷心のモラエスは徳島に渡り、そこでおヨネという娘と結婚した。六甲を開発したのはイギリス人グルーム、モラエスとは対照的に明るい太陽のような男。六甲山に別荘を造り、1903年日本初のゴルフ場を開発した。1929年にはドライブウエイーにバスも通るようになり、1932年には六甲ケーブルが完成、布引は開発から取り残され、六甲は開けた。
神戸の海は港湾とそうでない海にわかれる。サナトリウムや映画が上映されたのも神戸が日本で最初だという。須磨の水族館、パーマネントウェーブ、ラムネ、スーパーマーケット、ペスト流行も神戸が最初。神戸には1938年大水害があり、1945年には大空襲があった。水と火の大災害だ。そして1995年に大震災、谷崎潤一郎は関東大震災があったので地震がないという神戸に転居してきたと言うが、1995年にはいなくて良かった。
こんな神戸の四方山話、陳舜臣らしいエッセイである。
神戸ものがたり (平凡社ライブラリー)