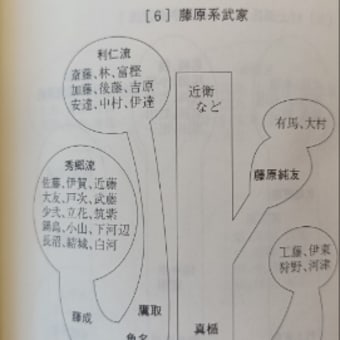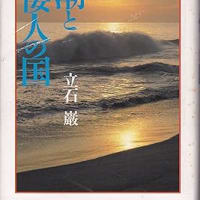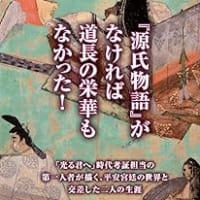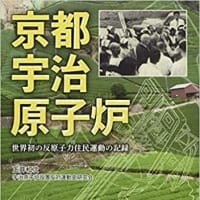古くはローマクラブによる「成長の限界」、その後米元副大統領アル・ゴアによる「不都合な真実」、そして毎年開かれるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)などの報道で、このまま経済成長を続けていたら人口爆発、宗教戦争や格差問題によるテロ多発、地球環境破壊などが進んで取り返しがつかない事態になるということ、多くの人が認識はしているはず。これは破滅論者の大予言ではなく、エネルギー枯渇や食糧問題、温暖化問題などはすべて科学的に検証されてきた破滅的シナリオである。見て見ぬ振りも限界であり、ハリケーンや台風、熱波に干ばつ、森林火災などが次々に報道される昨今、現実問題として、現在を生きている世代の問題として直視せざるを得ない事態である。
事実を再確認する。石油の採掘の経済合理性を計測する尺度に採取エネルギーと投資エネルギーの比率(ERoEI)があり、20世紀初頭には100:1だった。1990年には35:1になり、2019年現在平均は11:1。オイルサンドは3:1、バイオ燃料は1.05:1、原子力は10:1石炭は50:1、シェールガスは5:1、天然ガスは10:1、水力発電40:1、2019年平均11:1は現時点での加重平均である。ERoEIが10:1以下では現状では経済採算がとれず、資源があっても採掘できない判断になる。つまり、電気ガス水道などのインフラ価格上昇にとどまらず、化石燃料に依存して築き上げられてきた現代社会が成り立たなくなる懸念がある。これをロックイン現象と呼び、明確な出口対策が見当たらない。
もう一つの事実は地球温暖化。1880年以降の平均気温は2014年までに0.85度上昇。2050年には2度、2100年までに4.8度上昇することを回避する必要条件としてIPCCが示した指数はすべて満たされなかった。その間、IPCCが予想した地球気温展望は驚くほど正確に的中してきた。IPCCの2100年の地球環境予想は、海面1m上昇、東南アジアデルタ地帯での農作業が不可能になり、メキシコ、ベネズエラ、インド、インドネシア、フィリピンの大都市が海水に浸る。その結果は飢餓による難民発生、移民、流行病、社会の無秩序化による戦争発生などである。2100年に到達するずっと以前からこうした事態は進行し続ける。これに加えて生物多様性減少、海洋酸化、オゾン層減少、リンと窒素循環崩壊、淡水枯渇、化学汚染が不可逆的に進行している。
こうした各種パラメータは複雑系として相互に依存する関係である。どこかの時点で境界値を超えて破滅的に進行することが予想されている。これを回避する条件として2004年にメドウズが示したのが次の3つ。世界人口の2040年時点での75億人での安定化、工業生産を2000年度の20%に安定化、農業生産性向上による21世紀末人口最大80億人での生活維持。破滅に向かう時点とはいつなのか。2004年以降、15年が経過し、いずれの指数も改善していない。成長の限界を主張したメドウズのモデルを2008-2012年にオーストラリアの科学者グラハム・ターナーがリアルデータで検証、最新化した。それによると、メドウズのモデルである資源、食料、サービス業生産、工業生産、人口、汚染の各パラメータは2020年ころに境界値を迎え、2030年までに一気に崩壊に向かう。現在はちょうどその境界値超えの時点に差し掛かっている。
崩壊のプロセスについて1.金融 2.経済 3.政治 4.社会 5.文化の5段階あるとして、ロシアのエンジニア、ドミトリ・オルコフの研究がソ連とアメリカ崩壊をモデル化して有名になった。旧ソ連の崩壊は第3段階の政治崩壊でとどまった。オルコフは第6段階として生態系崩壊を追加、ここまで崩壊が進むと社会再生は困難としている。
災害時に助け合うというのは、全社会が崩壊していないからで、ハリケーンや台風被害の地域で見られる。また戦争でさえ第4段階である社会の崩壊は食い止められてきた。それでも、エネルギー問題と地球環境問題はそれらを遥かに凌駕する。一気に第6段階まで突き進む可能性、というよりほぼ必ず近未来に起きる事態であること、全人類はどのように受け止められるのか、これが現在私達が生きているこの地球である。本書内容はここまで。
本書を読み終えた読者は世界が崩壊にひんしていること強く認識するだろうが、その認識に見合う具体的行動を起こせるのだろうか。国連に行って演説をする、そういう立派な行動でさえ、どれだけの人たちを次の具体的行動に向かわせるのだろうか。”How dare you” 、多くの人達が記憶にとどめたセリフで今年の流行語大賞にノミネートされるだろうが、次の行動は、政策は、具体策は、進次郎大臣にだけ向けられた質問ではないだろうと感じる。その結果が、移民排斥や貿易戦争ではあまりに悲しい。