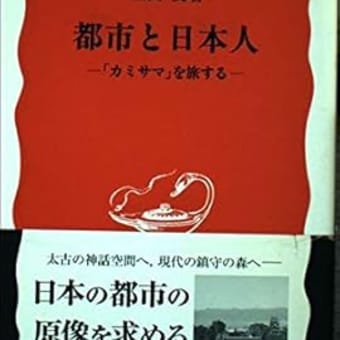2021年1月に亡くなった半藤一利のエッセイ集で、あとがきを書いたのがその前月だったとのこと。同様のエッセイ集の第二弾もだそうという計画があったと言うが、本書あとがきが絶筆、発刊は2021年3月。
本を読むことが学ぶことだった、という半藤さん。夏目漱石の晩年の漢詩「人間五十今過半 恥為読書誤一生」に行き当たり、読書の方法を誤ると一生も誤る、ということを学んだ。
いくつかに分類されたエッセイの中でも、昭和28年に銀座に本社があった文藝春秋社に就職し、その界隈で青春時代を過ごしていた頃の話題が面白い。昭和25年、大学生になっていた筆者の父が、がん闘病のため京橋にあったがん研究所に入院していた。手術をしたが余命幾ばくもないと執刀医に告げられる。父は真冬なのに「アイスクリームが食べたい」と落語のセリフのようなことを言う。それを聞いた母が言うには「銀座の富士アイス、資生堂、ライオンにならあるよ」。焼け跡だった銀座もその頃には復興し、都電が三系統走り、交差点では占領軍のMPに代わり日本のお巡りさんが交通整理をしていた。整理の腕前が素晴らしいので、外国人の二人連れが「ブラボー!」なんて褒めてくれている。二階建ての本建築の店舗が並ぶ銀座通りで、行き交うGIやPXになっていた服部時計店の横を通り過ぎて、やっとこさたどり着いた店で、京橋まで持って帰りたいというと「溶けちゃうよ」と断られる。事情を話し、なんとか持たせてもらったアイスを手に病院に走って帰った大学生の半藤一利は、アイスをうまそうに食べてくれた父を見て満足した。父は48歳、三日後に亡くなった。いい話。
昭和27年に文藝春秋の入社試験を受けた。三次試験まであり合格すると、西銀座五丁目にあった五階建て本社ビルの地下にあった文春サロンのレストランで6人の受験生が昼飯のご馳走にありついた。目の前に並べられたのは初めて食べる西洋料理。ナイフとフォークなどは使い慣れないので、お箸を頼んで、置かれたスープでライスを平らげてお代わりした。これで終わりかと思ったら、続いて別の皿が出てきたので、再びライスをぺろりと平らげお代わり。メインディッシュの肉料理まで5皿のライスを平らげたのを見た初老の紳士が呆れて「デザートでもライスを頼むのかね?」と聞いてくる。その老人が佐佐木茂索社長だった。このときから会社が麹町に移転するまでの13年間を銀座界隈で過ごした。このころは銀座1丁目から8丁目まであり、銀座西にも1-8丁目があった。昭和26年に木挽町が銀座東と改称されて、銀座24丁となり、現在では統合され銀座8丁となったのは昭和44年だそうだ。
仮採用時期で入社前の3月1日、会社に来ないかと言われ初出勤。することもなくヒマに過ごした数日後、編集長に「酒が飲めるやついるか」と呼ばれ「飲めます」と答えると桐生の坂口安吾先生から原稿を受け取る仕事を言いつかった。「今日は遅くなる」と家に連絡だけ入れて、桐生に向かうと先生は原稿の話なんか聞いていないという。それでも、せっかく来たんだからまあ泊まっていけ、と進められその日から1週間、酒を付き合いながら話を聞かされた。「信長」原稿をかきあげた直後だったという先生は、古代史から戦後日本の歴史話を滔々と話して聞かせてくれた。半藤青年にとっては値千金の一週間だったが、家の母は心配して会社に電話をしてきたという。電話に出た編集者は「ハンドウ?そんな社員はおりませんよ」と答えたという。しかしそれで気が付いた編集長、坂口先生宅にあわてて電話をしたきた。「おまえ1週間も泊まり込んで、なんで連絡してこないんだ! 雑誌はとうに出版されたんだぞ」。翌朝、先生の三千代夫人が40枚の原稿を渡してくれて、「これで半分、残りは明日の午後、東京に出るついでがあるから浅草駅で私がお渡しする」と言ってくれた。おかげでひとまず帰ることができたという。帰社した自分を見た編集長「なんか心配だなあ、将来が」と呆れた声を出した。のんびりした話である。