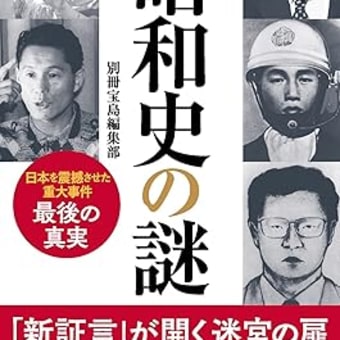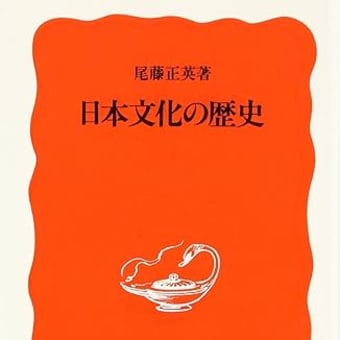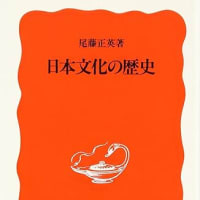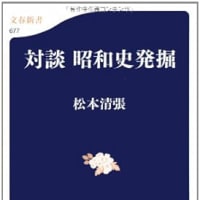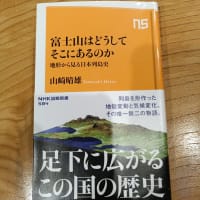世界各国の君主をどのように呼ぶのか、という一冊。日本では、天皇陛下、皇后陛下、皇太子、皇嗣、親王、内親王などというが、果たして外国の君主を日本語でなんと呼べば良いのかというお話。筆者は現イギリス連邦王国女王の息子で王位継承権のある人物を「チャールズ皇太子」と呼ぶことに疑問を投げかける。
7世紀初頭の遣隋使で「隋の皇帝を『天子』と呼び、自らも天子と表現したことに、隋皇帝は「冊封国から朝貢に来たものが、何!」と激怒した。使者の小野妹子は、皇帝から受け取った怒りの返信を無くしたことにするしかなかった。国としての名前も君主の呼び方も定まらず、法律も徴税も、歴史書も暦も年号も、通貨もない場所からの使者が、恥ずかしいことを言ってしまったこと、それは推古天皇や厩戸皇子でなくても分かったはず。大王推古が「返書を紛失した」という小野妹子の言い訳を許したのは当然であろう。その後、その恥辱は天智・天武天皇時代まで言い伝えられて、7世紀中盤からの律令制度設計、都制定、日本書紀編纂、大宝律令制定、和同開珎鋳造などにつながった。日本では、古代には国名さえ呼び名が定まらず、7世紀末になり天武朝時代から自国を日本と称し、それまでの「おおきみ」から「天皇(スメラミコト)」号を使い始めた。相手国の王様をなんと呼ぶかは重要だというお話。
中国では、いくつもの国に分かれていた諸侯が、何世紀もかかって秦と六国にまとまり、その後紀元前2世紀ころに漢王朝となって統一されたことで中華王朝と皇帝が誕生した。諸侯たちとの関係は言わば「国際関係」的な多元性があったわけだが、皇帝を頂点とする統一王朝に転化、実効的支配関係にまでも及ぶことで天子が君臨する天下国家にまで成長したと言える。
一方、西方にある地中海沿海地方では、当初は都市国家が併存していた。ローマがイタリアを制覇し、ポエニ戦争を戦うに及んで大きなブロックにまたがり、それらが対抗した内乱を経由して単一の帝国(インペリウム)に収斂した。その内容は、国際関係に見紛うほども多元性に富んではいたが、実効支配の外にまで包括している点では、漢王朝の天下とローマ帝国は軌を一にしていると言える。インペラトールを皇帝と訳すことは故なきことではなかった。中華王朝の天子は天命を受けて天下に命令を発出したが、ローマでは命令権(インペリウム)が及べば帝国(インペリウム)となる。それを統べるのがインペラトール、皇帝である。
中華王朝では、冊封関係にある諸侯に王の称号を授けるという、儒教的爵制秩序で帝国の関係を律していた。ローマでは各地のRexたちが使節を皇帝のいる場所に送り込み、皇帝は宮廷大礼服を授け、rexの公称を許した。中華王朝の皇帝と諸侯王の関係と相似形であり、rexが王と訳されることにも頷ける。
ローマ帝国は、その後東西に分立、ゴート族、ヴァンダル族などゲルマン系移民集団の統御に失敗し、rex授与ができない状態になる。東ではコンスタンティノープルの教会と一体化、ササン朝との死闘で疲弊した末に、イスラームの勃興に遭って大きな打撃を受ける。8世紀になると、ライン川を超えてきたフランク族は勢力をさらに拡大。カール大帝の勢威が届く版図にローマ教会の布教県を重ね合わせる形で西欧社会に移行する前の帝国の形が定まってくる。その後は3つに分かれ、仏、独、伊の原型となる。インペラトールの形を保っていたのはキリスト教のおかげであった。キリスト教のトップをローマ教皇と呼ぶことは示唆に富む。rexが王でありroi、公はdux=duc、伯はcomes=comteと訳されるのは、古代ローマ帝国の王、軍団長、地方総督に相当する。かたや、ゲルマン系・ノルマン系の君主はkingであり、語幹のkinは家系・血筋、自主的な称号である。
寒冷化が招いたともいわれる古代ローマ帝国の解体は、その後は温暖化に転じることで欧州中世は一定の安定を保っていたが、14世紀のペスト大流行が、キリスト教への不信を招く。結果として現れたのが宗教改革とルネッサンス。政治と経済にまたがる各種革命は内乱と戦争につながり、すでに多元的だった欧州は分裂した小国に分かれていった。大きく言えば、神聖ローマ皇帝の後継を自認するハプスブルグ家と、シャルルマーニュの後継を自認するフランス王の対抗軸に分かれ、欧州の国際政治は進むなかで、ローマと皇帝の跡目争いの中で、細分化された皇帝と王が量産された。ナポレオン時代の欧州は、自ら皇帝を称するナポレオンが支配する地域以外にも、多くの王国と帝国が存在し、皇帝はローマ時代の王に過ぎない存在であった。一方、ロシアでは君主はツァーリ、オスマンではシャー、ムスリムのリーダーはスルタン、と呼ばれる。
日本での天皇称号は、遣唐使が廃止された後、日本書紀に始まる六国史も途絶えて、10世紀の後村上天皇以降の諡号(死後の称号)は「院」、ミカド、禁裏、主上、上などと呼び名は並立する。天皇という呼び名は対中国に向けた見栄だったのか。実際、日本の人たちの中で、皇と王の違いをどれほど意識しているだろう。中国の史書「新唐書」日本伝では、日本が君主を「天皇」と号する、とは述べられているが、在位した日本の天皇は「王」と記している。冊封体制の関係で、中国皇帝と冊封関係にある国の王が「天皇」であるはずがないからであろう。日本からの使節も、皇と王に大きな違いを感じていないとすれば、「日本国王」と言う文書を受け取っても大きな違和感を感じなかった、劣位も感じなかったのかもしれない。足利義満が明朝から与えられた「日本国王」の称号を見て、国内的には太政大臣に登りつめた義満は、それを「王権奪取」と喜んだのだろうか。国内的には、その後、日本国王も五山僧が送ったという太上天皇称号も継続せず、征夷大将軍は「公方」、江戸時代には「公儀」とも呼ばれる。
対外的には、江戸時代の朝鮮王朝との関係の中で、対馬藩の宗氏が、征夷大将軍を「日本国王」と書き換えてしまう事件が勃発。都の朝廷を気遣う江戸幕府では、それを機に将軍の対外呼称を「大君」と統一、それは幕末まで継続してペリー来航を迎える。ペリーは日本の権力機構を「二重権力」と称し、日本には聖職的皇帝と世俗的皇帝が居ると解釈した。
水戸学が唱えた「尊王攘夷」だが、もとは儒学の尊王論であり、周の天子を「王」のモデルとしていたことから、元々「尊王」と書いた。「尊皇攘夷」であるはずだという議論は、皇国思想から始まり、中国の呼び名を「支那」と変えて、日本帝国、大日本帝国の天皇、という具合に変化、日米和親条約以降の日本は「大日本帝国」となる。しかし条約を結んだのは将軍、つまり大君である。「尊皇攘夷思想」はこうした一大矛盾解消のために必要なパラダイム変更だった。尊皇思想の高まりを受け、18世紀末に即位していた光格天皇は、1840年に崩ずるまでに呼び名を「院」から「天皇」に戻した。そして「大政委任論」が浮上、尊王攘夷運動と相まって「条約勅許問題」、大政奉還へと連なり、条約相手国が望む「二重主権」解消に繋がる。英国公使パークスは将軍慶喜との面会では"Your Majesty"ではなく"Your Highness"と呼びかけた。薩長勢力が最後まで慶喜の権力抹消にこだわったのは、英国の入れ知恵があったのかもしれない。
東アジアでは、中国も朝鮮も朝貢国と冊封体制を意識、日本との中間的位置づけとなる対馬、琉球は中国日本両国に朝貢した。江戸の大君は「日本国大君殿下」となるため、東アジア関係では欧米諸国のような「二重権力」は問題にならなかった。これが、その後の明治政府では天皇称号に「陛下」をつけることにより、東アジア諸国間の関係矛盾・対立につながる。中国でも朝鮮でも「陛下」をつけるのは中華皇帝でしかなく、日本国王はあくまで殿下のはずだからである。日本はこの違いに鈍感であった。維新政府は外国の条約締結国の君主は全部「皇帝」と称することに決めてしまう。イギリスでもイタリア、スウェーデンもすべて皇帝、となると、皇帝のCrown Princeは皇太子となるが、イギリス王国の皇太子、サウジアラビア王国の皇太子、という称号には大きな矛盾がある。英語で書簡を交わす相手なら大きな問題にならなくとも、漢字を解する中国、朝鮮との間では重大問題に発展、結果として日清戦争が勃発した。しかし、その問題はさらなる大矛盾をはらんだまま、外面的には日朝併合と1911年の辛亥革命で水面下に沈む。朝鮮王朝にとって見れば、それまでの隣国同士の有隣関係・対等関係が、天皇陛下と朝鮮王との関係に成り下がったのが日朝併合。日帝に対する怨嗟と呪詛を半島内にはらんだまま、朝鮮人民は終戦までの36年の時を過ごすことになる。
やがて世界を巻き込む第一次世界大戦では、結果として帝国を形成していたドイツ、オーストリア、オスマン、そして革命により戦線を離脱したロシアという「帝国」が体制変更することになる。新たに姿を表したのが、アメリカ合衆国とソビエト連邦、そして装いを新たにしようとし始めた大英帝国あらため英国連邦、つまり旧植民地が対等なコモンウェルス(連邦)であった。
第一次大戦後の平和交渉後、世界に存在していた明治時代の「帝国」はもはや日本だけになっている。中国に対する「21箇条の要求」は帝国主義的な侵略イメージが国際的に広がっていることを、日本の政治家たちはどれほど肌身に感じていただろうか。領土拡大を夢想していた軍人には、それは明治以来の夢を叶える快感と思えたのかもしれない。そんな大日本帝国をアメリカはいつか懲らしめてやる、と考えていたに違いない。そのほんの50年ほど前まで、外交のイロハも知らなかった国が領土拡大主義に染まっている姿は、アメリカの理想主義的正義による邪悪勢力討伐論に火をつけた。「リメンバー・パールハーバー」は起こるべくして起きた。そうした文脈で、戦後の日本占領政策を考えると、象徴天皇を認め、民主憲法を施行させたことは当然の流れである。米国にとっては第二次大戦も「帝国」を否定する戦いだった。
現代世界に残る帝国は存在しない。そうした中での上皇・上皇后・皇嗣称号問題があった。戦後も一時的に存続したイランのパウラヴィー朝の皇帝も1979年革命でパーレヴィ国王となった。しかし変わらなかったのが皇嗣の称号である皇太子。チャールズ皇太子、ムハンマド皇太子は妥当なのか。女性の場合、1980年に即位したオランダのベアトリックス女王が1963年に来日した際には、Crown Princessを皇太子とはせず内親王殿下と称した。象徴たる天皇とその継嗣をどのように表現するのか、世界情勢や各国対応をよく見て参考にすべきであろうが、象徴天皇という存在は日本にしかない。漢語で王の継嗣は王世子、王太子、国民的議論と合意が必要である。
奈良の石上神宮伝来の七支刀に書かれた銘文「百済王世子」、この読み方を日本の歴史家たちは知らなかったのは、嘆かわしい。それは日本に「王世子」がいなかったから。チャールズ皇太子という称号についても、同様の感想を持つ。本書内容は以上。
世界歴史の流れから日本を見るとどうなるか、「君主号」という切り口からこんなに話が展開できるとは予想外だった。思った以上に深く重い内容。読み応えがあった。天皇家・宮家・皇嗣問題に関心がある方にはおすすめの一冊。