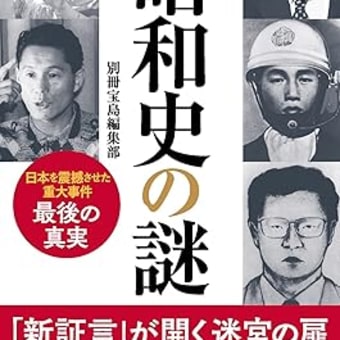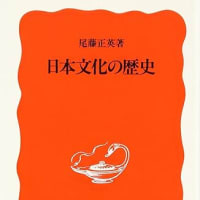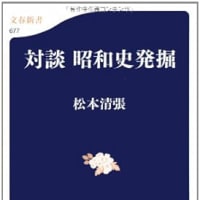都会的おすまし椎名誠風味・諧謔的23区都民のローカル差別付き分類ープチ昭和史付き by 泉麻人 昭和の最後63年の発刊である。ちょっとつまみ食いしてみよう。
港区、昭和22年に23区になったときに赤坂区、麻布区、芝区が合併して発生した区。白金や三田、高輪、芝公園、浜松町なども含まれる。当時の芝浦にはダルマ船が1000艘も浮かび水上生活者が暮らしていた。昭和30年代後半にはそうした水上生活者を主人公にしたドラマ「ポンポン大将」が桂小金治を主人公にNHKで放送された。六本木には外人が多いが、それは各国大使館が多いのと共に、終戦後、今の六本木ミッドタウン、前の防衛省があったところにあった赤坂第一連隊の跡地が接収され米軍本部であるハーディーバラックスがあったから。GHQのアメリカ兵たちを相手にしたバーやカフェーが立ち並んだ。そうした歓楽街では日本人バンドが集まり、遊び人グループが形成された。モータリゼーションの波が押し寄せる頃にはオープンカーを手に入れた遊び人たちが夜更けの六本木から夜明けの横浜や湘南を目指した。六本木キャンティー前の斜列駐車はこの頃始まって定着した。30年代から40年代のGSブームに乗って出現したゴーゴー喫茶はディスコとなり今の六本木に受け継がれている。
文京区は関東大震災前、山の手の中心街だった。江戸時代の大名屋敷跡が学校や六義園、小石川植物園、椿山荘などとなったため文京区と名付けられた。古い住宅地であり老人人口が多い。後楽園といえば東京ドームではなく、小石川後楽園庭園である。家光が作らせ光圀が完成した庭園である。その横にできた後楽園遊園地は古くから文京地区に暮らす老人にとっては鬱陶しい存在であり、古い京都人にとっての京都タワーのような存在。文京区自体が東京の中の京都的な存在であり渋谷や新宿は京都にとっての神戸や大阪のような存在とも言える。
世田谷区にある自由が丘駅は東横線開通当時は九品仏駅だった。しかしその2年後大井町線が開通、自由が丘駅よりも九品仏に近いところに駅ができたため、そちらを九品仏にすべきとの声から駅名が変更、自由ヶ丘学園が開校した時だったのでそれを駅名とした。三軒茶屋はかつてこのあたりに角屋、田中屋、信楽屋の三軒の追分茶屋があったことから名付けられた。厚木大山街道では青山以西で唯一の盛り場だった。昭和39年のオリンピックに伴い道路が拡幅、首都高が建設、玉電が撤去されて高層ビルが立つようになった。昭和52年4月には新玉川線が地下に開通して、玉電撤去以降不便だった三軒茶屋が再び渋谷と直通につながった。(これは僕も覚えている。市が尾から赤坂にあった会社まで通勤を始めたのが昭和52年4月1日、その日にはまだ自由ヶ丘を回って行ったのが、4月4日からは直通で行けるようになったのだ。)
練馬区は昭和22年に板橋区から独立した専業農家が目立つ地区だった。練馬といえば大根、現在の平和台、北町、春日町、田柄台地を中心に昭和30年代中頃までは盛んに大根が促成されていたが、その後石神井、大泉に移り今では姿を消してしまった。昭和60年になると光ヶ丘団地が形成されたが、ここは米軍駐留住宅地で、グラントハイツと呼ばれる場所だった。練馬ナンバーを嫌う住民がいるのも特徴的で、練馬はダサいと思っているのは、品川、多摩、足立と練馬に陸運局自動車検査場ができて昭和37年から各ナンバーの登録が始まってからである。大根を作っていた頃であり、練馬というナンバーから大根を連想、車という近代的な乗り物なのに「大根」を想像させることが許せなかったから。
この本には飲み屋では盛んに議論されるローカルなプチ差別が満載されている。中央区の明石町に住む古老たちは月島や勝どきの人間を心のなかで「ふん、新参者」と思っている。新宿区落合の高台に住む住民たちは山の手意識が強く、神田川沿いの住民たちが神田川が氾濫して水に浸かっていると「まあ、大変ねえあのあたりは低いから」とこちらは優越感に浸っている。文京区の古老はゲートボールに夢中な老人を見て、「遊び方を間違っている」などと揶揄し、国立劇場でやっている歌舞伎や文楽を見に行く老人を「芸能の楽しみ方がちょっと違う」などと蔑んでいるという。差別ネタ満載なのであるが、そんなに嫌味はない。東上線沿線の駅前には毒蝮三太夫や橘家圓蔵が来やすそうな街並みだ、などと指摘されるとそうだなと思ってしまう。コンパ芸を本にした、というような解説を書いているのは川本三郎であり。バブル真っ盛りの1988年に発刊された飲み会話題作り準備マニュアル本である。