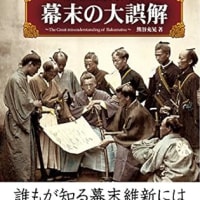ルワンダといえば、今でも内戦が続き、フツ族とツチ族に分かれての果てしない内戦が続く国、との報道を通してしか知らないアフリカの国であるが、その国が独立して間もないときに日本人がこのように重要な働きをして大統領をはじめ現地の人たちに大変な感謝をされていたこと、誇らしく思える程である。
ルワンダのような農業国は経済発展のために工場を建てっても仕方がない、農業自体を発展させて国民に自信を持ってもらうことが幸せにつながる、という考えから、特産品であったコーヒー栽培の効率化を図り、もうひとつの輸出品であった鉱山開発に力を入れた。そして、財政赤字解消のために為替制度の改革、適正為替レートの設定、二重為替レートの解消、商品の最低価格の見直し、外国人に有利だった税制改正などを矢継ぎ早におこなった。それらに手をつけるに先立って、外国人の識者に話を聞くのではなく、地元の人たちの本音とローカルな事情を調査することに専念した。ともすれば、インテリである外国人顧問や外国からのビジネスマンに状況を聞いたりするのであるが、かれらはどうしても既得権益を守ろうとする。地元の人たちはうまく説明できなくても、自分たちが何に困っているのか、どうしたいのか、なぜこうなっているのか、などの本当の実態を伝えてくれる。筆者はこうしたローカルな声を聞いて回った。この姿勢は地元の人の信頼を得ることにたいへんつながった。
ルワンダは第一次大戦前はドイツの植民地、それ以降はベルギーの信託統治があったため、ベルギー人が顧問として滞在し、学校教育はフランス語、貨幣はフランであった。コーヒーを増産しても世界の需要は低迷しており、積み出し港までは海のないルワンダからは輸送賃がかさみ有利ではなかった。そしてそれがルワンダ人のためになるように、ルワンダ会社法の改正、ルワンダ人による経営のために経営者はルワンダに常駐する義務があることなどを決めた。
また商品の最低価格設定では、ルワンダ人がビールを好んで飲み、悪いケースではそれにより家計が破綻するような場合もあることを考慮して、一般的な日常生活に必要な商品価格を25-40フランに設定し、ビールの価格を35フランとした。こうすることにより、日常必要品よりも少し高めのビールを買う前に必需品を買い、余裕が出てきた人はビールを飲める、というシナリオを考えたのである。おなじような考え方で、1年間一生懸命働いたら家を一軒立てられるような材料価格設定を意図した。これによりせっかく稼いだお金を飲んでしまわず、貯蓄すれば家も建てられると思えるようにしたというのである。
筆者によれば、途上国に一番乏しい資源は「能力ある人」であると。そして発展を阻むのも人であり、発展を進めるのもやはり人であると。ここで、重要なことを指摘している、それは言語の問題。小中学校の教科書さえ現地語ではなくフランス語のものしかなく、高等教育はすべてフランス語か英語、高等教育を受ける若者は留学し、一般のルワンダ人とのあいだに超え難いエリート意識を植えつけられて成人するという。つまり教育に力を入れても、母国語による教育が広められなければルワンダのために働く知識人は生まれてこないというのである。日本が明治の時代になぜ成長できたか、日本語への翻訳を一生懸命行い、すべての高等教育を日本語で行ったことに思いを飛ばした。日本語しか話せない、グローバル化に遅れる、という議論があるが、国家拡大時には文明の日本語化は有効であったはずである。単なる技術援助はプラスにはならないし、方針なき援助はかえって害をなす、というのが筆者の主張である。
今は内戦であれるルワンダの独立直後のお話ではあるが、国が独立して発展をする夜明け前のようなその地点に立てたこと、そしてその一翼を担えたことは大いに価値のあることであり、満足もできただろうと思える。筆者の貢献がなんとか今のルワンダにも残っていれば、その考え方を継承する人材が残っていればと祈りたい気がする。