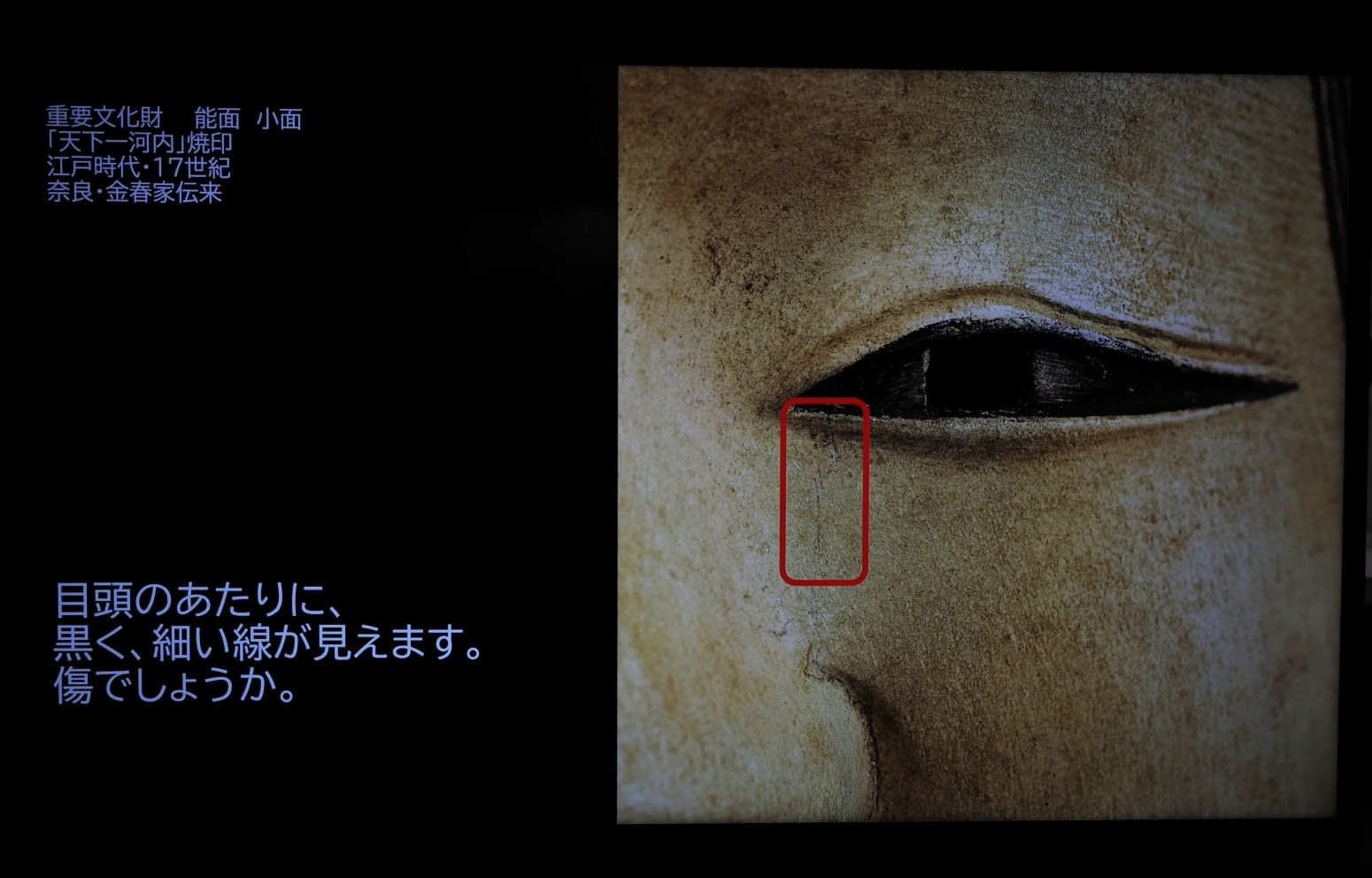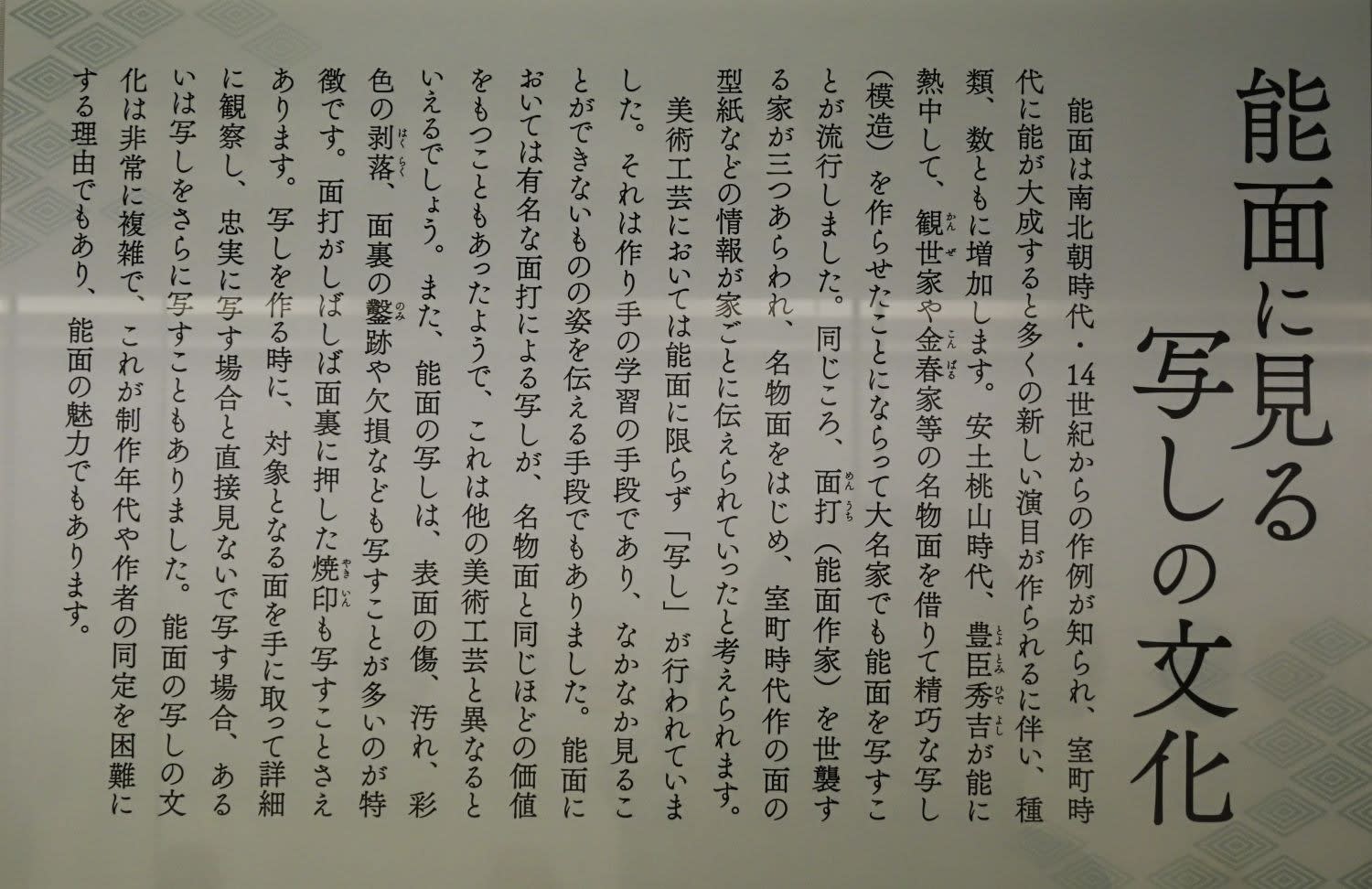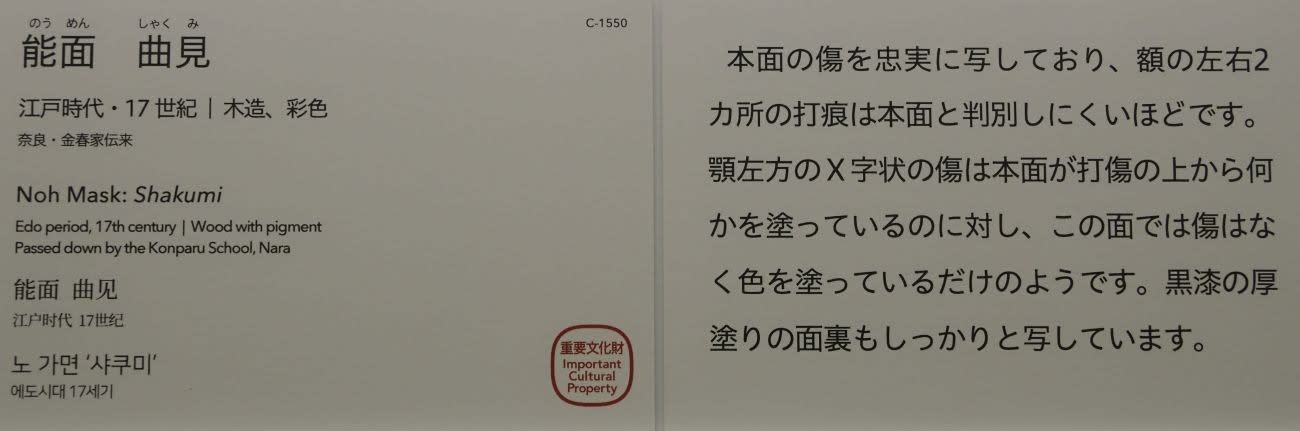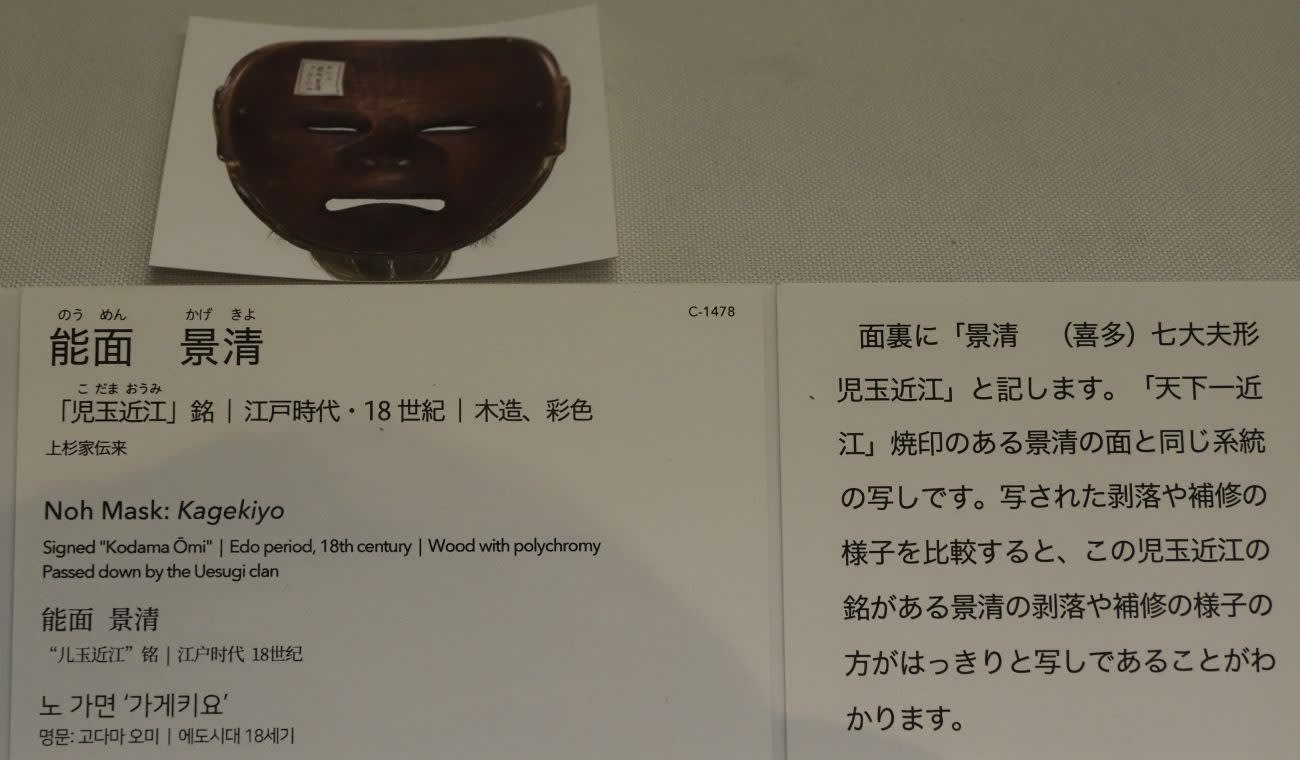盆栽苑を、入り口側から撮影。

上の写真の中央部の土壁を背景に、可愛い白梅。

和室床の間の盆栽。


盆栽に水やり光景を初めて撮影。
銅製のじょうろで、盆栽専用でデカい。 (じょうろが隠れて見えませんが)
蓮口から、細い水流で水やりされていますが、この直前まで、シャワ-でした。

推定寿命90年の長寿梅。 枝先から。小さな新芽が。

ヒナソウが可憐。 風格ある盆器と、意外に合う。
推定樹齢50年と、盆栽では若造ですが、鉢などのデザインと相まって、凛とした風格。



クリスマスローズ(ニガー)

オモト(万年青)は、江戸時代から栽培の歴史がある(幾たびか、ブームもあった)
葉の状態や葉姿、柄などの特徴を”芸”というようだ。
この盆栽だと、葉の形が
熨斗葉(のしば):葉が熨斗を折ったような折れ方をするもの。
剣葉(けんば):角とも。棒状に先の尖ったもの
の二つの芸が見える。 キャプションがなかったので、私の推定です。
鉢と調和して、美しい。

いつ見ても、名品と思う、蝦夷松。


以上、早春の昭和記念公園から、植物の息吹きをお届けしました。