歴史館の2F(江戸時代)から、1Fの明治以降の展示に。
明治の初期は、コレラが流行した。 これが近代水道のきっかけとなった。

新宿の淀橋に大規模な浄水場が建設された。 下の図で、左上のオレンジ色が淀橋浄水場、中央上部が、本郷給水所(この歴史館がその位置)、左下が芝給水所。

淀橋浄水場は、廃止となり、現在は西新宿の高層ビル群となっています。

高層ビル群 右の道路のように見えるのは、新宿駅と線路。

右端は蛇体鉄柱式共用栓で、後の水道の蛇口の語源となった。 黄色は消火栓。

馬水槽。 明治36年(1906年)にロンドン市牛馬給水槽協会から寄贈されたもの。

うしろは、人用か。

当時の東京府庁舎横の馬水槽。 下部には犬猫用の水槽も。





















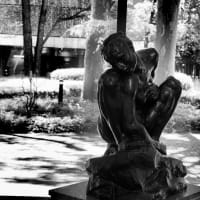
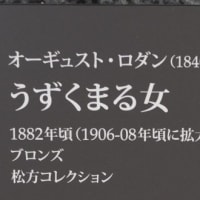






その頃中野にいましたのでした。^±^
十二社(じゅうにそう)には大きな池があった記憶が。
コレラはコロリって言ってたんですよね。^±^
返信が遅れてすみませんでした。
十二社(じゅうにそう)は初めて聞く
地名で、Webで調べると、淀橋浄水
場のすぐ近くにあった熊野神社関係の
地名なんですね。角筈熊野十二社とし
て広重の名所江戸百景の絵にもなって
いますね。 池も昭和43年に残念な
がら埋め立てられたようです。