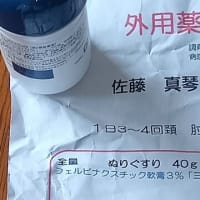最近読んだ「筆跡鑑定ハンドブック」魚住和晃著から紹介します。
神戸に老人医療の実績で評判の医師花房先生に、筆者の父親がパーキンソン病が原因か身のこなしが不自由になったので診ていただいた時、先生から、蚊取り線香のように鉛筆でくるくると渦巻きを書いてくださいと言われた。
その結果まだ大丈夫で、もし、病気が進んでいると円がゆがみ、等間隔に渦巻きを描くことが困難になり、線質も震えがちになる、もしくは円が小さくしか描けなくなるとのこと。 この花房先生の方法は、長年の経験とアイディアから生み出されたものであろうが、この発想法を筆跡に応用することで、筆跡鑑定の医療への効用が見出されてくる。
筆跡を見ることによって外見ではわからない患者の体調を認識いえるとすれば、それだけでも医療への応用ができるであろう。 漢字にしても平仮名にしても、字形は直線と曲線の組み合わせでできている。これを運筆の働きからみた言葉にすると直線は「直勢」、曲線は「曲勢」という。渦巻きは曲勢のうち円勢ばかりを続けて運筆するもので、きれいに描こうとすればなめらかに鉛筆を動かし、かつ間隔をそろえようという意識が働く。
ここに文字を書くこととの共通点がある。渦巻きを書かせることは文字を書く運動のうちの、円勢の機能を集中的に見ているのである。 障害が起きてくると渦巻きが大きく書けなくなるというのは、筆跡の視野性に関連することが考えられる。
たとえば葉書や封筒に宛名を書く場合、始めにどの大きさで、どの位置に書くのが適当であるかを考える。近頃はマンション住まいの人が多いからその分だけ宛名の行数増えて、うつかりすると入りきらなかったり、ずいぶん不恰好になって大弱りすることがある。 あらかじめレイアウトのことまで考えて書くはずもない無頓着な人でも、その人なりに書き方は一貫しているもので、それが筆跡の視野性ある。
障害の生じることによってっこの感覚が失われてしまったり、そうした意識が働かなくなって、通常の自己筆跡から乖離してしまうのである。私は今でも年賀状は手書きにこだわり、宛名はワープロだが、近況や、挨拶を毛筆か万年筆で書いている。いただく賀状の中で従来のびのびとした字を書かれた方が、字が小さくなり、小刻みな振るえをおびてきたときに、ハットすることがある。闊達であった筆跡の視野性が、障害に発生によって阻害されているのである。
この方がワープロで印刷されて賀状をお送りくださった場合、私はその異変に気づくずべはない。 花渕先生の方法は科学的というよりは経験的・職人的であるが、患者に精神的にも体力的にも負担をかけず、即時におおよその状況を把握する効果的な方法である。 筆跡から身体の異変を診るのとは逆に、筆跡を元の状態に回復することも医療につながる。近年は音楽療法の効果が話題になってきているが、書道療法も当然ながら開発されなければならない。
筆跡は手によって書かれるものだが、それを動かす命令系統は中枢神経にある。中枢機能が回復しなくては筆跡を回復できないことからすれば、もし筆跡を回復すれば中枢機能も回復したという逆の倫理がなり立つであろう。 つまりリハビリテーションにおける習字や書道は、筋肉的な運動機能の回復にとどまらない、中枢神経の機能回復に有効な分野としての可能性をもっている。 ここで求められるのは、すぐれた書家という意味ではなく、あくまでも医療の立場に立った筆跡の専門家である。