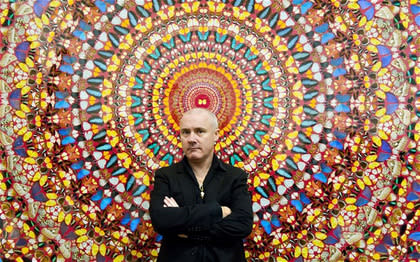Beata Beatrix
Dante Gabriel Rossetti
テート・ブリテンで開催中の、「ラファエル前派展」、終わる間際(13日で終了)に行ってきました。いやーーーー、すっごい混みようでした。人疲れしそうだから、さら~っと流して見よう、と思っていたけど、見始めると真剣に見てしまい、3時ごろに入って、結局出たのは5時半閉館ぎりぎり。「歴史」「自然」「美」などのテーマに部屋が分かれていましたが、「宗教」の部屋が結構面白かった。ラファエル前派って、上の絵のような美人画が人気で良く知られているけれど、宗教を題材にした絵も結構描いていたんですね。

Mariana
John Everett Millais
腰掛けの朱色とドレスの紺色の対比が効果的でキレイ。美しい背景と、美しい女性を題材に「あーー、根つめて刺繍してたら、疲れたーー、腰痛い~」なリアリズムが盛り込まれているところがイイですね。画面のど真ん中に縦に人物を据えて画面を右と左に分けちゃうのって、かなり斬新な構図なんじゃないかと思うけど、ぎくしゃくしないでうまくまとまっている。
絵とは関係無いけど面白い! と思ったのは、この絵のプロブナンス(来歴)。テートが1999年から管理してる絵なのですが、「イギリス政府に、税金の代りに収められたものを、政府がテート・ギャラリーに振り分けた」、となっていました。へえー、政府って、税金、物納でも可なんだー。...ていうか、「借金(税金)のカタに、これはもらっておく」って感じー? これを元々持ってた所有者、こういう資産はあるけど現金が無い状態の、貴族の末裔か何かだったのかなー、なんて想像が膨らんでしまった。「えええぇ、お代官様、それだけはご勘弁をーーー」なんちて。

Valentine Rescuing Sylvia from Proteus
William Holman Hunt
シェークスピアの初期の喜劇「ヴェロナの二紳士」を題材にした絵。シルヴィア(中央で膝をついている女性)に狼藉をはたらこうとしていたプロテウス(右)を、彼の親友、バレンタインが止めに入ったところ。左側に立っているお小姓姿に身をやつした女性は、プロテウスが故郷で付き合っていたジュリア。恨めしそうにプロテウスを見つめながらも、彼にもらった指輪を背中側でいじっています。
ラファエル前派って、色鮮やかで衣裳はコスプレ的にド派手で、ドラマチックな絵画が企画・演出されているところが見ごたえがあります。ベルベットやゴブラン織りなど、厚みのあるゴージャスな布のテクスチャーの表現も優れていて、触ったら本当に布の感触があるんじゃないかと錯覚してしまう。人物の表情もリアルで、私の頭の中では勝手に登場人物がセリフをしゃべり始めてしまいます。「いてっ。いってえなぁー。バレンタイン、そんな本気で殴んなくったっていいじゃんかよぅー、ちょっとふざけただけなんだから。」えーと、実際は良家のお坊ちゃんなので、こんなしゃべり方はしないと思います。ところでこのプロテウス、結構イケメン君だよね。

The Man of Sorrows
William Dyce
宗教ネタ、行きます。荒野で瞑想するイエス。でも背景は砂漠ではなく、スコットランド。下の絵画では、背景をスペインのアルハンブラ宮殿にしちゃったり、宗教画なんだけど、各作家の美意識に従って結構好き勝手にやってるところが面白い。

The Finding of the Savior in the Temple
W H Hunt
「過ぎ越しの祭り」で親子三人、エルサレムに出向いた帰りにイエスが迷子になっちゃった時の絵です。というより、イエスは勝手に一人でエルサレムに残って当地の知識人達と寺で議論を戦わせていたのですが、てっきりイエスは自分達と一緒に着いてきて居るとばかり思っていたマリアとヨゼフ、途中でイエスが居ないのに気付いて3日間探し回ってやっと見つけた、という話。マリア様の、「んもうーっんもうー、この子はーーっ。三日も探したのよ、心配したのよーー」っていう表情がよくでてる。これに対して、「...ていうか、僕が父さん(神)の家にいるの、当然じゃない。どうしてもっと早く迎えに来ないワケ?」っていう表情のイエス。あ、このセリフは今日本で人気の漫画、「聖おにいさん」から拝借しました。イエス、確かにそういう顔してる。周りの知識人達は、アラブ系の濃ゆい顔に描かれているのに対して、イエスとマリア様は妙に西洋寄りな顔っていうところも面白い。紫やマジェンタやビリディアンといった鮮やかな色がポイント的に使われていて画面がキリッと引き締まっています。

Christ in the House of Parents
J E Millais
マリア様とイエスが、お父さんのヨゼフの大工仕事の工房に居る日常生活を描いた絵画。イエスが仕事を手伝っていて、手に怪我してしまったところをマリア様が慰めているところ。「ママ~、お手てに釘が刺さっちゃったのー。痛いよー」っていう、ちょっと情けない顔のイエス。上の絵の小ざかしい顔のイエスとは随分違う。大工のヨゼフ父さんは思いやり深そう。後にイエスが十字架に架けられるのを暗示する絵ですが、血が一滴、足の、楔が打ち込まれることになる場所にも滴っているところがまた芸が細かい(この画像では小さくて見えないけど)。

The Shadow of Death
William Holman Hunt
もう少し成長したイエス。ヨゼフ父さんの工房で大工仕事の後、大きく伸びをしたら、その影が後ろの大工道具をかけてある木の板に、まるで十字架に架けられているかのように映って「なな、何て不吉な!」と、マリア様が慌てふためいている様子を描いたもの。...しかしこのストレッチの仕方、ポーズにムリがあるよねー。こんな中途半端な伸ばし方じゃぁ、肩の疲れは取れないぞー。ところでこういう感じの、ちょっとヒッピー(死語)っぽい、純真な目をした若者って、イギリスに結構いるよね。
あとこの絵は、マリア様の着ている服の表現が素晴らしい。太い麻の糸で織られた目の粗い麻布を藍で染めました、っていうごわごわした感じが、すーっごくリアルに描かれているのです。おぉ、なんてエスニックでおしゃれなのかしら。これはウィリアム・ハントが、実際にナザレ、ベツレヘム、エルサレムを訪れて、当地で描いたものとかで、現地の人が着ているものを観察して描いた模様。しかし向かって右のノコギリ、今の時代でも使えそうなピッカピカで立派なものだけど、この時代にこんなにキレの良さそうなのこぎりが、果たしてあったのか? (細かいことにウルサイ)。

The Light of the World
W H Hunt
ヨハネの黙示録3‐20の、「私が扉をノックする音を聞き、戸を開けるなら、私は中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう」で、イエスが人類の魂を救う光を携えて、ドアをノックする、の図。キリストの訪問はありがたいですが...しかしバックライトで顔を照らすの、やめてくださいね、怖いから。...と、つい頭の中で突っ込みを入れてしまう私でした。イエスの持っているランタン、とても装飾的で、うちにも一個欲しいです。これで魂が救われるっていうのなら、なおさら欲しいです。

Chill October
J E Millais
最後はちょっと地味なんですが、荒涼としたスコットランドの10月を描いた何の変哲もない風景画...なんだけど、なんか、妙にひきつけられます。空気が湿っていて、寒々とした天候が肌で感じられるようなグレー・トーンなのにも関わらず、画面は何だか光っているよう。手前の立ち枯れた草は、綿密に描き込まれていて、雑草なのに主役級の扱い。不思議な魅力のある絵です。これは個人蔵なので(持ち主は、Lloyd Webber卿)、また見る機会は無いんだろうな、っていうのが残念。