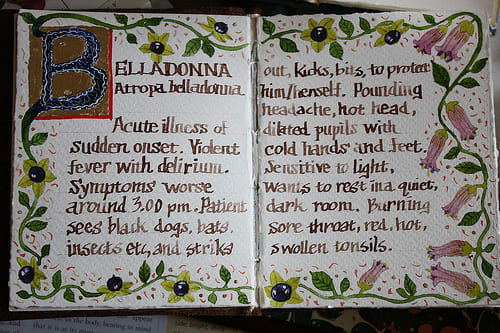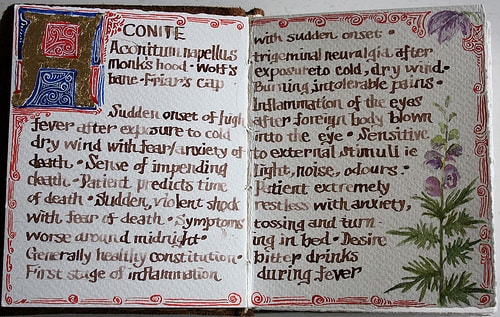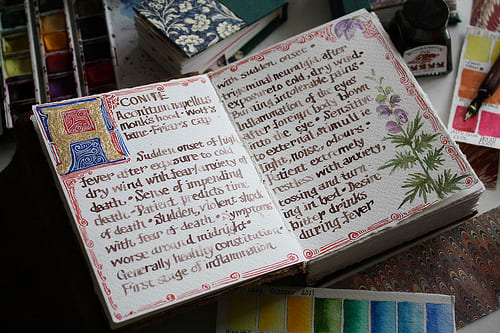装飾アルファベットのCは、端っこをしゃわしゃわー、っとゴージャスな感じに飾って遊んでみました。題材にしたハーブはCrataegus、一般名はHawthornで、日本だとサンザシにあたります。この実を果実酒にして毎日少しだけ飲むと、心臓の滋養強壮にとても良くて、血圧やコレステロール値を下げる効果もあります。毒性や中毒性も無いので、毎日長期間飲んでも大丈夫。私が通ったホメオパシーの学校の先生は、「誰でも50歳を過ぎたら、これを飲むべし!」と言っていました。
何でも昔、アイルランドのお医者さんで、「あの医者にかかるとどんな心臓病でもたちまち治してくれる」と評判の高い医者がいたそうです。そのお医者さんが使っていたのは、実はどこの生垣にも見られる、このHawthornだったとか。そのおかげで、そのお医者さん、相当の財を成したそうです。彼の死後、自分の父が、普通に生えている植物で暴利を貪るのをみかねていたのか、娘さんがその秘密を世の中に知らせたそうな。

これは途中経過の様子。箔を下書きの上に置いたところ。

ページ全体の完成図。Cの内側には、サンザシの花を描き、文章の回りはサンザシの実で飾りました。右下に居るのはBullfinchという鳥(辞書で調べたら、日本語では「ウソ」という名だそうな...初めて聞いたわ、そんな鳥の名)。Bullfinchって、実物はもっとぷっくり丸い形をしているんだけど、なんだか妙にスリムなBullfinchになってしまった。