『和泉式部日記』(ソフィア文庫)の注訳で
これまでとちょっと趣の異なる解釈を取り入れた
和歌文学の研究者近藤みゆきと
お能の解説などでテレビでもお見かけする水原紫苑
の講演会を聴きに行きました。
恋多き天才的な歌人、和泉式部はそういうイメージでとらえられる。
当時からも道長が「浮かれ女(め)」と評したように、
通い婚の自由恋愛、であっても、かなり自由奔放な女性、
しかし、その歌の才能がすべてを浄化して歌の歴史に名を残してきた、
そんなイメージですよね。
ところが、和泉式部の歌にふれて、目からウロコ、でした。
冥(くら)きより冥き道にぞ入りぬべき
はるかに照らせ山のはの月
デビュー作の歌、和泉式部25歳ぐらい、
多情な恋のなかで、罪深い我が身、仏に救済を求めて、ということですが、
ドロドロしたなかに、なにかそこを突き抜ける、透明感があります。
冥き道を彼方まで照らす山の端の煌めく月、
その後の人生を予知していたかのように、孤独です。
愛した人をことごとく失い、期待していた子にも先立たれ、
再婚した夫にも捨てられる運命、
歌を後世に残すためにのみ、そのような人生を与えられたかのように…。
白露も夢もこの世もまぼろしも
たとへていへば 久しかりけり
なにに例えて久しいといっているのでしょうね、
本歌のように移り気な恋心、に収まりきれないような、和泉式部の境地ではないでしょうか。
ものおもへば沢の蛍も我が身より
あくがれ出づるたま(玉OR魂)かとぞみる
謡曲「葵上」にも取り入れられているそうで、源氏物語からではなく、
六条御息所の生霊をこのように表現した世阿弥は、この歌がわかっていた!、
のだそうです。これって、すごいことです。観客にとって、
六条御息所の生霊は世阿弥を離れ、能面般若、として定着していったのですから。
ちなみにこの歌は50歳ごろの作で、
二番目の夫に忘れ置かれて貴船寺を訪れ、禊ぎをした御手洗川にとぶ蛍をうたった、とある。
百人一首で有名な(わたしはこれしか暗唱できませんでした)、最晩年のうた
あらざらんこの世のほかの思ひいでに
今ひとたびの逢ふこともがな
不思議ですね、1000年前に生き切った一人の女性の肉声が時間を越え、
直接いまを生きる私たちに聞こえてくるようです。
身を分けて涙の川のながるれば
こなたかなたの岸とこそなれ
こういう歌をどうとらえるのでしょうか、
水原さんは、“身体が宇宙となり、彼岸と此岸(しがん)の真ん中にいる”
そういう宇宙とむすびついた我に目覚めている、
和泉式部はこころそのものをうたって、孤独をみつめ宇宙を背負う、
ひとり個としてそびえたつ、そういう歌人であった、と評しています。
紫式部もそれを直感していた、日記に残した評価はちょっとしたやっかみね。
ところで、帥宮に迎え入れられて宮廷入りした和泉式部、
愛があれば身分の差なんて、などという甘いものではないのですね。
受領階級の身分では妻(サイ)はもちろん、妾(ショウ)とも愛人とも認知されない。
あくまで身分は使用人の女房、お手つきの“召人(めしうど)”なのです。
男女の仲では歌の水準に見合って対等に見えても、
たとえ日に3.4回も訪れがあっても、子をなしても(幼くして出家)、です。
ですから、同じく受領階級の紫式部の“もの思い””憂し、浮し身の哀しみ”と共通するのです。
正妻に勝利して独占してもこの“もの思い”からは抜けることができない、
誇り高き歌人は、
帥宮の死とともに宮中を追われ、日記文学を残すことになるわけですね。
(2009/06/05 よみうりホール)
これまでとちょっと趣の異なる解釈を取り入れた
和歌文学の研究者近藤みゆきと
お能の解説などでテレビでもお見かけする水原紫苑
の講演会を聴きに行きました。
恋多き天才的な歌人、和泉式部はそういうイメージでとらえられる。
当時からも道長が「浮かれ女(め)」と評したように、
通い婚の自由恋愛、であっても、かなり自由奔放な女性、
しかし、その歌の才能がすべてを浄化して歌の歴史に名を残してきた、
そんなイメージですよね。
ところが、和泉式部の歌にふれて、目からウロコ、でした。
冥(くら)きより冥き道にぞ入りぬべき
はるかに照らせ山のはの月
デビュー作の歌、和泉式部25歳ぐらい、
多情な恋のなかで、罪深い我が身、仏に救済を求めて、ということですが、
ドロドロしたなかに、なにかそこを突き抜ける、透明感があります。
冥き道を彼方まで照らす山の端の煌めく月、
その後の人生を予知していたかのように、孤独です。
愛した人をことごとく失い、期待していた子にも先立たれ、
再婚した夫にも捨てられる運命、
歌を後世に残すためにのみ、そのような人生を与えられたかのように…。
白露も夢もこの世もまぼろしも
たとへていへば 久しかりけり
なにに例えて久しいといっているのでしょうね、
本歌のように移り気な恋心、に収まりきれないような、和泉式部の境地ではないでしょうか。
ものおもへば沢の蛍も我が身より
あくがれ出づるたま(玉OR魂)かとぞみる
謡曲「葵上」にも取り入れられているそうで、源氏物語からではなく、
六条御息所の生霊をこのように表現した世阿弥は、この歌がわかっていた!、
のだそうです。これって、すごいことです。観客にとって、
六条御息所の生霊は世阿弥を離れ、能面般若、として定着していったのですから。
ちなみにこの歌は50歳ごろの作で、
二番目の夫に忘れ置かれて貴船寺を訪れ、禊ぎをした御手洗川にとぶ蛍をうたった、とある。
百人一首で有名な(わたしはこれしか暗唱できませんでした)、最晩年のうた
あらざらんこの世のほかの思ひいでに
今ひとたびの逢ふこともがな
不思議ですね、1000年前に生き切った一人の女性の肉声が時間を越え、
直接いまを生きる私たちに聞こえてくるようです。
身を分けて涙の川のながるれば
こなたかなたの岸とこそなれ
こういう歌をどうとらえるのでしょうか、
水原さんは、“身体が宇宙となり、彼岸と此岸(しがん)の真ん中にいる”
そういう宇宙とむすびついた我に目覚めている、
和泉式部はこころそのものをうたって、孤独をみつめ宇宙を背負う、
ひとり個としてそびえたつ、そういう歌人であった、と評しています。
紫式部もそれを直感していた、日記に残した評価はちょっとしたやっかみね。
ところで、帥宮に迎え入れられて宮廷入りした和泉式部、
愛があれば身分の差なんて、などという甘いものではないのですね。
受領階級の身分では妻(サイ)はもちろん、妾(ショウ)とも愛人とも認知されない。
あくまで身分は使用人の女房、お手つきの“召人(めしうど)”なのです。
男女の仲では歌の水準に見合って対等に見えても、
たとえ日に3.4回も訪れがあっても、子をなしても(幼くして出家)、です。
ですから、同じく受領階級の紫式部の“もの思い””憂し、浮し身の哀しみ”と共通するのです。
正妻に勝利して独占してもこの“もの思い”からは抜けることができない、
誇り高き歌人は、
帥宮の死とともに宮中を追われ、日記文学を残すことになるわけですね。
(2009/06/05 よみうりホール)












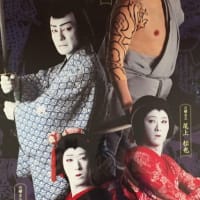



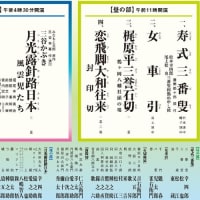

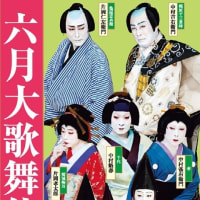








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます