「日本人の叡智」という本があります。著者は磯田道史。
のちに「無私の日本人」(2012刊)で、歴史に埋もれた優れた先達を発掘した。
それに先立ち、2011.3.11の震災直後に出版し、
美しい日本の自然に調和した、
先人たちが残した数々のことばを収集したもの。
一人見開き2pで戦国期慶長から平成まで98人のことばが紹介されている。
序文に述べられている、著書のそのいきさつが面白い。
古文書にくぎ付けになり、没頭するあまり図書館で倒れ救急車で運ばれたことがある、
そうで、
もうこうなると、先人たちが、そのことばが、世に出たくて彼を押し倒した、
とでもいわざるをえない。
江戸中期の17C 朱子学を極めた学者のことば
学問の道さまざまありといえども
畢竟は、心をみがくことにとどまれり
無私の日本人でも紹介された、中根東里
出る月を待つべし
散る花を追うことなかれ
(桜は散っても、月は必ず出てくる。それを待つ時間をどのように大切に生きるか)
それが問われているのですね。
学問の真髄は情緒 、という岡潔の言葉もある。
また、名人といわれる人のことばも味わい深い。
自己訓練から始まり、自力で発足させたものが習慣となり、
その積み重ねが大きな成果となる、
という松田権六、
自己を成長させるには繰り返し自己の限界に挑戦せよ
新しい力がわく
と大錦。
それらを一言でいえば、日本人固有の、しかも人としての
“叡智”
というべきなのですね。
ただ哀しいかな、
美しい日本の自然との調和、というモチーフ、
震災での原発のベルトダウンで喪失してしまった、
その伝統的な価値観がどういう変貌をしていくのでしょうか。
さて、最後に日本人の叡智について、わたしは、思います、
磯田氏は、それを歴史上の人物、すなわちその痕跡である書物に求めたわけですが、
連綿とつづく、市井の人々の到達した境地、
たとえば、病院の片隅で病床に伏し病院のスタッフに、ただ感謝の言葉を残して静かに逝く、孤独な老女のたどり着いた境地、について同じように、
人間の叡智、荘厳さ、を思います。
のちに「無私の日本人」(2012刊)で、歴史に埋もれた優れた先達を発掘した。
それに先立ち、2011.3.11の震災直後に出版し、
美しい日本の自然に調和した、
先人たちが残した数々のことばを収集したもの。
一人見開き2pで戦国期慶長から平成まで98人のことばが紹介されている。
序文に述べられている、著書のそのいきさつが面白い。
古文書にくぎ付けになり、没頭するあまり図書館で倒れ救急車で運ばれたことがある、
そうで、
もうこうなると、先人たちが、そのことばが、世に出たくて彼を押し倒した、
とでもいわざるをえない。
江戸中期の17C 朱子学を極めた学者のことば
学問の道さまざまありといえども
畢竟は、心をみがくことにとどまれり
無私の日本人でも紹介された、中根東里
出る月を待つべし
散る花を追うことなかれ
(桜は散っても、月は必ず出てくる。それを待つ時間をどのように大切に生きるか)
それが問われているのですね。
学問の真髄は情緒 、という岡潔の言葉もある。
また、名人といわれる人のことばも味わい深い。
自己訓練から始まり、自力で発足させたものが習慣となり、
その積み重ねが大きな成果となる、
という松田権六、
自己を成長させるには繰り返し自己の限界に挑戦せよ
新しい力がわく
と大錦。
それらを一言でいえば、日本人固有の、しかも人としての
“叡智”
というべきなのですね。
ただ哀しいかな、
美しい日本の自然との調和、というモチーフ、
震災での原発のベルトダウンで喪失してしまった、
その伝統的な価値観がどういう変貌をしていくのでしょうか。
さて、最後に日本人の叡智について、わたしは、思います、
磯田氏は、それを歴史上の人物、すなわちその痕跡である書物に求めたわけですが、
連綿とつづく、市井の人々の到達した境地、
たとえば、病院の片隅で病床に伏し病院のスタッフに、ただ感謝の言葉を残して静かに逝く、孤独な老女のたどり着いた境地、について同じように、
人間の叡智、荘厳さ、を思います。












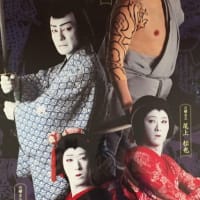



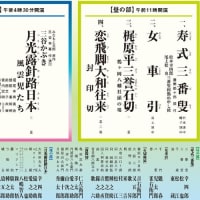

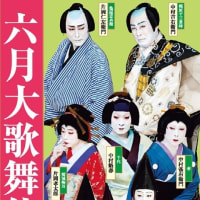








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます