───僕は、死なないよ。死んでたまるものか。
窓の外には海。よく晴れて、海面がきらきらと輝いている。
前にこの部屋に泊まってから、もう30年以上経つのだろうか。部屋は多少古びた印象がある程度で、どこも変わらなく見えた。もっとも、あの時は年末で、窓の外はどんよりとした分厚い雲と荒れた海、波に舞う雪、おまけに窓の下は銀世界。それに対して初夏の海は穏やかで気持ちいい。
窓を開けると、爽やかな風が潮の香りを運んできた。
こんな季節にここへ来たなら、死のうと思って来たこともふわりと風に流されて忘れてしまうのではないだろうか。
前にここへ来た時、倖人は死ぬつもりだった。
さして、どうしても死にたくなるような追い詰められた状況でもなかったと今なら思う。何故死のうなどと思っていたかももう思い出せないくらいだ。死ななくて本当に良かった、と思う。
それを思いとどまったのは、あの少年と出会ったおかげだ。
彼は、僕よりもずっと思いつめた瞳をしていた───
目を閉じると、まるで今目の前で見ていたかのようにあの少年の面影を思い浮かべることが出来る。それを確認して目を開け、倖人は窓際の椅子から離れて座敷に無造作に置いていた小さな手荷物を開き、中から一冊の本を取り出した。
ハードカバーの古い本。
この本を出した担当は倖人である。
倖人が編集者として初めて手がけた本だが、たいして売れはしなかった。
この本がどうやればある程度売れるのかを今の倖人は知っている。いや、当時でもそうすれば売れるだろうことは考えたし、実際上の人間はそうしろと指示した。けれどあの頃の自分は若かったのだ。
この作品を、ただお涙頂戴で薄っぺらく売りさばくのが嫌だった。
今の自分なら少しでも多くの読者の目に触れるためにあえてその手段を使い、自分が金儲け主義だと揶揄されることも厭わなかっただろう。しかしだからといってこれをその手段で再販することは躊躇われた。
多分この本の前では、あの頃の駆け出しで本を出版することの重みを履き違えていた青臭い自分に戻ってしまうのだ。
思えば、こうやれば売れるという手段が判っていたのに倖人の頑固な意見を通して売れない本にしてしまったにもかかわらず、その責任を強くは問わずにいた上の人間は器が大きかったのだろう。おかげで今ではいっぱしの、新人発掘には定評のある編集者と呼ばれるまでになれた。
ページを捲る。
原稿の段階でも何度も何度も推敲し、こうして本になってからも───自分が手がけたほかのどの本よりも何度も何度も繰り返し読んで、あまり読むものだから本が傷んでこれでもう4冊目。自分は在庫で残っていたものの一部を引き取ってきたのでまだ何冊かは手元にあるが、すでに絶版で書店で手に入れることは出来ない。たいした部数出回っていないので古本屋で見つけることすら困難なはずだ。
そんなに何度も読んでも、やはり作品としては稚拙と言わざるを得ない。
この言い回しをこう直せたら、この人物の心情をもっと描けていたら、この章とこの章を入替えて並べてみたら?
出来もしない『たら・れば』を何度繰り返しただろう。
暗誦できるほど何度も読んだ本をぱらぱらと捲ると倖人は窓の外に目を移した。
輝く海は、ほんのりと色をつけ始めていた。夕暮れが近づいている。
ふと窓の下、松の並木に佇む人影が目についた。
シルエットからすぐに女性だということが見てとれる。まっすぐの長い髪。ふくらはぎまで隠れるくらいのロングスカート。つばの広い帽子を海風に攫われないように手で押さえて海を見ている。
『昭和の美少女』みたいなスタイルだな、と思うと少し可笑しくなった。映画か、それとも歌謡曲か。
きらきら輝く夕暮れの海とそれを見つめる美少女。なかなか懐かしい絵柄だ。青春時代に憧れたようなシチュエーション。若い頃ならあそこまで下りていって、声を掛けてみたかもしれない。今は、実際顔を見てみて美少女じゃなかったとか、そう若くなかったとか、そういうオチで台無しにするくらいなら美しい絵柄はそのままにして触らないようにしようと思う。老いたのだな、と思うと自嘲するような溜息が出た。良い景色を見たところで、せっかく温泉宿に来たんだから温泉に入ろう。
本を窓際の低いテーブルに置いて浴衣を羽織り、部屋を出る。少し温泉でゆっくりして戻ってくれば、夕食が用意されている筈だ。
タオルを肩にかけ、1階に下りてロビーから大浴場への通路に向かう。その時、入り口の自動ドアが開いて外から人がひとり入ってきた。
あ。
さっき見た、『昭和の美少女』じゃないか。
あのつばの広い帽子を脱いで手に持ち、落ち着いた様子で姿勢よく歩いている。
顔だちは───予想以上に美しかった。
博多人形のように白く滑らかそうな肌。整った目鼻立ち。真っ直ぐでさらさらの黒髪。前髪をカチューシャで押さえている。
若い頃なら声を掛けていただろうと思ったが、声を掛けてしまってこの美人だったなら逆に腰が引けてしまったかもしれない。
しかし、僕ももういい大人だ。というよりもういいおじさんだ。まだリタイアはしていないが下手をするとおじいさんと呼ばれてしまう年だ。そして女性にだらしないいやらしい親爺だなどと思われるのは心外だと思う程度の自制心はある。
だから、いくら美女でもじろじろ見るのは失礼きわまりない。
と、心の中で様々な言い訳をすると目を逸らしてそのまま目的地である大浴場を目指そうとした──その時、目の端に何かがひっかかった。
彼女は、手にあの帽子と、そして本を一冊携えている。
あの本は───
自制心とやらはどこへ行ったのか、倖人は咄嗟に通り過ぎた彼女の背中を叩いた。
彼女は驚いたように(当然である)びくりと振り返り、目をぱちぱちと何度も瞬いた。この時点でどう見ても不審なナンパにしか見えまい。
「ああ、いきなりすみません。その──本を、どこで手に入れられたのかと思いまして」
慌てて取り繕い、紳士ぶってみたもののこちらはタオルを肩にかけた浴衣姿のオジサンである。どう考えても怪しい。
「この本ですか?」
鈴を転がすという表現があるが、まさしくそれがぴったりの、細く美しく心地よい声。
しかし彼女は少し怯えたようにも見える。ああ、失敗した──と思った途端、彼女はふんわりと微笑んだ。
「以前、図書館で見て、とても気に入ったのですがどこを探しても売っていないもので──その図書館に掛け合ったら払い下げてくれたのです」
そういうのは、アリなのか。
目から鱗が落ちたような気分だ。
と言うよりも、公立だか私設だか知らないが蔵書をそんなに簡単に払い下げるとは、よほど図書館からたいした価値がないと思われていたのだろう。そもそも、図書館にこの本が置いてあったこと自体が驚きだ。これを加えるとは、選んだ司書にも会ってみたい。
彼女の持つそれを見せてもらうと、保護はされているもののそう傷んだ様子はない。借り手もあまり無かったのだとみえる。
しかし、彼女はこの本を気に入ったのだ。
「それがどうかなさいまして?」
「いえ、その本は───僕も色々思いいれがありまして。無名作家の古い本だし絶版だから仰る通り入手困難なのにと気になったんですよ。本当に不躾に申し訳ありませんでした」
いいんです、と彼女は微笑んで頭を下げた。
「こちらにはご家族で?」
詮索する気はなかったが、彼女がこの本のどこが気に入ったのかを詳しく聞いてみたかった。編集者として、読者の生の素直な感想を是非聞いてみたいとも思った。
それ以上に、彼女ともう少し話してみたいと思ったことは心の奥底へ押し込める。これはナンパじゃない。純粋な興味だ。
「いえ、ひとりです。おかしいでしょう?女ひとりで温泉宿なんて。この本の折り返しの著者紹介の欄にここの写真があったでしょう。これはどこなのかしらとずっと探していて、やっと見つけたんです」
「今日び、女性の『おひとりさま』は珍しくないですよ」
そう言うと彼女はくすくすと笑いを漏らした。
「この本の、どこがそんなに気に入ったんですか」
「───主人公の想いが苦しいくらい伝わってくるんですよね。まだ素人ですけどわたしも小説を書いていて、こんなふうに自分や登場人物の想いを読む人に伝えられるものが書きたいと思っています」
彼女は作家志望なのか。
少し、胸が高鳴った。彼女はいったいどんな作品を書くのだろう。
しかしいきなり自分が文芸雑誌の編集長だなんて自己紹介したら素直な感想が聞けなくなるだろう。自分も文章を書いているという彼女の感想をもっと聞きたくなった。こうなったら一大決心だ。
「なら、夕食でもご一緒にいかがですか、僕も一人なので。あんな珍しい本の愛読者仲間を見つけたんだ、あの本の話をもっとしたいですよ。そこのラウンジに用意してもらえば大丈夫でしょう」
さすがに初対面の若い女性を自分の部屋へ呼ぶことは出来ない。あくまで、下心ではないのだ。彼女は可笑しそうに喜んで、と答えた。
実のところ、若い頃にだって見ず知らずの女性に声をかけて成功したためしがない。
誓って下心は無いんだよ、と数年前に先立った妻を思い浮かべて言い訳をした。
自殺の名所などと有り難くもないだろう別名で呼ばれていたその岸壁は、確かにここから飛び降りればひといきに楽になれそうで、あの世からたくさんの亡者がこちらへおいでと手招きしているように思えた。そこにぽつりと腰掛けていたあの少年は当時、13歳だか14歳の中学生だった。凍りつくような寒さなのに、分厚いコートを着ることもせずただぼんやりと海を見つめていた。
自分も飛び降りようかと思ってそこまで行ったのに、きみ、そんなところで危ないよと声を掛けたのだ。
その時、彼は倖人を振り返ると──今にも飛び降りそうな顔をしていながらこう言った。
僕は、死にたくありません。
自分が飛び降りようかと思っていたことなど忘れたように倖人は少年をそっと立ち上がらせて、まずは岸壁から遠ざけた。
聞いてみると、両親とここへ旅行に来たのだという。宿泊先は倖人と同じ岸壁近くのホテルだった。いきなり駆け出して発作的に飛び降りたりしないかが気がかりで、幼い子供の手を引くように少年の手を握って引っ張るようにホテルへ連れ帰った。少年の手は氷のように冷たかった。
両親は少年を心配して探していたらしい。引き渡すと母親は泣きながら倖人に礼を言った。父親も目を真っ赤にして頭を下げた。
倖人が一人だと知ると、夕食に同席するよう誘ってくれた。
それから、その少年と夜通し話をした。その時、彼は一冊のノートを見せてくれたのだ。
ふんわりと良い香りがして、倖人は我に帰った。
「お水、お飲みになります?」
あの鈴を転がすような声が聞こえた。白く細い指が差し出すコップを受け取るとその中の透明の液体を一気に呷る。閉じていたらしい目を開くと、あの博多人形のような白い肌が見えた。
「大丈夫ですか?」
みっともない。禁酒中なのについ飲んでしまったのが悪かった。
彼女もビールくらいは飲んでいたように思うが、とにかくいい年をして今日会ったばかりの若い娘の前で酔いつぶれてしまうとはなんという失態。おぼろげに記憶はあるが結局部屋まで送られてしまった格好のようだった。
「本当、あの本を持ち歩いてらっしゃるんですね。それもすごく読み込んでらして」
彼女は窓際のローテーブルに置いたままにしていたあの本に気付いたようだった。
「……申し訳ない。気にせずお部屋に戻って下さい」
既に敷いてあった布団の上にごろりと横になると天井に向けて酒臭い息を吐き出した。これじゃあ、仮に下心があったとしても彼女に手を出すどころじゃない。だいたい、こんな深夜に見ず知らずの困った酔っ払い親爺の介抱などいつまでもさせるのは可哀想だ。
彼女は布団の横に座り直して、何故か微笑んでいるようだった。
「もし差し支えなければ、さっきのお話の続きをお聞きしたいと思って」
「さっきの話──?」
そうか。
酔ったせいであの少年の話をしたのだ。
あの話は亡くなった妻にすらしていなかったのに。
自分がさしたる理由もなく死を考えて自殺の名所に行ってしまうような男だと、惚れた女には知られたくないとかそういう思いでもあったのかもしれない。逆に自分のことを何も知らない相手だから、うっかりと口が軽くなってしまったのだ。
倖人はのろのろと起き上がると、窓際に置いたあの本を手に取りぱらぱらと捲った。
「僕は、死なないよ。死んでたまるものか」
読まずとも覚えたフレーズ。
病に倒れた主人公は、それを恋人である看護婦にずっと隠していたのだが、彼女も看護婦である。ついに彼の病のことは彼女に知れてしまう。治らぬ病だと知っている看護婦と、告知されなくてもそれをとうに察している主人公。
主人公はそれを知りながら、恋人に繰り返しそう言うのだ。
まるで、まじないのように。
「あの少年が見せてくれた大学ノートには、鉛筆書きでびっしりと小説が綴られていたんです。子供の頃から物語を書くのが好きで、もう何十冊もあるという。いつもノートを持ち歩いて、暇があれば物語の続きを書いていたのだとか」
「もしかして───その男の子の小説が」
倖人は手元の本を閉じ、表紙を大事そうに撫でながらそれをじっと見つめた。
「恋愛などしたこともない30年以上前の中学生が空想で書いた恋愛小説です。好きな女の子とまだキスもしたことないような」
幼さの残る彼の顔を思い出す。
「でも、彼が本当に書きたかったのは、これだったと思うんです」
僕は、死なないよ。死んでたまるものか。
「彼は、白血病でした。ドラマなんかでも題材にされていましたが、当時はまだ化学療法も発達していなくて本当に今よりもずっと『不治の病』だった」
彼は大学ノートに鉛筆で、好きな女の子に、自分は死なない、絶対元気になって帰ってくるからねと必死でメッセージを送っていた。
「それから1年も経たずに、彼は亡くなりました。僕は、ご両親に了解を得て彼の小説を出版することにしたんです」
独り言のように、手元の本を見つめながら語っていた倖人はふと顔を上げた。
彼女は泣きそうな潤んだ目で、唇を噛み締めている。
白血病で若くしてこの世を去った中学生の少年が、自分の死と向き合いながら祈りのように書いた恋愛小説。
そんな謳い文句をつければ、きっとこの本は売れただろう。それでも、彼の想いをたくさんの人に読んでもらって、たくさんの人に彼が生きたという痕跡を残す──そうすることもまた是だったはずだ。しかしそれは倖人には出来なかった。
ただ、彼の両親と、彼の友人たちと、彼が思いを寄せていた倖人は名前も知らない少女に。そして倖人自身に。
彼が生きた証しを残してやりたかった。それだけだったのだ。
あの日この岸壁で出会って、わずか一年足らずの交流しかなかったあの少年のことを。
倖人は決して忘れたくはなかったのだ。
あの時、倖人は彼に救われたのだから。
彼女は話して下さってありがとうございましたと丁寧に礼をして、倖人の部屋を出ていった。
翌朝ロビーに出ると、彼女は小さな荷物を持ってチェックアウトするところだった。
「昨夜は本当にご迷惑をおかけしました」
謝罪すると彼女はあの鈴を転がす声でどういたしまして、と笑った。
一緒に外へ出る。最初に見た時のように、風に帽子が飛ばないよう片手で押さえた。
「少し海を眺めてから、帰ります」
倖人ははたと思いついて、慌てて自分のジャケットの胸ポケットを探った。良かった、名刺入れを入れたままだ。
「良かったら、連絡下さい。あなたの作品を是非読んでみたい」
名刺を渡すと彼女は帽子を押さえた手を外し、両手でそれを受け取った。昨夜の話を聞いていれば倖人が出版社の人間だということはきっと彼女も察しているだろう。
彼女は何故か照れくさそうな顔をして、ありがとうございます、と言った。
松並木の方へ向かって歩いてゆく彼女を見送りながら、倖人は胸いっぱいに海風を吸い込む。
それを吐き出すように、声を上げた。
「僕は───」
彼女は小さく振り返って、きょとんとした顔を見せる。美しいというより、可愛らしい。
「僕は、癌なんだそうです。もう長くないかもしれない」
何故そんなことを言う気になったのか、自分でもわからない。
「でも、僕は死なない。死んでたまるもんか。じいさんになって、老衰で死ぬまで生きてやります」
30年以上の時を経て、このホテルを訪ねようと思ったのは──それを心に刻み直すため。
じいさんになるまで生きていたかったはずの、あの少年の分まで。僕は諦めない。
彼女は驚いた瞳を一瞬悲しそうに曇らせ、最後に優しげに微笑んだ。
「帰ったらご連絡します。わたしの書いたもの、読んで下さいね」
彼女が手を振る。
倖人もそれに応えて、大きく手を振った。
禁無断複製・転載 (c)Senka.Yamashina
これは「恋愛お題ったー」で出題されたキーワードを元に即興で創作したお話です。
テーマ:ヤマシナセンカさんは、「深夜のホテル」で登場人物が「見つめる」、「人形」という単語を使ったお話を考えて下さい。
窓の外には海。よく晴れて、海面がきらきらと輝いている。
前にこの部屋に泊まってから、もう30年以上経つのだろうか。部屋は多少古びた印象がある程度で、どこも変わらなく見えた。もっとも、あの時は年末で、窓の外はどんよりとした分厚い雲と荒れた海、波に舞う雪、おまけに窓の下は銀世界。それに対して初夏の海は穏やかで気持ちいい。
窓を開けると、爽やかな風が潮の香りを運んできた。
こんな季節にここへ来たなら、死のうと思って来たこともふわりと風に流されて忘れてしまうのではないだろうか。
前にここへ来た時、倖人は死ぬつもりだった。
さして、どうしても死にたくなるような追い詰められた状況でもなかったと今なら思う。何故死のうなどと思っていたかももう思い出せないくらいだ。死ななくて本当に良かった、と思う。
それを思いとどまったのは、あの少年と出会ったおかげだ。
彼は、僕よりもずっと思いつめた瞳をしていた───
目を閉じると、まるで今目の前で見ていたかのようにあの少年の面影を思い浮かべることが出来る。それを確認して目を開け、倖人は窓際の椅子から離れて座敷に無造作に置いていた小さな手荷物を開き、中から一冊の本を取り出した。
ハードカバーの古い本。
この本を出した担当は倖人である。
倖人が編集者として初めて手がけた本だが、たいして売れはしなかった。
この本がどうやればある程度売れるのかを今の倖人は知っている。いや、当時でもそうすれば売れるだろうことは考えたし、実際上の人間はそうしろと指示した。けれどあの頃の自分は若かったのだ。
この作品を、ただお涙頂戴で薄っぺらく売りさばくのが嫌だった。
今の自分なら少しでも多くの読者の目に触れるためにあえてその手段を使い、自分が金儲け主義だと揶揄されることも厭わなかっただろう。しかしだからといってこれをその手段で再販することは躊躇われた。
多分この本の前では、あの頃の駆け出しで本を出版することの重みを履き違えていた青臭い自分に戻ってしまうのだ。
思えば、こうやれば売れるという手段が判っていたのに倖人の頑固な意見を通して売れない本にしてしまったにもかかわらず、その責任を強くは問わずにいた上の人間は器が大きかったのだろう。おかげで今ではいっぱしの、新人発掘には定評のある編集者と呼ばれるまでになれた。
ページを捲る。
原稿の段階でも何度も何度も推敲し、こうして本になってからも───自分が手がけたほかのどの本よりも何度も何度も繰り返し読んで、あまり読むものだから本が傷んでこれでもう4冊目。自分は在庫で残っていたものの一部を引き取ってきたのでまだ何冊かは手元にあるが、すでに絶版で書店で手に入れることは出来ない。たいした部数出回っていないので古本屋で見つけることすら困難なはずだ。
そんなに何度も読んでも、やはり作品としては稚拙と言わざるを得ない。
この言い回しをこう直せたら、この人物の心情をもっと描けていたら、この章とこの章を入替えて並べてみたら?
出来もしない『たら・れば』を何度繰り返しただろう。
暗誦できるほど何度も読んだ本をぱらぱらと捲ると倖人は窓の外に目を移した。
輝く海は、ほんのりと色をつけ始めていた。夕暮れが近づいている。
ふと窓の下、松の並木に佇む人影が目についた。
シルエットからすぐに女性だということが見てとれる。まっすぐの長い髪。ふくらはぎまで隠れるくらいのロングスカート。つばの広い帽子を海風に攫われないように手で押さえて海を見ている。
『昭和の美少女』みたいなスタイルだな、と思うと少し可笑しくなった。映画か、それとも歌謡曲か。
きらきら輝く夕暮れの海とそれを見つめる美少女。なかなか懐かしい絵柄だ。青春時代に憧れたようなシチュエーション。若い頃ならあそこまで下りていって、声を掛けてみたかもしれない。今は、実際顔を見てみて美少女じゃなかったとか、そう若くなかったとか、そういうオチで台無しにするくらいなら美しい絵柄はそのままにして触らないようにしようと思う。老いたのだな、と思うと自嘲するような溜息が出た。良い景色を見たところで、せっかく温泉宿に来たんだから温泉に入ろう。
本を窓際の低いテーブルに置いて浴衣を羽織り、部屋を出る。少し温泉でゆっくりして戻ってくれば、夕食が用意されている筈だ。
タオルを肩にかけ、1階に下りてロビーから大浴場への通路に向かう。その時、入り口の自動ドアが開いて外から人がひとり入ってきた。
あ。
さっき見た、『昭和の美少女』じゃないか。
あのつばの広い帽子を脱いで手に持ち、落ち着いた様子で姿勢よく歩いている。
顔だちは───予想以上に美しかった。
博多人形のように白く滑らかそうな肌。整った目鼻立ち。真っ直ぐでさらさらの黒髪。前髪をカチューシャで押さえている。
若い頃なら声を掛けていただろうと思ったが、声を掛けてしまってこの美人だったなら逆に腰が引けてしまったかもしれない。
しかし、僕ももういい大人だ。というよりもういいおじさんだ。まだリタイアはしていないが下手をするとおじいさんと呼ばれてしまう年だ。そして女性にだらしないいやらしい親爺だなどと思われるのは心外だと思う程度の自制心はある。
だから、いくら美女でもじろじろ見るのは失礼きわまりない。
と、心の中で様々な言い訳をすると目を逸らしてそのまま目的地である大浴場を目指そうとした──その時、目の端に何かがひっかかった。
彼女は、手にあの帽子と、そして本を一冊携えている。
あの本は───
自制心とやらはどこへ行ったのか、倖人は咄嗟に通り過ぎた彼女の背中を叩いた。
彼女は驚いたように(当然である)びくりと振り返り、目をぱちぱちと何度も瞬いた。この時点でどう見ても不審なナンパにしか見えまい。
「ああ、いきなりすみません。その──本を、どこで手に入れられたのかと思いまして」
慌てて取り繕い、紳士ぶってみたもののこちらはタオルを肩にかけた浴衣姿のオジサンである。どう考えても怪しい。
「この本ですか?」
鈴を転がすという表現があるが、まさしくそれがぴったりの、細く美しく心地よい声。
しかし彼女は少し怯えたようにも見える。ああ、失敗した──と思った途端、彼女はふんわりと微笑んだ。
「以前、図書館で見て、とても気に入ったのですがどこを探しても売っていないもので──その図書館に掛け合ったら払い下げてくれたのです」
そういうのは、アリなのか。
目から鱗が落ちたような気分だ。
と言うよりも、公立だか私設だか知らないが蔵書をそんなに簡単に払い下げるとは、よほど図書館からたいした価値がないと思われていたのだろう。そもそも、図書館にこの本が置いてあったこと自体が驚きだ。これを加えるとは、選んだ司書にも会ってみたい。
彼女の持つそれを見せてもらうと、保護はされているもののそう傷んだ様子はない。借り手もあまり無かったのだとみえる。
しかし、彼女はこの本を気に入ったのだ。
「それがどうかなさいまして?」
「いえ、その本は───僕も色々思いいれがありまして。無名作家の古い本だし絶版だから仰る通り入手困難なのにと気になったんですよ。本当に不躾に申し訳ありませんでした」
いいんです、と彼女は微笑んで頭を下げた。
「こちらにはご家族で?」
詮索する気はなかったが、彼女がこの本のどこが気に入ったのかを詳しく聞いてみたかった。編集者として、読者の生の素直な感想を是非聞いてみたいとも思った。
それ以上に、彼女ともう少し話してみたいと思ったことは心の奥底へ押し込める。これはナンパじゃない。純粋な興味だ。
「いえ、ひとりです。おかしいでしょう?女ひとりで温泉宿なんて。この本の折り返しの著者紹介の欄にここの写真があったでしょう。これはどこなのかしらとずっと探していて、やっと見つけたんです」
「今日び、女性の『おひとりさま』は珍しくないですよ」
そう言うと彼女はくすくすと笑いを漏らした。
「この本の、どこがそんなに気に入ったんですか」
「───主人公の想いが苦しいくらい伝わってくるんですよね。まだ素人ですけどわたしも小説を書いていて、こんなふうに自分や登場人物の想いを読む人に伝えられるものが書きたいと思っています」
彼女は作家志望なのか。
少し、胸が高鳴った。彼女はいったいどんな作品を書くのだろう。
しかしいきなり自分が文芸雑誌の編集長だなんて自己紹介したら素直な感想が聞けなくなるだろう。自分も文章を書いているという彼女の感想をもっと聞きたくなった。こうなったら一大決心だ。
「なら、夕食でもご一緒にいかがですか、僕も一人なので。あんな珍しい本の愛読者仲間を見つけたんだ、あの本の話をもっとしたいですよ。そこのラウンジに用意してもらえば大丈夫でしょう」
さすがに初対面の若い女性を自分の部屋へ呼ぶことは出来ない。あくまで、下心ではないのだ。彼女は可笑しそうに喜んで、と答えた。
実のところ、若い頃にだって見ず知らずの女性に声をかけて成功したためしがない。
誓って下心は無いんだよ、と数年前に先立った妻を思い浮かべて言い訳をした。
自殺の名所などと有り難くもないだろう別名で呼ばれていたその岸壁は、確かにここから飛び降りればひといきに楽になれそうで、あの世からたくさんの亡者がこちらへおいでと手招きしているように思えた。そこにぽつりと腰掛けていたあの少年は当時、13歳だか14歳の中学生だった。凍りつくような寒さなのに、分厚いコートを着ることもせずただぼんやりと海を見つめていた。
自分も飛び降りようかと思ってそこまで行ったのに、きみ、そんなところで危ないよと声を掛けたのだ。
その時、彼は倖人を振り返ると──今にも飛び降りそうな顔をしていながらこう言った。
僕は、死にたくありません。
自分が飛び降りようかと思っていたことなど忘れたように倖人は少年をそっと立ち上がらせて、まずは岸壁から遠ざけた。
聞いてみると、両親とここへ旅行に来たのだという。宿泊先は倖人と同じ岸壁近くのホテルだった。いきなり駆け出して発作的に飛び降りたりしないかが気がかりで、幼い子供の手を引くように少年の手を握って引っ張るようにホテルへ連れ帰った。少年の手は氷のように冷たかった。
両親は少年を心配して探していたらしい。引き渡すと母親は泣きながら倖人に礼を言った。父親も目を真っ赤にして頭を下げた。
倖人が一人だと知ると、夕食に同席するよう誘ってくれた。
それから、その少年と夜通し話をした。その時、彼は一冊のノートを見せてくれたのだ。
ふんわりと良い香りがして、倖人は我に帰った。
「お水、お飲みになります?」
あの鈴を転がすような声が聞こえた。白く細い指が差し出すコップを受け取るとその中の透明の液体を一気に呷る。閉じていたらしい目を開くと、あの博多人形のような白い肌が見えた。
「大丈夫ですか?」
みっともない。禁酒中なのについ飲んでしまったのが悪かった。
彼女もビールくらいは飲んでいたように思うが、とにかくいい年をして今日会ったばかりの若い娘の前で酔いつぶれてしまうとはなんという失態。おぼろげに記憶はあるが結局部屋まで送られてしまった格好のようだった。
「本当、あの本を持ち歩いてらっしゃるんですね。それもすごく読み込んでらして」
彼女は窓際のローテーブルに置いたままにしていたあの本に気付いたようだった。
「……申し訳ない。気にせずお部屋に戻って下さい」
既に敷いてあった布団の上にごろりと横になると天井に向けて酒臭い息を吐き出した。これじゃあ、仮に下心があったとしても彼女に手を出すどころじゃない。だいたい、こんな深夜に見ず知らずの困った酔っ払い親爺の介抱などいつまでもさせるのは可哀想だ。
彼女は布団の横に座り直して、何故か微笑んでいるようだった。
「もし差し支えなければ、さっきのお話の続きをお聞きしたいと思って」
「さっきの話──?」
そうか。
酔ったせいであの少年の話をしたのだ。
あの話は亡くなった妻にすらしていなかったのに。
自分がさしたる理由もなく死を考えて自殺の名所に行ってしまうような男だと、惚れた女には知られたくないとかそういう思いでもあったのかもしれない。逆に自分のことを何も知らない相手だから、うっかりと口が軽くなってしまったのだ。
倖人はのろのろと起き上がると、窓際に置いたあの本を手に取りぱらぱらと捲った。
「僕は、死なないよ。死んでたまるものか」
読まずとも覚えたフレーズ。
病に倒れた主人公は、それを恋人である看護婦にずっと隠していたのだが、彼女も看護婦である。ついに彼の病のことは彼女に知れてしまう。治らぬ病だと知っている看護婦と、告知されなくてもそれをとうに察している主人公。
主人公はそれを知りながら、恋人に繰り返しそう言うのだ。
まるで、まじないのように。
「あの少年が見せてくれた大学ノートには、鉛筆書きでびっしりと小説が綴られていたんです。子供の頃から物語を書くのが好きで、もう何十冊もあるという。いつもノートを持ち歩いて、暇があれば物語の続きを書いていたのだとか」
「もしかして───その男の子の小説が」
倖人は手元の本を閉じ、表紙を大事そうに撫でながらそれをじっと見つめた。
「恋愛などしたこともない30年以上前の中学生が空想で書いた恋愛小説です。好きな女の子とまだキスもしたことないような」
幼さの残る彼の顔を思い出す。
「でも、彼が本当に書きたかったのは、これだったと思うんです」
僕は、死なないよ。死んでたまるものか。
「彼は、白血病でした。ドラマなんかでも題材にされていましたが、当時はまだ化学療法も発達していなくて本当に今よりもずっと『不治の病』だった」
彼は大学ノートに鉛筆で、好きな女の子に、自分は死なない、絶対元気になって帰ってくるからねと必死でメッセージを送っていた。
「それから1年も経たずに、彼は亡くなりました。僕は、ご両親に了解を得て彼の小説を出版することにしたんです」
独り言のように、手元の本を見つめながら語っていた倖人はふと顔を上げた。
彼女は泣きそうな潤んだ目で、唇を噛み締めている。
白血病で若くしてこの世を去った中学生の少年が、自分の死と向き合いながら祈りのように書いた恋愛小説。
そんな謳い文句をつければ、きっとこの本は売れただろう。それでも、彼の想いをたくさんの人に読んでもらって、たくさんの人に彼が生きたという痕跡を残す──そうすることもまた是だったはずだ。しかしそれは倖人には出来なかった。
ただ、彼の両親と、彼の友人たちと、彼が思いを寄せていた倖人は名前も知らない少女に。そして倖人自身に。
彼が生きた証しを残してやりたかった。それだけだったのだ。
あの日この岸壁で出会って、わずか一年足らずの交流しかなかったあの少年のことを。
倖人は決して忘れたくはなかったのだ。
あの時、倖人は彼に救われたのだから。
彼女は話して下さってありがとうございましたと丁寧に礼をして、倖人の部屋を出ていった。
翌朝ロビーに出ると、彼女は小さな荷物を持ってチェックアウトするところだった。
「昨夜は本当にご迷惑をおかけしました」
謝罪すると彼女はあの鈴を転がす声でどういたしまして、と笑った。
一緒に外へ出る。最初に見た時のように、風に帽子が飛ばないよう片手で押さえた。
「少し海を眺めてから、帰ります」
倖人ははたと思いついて、慌てて自分のジャケットの胸ポケットを探った。良かった、名刺入れを入れたままだ。
「良かったら、連絡下さい。あなたの作品を是非読んでみたい」
名刺を渡すと彼女は帽子を押さえた手を外し、両手でそれを受け取った。昨夜の話を聞いていれば倖人が出版社の人間だということはきっと彼女も察しているだろう。
彼女は何故か照れくさそうな顔をして、ありがとうございます、と言った。
松並木の方へ向かって歩いてゆく彼女を見送りながら、倖人は胸いっぱいに海風を吸い込む。
それを吐き出すように、声を上げた。
「僕は───」
彼女は小さく振り返って、きょとんとした顔を見せる。美しいというより、可愛らしい。
「僕は、癌なんだそうです。もう長くないかもしれない」
何故そんなことを言う気になったのか、自分でもわからない。
「でも、僕は死なない。死んでたまるもんか。じいさんになって、老衰で死ぬまで生きてやります」
30年以上の時を経て、このホテルを訪ねようと思ったのは──それを心に刻み直すため。
じいさんになるまで生きていたかったはずの、あの少年の分まで。僕は諦めない。
彼女は驚いた瞳を一瞬悲しそうに曇らせ、最後に優しげに微笑んだ。
「帰ったらご連絡します。わたしの書いたもの、読んで下さいね」
彼女が手を振る。
倖人もそれに応えて、大きく手を振った。
禁無断複製・転載 (c)Senka.Yamashina
これは「恋愛お題ったー」で出題されたキーワードを元に即興で創作したお話です。
テーマ:ヤマシナセンカさんは、「深夜のホテル」で登場人物が「見つめる」、「人形」という単語を使ったお話を考えて下さい。













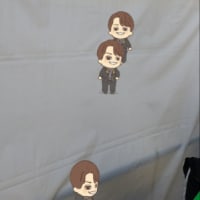






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます