
「サヨンの鐘」という歌、または映画のことを知っている人は、日本ではもう少ないかもしれません。
「サヨンの鐘」の歌は西条八十作曲、古賀政男作曲で、1941年(昭和16年)に渡辺はま子さんの歌でレコードになっています。
そして、映画は1943年(昭和18年)に作られています。
サヨンは台湾の少数民族、タイヤル族の女性で、1938年(昭和13年)に出征する日本人の先生を雨の中見送りに行き、丸木橋を渡っていたときに雨で増水した川に落ちて亡くなってしまったという人です。
この話はその後愛国美談として伝えられたために、さまざまな虚像が加わって、評価されるにしろ、批判されるにしろ、実際のサヨンという一人の実在した女性からは遠く離れたところで議論されるようになってしまいました。
でも、サヨンという人が本当に実在し、これは本当にあった話だということを、サヨンとその先生を直接知っていたという方に教えていただきました。

この方は、タイヤル族最後の頭目という84歳のハユン・ユラオさん。
日本名では杉村清さん、中国名では韋清田さんとおっしゃいます。
サヨンと同じ村の出身で、出征した日本人の先生、田北先生(映画では「武田先生」となっていますが、本当は「田北」だそうです)にも教わっていたそうです。

サヨンが亡くなった場所の近くには、現在はこのような立派な橋がかかっています。
「サヨン橋(莎韻橋)」という名前がつけられています。

サヨンが亡くなったのは、荷物を背負って山を下りてきて、丸木橋を渡ったときでした。
雨で川が増水し、水が濁っていたため、水に落ちたら姿が見えなくなり、荷物は見つかったものの、遺体は見つからなかったそうです。

「サヨン橋」から少し離れたところに、石碑があります。
「愛国乙女サヨン遭難碑」と彫ってあったようです。
サヨンの死後、台湾総督から「愛国乙女サヨンの鐘」が村に送られましたが、村が平地に移住した後、その鐘は誰かに盗まれてしまったということです。

1998年に南澳郷の地方政府により、サヨンの鐘が再び作られ、「サヨン記念公園」の中に鐘楼が作られました。公園入り口にある鳥居は、最近作られたものだそうです。

ここでは、毎日朝8時から夕方6時まで毎正時に、「サヨンの鐘」の日本語の歌と、その中国語版「月光小夜曲」が流れています。

現在のサヨンの鐘は、ひもが短くなっていて、残念ながら鳴らすことはできません。
サヨンの鐘は、ひとりひとりが心の中で鳴らす、ということでしょうか。
実際にあった出来事を考えるとき、私たちはなかなか先入観というものを取り去ることができません。
でも、先入観をなくして初めて、見えてくることもあるのではないでしょうか。
自分の仕事を真剣に行ったサヨンというひとりの女性のことに、先入観なしで思いをはせてみると、いろんなことが違って見えてくるかもしれません。(尾)
※莎韻紀念公園(サヨン記念公園)は、台湾鉄道武塔駅のそばです。
※2010年2月5日(金)の番組「文化の台湾」では、「サヨンの鐘」にまつわる話をご紹介しています。サヨンを直接知っていた杉村清さんのお話もお聴きいただけます。
番組を聴くには、上のバナーをクリック→2月5日をクリック→「文化の台湾」をクリックしてください。










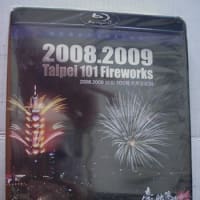

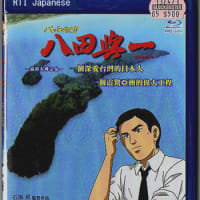
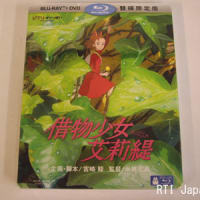



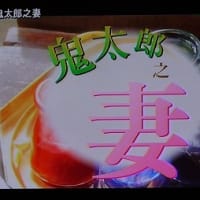


オンデマンドの不具合につきましては、恐れ入りますが、聞けなかった日付、番組名、御使用のソフト(Windows Media PlayerもしくはReal Player)をご記入の上、jpn@rti.org.tw までお問い合わせくださるようお願いいたします。
言われは知りませんが、韓国では有名らしいです。
表記法が記事毎に「原住民族」「先住民族」「少数民族」と別れているようですが、「原住民族」に統一されてみてはどうでしょう?