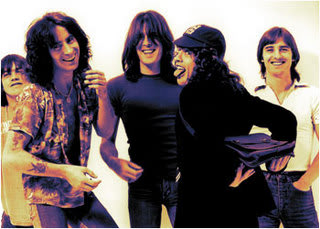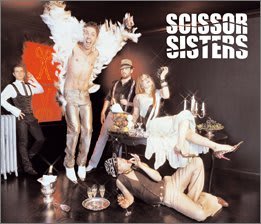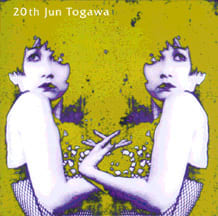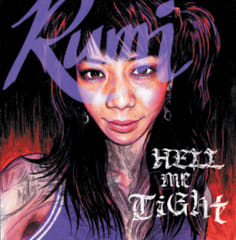あと1ヶ月もすれば、憂鬱な梅雨の季節がやってくる。そしてI AM KLOOTの出番である。
'01年『ナチュラル・ヒストリー』でデビューした、英国マンチェスターのトリオ。実はこの年のフジ・ロックで来日していたらしいのだが、私は見逃してしまった。(・・・ManicsとTricky目当ての初日に行って、さっさと帰ってきてしまったよ^^;;)というか、そのときはまだ彼らの存在など知らなかった、というのが正しい。その後、WOWOWで放映されたフジのライヴ・ビデオを友達に貸してもらったところ「おお・・・!いい歌唄ってる人たちじゃん」と膝を乗り出してしまったのが、このI AM KLOOTなのだった。
しかし、音と唄に惹かれてグッとテレビモニターを観たものの・・・じ、地味ッ! なんつーかそのう、いかにも無愛想かつ不景気そうな英国ワーキングクラスの、ややトウが立ったあんちゃん達であって(画像参照)しかもアコギ抱えたヴォーカルなんて、椅子に座っておるわよ。そんな有様にいささか面食らいつつも、やはりこの地味男の唄はいい。すごくいい声だし。冴えないツラしてるけど、このあんちゃんの唄と爪弾くメロは素晴らしい!
というわけで、早速彼らのアルバムを買いましたところ、もうあまりに心に体に馴染みすぎて、困った。(嬉しかったけど)
一言で表すなら、彼らの音楽はメランコリーだ。灰色の曇天の下、いつ止むとも知れなく降り注ぐ雨のような。雨は確かに気分を揚げてはくれないが、この音のように、静かな雨はむしろ嫌いではない。哀感とぬくもりと、ささやかな美しさに包まれるような気になるから。
マンチェスター出身とはいえ、バカ兄弟@Oasis系の音にはカスリもしない(笑>ワーキングクラスってとこだけかな、共通点)。以前、Turin Brakesのエントリでも書いたけど、むしろSSW系であり、ヴォーカルのジョニー・ブラムウェルは明らかに英国の伝統・偏屈唄歌いの系譜である。個人的に、彼らとの近似性を感じるのは故エリオット・スミスと、ソロになって間もない頃のニール・ヤング・・・って、2人とも米国人じゃん!^^;; なんだけども、まあそれはメローさや音における間の取り方が近いということであって、楽曲自体はむちゃくちゃ英国!!であるからして、UKアコースティク系をこよなく愛する人には是非ともお薦めしたいバンドである。
ただし、あんまりカッチリと「バンド」とか「ロック」って曲ではないし、和み系でもない。フォキーでもありキャバレーソング風でもあり、ねじれてところどころ尖ったポップ感は、当然イマドキのバンドとは一線を画しているというか、ひたすらマイペース(良く言えば)。たぶんバンド仲間も少ないだろうし、欲しいとも思ってない(苦笑)つるむの苦手だし流行はどーでもいい・・・そんな音楽である。しかし、彼らの核を成しているこうした部分が、非常に馴染む人には馴染む音であり、それは3枚目のアルバムとなる今作でも変わりようがない。(ちなみに2作目は、タイトルがまんまバンド名、しかも真っ黒なジャケに白抜き文字のみ、というあまりにハッキリし過ぎた態度だったせいか;; 日本盤未発売である)
ただし、これまでに比べて、全体的な音像に開かれた雰囲気が出てきた。そして、更に自分たちの在り方に確信を強めた曲作りをしているように感じる。どこにでもありそうで、ない唄。自分達のひねくれ加減と世の中のバカバカしさをいとおしむ余裕、だって俺もみんなそんなもんだろ、と優しく突き放すジョニーの声。
本当に彼の唄はいいなあ、と改めて思う。誰だっていつも楽しいわけじゃないし、いつも哀しいわけじゃない。その狭間で生きているんだから。
そんな風に思いながら、やはり灰色の空の日には『Gods and Monsters』を聴くと、気持ちが落ち着いてくるのであった。
ところで、今作は日本盤が出たので(・・・)それを買ったんだけど、ライナーノーツに載ってたジョニーの発言や、6月号RO誌のインタはなかなか面白かった。「ブレヒト/ワイルの『三文オペラ』を聴いてからソングライティングを始めた」とか「個人的にはダムドやピストルズやスカが好きなんだよ。ニュー・アコースティクなんてレッテル貼られちゃたまったもんじゃねえ!(大意>でもニュアンス的には絶対こんな感じなはず!)」とかのたまっちゃってさ。
なるほど、そう聞けばあるいは、ブレヒト/ワイルとパンクの間を繋ぐのがI AM KLOOTの音楽、とも言えるのかもしれない >少なくとも、私の中ではかなり納得であったわ。
※ 完全な余談ですが。一時期、私もブレヒト/ワイルにはハマったことがあった。きっかけはルー・リードやマリアンヌ・フェイスフル、トム・ウェイツやダグマー・クラウゼ等錚々たるメンツによるオムニバス『クルト・ワイルの世界~星空に迷い込んだ男』を聴いたこと。それまではボウイやドアーズで有名な“アラバマ・ソング”くらいしか知らなかったんですがねえ。アルバム自体超傑作です。レコード持ってたので油断してたら、いつのまにCDの『クルト・ワイルの世界~』は製造中止に!(涙)信じられな~い。・・・零細ブログの端っこで、熱烈再発希望を叫んでみたい気分である。
'01年『ナチュラル・ヒストリー』でデビューした、英国マンチェスターのトリオ。実はこの年のフジ・ロックで来日していたらしいのだが、私は見逃してしまった。(・・・ManicsとTricky目当ての初日に行って、さっさと帰ってきてしまったよ^^;;)というか、そのときはまだ彼らの存在など知らなかった、というのが正しい。その後、WOWOWで放映されたフジのライヴ・ビデオを友達に貸してもらったところ「おお・・・!いい歌唄ってる人たちじゃん」と膝を乗り出してしまったのが、このI AM KLOOTなのだった。
しかし、音と唄に惹かれてグッとテレビモニターを観たものの・・・じ、地味ッ! なんつーかそのう、いかにも無愛想かつ不景気そうな英国ワーキングクラスの、ややトウが立ったあんちゃん達であって(画像参照)しかもアコギ抱えたヴォーカルなんて、椅子に座っておるわよ。そんな有様にいささか面食らいつつも、やはりこの地味男の唄はいい。すごくいい声だし。冴えないツラしてるけど、このあんちゃんの唄と爪弾くメロは素晴らしい!
というわけで、早速彼らのアルバムを買いましたところ、もうあまりに心に体に馴染みすぎて、困った。(嬉しかったけど)
一言で表すなら、彼らの音楽はメランコリーだ。灰色の曇天の下、いつ止むとも知れなく降り注ぐ雨のような。雨は確かに気分を揚げてはくれないが、この音のように、静かな雨はむしろ嫌いではない。哀感とぬくもりと、ささやかな美しさに包まれるような気になるから。
マンチェスター出身とはいえ、バカ兄弟@Oasis系の音にはカスリもしない(笑>ワーキングクラスってとこだけかな、共通点)。以前、Turin Brakesのエントリでも書いたけど、むしろSSW系であり、ヴォーカルのジョニー・ブラムウェルは明らかに英国の伝統・偏屈唄歌いの系譜である。個人的に、彼らとの近似性を感じるのは故エリオット・スミスと、ソロになって間もない頃のニール・ヤング・・・って、2人とも米国人じゃん!^^;; なんだけども、まあそれはメローさや音における間の取り方が近いということであって、楽曲自体はむちゃくちゃ英国!!であるからして、UKアコースティク系をこよなく愛する人には是非ともお薦めしたいバンドである。
ただし、あんまりカッチリと「バンド」とか「ロック」って曲ではないし、和み系でもない。フォキーでもありキャバレーソング風でもあり、ねじれてところどころ尖ったポップ感は、当然イマドキのバンドとは一線を画しているというか、ひたすらマイペース(良く言えば)。たぶんバンド仲間も少ないだろうし、欲しいとも思ってない(苦笑)つるむの苦手だし流行はどーでもいい・・・そんな音楽である。しかし、彼らの核を成しているこうした部分が、非常に馴染む人には馴染む音であり、それは3枚目のアルバムとなる今作でも変わりようがない。(ちなみに2作目は、タイトルがまんまバンド名、しかも真っ黒なジャケに白抜き文字のみ、というあまりにハッキリし過ぎた態度だったせいか;; 日本盤未発売である)
ただし、これまでに比べて、全体的な音像に開かれた雰囲気が出てきた。そして、更に自分たちの在り方に確信を強めた曲作りをしているように感じる。どこにでもありそうで、ない唄。自分達のひねくれ加減と世の中のバカバカしさをいとおしむ余裕、だって俺もみんなそんなもんだろ、と優しく突き放すジョニーの声。
本当に彼の唄はいいなあ、と改めて思う。誰だっていつも楽しいわけじゃないし、いつも哀しいわけじゃない。その狭間で生きているんだから。
そんな風に思いながら、やはり灰色の空の日には『Gods and Monsters』を聴くと、気持ちが落ち着いてくるのであった。
ところで、今作は日本盤が出たので(・・・)それを買ったんだけど、ライナーノーツに載ってたジョニーの発言や、6月号RO誌のインタはなかなか面白かった。「ブレヒト/ワイルの『三文オペラ』を聴いてからソングライティングを始めた」とか「個人的にはダムドやピストルズやスカが好きなんだよ。ニュー・アコースティクなんてレッテル貼られちゃたまったもんじゃねえ!(大意>でもニュアンス的には絶対こんな感じなはず!)」とかのたまっちゃってさ。
なるほど、そう聞けばあるいは、ブレヒト/ワイルとパンクの間を繋ぐのがI AM KLOOTの音楽、とも言えるのかもしれない >少なくとも、私の中ではかなり納得であったわ。
※ 完全な余談ですが。一時期、私もブレヒト/ワイルにはハマったことがあった。きっかけはルー・リードやマリアンヌ・フェイスフル、トム・ウェイツやダグマー・クラウゼ等錚々たるメンツによるオムニバス『クルト・ワイルの世界~星空に迷い込んだ男』を聴いたこと。それまではボウイやドアーズで有名な“アラバマ・ソング”くらいしか知らなかったんですがねえ。アルバム自体超傑作です。レコード持ってたので油断してたら、いつのまにCDの『クルト・ワイルの世界~』は製造中止に!(涙)信じられな~い。・・・零細ブログの端っこで、熱烈再発希望を叫んでみたい気分である。